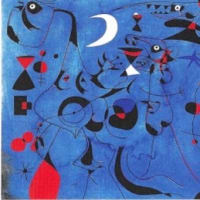平日ながら、春休みなので、東京府中の古墳巡りに行った。
都内の古墳は、東西に流れる多摩川の北岸沿いに点在しており、
とりわけ武蔵国の国府があった府中市には二つの古墳群がある。
言い換えれば、関東では一般に縄文遺跡なら豊富にあるものの、
大和〜奈良時代の古代になると史跡はグッと減るのだが、さすが”府中”は古代の史跡に満ちている。
京王線に乗り、府中の1つ先の分倍河原(ぶばいがわら)で降りる(この地名で多摩川に近いことがわかる)。
分倍河原は、新田義貞と北条幕府軍が戦った中世の古戦場もあるのだが、そこは碑があるだけなので省略。
まずは駅の東側出口に出て、近くで昼食をと、チェーン店ながら手頃な値段で私の定番”五目焼きそば”を食せる「れんげ食堂Toshu」に入る。
ここは「そば少なめ」とか「エビ抜き」とかも選べる。
私が食べたいのは”五目”部分なので、糖質を減らすため「そば少なめ」を選んだ(30円引き)。
さて、ここからスマホのGoogleマップのナビを頼りに、古墳巡りを開始。
古墳群は、ここ付近だけ南北に走る京王線の西側にある。
最初に訪れた「首塚古墳」は、民家脇の空き地の盛土の上に稲荷の祠が建っているだけで、古墳には見えない。
南下してJR南武線の踏み切りを越え、高倉塚古墳(市史跡)に達する(写真)。
ここは明確な円墳で、石段がついていて、天辺(てっぺん)まで登れる。
ただ、人様の墓の上を土足で歩くってあまりいい気分でない。
この古墳は付近の古墳群の代表で、それを高倉塚古墳群という。
往路を戻って、地元鎮守の八雲神社に参拝。
訪れた地の鎮守社には必ず挨拶することにしている。
そこから北上して達した高倉20号墳は、日本通運の敷地内なので入れず、
遠くからの目視で済ませる。
古墳群というものの、実は宅地化で消失したものが多く、墳として残っているのは数えるほどで、
残っていても私有地内にあったりする。
西に進んで、JR南武線の西府(にしふ)駅前にあるのが御嶽塚古墳(市史跡)。
江戸時代以降、頂上に御嶽(みたけ)神社の祠が置かれて、多摩川上流の武州御岳山※登拝の代わりとなっていたようだ(写真)。
※御岳山の頂上に御嶽神社がある。
ここは緩い円墳で、古墳というより小丘で周囲ともども公園化している。
この付近にも古墳が点在し、合わせて御嶽塚古墳群という。
その公園でトイレを借りて、南武線を地下道でくぐって北上し、
甲州街道に出ると目の前に熊野神社がある。
神社の奥に目指す古墳があるのだが、神社の手前にその古墳についての立派な展示館があるので、まずはそこに入る(もちろんトイレ完備)。
なんで立派な展示館があるかというと、ここの古墳が「国史跡」に指定されているから。
ここの古墳は、方墳の上に円墳が乗った全国的にも珍しい「上円下方墳」(方円墳)で、
しかもその方円墳の中では最古で最大だという。
石積みの頑丈な古墳はしっかり残っていて、玄室のある内部も堅牢に作られていて、
その再現版が資料館の隣にあって、玄室まで入れる(上写真)。
ということで技術的にも当時最高度の古墳で、地元府中の相当な有力者の墓だったようだ。

資料館を出て熊野神社を参拝して、拝殿・本殿(ともに市有形文化財)の奥に、ご神体のごとく鎮座する武蔵府中熊野神社古墳を周囲から眺める(写真:中には入れない〕。
もちろんここが府中古墳巡りのハイライト。
この後は、車で混雑している甲州街道(国道20号)を西に進み、国立(くにたち)市に入る。
20号が日野バイパスとして左に折れて旧甲州街道と分かれる所に、下谷保(やほ)古墳がある。
地図上では2号墳、1号墳、8号墳と並んでいるが、実際に行けるのは1号墳だけ。
古墳巡りはこれで終了だが、ここまで来たのだから少し先の谷保天満宮に足を伸ばす。
谷保天満宮は、国立市(国分寺と立川の間の地という意味)周辺では最も有名な神社で、
菅原道真を祀る天満宮としては東国第一という(文京区の湯島天神より格上)。
江戸時代、口さがない江戸市民からは「やぼてん」と呼ばれていた。
ここから、説明板以外何もない仮屋上史跡群を見て、JR南武線谷保駅に着く。
そこから分倍河原で京王線に乗換えて帰宅した。
もともと古墳巡りが目的だったので以上のルートにしたのだったが、
帰宅して地図を見返したら、もう少し西に歩けば「くにたち郷土文化館」があった。
郷土資料館を1つ行き損なった。