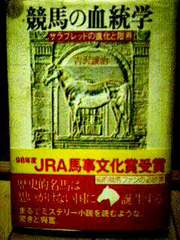昨年のマイルチャンピオンシップを勝ったブルーメンブラットの父はアドマイヤベガという活躍馬でした。
デビューは2歳11月。新馬戦は1着で入線したものの走行妨害を取られ4着に降着。このためまだ未勝利戦に出られたのですが,12月初めの1勝馬クラスの特別戦に出走。記録上も初勝利を上げると,暮れには重賞にも出走し,これを制しました。
当然ながら目指すはクラシック。まず弥生賞からキャンペーンを開始。2着とまずまずのスタートを切り皐月賞に。ここは1番人気に推されたのですが,おそらく体調面が整わなかったものと思われ,6着に敗退してしまいました。しかし続くダービーではゴール前で争う2頭を外から交わして優勝。見事に大レースを制覇しました。
秋は当時は菊花賞のトライアルであった京都新聞杯から始動。ここで重賞3勝目を上げて菊花賞に向いましたが,距離だったか体調だったか,皐月賞と同じく6着に敗退。残念ながらこれが現役最後のレースになってしまいました。
2005年の中山大障害を制して同年の最優秀障害馬に選出されたテイエムドラゴン,2006年の桜花賞を優勝したキストゥヘヴンはこの馬の産駒。早世してしまったのが残念な馬です。
第三部定理五の証明は容易というか,もうすでにこの定理を引き出す説明の中でなされているということもできるかもしれません。ここでは背理法を用いて証明してみましょう。
今,AとBがあって,AはBを,またBはAを滅ぼすことができると仮定します。すなわちAとBは相反する本性を有すると仮定するわけです。そしてこの上で,AとBとがXという同じ主体の中にあるとします。そこでこのことは,ある主体の中に,その主体を,あるいはその主体を構成する部分を滅ぼし得るようなものが,この主体自身のうちにあるということを直ちに意味することになります。したがって,このXは,Xそれ自身によって,あるいはX自身のうちにあるAないしはBによって,滅ぶということに,あるいは少なくとも滅び得るということが帰結します。したがってこの場合,知性は単にXに注目するだけで,いい換えればX以外の何ものにも注目することなく,Xの存在を除去し得るということになります。
しかしこれを主張することは,第二部定義二に反するということになります。すなわちこの定義が意味しているところは,事物の本性というものはそのものの存在を定立するけれども排除はしないということなのであって,そのゆえに,知性は単にあるものに注目するだけではそのものの存在を除去するようないかなるものをも見出すことはできないということであるからです。
したがって,もしも知性があるものの存在が排除される原因,あるいはあるものの実在性が低下するような原因を発見するとすれば,それはそのもの自身のうちではなく,そのものの外部に見出すことになります。よって相反する本性を有するようなものは,各々の主体の外部にのみあるのであって,同一の主体の中にはあることはできないのです。
デビューは2歳11月。新馬戦は1着で入線したものの走行妨害を取られ4着に降着。このためまだ未勝利戦に出られたのですが,12月初めの1勝馬クラスの特別戦に出走。記録上も初勝利を上げると,暮れには重賞にも出走し,これを制しました。
当然ながら目指すはクラシック。まず弥生賞からキャンペーンを開始。2着とまずまずのスタートを切り皐月賞に。ここは1番人気に推されたのですが,おそらく体調面が整わなかったものと思われ,6着に敗退してしまいました。しかし続くダービーではゴール前で争う2頭を外から交わして優勝。見事に大レースを制覇しました。
秋は当時は菊花賞のトライアルであった京都新聞杯から始動。ここで重賞3勝目を上げて菊花賞に向いましたが,距離だったか体調だったか,皐月賞と同じく6着に敗退。残念ながらこれが現役最後のレースになってしまいました。
2005年の中山大障害を制して同年の最優秀障害馬に選出されたテイエムドラゴン,2006年の桜花賞を優勝したキストゥヘヴンはこの馬の産駒。早世してしまったのが残念な馬です。
第三部定理五の証明は容易というか,もうすでにこの定理を引き出す説明の中でなされているということもできるかもしれません。ここでは背理法を用いて証明してみましょう。
今,AとBがあって,AはBを,またBはAを滅ぼすことができると仮定します。すなわちAとBは相反する本性を有すると仮定するわけです。そしてこの上で,AとBとがXという同じ主体の中にあるとします。そこでこのことは,ある主体の中に,その主体を,あるいはその主体を構成する部分を滅ぼし得るようなものが,この主体自身のうちにあるということを直ちに意味することになります。したがって,このXは,Xそれ自身によって,あるいはX自身のうちにあるAないしはBによって,滅ぶということに,あるいは少なくとも滅び得るということが帰結します。したがってこの場合,知性は単にXに注目するだけで,いい換えればX以外の何ものにも注目することなく,Xの存在を除去し得るということになります。
しかしこれを主張することは,第二部定義二に反するということになります。すなわちこの定義が意味しているところは,事物の本性というものはそのものの存在を定立するけれども排除はしないということなのであって,そのゆえに,知性は単にあるものに注目するだけではそのものの存在を除去するようないかなるものをも見出すことはできないということであるからです。
したがって,もしも知性があるものの存在が排除される原因,あるいはあるものの実在性が低下するような原因を発見するとすれば,それはそのもの自身のうちではなく,そのものの外部に見出すことになります。よって相反する本性を有するようなものは,各々の主体の外部にのみあるのであって,同一の主体の中にはあることはできないのです。