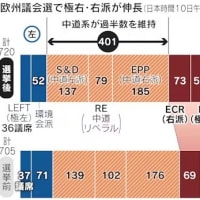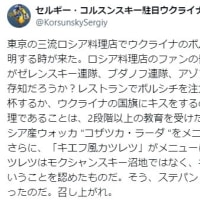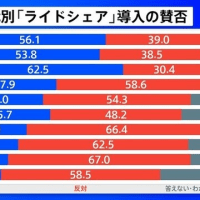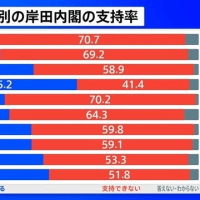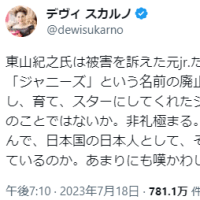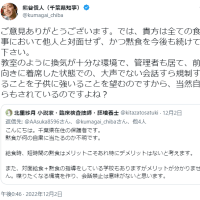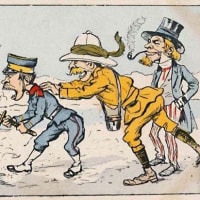宮崎県知事に当選したそのまんま東こと東国原氏ですが、一時は「談合は必要悪」と言明して不興を買い、すぐに発言を撤回するという一幕がありました。今では談合否定派の立場に立つようなのですが、これはどうなのでしょうか? 私が東国原氏に期待することは特にないのですが、談合を積極的に推し進めていく、というのであれば応援したいところでもあります。
ともすると悪であると断定され、とにかく排除されるべきものと見なされがちな談合ですが、そのあたりに私は疑問を感じるわけです。もちろん談合にも悪い点はあるわけですが、しかし談合を廃した結果はどうなのでしょうか? 競争によって入札価格が下がることで、そのしわ寄せで犠牲を強いられるのは下請け企業であり、その労働者でもあります。税金からの支出が減っても、それ以上に労働者の手取りが減ってしまうようでは意味がありません。
以前に家電量販店で働いていたことがあるのですが、この業界はどこも業績が悪い、低い利益率が収益性を圧迫し、売れても売れても儲からない泥沼にはまっているわけです。どうしてこうなったかと言えば値下げ競争のため、以前は¥70で仕入れて¥100で売っていた商品を他店との値引き競争に負けないために¥90に下げ、¥80に下げる、¥100から¥80への値引きは買う側からすれば2割引ですが、仕入れ値の¥70を差し引いた利益は¥30から¥10へ、販売側からすれば利益は3分の1まで減ってしまう、こんなことを繰り返していたのです。
家電製品はまだましで、PCなど情報機器はもっと悲惨です。情報機器の卸売りをやっていたこともあるのですがPC関連商品の利益率は軒並み10%以下、¥90で仕入れて¥98で売るような商売でした。10万円の商品を売っても利益は100円しかないなんてのもPCパーツ業界では珍しくはありません。これでは次々と潰れる会社が出るのも当たり前です。
たとえば仕入れ値が¥100の商品があったとしましょう。これの小売価格がいくらだったら納得できるでしょうか? ¥150くらいで売っても罰は当たらないでしょうか? しかし、隣の店が¥120で売り出したら? そうなると¥150ではもはや売れませんから、こちらも対抗して¥120まで値下げするしかありませんね。お客さんから見れば¥150→¥120で20%の割引、一方で販売側の利益は¥50→¥20で60%ダウン、こうなると売る側はやっていけなくなってしまいます。
さて¥50→¥20まで利益が低下してしまった販売側はどうしたらいいのでしょうか? 一般にはここで販売量の拡大を目指します。¥120でも2つ売れれば利益は¥40確保、たくさん売って利益率の低下を補おう、と。ところが、いくら値引き競争を繰り広げたところで消費者側の購買量はそんなに増えません。客の数は一定である以上それを取り合うしかなくなってしまい、それに失敗した販売側は経営破綻へと突き進みます。
顧客の取り合いに負けて敗れ去る、それを防ぐためにはどうすべきか? ここで自分だけは助かろうとする利己的な会社はさらなる値引き競争で顧客の確保に走ります。製品を¥110まで値下げして、その低価格を武器によそから顧客を根こそぎ奪い、自分の会社だけは助かろうとします。しかし、そうはさせじと隣の会社は¥108まで値下げ、さらに隣の会社は¥105で勝負! このレベルの値引き競争となると消費者へはほとんど恩恵がありませんが(¥110が¥108に値下げされてもあまり嬉しくないでしょう?)、販売側では血で血を洗う競争が繰り広げられているわけです。
この不毛な争いをやめ、全員で生き延びる方法があります。それは値引き競争をやめることです。自分一人だけ値引きして他社を出し抜こうとせずに、みんなで価格を一定の水準に保つこと、値引きはやめて¥150に価格を保つことで、少ない顧客でも各社がきっちり生き延びることができるようになり、無理をする必要がなくなります。これは公共の精神に則った素晴らしいアイデアではないでしょうか?
実は超のつく最高レベルの談合社会は土建業界、公共工事の世界ではなくアメリカはメジャーリーグにおいて見ることができます。この辺はメジャーリーグへの追随が著しい日本プロ野球でも同様ですが、とにかくメジャーリーグでは「共存共栄」の名の下に特定の団体が突出することが許されません。中には企業努力によって莫大な利益を上げるチームもあれば放漫経営によって赤字の球団もある訳ですが、共存共栄の理念の元にメジャーリーグ機構から利益の分配が行われ、特定チームに富が集中しない、下位に低迷するチームにもリーグ全体の利益が還元されるようになっており、チーム単独では赤字でも運営が続けられる仕組みが整備されている訳です。
徹底した再分配が行われるのは財源だけではありません。ドラフト制度によって選手獲得の機会が完全に保証され、スカウティングに力を入れたチームもそうでないチームにも平等にドラフト指名の権利が与えられます。またFA制度によって有力選手を獲得したチームは新人獲得のためのドラフト指名権を譲渡するルールにより、主力選手が流出しても代わりに新人選手獲得の機会が優先的に与えられる、損失には必ず保証がついてきます。
そして「贅沢税」制度、これはチームの年俸総額が一定水準を超えたチームに対して課される課徴金であり、これがまた経営基盤の弱いチームに分配されます。高年俸の大物選手を複数抱える金満球団に課徴金を課すことでその戦力的な突出を抑制し、弱小球団への補助に充てることで戦力均衡を図るわけです。廃案になってしまいましたが「サラリーキャップ制度」、これは選手の年俸額に上限を設けることで特定の選手ばかりが高額の年俸を手にすることがないようにするものでした。
このようにメジャーリーグでは徹底的な利益の分配により特定チームばかりが儲けたり特定チームが破綻したりすることを防ぎ、各種のルール制限により特定チームへの戦力の集中を防いで弱小チームに選手獲得の機会を確保、年俸抑制策によって特定の選手の一人勝ちを許さない世界が構成されているわけです。利益分配の発想がなく特定の企業だけが莫大な利益を上げ、各社の経営層が天文学的な報酬を受け取る一方で日々の生活にも困窮する貧困層が目立つアメリカ社会で、ここまで極端な福祉社会が生まれたのは皮肉なことです。
日本でも、パ・リーグ全体が経営危機に陥ったとなればドル箱である巨人戦をパ・リーグにも解放して利権を分配、共存共栄路線を貫きました。これが普通の会社間のことであれば、経営危機に陥った企業を救うために既得権益を手放してまで利益を分け合うという発想は生まれたでしょうか? あるいは楽天が新規参入したとき、拡大ドラフトと称して各球団は楽天へと選手の供与を行いました(制限はありましたが)。誰かが新しい会社を設立したときに、同業他社が自分たちの販路を新設の会社に分け与えるようなことをするでしょうか?
不思議なことに、ガチガチの競争社会であるアメリカの、それも競争こそが本分であるスポーツ界において最も強固な談合社会を見ることができる訳です。これが欧州のサッカーリーグであれば特定のクラブばかりが強くなり、弱小クラブが経営破綻したり降格という形でリーグからはじき出される競争社会が普通に見られるのですが・・・
ともあれスポーツ選手が競争にさらされるのは悪いことではないと思うのです。全員ではないかもしれませんが、好きでやっていること、自ら選んだ道なのですから。私も自分の好きなことでなら競争は歓迎です。ブログの読者獲得競争だったり、研究成果を競ったり、ゲームの攻略を競ったり、そういう競争だったら望むところです。好きなことなら、激しい競争も楽しいものです。
しかし、競争が苦痛になる場合もあります。たとえば、仕事。私は仕事が嫌いです。こんなものに血道を上げて競い合う気はさらさらありません。しかし、競い合うことを迫られます、会社が生き残るために。自分の好きなことで競い合うのはかまいませんが、不本意なことで競い合うことを余儀なくされるとしたらどうでしょうか? 自分の好きなことを仕事にできた人はいいですが、多くの人は好きだからではなく生きるために仕事をしているはずです。そんな仕事に全身全霊を捧げて競い合うことを強いられることを歓迎できる人はどれだけいるでしょうか?
営業をやっていたこともあるのですが、その役目はすなわち顧客を獲得すること、だからどんどん営業をかけて新規顧客を開拓していくわけですが、そうこうしている間に既存の顧客が他社の営業に奪われる、そんな繰り返しでした。顧客の総数は元から決まっているわけで、それを奪い合っているだけ、私が努力して他社の顧客を自社に引き込むのと同様に、他社の営業も努力して私の顧客を自分の会社に引き入れる、一歩下がって眺めてみれば、労多くして産むところは何もない、全くの無駄な行為に見えます。お互いに営業活動をやめれば自分の顧客を奪われることはなくなり、他人の顧客を奪いにいく必要もなくなる、それでお互いが楽になれると思ったものです。
先日、派遣社員の友人が契約を打ち切られました。私の友人だけではなく、その会社の派遣社員を一斉に契約打ち切りだとか。どうやら派遣会社A社が時給¥2000(派遣社員の取り分はこの7割くらいが相場)程度で業務を請け負っていたところ、別の派遣会社B社が時給¥1800(推定)程度で営業をかけてきたようです。そこで受け入れ先のC社はより一層のコスト削減のために派遣会社A社との契約を打ち切り、B社と新たに派遣契約を結んだわけです。A社からの派遣社員は失業、A社も得意先を失うことになりましたが、この先A社及びA社所属の派遣社員はどうすべきでしょうか? A社は得意先を奪い返すべく、今度は時給¥1600くらいで営業をかけるかもしれませんね。しかしそれによって顧客を奪い返せたとしても、A社の取り分もA社所属の派遣社員の取り分も激減です。それよりB社と値下げ競争を繰り広げるのではなく、談合してお互いの取り分を守りあった方がよかったのではないでしょうか? B社にしたところで新規獲得のために無理をして価格を引き下げたでしょうに・・・
(ちなみにC社は上場企業で業績好調です。この件は労働者の給与は会社の業績によって上がるのではなく、労使間の力関係によってのみ上昇することを端的に表しています)
そんなわけで、社会全体のことを考えるのであれば我々はもっと談合すべきではないか、それが共存共栄への道ではないかと思うのです。値引き競争をやめて利益率を一定の水準に保てば下請けにしわ寄せがいくこともなくなります。そして営業活動を控えて他人の顧客に手を出すことをやめれば、休日や深夜まで不毛なパイの奪い合いを繰り広げることもなくなります。椅子取りゲームをやめてお互いに分け合えばもはや営業活動は不要となり、それだけ余暇も生まれます。そうなってこそ安倍総理の言う子作りの時間だって確保できそうなものですし、社会活動への参加も可能になるというものです。
サッカー選手が競い合うのは歓迎ですが、サラリーマンを競わせようとする動きにはNO!を。我々は好きでサラリーマンをやっているのでしょうか(サラリーマンが子供の頃の夢だった人はどれだけいますか?)。競争に力を入れれば入れるほど、相手も負けじと力を入れてくるもの、ひとたび競争が始まればそれは激化の一途をたどるものであり、我々への負荷は増えるばかりです。そうなる前に、談合してお互いの取り分を侵さないようにした方がよいのではないでしょうか。そうすることで我々の仕事への負荷も減り、仕事以外へ振り向ける余力も増えるはずです。仕事の負担が減って余裕ができれば、それだけ夢を追う時間が増える、仕事のために夢を犠牲にしないで済む世界に近づけるような気がします。談合と共存共栄は紙一重なのです。