「パーキンソン・プラス症候群」とは,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)のようにパーキンソン症状に加え,錐体外路系以外の神経変性に伴う症状を呈する疾患群をさすが,これらに対するリルゾールの効果を検証するランダム化比較試験(NNIPPS: Neuroprotection and Natural History in Parkinson Plus Syndromes)の結果が報告された.この試験はヨーロッパ(仏独英)のNNIPPS study groupにより行われた研究である.
リルゾールはグルタミン酸毒性仮説に基づいて開発されたALS治療薬で,海外ではじめて認可され,日本でも唯一のALS治療薬として1999年から承認されている.パーキンソン・プラス症候群に対してリルゾールの効果が検討された理由は,上記のグルタミン酸毒性抑制以外にも,電位依存性ナトリウムチャネルの阻害作用,フリーラジカル消去作用,抗アポトーシス作用,神経栄養作用など多岐にわたる薬理効果を有することと,MSAの疾患モデルであるαシヌクレイン変異マウスに対し,一部神経症状の改善をもたらしたことが挙げられる(しかし確固たる根拠があってこの薬剤が選ばれたというわけではないようだ).
方法は,30歳以上で発症し,1年以上持続する無動・筋強剛(akinesia-rigidity syndrome)を呈する症例のうち,PSPないしMSAのinclusion criteriaを満たす症例を対象とした(NNIPPS criteriaという新しい診断基準を作成した).primary end-pointは生存,secondary end-pointは運動機能スケールの低下速度とした.必要症例数はPSPおよびMSAの各群の死亡の相対危険度の40%減少を検出できるように設定した.患者を実薬群(50-200mg/day)と偽薬群に分け,36か月にわたり経過観察した.
結果として767名が無作為に割りつけられ,そのうち760名に対しIntent To Treat (ITT) 解析が行われた(層別解析ではPSPが362名,MSAが398名であった).経過観察の中央値は1095日(249~1095日)であった.経過観察中,342名が死亡し,うち112名で剖検が行われた.リルゾールの効果に関しては,PSPおよびMSAいずれの群においても生存に対する有効性は認められなかった.同様に運動機能の低下に関しても効果はなかった.特に問題となる副作用もなかった.剖検症例をもとにNNIPPS 診断基準の妥当性が検討されたが,非常に確度が高いことが分かり,この診断基準は今後の治療研究に十分使用できるものであると考えられた.
以上のような結果で,残念ながらリルゾールはPSPやMSA(MSA-P)に無効であったわけだが(調べてみると,パーキンソン病やハンチントン病,ニューロパチック・ペインでもランダム化比較試験が行われていて,いずれも無効であった),それでもこの論文を取り上げたのは,病態解明に関する基礎研究の途上で,まだ十分にその病態機序が分からなくても,可能性があるのであれば,きちんと計画された大規模研究ならchallengeしてみても良いという考えもあるのだということを認識したことと,そのためには大規模な臨床研究を計画するスキルをこれからの臨床医は身につける必要があるということである.とくに後者については一部の大学ではそのような勤務医向けの講義を行っているところもあるようである(しかし残念ながらまだ稀である).ぜひ若いドクターには基礎研究のみでなく,積極的に臨床研究のデザインの仕方や評価の仕方について学んでほしい.
Brain. 2008 Nov 23. [Epub ahead of print]
追伸;忙しくて更新する余力がなかったのですが,新年になりましたのでまた頑張ろうと思います.本年もどうぞ宜しくお願いいたします.
リルゾールはグルタミン酸毒性仮説に基づいて開発されたALS治療薬で,海外ではじめて認可され,日本でも唯一のALS治療薬として1999年から承認されている.パーキンソン・プラス症候群に対してリルゾールの効果が検討された理由は,上記のグルタミン酸毒性抑制以外にも,電位依存性ナトリウムチャネルの阻害作用,フリーラジカル消去作用,抗アポトーシス作用,神経栄養作用など多岐にわたる薬理効果を有することと,MSAの疾患モデルであるαシヌクレイン変異マウスに対し,一部神経症状の改善をもたらしたことが挙げられる(しかし確固たる根拠があってこの薬剤が選ばれたというわけではないようだ).
方法は,30歳以上で発症し,1年以上持続する無動・筋強剛(akinesia-rigidity syndrome)を呈する症例のうち,PSPないしMSAのinclusion criteriaを満たす症例を対象とした(NNIPPS criteriaという新しい診断基準を作成した).primary end-pointは生存,secondary end-pointは運動機能スケールの低下速度とした.必要症例数はPSPおよびMSAの各群の死亡の相対危険度の40%減少を検出できるように設定した.患者を実薬群(50-200mg/day)と偽薬群に分け,36か月にわたり経過観察した.
結果として767名が無作為に割りつけられ,そのうち760名に対しIntent To Treat (ITT) 解析が行われた(層別解析ではPSPが362名,MSAが398名であった).経過観察の中央値は1095日(249~1095日)であった.経過観察中,342名が死亡し,うち112名で剖検が行われた.リルゾールの効果に関しては,PSPおよびMSAいずれの群においても生存に対する有効性は認められなかった.同様に運動機能の低下に関しても効果はなかった.特に問題となる副作用もなかった.剖検症例をもとにNNIPPS 診断基準の妥当性が検討されたが,非常に確度が高いことが分かり,この診断基準は今後の治療研究に十分使用できるものであると考えられた.
以上のような結果で,残念ながらリルゾールはPSPやMSA(MSA-P)に無効であったわけだが(調べてみると,パーキンソン病やハンチントン病,ニューロパチック・ペインでもランダム化比較試験が行われていて,いずれも無効であった),それでもこの論文を取り上げたのは,病態解明に関する基礎研究の途上で,まだ十分にその病態機序が分からなくても,可能性があるのであれば,きちんと計画された大規模研究ならchallengeしてみても良いという考えもあるのだということを認識したことと,そのためには大規模な臨床研究を計画するスキルをこれからの臨床医は身につける必要があるということである.とくに後者については一部の大学ではそのような勤務医向けの講義を行っているところもあるようである(しかし残念ながらまだ稀である).ぜひ若いドクターには基礎研究のみでなく,積極的に臨床研究のデザインの仕方や評価の仕方について学んでほしい.
Brain. 2008 Nov 23. [Epub ahead of print]

追伸;忙しくて更新する余力がなかったのですが,新年になりましたのでまた頑張ろうと思います.本年もどうぞ宜しくお願いいたします.











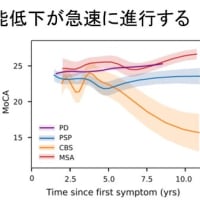
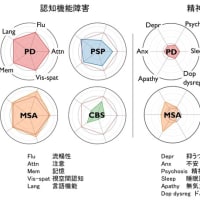


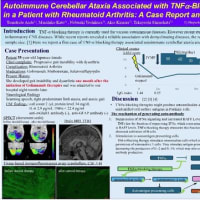










大学を離れるとなかなか原著を読む時間がとれないのが悩みの種です。
臨床に根ざした視点から、面白い論文を紹介いただき、楽しく読ませていただいています。
今後も宜しくお願い申し上げます。