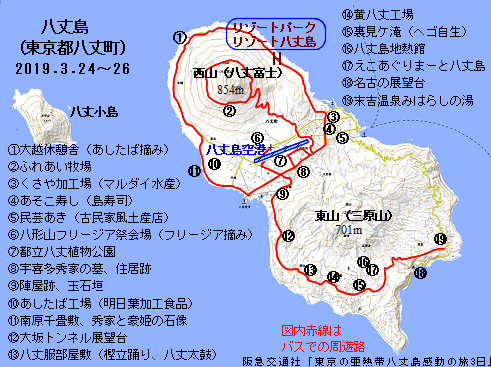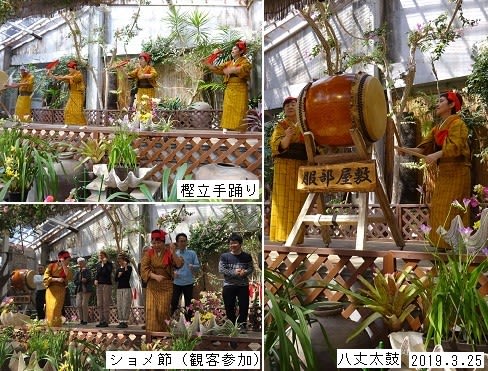セリ科シシウド属のアシタバ(明日葉)、似たハマウドも同様の場所で見られます。
見分けは、茎を切った際に出る汁の色で、アシタバは黄色、ハマウドは白色です。

始めて見る植物が多く、「八丈島の植物ガイドブック」にお世話になりました。
バラ科キイチゴ属のカジイチゴとハチジョウクサイチゴ(八丈草苺)です。
見分けは、前者は葉が掌状に3-7中裂で茎に刺無。後者は葉が3小葉で茎に刺有。

スミレ科スミレ属のシチトウスミレ(七島菫)、タチツボスミレの変種です。
母種に比べ、葉に光沢があり、托葉が大きく切れ込みが粗い特徴が見られます。

スミレ科スミレ属のアツバスミレ(厚葉菫)、スミレの海洋型だそうです。
母種に比べ、葉が厚く光沢があり、シチトウスミレとともに多く見られます。
両者の見分けは、茎の有無、葉の形、柱頭の形、側弁の毛の有無などです。

タデ科イタドリ属のハチジョウイタドリ(八丈虎杖)、イタドリの変種です。
母種に比べ、大型で葉に光沢があるとのことで、確かに光っています。

アジサイ属のガクアジサイとラセイタタマアジサイ(羅背板玉紫陽花)?
花がない時期ですが、葉の大きさや厚さ、ざらざら感からラセイタ・・かな。
ラセイタタマアジサイはタマアジサイの変種で、伊豆諸島固有種だそうです。

キブシ科キブシ属のハチジョウキブシ(八丈木五倍子)です。
キブシに比べ、花序が大きく、ごつい花だなあと思って調べてみると本種でした。

ウコギ科タラノキ属のシチトウタラノキ(七島楤木)、タラノキの変種です。
伊豆諸島固有種で、茎や葉にほとんど刺がないのが特徴です。

カヤツリグサ科の伊豆諸島固有種は、ハチジョウカンスゲやオオシマカンスゲ。
シダ植物は、大きなヘゴから、小さな伊豆諸島固有種のハチジョウウラボシ。
帰化植物も多く、アカバナルリハコベやマツバウンランが花盛りでした。

バラ科サクラ属のオオシマザクラ(大島桜)、伊豆諸島準固有種です。
ソメイヨシノの親であり、桜餅の葉にも使われなど、人と関りの深いサクラです。
主な特徴は、葉、花、芽などが無毛、葉の鋸歯の先が糸状に伸びることです。