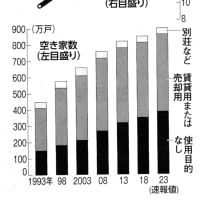動物の食べ物の内訳を表現するには占有率が使われますが、普通はその平均値で表現されます。しかし、例えば同じ平均値50%でも、半分の試料が 100%を占めていて、残りの半分が0% でも、平均値50%になりますし、全てのサンプルが 50%を占めていても 平均値 同じ50%です。同じ50%でもこの二つは意味が違います。そこで私は「占有率順位曲線」という表現方法を開発しました。これはサンプルごとに 占有率の大きいものから小さいものへ順番に並べたものです。これを使う 平均値だけでは表現できなかった内容が表現できるのです。今回の浦和のタヌキの場合の曲線を説明します。

カーブの形として特徴的なのは果実、種子でほぼ直線的に下がっています。これはほとんどのタヌキが果実を食べたということで、最高値はほぼ100%です。Dの植物の支持組織は茎や枝などで、L字型ですが、これは一部のタヌキはたくさん食べたが、多くのタヌキは少ししか食べていないということで、春に一部のタヌキが好んで食べるようです。Bの昆虫もL字型ですが、最高値は低めです。昆虫はどこにでもいるのですが、小さいのでまとまった量は食べられないのだと思います。Eの作物と人工物はLというよりIに近い形で、出現頻度が低いことを示しています。これらは供給が限られ、見つかれば好んで食べますが、そういう事例は少ないことを示しています。その他のものは最高ちも低く、頻度も低いのであまり重要な食物とは言えないものです。ただしDの葉は頻度はかなり高く、供給量は多いがタヌキが好んでは食べないことを示しています。
このように占有率-順位曲線でわかることがありました。