のんびり気軽にさんぽがてら。
本日は京都は右京区の「常寂光寺(じょうじゃっこうじ)」です。
…読み方合ってるよね?ね?
久々に行ってきました、京都。
いやー、やっぱりいいトコロです。またいつか住みたいですね。
今年の真夏の炎天下なら、がらがらかなーって思いましたが、やっぱりお客さんはおりました。
(↑当たり前か)
今回は三千院方面へ出向きましたんで、また機会あったら順次紹介していきたいと思います。
そんなこんなで、右京区は「常寂光寺」ですね。
開山は「日禎上人(にっしん・しょうにん)」です。
その「日禎上人」は大納言「広橋国光」の子として、永禄四年(1561)に誕生しました。
(※広橋家[ひろはしけ]:文官の家柄である名家、公家。藤原北家日野流。十三名家の一つ)
近い事件としては、「桶狭間合戦」が永禄三年(1560)なんで、新しい戦国の風が吹いた頃のことです。
ちなみに、日野家ニ十八代当主に「日野輝資(ひの・てるすけ)」という方がおりますが、持てる資料で調べた結果別人みたいでした。
兄弟なのかな?
ともかく、「日禎上人」は幼い頃に日蓮宗の大本山「本圀寺」に入れられ、なんとわずか十八歳にして法灯を継いでいるのです。
「法灯を継ぐ」ってーのは、後継者みたいな意味ですから、”宗学と歌道への造詣深く”という一文はあながち誇張とか冗談ではなさそう。
それだけでなく、若き秀才は人気面でも人並み外れており、虎退治で有名な「加藤清正」、関ヶ原で歴史的寝返りをした「小早川秀秋」、秀吉の実姉「日秀」などの戦国武将から京都町衆に至るまで多くの帰依者がいたのです。
しかし、天下人「豊臣秀吉」の出仕に応じなかったことから「本圀寺」を離れ、隠棲することとしたのでした。
この時の「日禎上人」は不受不施(ふじゅ・ふせ)という、「信者以外からの施しは受けず,また他宗の者には施しをしない」というある意味理にかなった、ある意味頑固な教えを守ったためであるようです。
日蓮宗にはこちらを教義とした宗派もあり、江戸幕府から邪宗として弾圧されています。
ともかく、隠棲することとした時代の秀才「日禎上人」の選んだ土地が、もとは百人一首の選者として名高い「藤原定家」の山荘「時雨亭」付近であるらしい、小倉山の中腹であるこちらなのでした。
(注:現在残っている「時雨亭」はこの付近にあったんだよーっ、て建てられたもので当時のものではありません)
京都の豪商「角倉了以(すみのくら・りょうい)」、角倉家宗家「角倉栄可(すみのくら・えいか)」らが土地を寄進し、「小早川秀秋」ら各武将たちが建立に寄与したのです。
隠棲の庵は後に寺へと改められ「常寂光寺」となるのでした。
看板の文句をそのまま借りると、幽雅閑寂(ゆうが・かんじゃく)で、日蓮宗の教義にある「常寂光土(じょうじゃっこうど)」の観があるところから、「常寂光寺」という寺名がつけられたのです。
四字熟語連発でなんだか分かりづらいですね。
えーっと、静かで趣が深く上品な雰囲気で、仏の悟りである真理そのものが具現しているような、最高の世界っぽいんだよーということみたいです。
物凄いベタ褒めですよ。
こちらの仁王門はちゃっかり元居た「本圀寺」から移築された、南北朝時代もの。
(※解体修理はされていますが、基本的には同時代)
安置されている仁王像は運慶作で「長源寺」より移されたもの。
さらに本堂は桃山城・客殿からの一部を移築・修造したもの。
色々なところから拝借してます。
元和六年(1620)だから…江戸時代建立の多宝塔(※写真)はオリジナルで重文。
当時の京都町衆の財力をしのばせるほど秀麗なものなんだって。
また、京都屈指の紅葉の名所として知られ、山の斜面と合った景色が大変に良いそうですが…ひでるさん行ったのはやっぱり真夏で空いている時期なのでした。
ひでるさんが行った時はものすごーく色気ない、地味パンフレットでしたが、こちら変わったでしょうか?
もしそのままなら、少し頑張った方が良いと思われますが。

[住所]
常寂光寺 京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3
★宜しければ応援クリックお願いします。 ⇒ 【人気blogランキング】
※そんなこんなで写真集も出ている「常寂光寺」です。
お寺の四季風景というのは、なにゆえこんなにいいもんなんでしょうか?
本日は京都は右京区の「常寂光寺(じょうじゃっこうじ)」です。
…読み方合ってるよね?ね?
久々に行ってきました、京都。
いやー、やっぱりいいトコロです。またいつか住みたいですね。
今年の真夏の炎天下なら、がらがらかなーって思いましたが、やっぱりお客さんはおりました。
(↑当たり前か)
今回は三千院方面へ出向きましたんで、また機会あったら順次紹介していきたいと思います。
そんなこんなで、右京区は「常寂光寺」ですね。
開山は「日禎上人(にっしん・しょうにん)」です。
その「日禎上人」は大納言「広橋国光」の子として、永禄四年(1561)に誕生しました。
(※広橋家[ひろはしけ]:文官の家柄である名家、公家。藤原北家日野流。十三名家の一つ)
近い事件としては、「桶狭間合戦」が永禄三年(1560)なんで、新しい戦国の風が吹いた頃のことです。
ちなみに、日野家ニ十八代当主に「日野輝資(ひの・てるすけ)」という方がおりますが、持てる資料で調べた結果別人みたいでした。
兄弟なのかな?
ともかく、「日禎上人」は幼い頃に日蓮宗の大本山「本圀寺」に入れられ、なんとわずか十八歳にして法灯を継いでいるのです。
「法灯を継ぐ」ってーのは、後継者みたいな意味ですから、”宗学と歌道への造詣深く”という一文はあながち誇張とか冗談ではなさそう。
それだけでなく、若き秀才は人気面でも人並み外れており、虎退治で有名な「加藤清正」、関ヶ原で歴史的寝返りをした「小早川秀秋」、秀吉の実姉「日秀」などの戦国武将から京都町衆に至るまで多くの帰依者がいたのです。
しかし、天下人「豊臣秀吉」の出仕に応じなかったことから「本圀寺」を離れ、隠棲することとしたのでした。
この時の「日禎上人」は不受不施(ふじゅ・ふせ)という、「信者以外からの施しは受けず,また他宗の者には施しをしない」というある意味理にかなった、ある意味頑固な教えを守ったためであるようです。
日蓮宗にはこちらを教義とした宗派もあり、江戸幕府から邪宗として弾圧されています。
ともかく、隠棲することとした時代の秀才「日禎上人」の選んだ土地が、もとは百人一首の選者として名高い「藤原定家」の山荘「時雨亭」付近であるらしい、小倉山の中腹であるこちらなのでした。
(注:現在残っている「時雨亭」はこの付近にあったんだよーっ、て建てられたもので当時のものではありません)
京都の豪商「角倉了以(すみのくら・りょうい)」、角倉家宗家「角倉栄可(すみのくら・えいか)」らが土地を寄進し、「小早川秀秋」ら各武将たちが建立に寄与したのです。
隠棲の庵は後に寺へと改められ「常寂光寺」となるのでした。
看板の文句をそのまま借りると、幽雅閑寂(ゆうが・かんじゃく)で、日蓮宗の教義にある「常寂光土(じょうじゃっこうど)」の観があるところから、「常寂光寺」という寺名がつけられたのです。
四字熟語連発でなんだか分かりづらいですね。
えーっと、静かで趣が深く上品な雰囲気で、仏の悟りである真理そのものが具現しているような、最高の世界っぽいんだよーということみたいです。
物凄いベタ褒めですよ。
こちらの仁王門はちゃっかり元居た「本圀寺」から移築された、南北朝時代もの。
(※解体修理はされていますが、基本的には同時代)
安置されている仁王像は運慶作で「長源寺」より移されたもの。
さらに本堂は桃山城・客殿からの一部を移築・修造したもの。
色々なところから拝借してます。
元和六年(1620)だから…江戸時代建立の多宝塔(※写真)はオリジナルで重文。
当時の京都町衆の財力をしのばせるほど秀麗なものなんだって。
また、京都屈指の紅葉の名所として知られ、山の斜面と合った景色が大変に良いそうですが…ひでるさん行ったのはやっぱり真夏で空いている時期なのでした。
ひでるさんが行った時はものすごーく色気ない、地味パンフレットでしたが、こちら変わったでしょうか?
もしそのままなら、少し頑張った方が良いと思われますが。

[住所]
常寂光寺 京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3
★宜しければ応援クリックお願いします。 ⇒ 【人気blogランキング】
 | 常寂光寺の四季―水野克比古写真集 (京・古社寺巡礼) 水野 克比古 (2006/05) 東方出版 この商品の詳細を見る |
※そんなこんなで写真集も出ている「常寂光寺」です。
お寺の四季風景というのは、なにゆえこんなにいいもんなんでしょうか?
































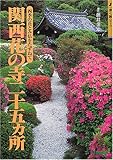



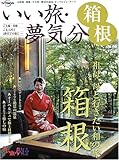




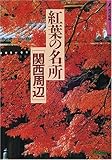








 」(※雨の女神「弥都波能売神(みづはのめ・のかみ))としか縁結ばれていませんが?
」(※雨の女神「弥都波能売神(みづはのめ・のかみ))としか縁結ばれていませんが?



