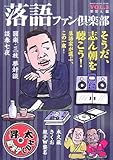のんびり気軽にさんぽがてら。
本日は京都は東山区の「大雲院」です。
ひでるさんの不確かな記憶では…自転車でえっちらおっちら坂を上った先にあったんですが、なんだか入れませんでした。
その↓写真は「なんだよー」と思って覗いたらお釈迦様が寝てらした(※涅槃像ですね)ので、写真を撮ってみたのです。
調べてみたら、通常は非公開なお寺でした。しかし、特別公開はあるようです。
あるいは、事前に申し込めば見られるのかもしれません。…なんかね、どちらかのサイトにそう書いてありました(笑)
本当かどうか確かめてはいないので、一応↓電話してみてね。
ひでるさんの言葉を鵜呑みにすると、きっと後悔しますよぉー。
そんな訳で実際中は見ていないですが「大雲院」です。
「龍池山大雲院(りゅうちざん・だいうんいん)」が正式名称。
天正十五年(1587)
信長の後継者たる地位を確保した「豊臣秀吉」が九州へ兵を進めている頃のこと。
こちらは「本能寺」で横死した「織田信長・信忠」親子の菩提を弔うため建立されました。
「正親町天皇」の勅命により、「御池御所」(※烏丸二条南)を賜った貞安(ていあん)上人が開山です。
なお、寺名は嫡男「織田信忠」の法名「大雲院仙巌」に因んだもので、山号は封建の地に由来しているのでした。
この「貞安上人」は法華宗と浄土宗との間で争われた安土宗論(あづちしゅうろん)にも加わっていたようなので、その縁からのご指名だったのかもしれませんね。
天正十八年(1590)
それから三年後。
この頃には小田原・北条氏を降伏させており、ほぼ天下統一となっておりました。
(※太閤になるのは次の年)
「豊臣秀吉」は都市計画とより広い寺域確保を目的とし、「大雲院」は寺町四条南に移されてしまうのです。
しかし「後陽成天皇」にも保護された「大雲院」そのは勅願所となり、十四の堂塔を有する名門寺院となったんですが、四条付近が商業地として発展するなかで昭和四十八年に現在の地へ移転されるのでした。
本堂背後の山鉾を模した、ちょっと形が特殊で目立つ塔は「祇園閣」というんだって。
また、元の四条にあった広大な寺域からは小学校が設立(永松小学校)されたんだとか。
本尊の「阿弥陀如来像」は大きなもので、墓地には「織田信長・信忠」父子の碑や「石川五右衛門」の墓があるんだって。
ちょっと行ってみたくありませんか?

[関連記事]
⇒ 人間五十年…の幸若舞「敦盛」
⇒ 迷う明智光秀「おみくじを引く人間心理」
⇒ 明智光秀の誤算「歴史を動かした手紙」
⇒ 謀反の理由は?「本能寺跡地」
⇒ 意外と知らない信長死後 「清洲会議」 [1 2 3 4 5]
⇒ お釈迦様・釈迦如来 (1・2・3・4・5・6)
[住所]
大雲院 京都市東山区祇園町南側594-1 (075-531-5018)
★宜しければ応援クリックお願いします。 ⇒ 【人気blogランキング】
※なんだか、名前だけだと斬鉄剣(漢字合ってるかな?)持っている方を思い出しちゃいますね。
あるいは…コナミ?
本日は京都は東山区の「大雲院」です。
ひでるさんの不確かな記憶では…自転車でえっちらおっちら坂を上った先にあったんですが、なんだか入れませんでした。
その↓写真は「なんだよー」と思って覗いたらお釈迦様が寝てらした(※涅槃像ですね)ので、写真を撮ってみたのです。
調べてみたら、通常は非公開なお寺でした。しかし、特別公開はあるようです。
あるいは、事前に申し込めば見られるのかもしれません。…なんかね、どちらかのサイトにそう書いてありました(笑)
本当かどうか確かめてはいないので、一応↓電話してみてね。
ひでるさんの言葉を鵜呑みにすると、きっと後悔しますよぉー。
そんな訳で実際中は見ていないですが「大雲院」です。
「龍池山大雲院(りゅうちざん・だいうんいん)」が正式名称。
天正十五年(1587)
信長の後継者たる地位を確保した「豊臣秀吉」が九州へ兵を進めている頃のこと。
こちらは「本能寺」で横死した「織田信長・信忠」親子の菩提を弔うため建立されました。
「正親町天皇」の勅命により、「御池御所」(※烏丸二条南)を賜った貞安(ていあん)上人が開山です。
なお、寺名は嫡男「織田信忠」の法名「大雲院仙巌」に因んだもので、山号は封建の地に由来しているのでした。
この「貞安上人」は法華宗と浄土宗との間で争われた安土宗論(あづちしゅうろん)にも加わっていたようなので、その縁からのご指名だったのかもしれませんね。
天正十八年(1590)
それから三年後。
この頃には小田原・北条氏を降伏させており、ほぼ天下統一となっておりました。
(※太閤になるのは次の年)
「豊臣秀吉」は都市計画とより広い寺域確保を目的とし、「大雲院」は寺町四条南に移されてしまうのです。
しかし「後陽成天皇」にも保護された「大雲院」そのは勅願所となり、十四の堂塔を有する名門寺院となったんですが、四条付近が商業地として発展するなかで昭和四十八年に現在の地へ移転されるのでした。
本堂背後の山鉾を模した、ちょっと形が特殊で目立つ塔は「祇園閣」というんだって。
また、元の四条にあった広大な寺域からは小学校が設立(永松小学校)されたんだとか。
本尊の「阿弥陀如来像」は大きなもので、墓地には「織田信長・信忠」父子の碑や「石川五右衛門」の墓があるんだって。
ちょっと行ってみたくありませんか?

[関連記事]
⇒ 人間五十年…の幸若舞「敦盛」
⇒ 迷う明智光秀「おみくじを引く人間心理」
⇒ 明智光秀の誤算「歴史を動かした手紙」
⇒ 謀反の理由は?「本能寺跡地」
⇒ 意外と知らない信長死後 「清洲会議」 [1 2 3 4 5]
⇒ お釈迦様・釈迦如来 (1・2・3・4・5・6)
[住所]
大雲院 京都市東山区祇園町南側594-1 (075-531-5018)
★宜しければ応援クリックお願いします。 ⇒ 【人気blogランキング】
 | 石川五右衛門 岡村 和雄 (2004/04) 新風舎 この商品の詳細を見る |
あるいは…コナミ?