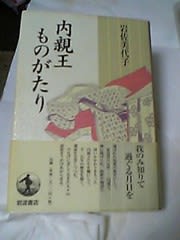本日は、激動の時代の中、波瀾の生涯を送った天皇について書かれたこの本を紹介します。
☆史伝 後鳥羽院
著者=目崎徳衞 発行=吉川弘文館 税込価格=2,730円
☆本の内容紹介
異数の幸運によって帝位につき、天衣無縫の活動をしながら、一転して絶海の孤島に生を閉じた後鳥羽院の生涯を、史実に基づき描き出す。和歌などの才能にあふれた多芸多能な側面にもふれ、生き生きとした人間像に迫る。
[目次]
起の巻
棺を蓋いて事定まらず/運命の四の宮/幼帝と権臣/十代の太上天皇
承の巻
和歌への出発/『新古今集』成る/秀歌と秘曲/狂連歌と院近臣/鞠を蹴り武技を練り/習礼と歌論
転の巻
北条殿か北条丸か/はこやの山の影/治天の君の苦悩/内裏再建の強行と抵抗/敗者の運命
結の巻
『遠島御百首』の世界/人それぞれの戦後/歌道・仏道三昧の晩年/氏王
この本は、長年にわたって後鳥羽院を研究して来られた目崎先生による後鳥羽院(1180~1239)の伝記です。後鳥羽院の生涯だけでなく、その時代背景、周囲の人々の動向にも触れられていて大変読み応えがあると思います
彼は、以仁王の謀反の年に生まれ、4歳の時に、安徳天皇を奉じての平家の都落ちによって思いがけず皇位につきます。つまり、大変な幸運の星の下に生まれた…と言っても良い人物でした。そんな後鳥羽天皇は十代後半で土御門天皇に譲位します。その頃から側近の源通親によって和歌の道を教えられ、やがて夢中になっていきます。和歌への熱中が、やがて「新古今和歌集」を編む原動力となるわけです。それと同時に蹴鞠に熱中したり、石清水八幡宮に徒歩で登山したりもしていますので、文武両道に優れているという印象を受けます。
また、この本は寵愛していた女房に死なれた後鳥羽院が、彼女を偲ぶ歌を詠むところから始まっていますので、なかなか情の厚い生年…というイメージも受けました。
しかしそればかりではなく、後鳥羽院は宮中の古い行事を復興させたりもしています。つまり彼は、朝廷の権威を取り戻そうとしていたのでした。そんな彼が新興勢力の鎌倉幕府と戦うことになる……これはごく自然なことだったかもしれません。
さらにこの本では、承久の変に至る朝廷の動きだけではなく、鎌倉幕府の動きにも詳しく触れられています。そして、戦いに敗れ、隠岐に流された後鳥羽院の晩年についても焦点が当てられています。後鳥羽院は孤独に耐えながら、「新古今和歌集」の改訂版を編むことになるのですが、彼にとって和歌がどんなに慰めになっていたかがひしひしと伝わって来るようで、切なくもあります。
こうしてみると、後鳥羽院の生涯は源平合戦に始まり、鎌倉幕府の開幕から承久の変に至るまでの激動の時代を生き抜いた、波瀾の生涯だったと言えそうです。この本ではそんな後鳥羽院の生涯が、激動の時代と重ね合わせて描かれています。研究書という色の濃い本ですが、色々なエピソードも織り込まれていますし(私は、後鳥羽院と皇位を争った三の宮惟明親王のその後と、後鳥羽院のご落胤で、父とは対照的な生き方をした氏王が大変興味深かったです。)、詳しい注釈もついています。後鳥羽院や、鎌倉時代初期について知りたい方にはお薦めです。
☆トップページに戻る
☆史伝 後鳥羽院
著者=目崎徳衞 発行=吉川弘文館 税込価格=2,730円
☆本の内容紹介
異数の幸運によって帝位につき、天衣無縫の活動をしながら、一転して絶海の孤島に生を閉じた後鳥羽院の生涯を、史実に基づき描き出す。和歌などの才能にあふれた多芸多能な側面にもふれ、生き生きとした人間像に迫る。
[目次]
起の巻
棺を蓋いて事定まらず/運命の四の宮/幼帝と権臣/十代の太上天皇
承の巻
和歌への出発/『新古今集』成る/秀歌と秘曲/狂連歌と院近臣/鞠を蹴り武技を練り/習礼と歌論
転の巻
北条殿か北条丸か/はこやの山の影/治天の君の苦悩/内裏再建の強行と抵抗/敗者の運命
結の巻
『遠島御百首』の世界/人それぞれの戦後/歌道・仏道三昧の晩年/氏王
この本は、長年にわたって後鳥羽院を研究して来られた目崎先生による後鳥羽院(1180~1239)の伝記です。後鳥羽院の生涯だけでなく、その時代背景、周囲の人々の動向にも触れられていて大変読み応えがあると思います
彼は、以仁王の謀反の年に生まれ、4歳の時に、安徳天皇を奉じての平家の都落ちによって思いがけず皇位につきます。つまり、大変な幸運の星の下に生まれた…と言っても良い人物でした。そんな後鳥羽天皇は十代後半で土御門天皇に譲位します。その頃から側近の源通親によって和歌の道を教えられ、やがて夢中になっていきます。和歌への熱中が、やがて「新古今和歌集」を編む原動力となるわけです。それと同時に蹴鞠に熱中したり、石清水八幡宮に徒歩で登山したりもしていますので、文武両道に優れているという印象を受けます。
また、この本は寵愛していた女房に死なれた後鳥羽院が、彼女を偲ぶ歌を詠むところから始まっていますので、なかなか情の厚い生年…というイメージも受けました。
しかしそればかりではなく、後鳥羽院は宮中の古い行事を復興させたりもしています。つまり彼は、朝廷の権威を取り戻そうとしていたのでした。そんな彼が新興勢力の鎌倉幕府と戦うことになる……これはごく自然なことだったかもしれません。
さらにこの本では、承久の変に至る朝廷の動きだけではなく、鎌倉幕府の動きにも詳しく触れられています。そして、戦いに敗れ、隠岐に流された後鳥羽院の晩年についても焦点が当てられています。後鳥羽院は孤独に耐えながら、「新古今和歌集」の改訂版を編むことになるのですが、彼にとって和歌がどんなに慰めになっていたかがひしひしと伝わって来るようで、切なくもあります。
こうしてみると、後鳥羽院の生涯は源平合戦に始まり、鎌倉幕府の開幕から承久の変に至るまでの激動の時代を生き抜いた、波瀾の生涯だったと言えそうです。この本ではそんな後鳥羽院の生涯が、激動の時代と重ね合わせて描かれています。研究書という色の濃い本ですが、色々なエピソードも織り込まれていますし(私は、後鳥羽院と皇位を争った三の宮惟明親王のその後と、後鳥羽院のご落胤で、父とは対照的な生き方をした氏王が大変興味深かったです。)、詳しい注釈もついています。後鳥羽院や、鎌倉時代初期について知りたい方にはお薦めです。
☆トップページに戻る