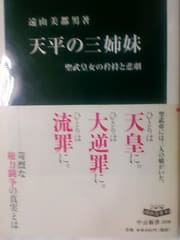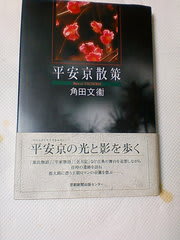今回は、奈良時代を扱った歴史評論の紹介です。
☆天平の三姉妹 ー聖武皇女の矜持と悲劇
著者=遠山美都男 発行=中央公論新社・中公新書2038 価格=882円
☆本の内容
聖武天皇には三人の娘がいた。生涯不婚を定められ、孝謙天皇(重祚して称徳天皇)となって権力を振るった阿倍内親王。光仁天皇の皇后でありながら、夫を呪詛したとして大逆罪に処された井上内親王。恵美押勝の乱に加わった夫を失った後、息子たちの謀反に連坐、流罪とされて没年すら伝わらない不破内親王。凄惨な宮廷闘争の背景にあったのは何か―。皇位継承の安定のために人生を翻弄された三人の皇女の物語。
[目次]
序章 松虫寺の墓碑銘
第1章 三姉妹の誕生
第2章 それぞれの出発
第3章 塩焼王流刑
第4章 遺詔
第5章 道祖王、杖下に死す
第6章 今帝、湖畔に果つ
第7章 姉妹の同床異夢
第8章 皇后の大逆罪
第9章 返逆の近親
終章 松虫姫のゆくえ
今年2010年は、平城遷都1300年に当たる記念すべき年ということで、奈良では色々な記念行事やイベントが行われているそうです。
私は奈良には、中学校の修学旅行で1回、行っただけなので、これを機に行ってみたいと思っているのですが、予定が立たずになかなか実行できないでいます。せめて、奈良時代の歴史の本を読んでみたいと思って、この本を手に取ってみました。
この、「天平の三姉妹」は、聖武天皇の3人の皇女、阿倍内親王(後の孝謙・称徳天皇)、井上内親王(後の光仁天皇皇后)、不破内親王(後の塩焼王妃)の生涯を時系列順にたどった本です。専門の先生が史料に基づいて書かれているので小説ではありませんが、所々物語風な書き方をしている箇所もあり、そういう意味では、山本淳子先生の「源氏物語の時代 ー一条天皇と后たちのものがたり」の奈良時代版という印象を受けました。
この本で一番嬉しかったことは、序章に書かれている不破内親王がモデルだとされる松虫姫の伝説を初め、不破内親王に多くのスペースが割かれていたことです。
女帝になった阿倍内親王や、伊勢斎王から光仁天皇の皇后になった井上内親王については、様々な本で取り上げられていますが、不破内親王について取り上げられた本って今まであまりなかったですよね。
実は不破内親王という方は、生年も没年もはっきりしないのだそうです。
後に天武天皇の孫に当たる塩焼王と結婚するのですが、聖武天皇がなぜ、塩焼王を不破内親王の夫に定めたか、この本で興味深い考察がされていました。
この時代の天皇の継承者は、天智・天武両天皇の血を受けている草壁皇子の子孫であることが条件だったそうです。確かに聖武天皇は草壁皇子の孫ですものね。
更に、聖武天皇の時代になると、藤原鎌足の子孫であることもブランドであり、天皇になる重要な条件の一つでした。そのようなわけで聖武天皇は、藤原不比等の娘、光明皇后を母に持つ阿倍内親王を、皇女でありながら自分の皇太子に立てたのです。
しかし、困ったのはそのあとです。女帝は結婚できないという不文律がありましたから…。そこで目をつけたのが塩焼王だった…ということです。
と言うのは、塩焼王は天智天皇の血は引いていませんが、父の新田部親王の母、五百重娘は鎌足の娘、つまり、れっきとした鎌足の子孫なのです。それで聖武天皇は、塩焼王を不破内親王と結婚させることによって、阿倍内親王の次の皇位継承者にしようとしたようなのですよね。
しかし、この計画は残念ながら失敗に終わります。塩焼王はやがて、罪を犯して流罪になってしまいます。どのような罪だったのかは不明ですが、この本では、塩焼王が聖武天皇側近の女官と密通したのではないか…と推察されていました。非常に納得という感じでした。
その後不破内親王は、恵美押勝の乱に加わった塩焼王との死別、承徳女帝を呪詛したことによって平城京から追放、赦されて帰京したものの、数年後に息子の氷上川継の謀反に連座して淡路国に流罪と、波乱に富んだ生涯を送るのですが、上でも書きましたように没年は不明です。平安遷都の翌年、延暦十四年(795)に、淡路国から和泉国に移されたことが記録されているので、その頃までは生きていたということになりますが…。
ただ、伊豆国に流されていた息子の川継は、延暦二十四年(805)に赦されて、後に官界に復帰している(このことは知りませんでした)ので、それだけは救いですね。
もちろんこの本には、不破内親王のことだけでなく、阿倍内親王や井上内親王についても詳しく書かれています。彼女たちはいずれも過酷な生涯を送りましたが、与えられた運命を受け入れ、精一杯生きたように思えます。
また、彼女たちの周辺人物や、奈良時代の政変についても詳細に解説されていますので、奈良時代の歴史のこともよくわかると思います。特に、奈良時代の皇位継承争いは苛烈で、そこがまた興味をそそられたりします。
それから、私はこの本を読んで、聖武天皇のイメージが変わりました。
聖武天皇というと、気の強い光明皇后の尻に敷かれた、ちょっと気の弱い天皇というイメージだったのですが、なかなか芯のしっかりした、個性的な天皇というイメージに変わりました。
考えてみると聖武天皇は、皇女を皇太子にしたこと、東大寺にあれだけ大きな仏像を作ったことなど、型破りな事をたくさんやっています。
また聖武天皇は、孝謙女帝となった阿倍内親王に向かって、「王を臣下にするのも、臣下を王にするのも、そなたの好きなようにすればよい。」とも言っていたそうで、これが道鏡を天皇にしようとしたことへもつながっていくのです。やはり、聖武天皇はただものではないかもしれません。
このように、「天平の三姉妹」は、3人の皇女の人生をたどりながら、奈良時代の歴史に触れることが出来る1冊です。平城遷都1300年のこの機会にぜひ堪能してみて下さい。
☆コメントを下さる方は掲示板へお願いいたします。
☆トップページに戻る
☆天平の三姉妹 ー聖武皇女の矜持と悲劇
著者=遠山美都男 発行=中央公論新社・中公新書2038 価格=882円
☆本の内容
聖武天皇には三人の娘がいた。生涯不婚を定められ、孝謙天皇(重祚して称徳天皇)となって権力を振るった阿倍内親王。光仁天皇の皇后でありながら、夫を呪詛したとして大逆罪に処された井上内親王。恵美押勝の乱に加わった夫を失った後、息子たちの謀反に連坐、流罪とされて没年すら伝わらない不破内親王。凄惨な宮廷闘争の背景にあったのは何か―。皇位継承の安定のために人生を翻弄された三人の皇女の物語。
[目次]
序章 松虫寺の墓碑銘
第1章 三姉妹の誕生
第2章 それぞれの出発
第3章 塩焼王流刑
第4章 遺詔
第5章 道祖王、杖下に死す
第6章 今帝、湖畔に果つ
第7章 姉妹の同床異夢
第8章 皇后の大逆罪
第9章 返逆の近親
終章 松虫姫のゆくえ
今年2010年は、平城遷都1300年に当たる記念すべき年ということで、奈良では色々な記念行事やイベントが行われているそうです。
私は奈良には、中学校の修学旅行で1回、行っただけなので、これを機に行ってみたいと思っているのですが、予定が立たずになかなか実行できないでいます。せめて、奈良時代の歴史の本を読んでみたいと思って、この本を手に取ってみました。
この、「天平の三姉妹」は、聖武天皇の3人の皇女、阿倍内親王(後の孝謙・称徳天皇)、井上内親王(後の光仁天皇皇后)、不破内親王(後の塩焼王妃)の生涯を時系列順にたどった本です。専門の先生が史料に基づいて書かれているので小説ではありませんが、所々物語風な書き方をしている箇所もあり、そういう意味では、山本淳子先生の「源氏物語の時代 ー一条天皇と后たちのものがたり」の奈良時代版という印象を受けました。
この本で一番嬉しかったことは、序章に書かれている不破内親王がモデルだとされる松虫姫の伝説を初め、不破内親王に多くのスペースが割かれていたことです。
女帝になった阿倍内親王や、伊勢斎王から光仁天皇の皇后になった井上内親王については、様々な本で取り上げられていますが、不破内親王について取り上げられた本って今まであまりなかったですよね。
実は不破内親王という方は、生年も没年もはっきりしないのだそうです。
後に天武天皇の孫に当たる塩焼王と結婚するのですが、聖武天皇がなぜ、塩焼王を不破内親王の夫に定めたか、この本で興味深い考察がされていました。
この時代の天皇の継承者は、天智・天武両天皇の血を受けている草壁皇子の子孫であることが条件だったそうです。確かに聖武天皇は草壁皇子の孫ですものね。
更に、聖武天皇の時代になると、藤原鎌足の子孫であることもブランドであり、天皇になる重要な条件の一つでした。そのようなわけで聖武天皇は、藤原不比等の娘、光明皇后を母に持つ阿倍内親王を、皇女でありながら自分の皇太子に立てたのです。
しかし、困ったのはそのあとです。女帝は結婚できないという不文律がありましたから…。そこで目をつけたのが塩焼王だった…ということです。
と言うのは、塩焼王は天智天皇の血は引いていませんが、父の新田部親王の母、五百重娘は鎌足の娘、つまり、れっきとした鎌足の子孫なのです。それで聖武天皇は、塩焼王を不破内親王と結婚させることによって、阿倍内親王の次の皇位継承者にしようとしたようなのですよね。
しかし、この計画は残念ながら失敗に終わります。塩焼王はやがて、罪を犯して流罪になってしまいます。どのような罪だったのかは不明ですが、この本では、塩焼王が聖武天皇側近の女官と密通したのではないか…と推察されていました。非常に納得という感じでした。
その後不破内親王は、恵美押勝の乱に加わった塩焼王との死別、承徳女帝を呪詛したことによって平城京から追放、赦されて帰京したものの、数年後に息子の氷上川継の謀反に連座して淡路国に流罪と、波乱に富んだ生涯を送るのですが、上でも書きましたように没年は不明です。平安遷都の翌年、延暦十四年(795)に、淡路国から和泉国に移されたことが記録されているので、その頃までは生きていたということになりますが…。
ただ、伊豆国に流されていた息子の川継は、延暦二十四年(805)に赦されて、後に官界に復帰している(このことは知りませんでした)ので、それだけは救いですね。
もちろんこの本には、不破内親王のことだけでなく、阿倍内親王や井上内親王についても詳しく書かれています。彼女たちはいずれも過酷な生涯を送りましたが、与えられた運命を受け入れ、精一杯生きたように思えます。
また、彼女たちの周辺人物や、奈良時代の政変についても詳細に解説されていますので、奈良時代の歴史のこともよくわかると思います。特に、奈良時代の皇位継承争いは苛烈で、そこがまた興味をそそられたりします。
それから、私はこの本を読んで、聖武天皇のイメージが変わりました。
聖武天皇というと、気の強い光明皇后の尻に敷かれた、ちょっと気の弱い天皇というイメージだったのですが、なかなか芯のしっかりした、個性的な天皇というイメージに変わりました。
考えてみると聖武天皇は、皇女を皇太子にしたこと、東大寺にあれだけ大きな仏像を作ったことなど、型破りな事をたくさんやっています。
また聖武天皇は、孝謙女帝となった阿倍内親王に向かって、「王を臣下にするのも、臣下を王にするのも、そなたの好きなようにすればよい。」とも言っていたそうで、これが道鏡を天皇にしようとしたことへもつながっていくのです。やはり、聖武天皇はただものではないかもしれません。
このように、「天平の三姉妹」は、3人の皇女の人生をたどりながら、奈良時代の歴史に触れることが出来る1冊です。平城遷都1300年のこの機会にぜひ堪能してみて下さい。
☆コメントを下さる方は掲示板へお願いいたします。
☆トップページに戻る