理系大学に入学して、3年が過ぎた。思えば、あっという間の日々であったなぁ。
まだ入学したての1年生の頃、大学の参考書や教科書選びに、困ることが多かった。これからちょっと、大学1年生から今までに読んだ、触れた、教科書と参考書をまとめておこうと思う。載せるものは推薦図書とかではなく、触れたものは覚えてる限り、すべて、紹介します。これから理工系へ進まれる方や、同じような分野を勉強されてる方の参考となれば、幸いです。
あと、あー、その本知ってるーみたいなコメント待ってますんで(笑)。それから、僕は、正式な所属は物理学科なので、他の分野では、少しおかしいとこがあるかもです。
大学の専門書の紹介の前に…、高校の理科の参考書である∑bestの「理解しやすい物理ⅠⅡ」「理解しやすい化学ⅠⅡ」「理解しやすい生物ⅠⅡ」と数学の「青チャート」は、この3年間で何千回も開きました。その理解不足は、大学レベルなのか高校レベルなのかは、いつも微妙なラインだと思います。
≪物理数学≫……主に、物理学科で開講されている数学のために書かれた本です。そうでないものもありますが。
・「改訂 微分積分」州之内治男、和田淳蔵著(サイエンス社) 極限、微分積分、偏微分、多重積分が載っている教科書です。基礎的な微積はこれ一冊でカバーできます。付録に1階、2階の微分方程式の基本解法が載っていて、便利です。
・基礎解析学コース「ベクトル解析」矢野健太郎・石原繁共著(裳華房) ベクトル解析、特にベクトル場などの理解は、なかなか1年生ではイメージが掴みにくいんですが、これは演習問題も簡単で、ガウスの定理、ストークスの定理まで、よくまとまっていると思います。
・村上正康他著「教養の線形代数・四訂版」(培風館) 数学科以外の人には、少し、数学チックすぎると感じるかもしれません。でも、最低限、線形代数で必要な知識はまとまっていて、非常に厳密に書かれているところがよいです。また、イントロダクションでは、高校数学の旧々カリキュラムで扱われていた平面の方程式の範囲も書かれています。
・「物理のための数学」和達三樹著、岩波書店 岩波の入門コースシリーズは、どれも、1年生には扱いやすくて、良いと思います。この物理数学もきちんと読めばわかるように書かれています。
・「演習 微分積分」「演習 線形代数」「演習 ベクトル解析」「演習 応用解析」 寺田他共著 (サイエンス社) 大学1or2年生向けの青チャート的ノリの参考書シリーズです。どれも非常に親切な解説で、授業中に解いた問題に加えこれらの中の良さそうな問題を試験前にきちんと演習しておけば、間違いなく単位はくるでしょう。
・「詳解 物理・応用 数学演習」 後藤他共著 (共立出版) 上の4冊の演習書で扱っている範囲のより難しい問題と扱ってないような範囲、デルタ関数や変分法や群論の導入部などのよく見かける問題が記載されている演習書です。俺は数学で困ったら、だいたい、これをまず開きます。
・「数学 -物理を学び楽しむために-」 田崎晴明著 これは本ではなく、田崎先生のページにアップされているのですが、僕は、非常に面白い、読み物として、扱ってます。あまり俺は賢いほうではないのでこう思うのかもしれないですが、初学者向けの教科書としては、少し厳密すぎます。すべての範囲を一通り学び終えた学生なら、面白いと感じれると思います。
・「物理数学の直観的方法」長沼伸一郎著 数学の本のくせに、定性的な話が豊富で理解しやすいです。rotの定性的意味、複素解析など、直観的に問いかける形なので、読んでいてわかったような気分に浸れるし、楽しいです。
≪力学・解析力学≫……ニュートン力学と解析力学の本です。
・「セミナーテキスト 力学」御子柴・二見・鈴木公共著(サイエンス社) これ一冊で必要な演習問題はすべて載っていると思います。また、問題の前にあるまとめが、素晴らしく、覚えなきゃな内容がすぐわかります。 ただ、解説がないのが、欠点ですね。
・岩波基礎物理シリーズ「力学・解析力学」 阿部龍蔵著 (岩波書店) このシリーズは最初からきちんと読めばわかるので好きなんですが、解析力学んとこが、特にわかりやすいと思います。
・「力学演習」青野修著 理工基礎物理学演習ライブラリ (サイエンス社) あんまり使わなかったですが、持ってた演習書。最初の物理学の導入のとこが面白いです。
≪電磁気学≫……マックスウェル方程式を説明する学問の本です。
・「Introduction to Electrodynamics」 David j. Griffiths著 英語の教科書であるという最大の欠点に目をつぶれば、良い教科書だと思います。ただ、ちょっと文字が他の本に比べて特殊なのと、会話調なのが気になりますが、電磁気で必要な知識は、これ一冊で網羅されていると思います(ゲージ変換や電磁波なども)。2章5章7章に比べて、3章4章6章のがわかりやすいかな。
・「電磁気学I,Ⅱ」 長岡洋介著(岩波書店) 物理で初めての範囲を大学でやるときは、岩波の入門コースは一読の価値があるんですが、電磁気も例外ではない。多重極展開が載ってないのと物質中の電磁気学の範囲が薄いのが欠点だが、この教科書で電磁気の大枠をつかむことができるはずだ。
・「理論電磁気学」 砂川重信著 たまにパラパラ書店で見るんですが、難しい教科書ですよね。上の教科書はマックスウェル方程式をクーロンの法則とビオサバールの法則から導出するような書き方でありますが、この教科書はマックスウェル方程式を既知として、話を展開していくタイプの教科書だったと思います。あんまり、僕は、参考になりませんでした。でも、砂川先生の考え方シリーズはいろんな科目で、有用です(特に一つ一つ紹介はしないですが)。
・「例解 電磁気学演習」長岡他共著 岩波の入門コースの演習書。簡単な電磁気のレポート問題なら、この本にだいたい記載されている。そういった意味で、電磁気で一番、開いた本でした。
・「詳解 電磁気学演習」後藤他共編 (共立出版) 上の演習書には載っていないもっと難しいレベルの問題が多く記載されている。上のと二冊で、レポート問題はどうにかなる。特に、特殊解法である鏡像法や等角写像のとこが載っているのが嬉しい。電磁波やプラズマや回路の問題も豊富です。
・ファインマン、レトイン、サンズ著「ファインマン物理学Ⅲ 電磁気学」(岩波書店) 定性的な話が多く載っていておもろいが、このファインマン物理学って、教科書ではないよね。一回だけ、レポートのネタに使ったことがあります、ってか、先生がこの本からレポートのネタとってるなーっと思ったからなんだけど。
≪量子力学≫……現代物理学の一つで、シュレディンガー方程式などが出てきます。波動関数、確率論など新しい内容ばかりです。
・「Quantum Mechanics」Schiff, McGraw-Hill著 シッフは、問題を解くという意味では優れていると言われてます。僕は、こーゆー系の教科書の割には、全体的にわかりやすく書いてある厳密な教科書だなーっと思いますが、あんまり初学者向きじゃない気がします。
・「Quantum Mechanics」 W.Greiner and B.Muller, Springer-Verlag著 グライナーもわかりにくいと思いますが、まぁまぁ有名なんで。2準位系のとこが詳しく載ってて多少使いました。
・「Introduction to Quantum Mechanics」 D.J.Griffiths著 グリフィスは前期量子論が無いのと訳書が無いのと問題の解答がないのが欠点なんですが、まぁまぁこれは上手くまとまっていると思います。英語が苦手じゃないなら、まあ、理屈を理解するのに持っていても良いと思います。
・「量子力学1&2」猪木慶治他著 (講談社) 最も一般的な教科書であると思う。きちんと読めば必ずわかる、という点で、素晴らしい教科書。だけど、やっぱり、独学で学ぶには難しい教科書だと思う。変分原理が載ってないのが欠点。散乱問題や摂動論はわかりやすい。
・「基礎量子力学」猪木慶治他著 (講談社) 独学で学ぶんだったら、これは理解しやすいかも。はじめはこの教科書で、じっくり量子論を理解していって、あとから厳密な教科書を使えば量子力学をあきらめなくてすみそう。
・「ファインマン物理学Ⅴ 量子力学」Feynman著 (岩波書店) 独特の切り口から量子力学を扱っている教科書…ではなく読み物(笑)。これもきちんと読めば必ずわかる、が、その価値があるかどうかは別。
・「詳解 量子力学演習」後藤他共編 (共立出版) レポートが出されて、はじめに、同じ問題がないかな?って探す本。そして、たいていある。物理を専攻としない人には高度すぎるかもしれないけど、わかりやすく書かれていると思う。量子化学や超伝導、量子統計、量子生物学なども載ってて、多彩。
≪熱力学・統計力学≫……統計力学がメインです。
・E.Fermi著「熱力学」(三省堂) 標準的な熱力の教科書。ある程度、文字も多くて、わかりやすい。でも、あんまりこれを使って、熱力を勉強しませんでした…。ってか、あまりちゃんと、熱力を勉強してないかも(笑)。
・「統計力学」長岡洋介著(岩波書店) 統計力学の標準的な教科書。わかりやすいっちゃわかりやすいが、多少、厳密さを欠くシーンがある。演習問題が一般的な良い問題が多いし、解説もある程度親切。
・大学演習「熱学・統計力学」久保亮五他著(裳華房) 問題量が半端なく多い。レポート出されて、同じ問題がないか探す参考書としては、超一流。たいてい載っている。持ってると安心する参考書の一つ(笑)。
・田崎晴明著「統計力学 I&II」 新物理学シリーズ 37,38 (培風館) 田崎先生の統計力学の教科書もわかりやすいです。そして、定量的にも定性的にも厳密です。この人の文章の書き方がちょっと僕に似てる気がするんですが、どうでしょうか?注ばかり読んでると時間が過ぎるのが早いです。
≪その他物理学の教科書≫
・「キッテル固体物理学入門」(丸善) 固体物理の基礎的な内容がきちんと書いてある教科書。訳が上手くないっという声を何人かから聞きますが、まぁ、許容範囲じゃん?これの演習問題集もあって、それはかなり使えます。格子系のほうが電子系よりわかりやすいと思います。
・「物性物理学」塚田捷著 (裳華房) 固体物理で一番開いた教科書。あんまり有名じゃないけど、わかりやすく色々な内容が載っている。超伝導と輸送方程式がわかりやすかったです。
・「計測における誤差解析入門」 John R. Taylor著 (東京化学同人) 誤差論の本はたいていわかりにくくて、意味わかんないのが多いんですが、この教科書はとってもわかりやすく書いてあります。問題も載っていて、実際の実験の誤差解析をする上で役に立ちます。ショーブネの判断基準や最小二乗法による線形回帰などは、必読です。
・「相対性理論入門講義」風間洋一著 (培風館) 相対論の内容がお話のような感じで書かれている。相対論はこの教科書しか見てないので詳しくはわからないが、この教科書は理解しやすかったと思う。
・「Optics」 E. Hecht著 光学のよく見かける教科書。内容が豊富…、だが、無駄な内容が多いという印象も。読み物としては面白いけど、教科書としては使いにくい。
≪数学系の教科書≫
・「入門・演習 数理統計」 野田一雄他著 数理統計学の教科書で演習問題の解説が無いのに目をつぶれば、良い教科書だと思う。独学できる。初めのほーは、簡単すぎ。推定んとこから、ちゃんと読まないとわかんなくなる。
・「グラフ理論」 恵羅他著 (産業図書) これは読み物的印象が強い。グラフ理論ってのは、物理学科としては、なんで存在してんのかよくわかんない科目であるが、まぁ、おもろいっちゃおもろい。もう、なんも覚えてないけどね(笑)。
≪化学系の教科書≫
・「理工系の基礎化学」(エース出版) 大学レベルの化学のだいたいが載っている教科書。案外、物理学専攻であっても、3年まで使ってた。前期量子論の内容は、厳密さは少々欠くかもしれないが、量子力学の意味わかんない教科書よりも全然わかりやすく書いてある。
・「アトキンス 物理化学」P.W. Atkins著 (東京化学同人) 物化の一般的な教科書。上巻しか持ってない。下巻を買う予定はないです。平衡と構造と変化に分かれてて、物理の教科書などよりも熱力や量力はわかりやすいと思う。熱力などをあきらめるなら、こっちを見てからあきらめましょう。案外、補遺が一番使えるかも。
・「マクマリー有機化学」 JOHN McMURRY著 (東京化学同人) 上中下巻にわかれる有機の一般的な教科書。上巻持ってて、中巻までは買う予定です。問題の解答は別冊ですが、演習問題以外は簡単な問題が多いです。基礎編もあって、化学を専門としない人は、あれを見てみると有機のアウトラインが掴めます。
・「現代有機化学」ボルハルト・ショアー著 (化学同人) 上下巻に分かれる、マクマリーでいまいちよくわかんなかったときに開く、俺にとって、サブ役の有機の教科書。これはこれでわかりやすくて、良い。
・「量子化学」 原田義也著 上下巻に分かれる量子化学の教科書。物理学専攻の学生にしてみると、なんて上手くまとまった量子力学の教科書なんだーっと思う。実は、俺の量子力学のメインの教科書。数学が苦手だけど、定性的なのばっかりなのもイヤっというわがままな俺みたいな方に、おススメ。かなり幅広い人にとって、役に立つ教科書だと思う。
・Trudy&James R.McKee著「マッキー生化学」(化学同人) 生化の教科書で、ヴォートなどに比べ少し定性的なもの。生物系を専攻してない人にとっては一番読みやすい生化の教科書だと思う。おもしろい話題も多いし、絵も多い。どーでもいいけど、夫婦で書いてる教科書なのかな…?持ってる教科書の中で一番デカい。
もちろん、これ以外にも沢山の本に触れてきましたが、なんせ、図書館や書店で沢山の本を見ていると、いちいち名前を覚えてないのもあって…。熱力や物化、生化、分子生物学などは、特に、謎な覚えてない教科書で助かってます。あと、授業で使う専用の教科書はここには載せませんでしたが、それも役に立ってます。っま、図書館や本屋に行きまくってれば、自然と…。
まだ、忘れてるのもあるかもしれないですから、この記事は、更新していくようにしたいと思います。
まだ入学したての1年生の頃、大学の参考書や教科書選びに、困ることが多かった。これからちょっと、大学1年生から今までに読んだ、触れた、教科書と参考書をまとめておこうと思う。載せるものは推薦図書とかではなく、触れたものは覚えてる限り、すべて、紹介します。これから理工系へ進まれる方や、同じような分野を勉強されてる方の参考となれば、幸いです。
あと、あー、その本知ってるーみたいなコメント待ってますんで(笑)。それから、僕は、正式な所属は物理学科なので、他の分野では、少しおかしいとこがあるかもです。
大学の専門書の紹介の前に…、高校の理科の参考書である∑bestの「理解しやすい物理ⅠⅡ」「理解しやすい化学ⅠⅡ」「理解しやすい生物ⅠⅡ」と数学の「青チャート」は、この3年間で何千回も開きました。その理解不足は、大学レベルなのか高校レベルなのかは、いつも微妙なラインだと思います。
≪物理数学≫……主に、物理学科で開講されている数学のために書かれた本です。そうでないものもありますが。
・「改訂 微分積分」州之内治男、和田淳蔵著(サイエンス社) 極限、微分積分、偏微分、多重積分が載っている教科書です。基礎的な微積はこれ一冊でカバーできます。付録に1階、2階の微分方程式の基本解法が載っていて、便利です。
・基礎解析学コース「ベクトル解析」矢野健太郎・石原繁共著(裳華房) ベクトル解析、特にベクトル場などの理解は、なかなか1年生ではイメージが掴みにくいんですが、これは演習問題も簡単で、ガウスの定理、ストークスの定理まで、よくまとまっていると思います。
・村上正康他著「教養の線形代数・四訂版」(培風館) 数学科以外の人には、少し、数学チックすぎると感じるかもしれません。でも、最低限、線形代数で必要な知識はまとまっていて、非常に厳密に書かれているところがよいです。また、イントロダクションでは、高校数学の旧々カリキュラムで扱われていた平面の方程式の範囲も書かれています。
・「物理のための数学」和達三樹著、岩波書店 岩波の入門コースシリーズは、どれも、1年生には扱いやすくて、良いと思います。この物理数学もきちんと読めばわかるように書かれています。
・「演習 微分積分」「演習 線形代数」「演習 ベクトル解析」「演習 応用解析」 寺田他共著 (サイエンス社) 大学1or2年生向けの青チャート的ノリの参考書シリーズです。どれも非常に親切な解説で、授業中に解いた問題に加えこれらの中の良さそうな問題を試験前にきちんと演習しておけば、間違いなく単位はくるでしょう。
・「詳解 物理・応用 数学演習」 後藤他共著 (共立出版) 上の4冊の演習書で扱っている範囲のより難しい問題と扱ってないような範囲、デルタ関数や変分法や群論の導入部などのよく見かける問題が記載されている演習書です。俺は数学で困ったら、だいたい、これをまず開きます。
・「数学 -物理を学び楽しむために-」 田崎晴明著 これは本ではなく、田崎先生のページにアップされているのですが、僕は、非常に面白い、読み物として、扱ってます。あまり俺は賢いほうではないのでこう思うのかもしれないですが、初学者向けの教科書としては、少し厳密すぎます。すべての範囲を一通り学び終えた学生なら、面白いと感じれると思います。
・「物理数学の直観的方法」長沼伸一郎著 数学の本のくせに、定性的な話が豊富で理解しやすいです。rotの定性的意味、複素解析など、直観的に問いかける形なので、読んでいてわかったような気分に浸れるし、楽しいです。
≪力学・解析力学≫……ニュートン力学と解析力学の本です。
・「セミナーテキスト 力学」御子柴・二見・鈴木公共著(サイエンス社) これ一冊で必要な演習問題はすべて載っていると思います。また、問題の前にあるまとめが、素晴らしく、覚えなきゃな内容がすぐわかります。 ただ、解説がないのが、欠点ですね。
・岩波基礎物理シリーズ「力学・解析力学」 阿部龍蔵著 (岩波書店) このシリーズは最初からきちんと読めばわかるので好きなんですが、解析力学んとこが、特にわかりやすいと思います。
・「力学演習」青野修著 理工基礎物理学演習ライブラリ (サイエンス社) あんまり使わなかったですが、持ってた演習書。最初の物理学の導入のとこが面白いです。
≪電磁気学≫……マックスウェル方程式を説明する学問の本です。
・「Introduction to Electrodynamics」 David j. Griffiths著 英語の教科書であるという最大の欠点に目をつぶれば、良い教科書だと思います。ただ、ちょっと文字が他の本に比べて特殊なのと、会話調なのが気になりますが、電磁気で必要な知識は、これ一冊で網羅されていると思います(ゲージ変換や電磁波なども)。2章5章7章に比べて、3章4章6章のがわかりやすいかな。
・「電磁気学I,Ⅱ」 長岡洋介著(岩波書店) 物理で初めての範囲を大学でやるときは、岩波の入門コースは一読の価値があるんですが、電磁気も例外ではない。多重極展開が載ってないのと物質中の電磁気学の範囲が薄いのが欠点だが、この教科書で電磁気の大枠をつかむことができるはずだ。
・「理論電磁気学」 砂川重信著 たまにパラパラ書店で見るんですが、難しい教科書ですよね。上の教科書はマックスウェル方程式をクーロンの法則とビオサバールの法則から導出するような書き方でありますが、この教科書はマックスウェル方程式を既知として、話を展開していくタイプの教科書だったと思います。あんまり、僕は、参考になりませんでした。でも、砂川先生の考え方シリーズはいろんな科目で、有用です(特に一つ一つ紹介はしないですが)。
・「例解 電磁気学演習」長岡他共著 岩波の入門コースの演習書。簡単な電磁気のレポート問題なら、この本にだいたい記載されている。そういった意味で、電磁気で一番、開いた本でした。
・「詳解 電磁気学演習」後藤他共編 (共立出版) 上の演習書には載っていないもっと難しいレベルの問題が多く記載されている。上のと二冊で、レポート問題はどうにかなる。特に、特殊解法である鏡像法や等角写像のとこが載っているのが嬉しい。電磁波やプラズマや回路の問題も豊富です。
・ファインマン、レトイン、サンズ著「ファインマン物理学Ⅲ 電磁気学」(岩波書店) 定性的な話が多く載っていておもろいが、このファインマン物理学って、教科書ではないよね。一回だけ、レポートのネタに使ったことがあります、ってか、先生がこの本からレポートのネタとってるなーっと思ったからなんだけど。
≪量子力学≫……現代物理学の一つで、シュレディンガー方程式などが出てきます。波動関数、確率論など新しい内容ばかりです。
・「Quantum Mechanics」Schiff, McGraw-Hill著 シッフは、問題を解くという意味では優れていると言われてます。僕は、こーゆー系の教科書の割には、全体的にわかりやすく書いてある厳密な教科書だなーっと思いますが、あんまり初学者向きじゃない気がします。
・「Quantum Mechanics」 W.Greiner and B.Muller, Springer-Verlag著 グライナーもわかりにくいと思いますが、まぁまぁ有名なんで。2準位系のとこが詳しく載ってて多少使いました。
・「Introduction to Quantum Mechanics」 D.J.Griffiths著 グリフィスは前期量子論が無いのと訳書が無いのと問題の解答がないのが欠点なんですが、まぁまぁこれは上手くまとまっていると思います。英語が苦手じゃないなら、まあ、理屈を理解するのに持っていても良いと思います。
・「量子力学1&2」猪木慶治他著 (講談社) 最も一般的な教科書であると思う。きちんと読めば必ずわかる、という点で、素晴らしい教科書。だけど、やっぱり、独学で学ぶには難しい教科書だと思う。変分原理が載ってないのが欠点。散乱問題や摂動論はわかりやすい。
・「基礎量子力学」猪木慶治他著 (講談社) 独学で学ぶんだったら、これは理解しやすいかも。はじめはこの教科書で、じっくり量子論を理解していって、あとから厳密な教科書を使えば量子力学をあきらめなくてすみそう。
・「ファインマン物理学Ⅴ 量子力学」Feynman著 (岩波書店) 独特の切り口から量子力学を扱っている教科書…ではなく読み物(笑)。これもきちんと読めば必ずわかる、が、その価値があるかどうかは別。
・「詳解 量子力学演習」後藤他共編 (共立出版) レポートが出されて、はじめに、同じ問題がないかな?って探す本。そして、たいていある。物理を専攻としない人には高度すぎるかもしれないけど、わかりやすく書かれていると思う。量子化学や超伝導、量子統計、量子生物学なども載ってて、多彩。
≪熱力学・統計力学≫……統計力学がメインです。
・E.Fermi著「熱力学」(三省堂) 標準的な熱力の教科書。ある程度、文字も多くて、わかりやすい。でも、あんまりこれを使って、熱力を勉強しませんでした…。ってか、あまりちゃんと、熱力を勉強してないかも(笑)。
・「統計力学」長岡洋介著(岩波書店) 統計力学の標準的な教科書。わかりやすいっちゃわかりやすいが、多少、厳密さを欠くシーンがある。演習問題が一般的な良い問題が多いし、解説もある程度親切。
・大学演習「熱学・統計力学」久保亮五他著(裳華房) 問題量が半端なく多い。レポート出されて、同じ問題がないか探す参考書としては、超一流。たいてい載っている。持ってると安心する参考書の一つ(笑)。
・田崎晴明著「統計力学 I&II」 新物理学シリーズ 37,38 (培風館) 田崎先生の統計力学の教科書もわかりやすいです。そして、定量的にも定性的にも厳密です。この人の文章の書き方がちょっと僕に似てる気がするんですが、どうでしょうか?注ばかり読んでると時間が過ぎるのが早いです。
≪その他物理学の教科書≫
・「キッテル固体物理学入門」(丸善) 固体物理の基礎的な内容がきちんと書いてある教科書。訳が上手くないっという声を何人かから聞きますが、まぁ、許容範囲じゃん?これの演習問題集もあって、それはかなり使えます。格子系のほうが電子系よりわかりやすいと思います。
・「物性物理学」塚田捷著 (裳華房) 固体物理で一番開いた教科書。あんまり有名じゃないけど、わかりやすく色々な内容が載っている。超伝導と輸送方程式がわかりやすかったです。
・「計測における誤差解析入門」 John R. Taylor著 (東京化学同人) 誤差論の本はたいていわかりにくくて、意味わかんないのが多いんですが、この教科書はとってもわかりやすく書いてあります。問題も載っていて、実際の実験の誤差解析をする上で役に立ちます。ショーブネの判断基準や最小二乗法による線形回帰などは、必読です。
・「相対性理論入門講義」風間洋一著 (培風館) 相対論の内容がお話のような感じで書かれている。相対論はこの教科書しか見てないので詳しくはわからないが、この教科書は理解しやすかったと思う。
・「Optics」 E. Hecht著 光学のよく見かける教科書。内容が豊富…、だが、無駄な内容が多いという印象も。読み物としては面白いけど、教科書としては使いにくい。
≪数学系の教科書≫
・「入門・演習 数理統計」 野田一雄他著 数理統計学の教科書で演習問題の解説が無いのに目をつぶれば、良い教科書だと思う。独学できる。初めのほーは、簡単すぎ。推定んとこから、ちゃんと読まないとわかんなくなる。
・「グラフ理論」 恵羅他著 (産業図書) これは読み物的印象が強い。グラフ理論ってのは、物理学科としては、なんで存在してんのかよくわかんない科目であるが、まぁ、おもろいっちゃおもろい。もう、なんも覚えてないけどね(笑)。
≪化学系の教科書≫
・「理工系の基礎化学」(エース出版) 大学レベルの化学のだいたいが載っている教科書。案外、物理学専攻であっても、3年まで使ってた。前期量子論の内容は、厳密さは少々欠くかもしれないが、量子力学の意味わかんない教科書よりも全然わかりやすく書いてある。
・「アトキンス 物理化学」P.W. Atkins著 (東京化学同人) 物化の一般的な教科書。上巻しか持ってない。下巻を買う予定はないです。平衡と構造と変化に分かれてて、物理の教科書などよりも熱力や量力はわかりやすいと思う。熱力などをあきらめるなら、こっちを見てからあきらめましょう。案外、補遺が一番使えるかも。
・「マクマリー有機化学」 JOHN McMURRY著 (東京化学同人) 上中下巻にわかれる有機の一般的な教科書。上巻持ってて、中巻までは買う予定です。問題の解答は別冊ですが、演習問題以外は簡単な問題が多いです。基礎編もあって、化学を専門としない人は、あれを見てみると有機のアウトラインが掴めます。
・「現代有機化学」ボルハルト・ショアー著 (化学同人) 上下巻に分かれる、マクマリーでいまいちよくわかんなかったときに開く、俺にとって、サブ役の有機の教科書。これはこれでわかりやすくて、良い。
・「量子化学」 原田義也著 上下巻に分かれる量子化学の教科書。物理学専攻の学生にしてみると、なんて上手くまとまった量子力学の教科書なんだーっと思う。実は、俺の量子力学のメインの教科書。数学が苦手だけど、定性的なのばっかりなのもイヤっというわがままな俺みたいな方に、おススメ。かなり幅広い人にとって、役に立つ教科書だと思う。
・Trudy&James R.McKee著「マッキー生化学」(化学同人) 生化の教科書で、ヴォートなどに比べ少し定性的なもの。生物系を専攻してない人にとっては一番読みやすい生化の教科書だと思う。おもしろい話題も多いし、絵も多い。どーでもいいけど、夫婦で書いてる教科書なのかな…?持ってる教科書の中で一番デカい。
もちろん、これ以外にも沢山の本に触れてきましたが、なんせ、図書館や書店で沢山の本を見ていると、いちいち名前を覚えてないのもあって…。熱力や物化、生化、分子生物学などは、特に、謎な覚えてない教科書で助かってます。あと、授業で使う専用の教科書はここには載せませんでしたが、それも役に立ってます。っま、図書館や本屋に行きまくってれば、自然と…。
まだ、忘れてるのもあるかもしれないですから、この記事は、更新していくようにしたいと思います。










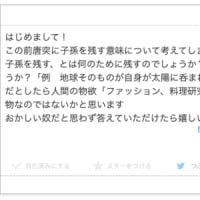
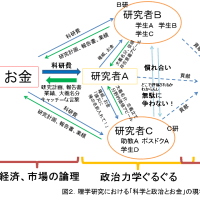
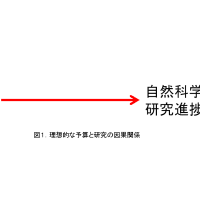
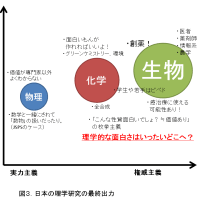
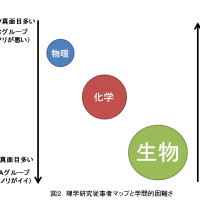
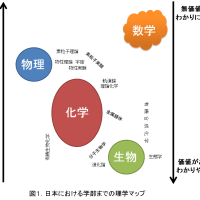

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます