よくネットで話題になる質問の1つ、映画「ドラえもん」で一番のトラウマは何か?と問われたら、俺は、1999年の「ドラえもん のび太の宇宙漂流記」の"眩惑の星"と答える。
宇宙に漂流することになってしまったドラえもん達一行は、ある星に不時着する。霧ばかりの星なのだが、霧が晴れていくと、そこはなんと地球、いつもの裏山なのだ。それぞれ家族のもとに帰るが、本当は植物性の化け物達がのび太たちを搾取しようとして眩惑を魅せていたのだ。
のび太は、地球で拾った星のかけらがお尻のポケットに入っており、座った時の痛さで現状の恐ろしさに気が付く。それをドラえもんや他の仲間に伝え、焦って、その星を後にする。
命からがら帰ってきた宇宙船のなかで、スネ夫が「幻でもよかったよ!もう、こんな宇宙ばっかり、嫌だ!」と言う。
初めてこの作品を観てから20年経っても、このシーンを最初に観た時のことが忘れられない。この世はすべてが眩惑の可能性があるのではないか?、ってね。
この作品の面白い教訓は、眩惑かどうかは「痛み」でわかるということ。痛い想いをすることで、それが眩惑かどうか悟ることができる。
この"眩惑の星"の本当に恐ろしいところは、映画のラストシーンで登場する。本当の地球に着いてからのシーンが、途中まで"眩惑の星"のシーンとまったく同一なのだ。しかし、のび太が先生に会い、テストが0点だったと分かったときに、「よかった」と地球であることを実感する。先生は「よかったとは、なにごとだ!」と怒るが、ドラえもんが「とりあえず、よかったんです」とフォローを入れる。
そう、現実は、常に「痛い」。
だから通常、誰も真実を知りたくないし、"考えすぎるな"と諭す。
だから通常、目の前の幻が幻だと分かっていても、その幻が継続するように仕組んでしまうし、自分を納得させられるような言葉を自分自身に繰り返そうとする。
だから通常、幻が醒めないための論理を自分のなかで大げさに構築し、その軸を大切に守りながら、急に真実の光を照らそうとする誰かを敵認定して、遠ざけようとする。
俺は30代なので、あと50年、目の前のあらゆる幻が幻のままで終われば、御の字であろう。
別に真実を観たいわけじゃない。あと50年ももたないであろう事柄かどうか、幻を作り出してくる元凶から体力を奪うことで見分けるだけだ。
そう、幻を魅せてくるなかでも、元凶が忍耐力によって運営されて、俺に忍耐力以外の部分での搾取をしようとしている場合、霧を晴らすのは比較的簡単である。眩惑に問い続ければ良いだけだからね。振り返れば、その「搾取」でさえも、逆にこちら側からの幻であることが殆ど。そして、心から謝罪したくなる。
本当に問題なのは、こちらの天賦の才と圧倒的な忍耐力を養分に、幻を魅せ続けてくるような場合。
結果を出し続け、期待に応えれば応えるほどに、社会的にも認められていく。一生消えない業の深い称号すら誰かへの"媚び諂い"ゆえであったことに、世界中で誰も気が付いていないほどに、直向きさと純粋さの演技に関して窮めてしまっていたのだとしたら、、もはやそれは現実なのではないかと思うけれど、でも、自分だけは知っている。
他人は「それでも、それで本当に実力がついているんだから、いいじゃないか」と言う。本当にそうなんだろうか?だって、眩惑ばかりのこの世の中で、手元に能力だけが残ることほど、虚しいことって他にないよ。
目の前の期待していた眩惑に対して、痛みを感じることで現実に戻れれば、「とりあえず、よかった」となるだろう。
その「とりあえず」は果たしてどれくらい続いてくれるのだろう?そして、生まれてからずっと眩惑を魅せられてきた事柄に、「とりあえず」は通用しないよね。
"どちらがどのように眩惑を魅せられていたのか"は、いつだって不正確に認識される。
奇跡的に成り立っていた眩惑を、才能の枯渇ではなく、痛みそのものが気が付かせてくれた。あの奇跡の眩惑から脱出するために、これまで何度も何度も、誰かを幻で魅了し、誰かを誹り欺き、誰かを利用し、誰かを傷つけた。
そのことを、いつか許してほしいと願っている。だって、、そうじゃないと、俺は生きてこれなかったのだから。
だからこそ今は、「幻でもよかったよ!」と声を荒げたいのかもしれない。
宇宙に漂流することになってしまったドラえもん達一行は、ある星に不時着する。霧ばかりの星なのだが、霧が晴れていくと、そこはなんと地球、いつもの裏山なのだ。それぞれ家族のもとに帰るが、本当は植物性の化け物達がのび太たちを搾取しようとして眩惑を魅せていたのだ。
のび太は、地球で拾った星のかけらがお尻のポケットに入っており、座った時の痛さで現状の恐ろしさに気が付く。それをドラえもんや他の仲間に伝え、焦って、その星を後にする。
命からがら帰ってきた宇宙船のなかで、スネ夫が「幻でもよかったよ!もう、こんな宇宙ばっかり、嫌だ!」と言う。
初めてこの作品を観てから20年経っても、このシーンを最初に観た時のことが忘れられない。この世はすべてが眩惑の可能性があるのではないか?、ってね。
この作品の面白い教訓は、眩惑かどうかは「痛み」でわかるということ。痛い想いをすることで、それが眩惑かどうか悟ることができる。
この"眩惑の星"の本当に恐ろしいところは、映画のラストシーンで登場する。本当の地球に着いてからのシーンが、途中まで"眩惑の星"のシーンとまったく同一なのだ。しかし、のび太が先生に会い、テストが0点だったと分かったときに、「よかった」と地球であることを実感する。先生は「よかったとは、なにごとだ!」と怒るが、ドラえもんが「とりあえず、よかったんです」とフォローを入れる。
そう、現実は、常に「痛い」。
だから通常、誰も真実を知りたくないし、"考えすぎるな"と諭す。
だから通常、目の前の幻が幻だと分かっていても、その幻が継続するように仕組んでしまうし、自分を納得させられるような言葉を自分自身に繰り返そうとする。
だから通常、幻が醒めないための論理を自分のなかで大げさに構築し、その軸を大切に守りながら、急に真実の光を照らそうとする誰かを敵認定して、遠ざけようとする。
俺は30代なので、あと50年、目の前のあらゆる幻が幻のままで終われば、御の字であろう。
別に真実を観たいわけじゃない。あと50年ももたないであろう事柄かどうか、幻を作り出してくる元凶から体力を奪うことで見分けるだけだ。
そう、幻を魅せてくるなかでも、元凶が忍耐力によって運営されて、俺に忍耐力以外の部分での搾取をしようとしている場合、霧を晴らすのは比較的簡単である。眩惑に問い続ければ良いだけだからね。振り返れば、その「搾取」でさえも、逆にこちら側からの幻であることが殆ど。そして、心から謝罪したくなる。
本当に問題なのは、こちらの天賦の才と圧倒的な忍耐力を養分に、幻を魅せ続けてくるような場合。
結果を出し続け、期待に応えれば応えるほどに、社会的にも認められていく。一生消えない業の深い称号すら誰かへの"媚び諂い"ゆえであったことに、世界中で誰も気が付いていないほどに、直向きさと純粋さの演技に関して窮めてしまっていたのだとしたら、、もはやそれは現実なのではないかと思うけれど、でも、自分だけは知っている。
他人は「それでも、それで本当に実力がついているんだから、いいじゃないか」と言う。本当にそうなんだろうか?だって、眩惑ばかりのこの世の中で、手元に能力だけが残ることほど、虚しいことって他にないよ。
目の前の期待していた眩惑に対して、痛みを感じることで現実に戻れれば、「とりあえず、よかった」となるだろう。
その「とりあえず」は果たしてどれくらい続いてくれるのだろう?そして、生まれてからずっと眩惑を魅せられてきた事柄に、「とりあえず」は通用しないよね。
"どちらがどのように眩惑を魅せられていたのか"は、いつだって不正確に認識される。
奇跡的に成り立っていた眩惑を、才能の枯渇ではなく、痛みそのものが気が付かせてくれた。あの奇跡の眩惑から脱出するために、これまで何度も何度も、誰かを幻で魅了し、誰かを誹り欺き、誰かを利用し、誰かを傷つけた。
そのことを、いつか許してほしいと願っている。だって、、そうじゃないと、俺は生きてこれなかったのだから。
だからこそ今は、「幻でもよかったよ!」と声を荒げたいのかもしれない。










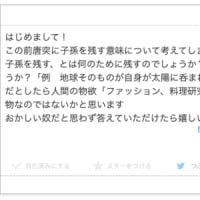
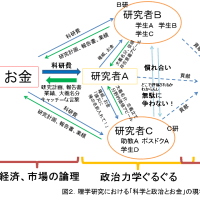
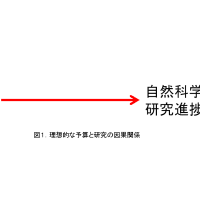
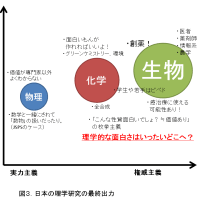
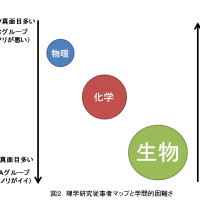
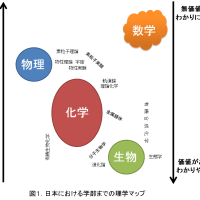

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます