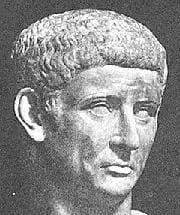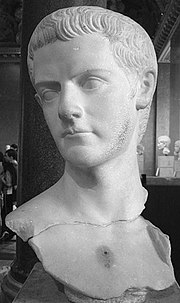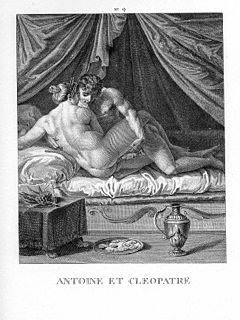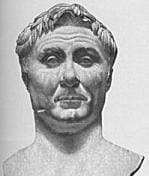ローマ人列伝を気が向くままにつづっているわけですが、書きながら「あ~これ説明したいなー」とか「こういう基礎知識あればもっと楽しんでいただけるのに!」と思うことが多々あります。
ティベリウス伝を終えてひと段落ついたタイミングでもあるので、「ローマ史の簡単な基礎知識」を書き綴って行きます。
列伝形式ではないのでちょっと退屈かも知れませんが「ふーん」程度にナナメ読みしていただけるとこれからもっと楽しめると思います。
【基礎的な歴史】
超カンタンなローマ史を書いてみました。
よろしければどうぞ。
超カンタンローマ史(外部リンク)
【敗者の同化】
古代ローマが世界国家として最大の領土を誇った理由のひとつにこの「敗者の同化」というキーワードがあります。それまでの国家といえば基本的に侵略国家。隣に自分たちと違う民族があれば侵略し、略奪し、それ以降は土着の文化を認めませんでした。
一度は力に屈しても人間は「支配されている」と感じるだけで反抗したくなるものです。虎視眈々と支配者の力が衰えるのを狙い反乱を起こします。侵略し、支配し、反乱され、それを討伐する、という繰り返しでは領土を拡大し続けることは出来ません。
しかしローマは違いました。
たとえば安全のために隣国と戦争を行ったとしても勝った後にはその国の文化がそのまま存続することを認めました。
古代においておおきなイデオロギーの対立は「宗教戦争」ですがローマ人は土着の宗教すら認めました。それにはもともと「30万の神がいる」と言われたローマの多神教文化も大きく影響しています。
自分たちの文化、宗教も認められ、更に最強の軍を誇るローマ軍に安全を保証される。その見返りは決して無理のない税金のみ。
植民地(古代ラテン語ではプロヴィンチア、つまり属州、の意)の人々にとってローマ庇護の下にいるのは決して損なことではなかったのです。
だからこそ属州の内乱も少なく、背中から攻められる不安がなかったローマは常に「外へ外へ」攻めていればよかったのです。
なぜこの「敗者の同化」という考え方がローマに定着したのか?
それはそもそもこのローマという国の成り立ちから始まっています。
ローマの始まりは紀元前753年、ロムルスという若者が建国したことから始まります。

(ロムルスは双子で更に捨てられて狼に育てられた、という伝説があります。狼の乳を吸っているのがロムルスと兄弟レムス)
もともとトロイ戦争の敗北者たちの集まりだったローマ人。兵士の若者はたくさんいましたが嫁となる女性が不足していました。そこで王ロムルスは近所のサビーニ族に目をつけます。にぎやかな祭りを開催しサビーニ族の男性を招待しもてなします。そのすきに女性を強奪。

その様子をあらわした彫刻。がっつり強奪してます。しかしながら今でも欧米では結婚式後に新郎が新婦を抱き上げて家に入る習慣があります。それはこの故事から。
女を奪われたサビーニ族はもちろん激怒。しかしロムルスは女性たちを決して強引に扱わず正式な妻とします。
サビーニ族とローマの戦いは続きますが、そのうちにサビーニ族の女性は「ローマの男性は優しいし、わざわざサビーニに戻りたくないわ」と言い出します。
女性の声を武器にローマは和平を申し出ます。
その際の和平の条件が決してサビーニに手下になれ、ということではなく、「どうせなら一緒の国にしちゃおうぜ」ということ。
娘たちが決して邪険な扱いを受けているのではなく、むしろ幸せに生活している、更に屈強な男の多いローマと一緒になるならまぁいいか、とサビーニもこれを受け入れます。
この出来事からローマが始まりました。
以後、長い歴史の中でもローマ人は蛮族を決して邪険に扱うことなく、むしろ積極的に自分たちの知恵を与えその土地の発展に尽くすようになりました。
特にこの傾向が顕著だったのがカエサル。彼は平定したガリア(今のフランス)の部族を積極的に保護しました。更にはどんどんローマ市民権や自らの名(当時のローマでは氏族(後でかきます)が同じなら助け合う、という不文律がありました)も与えます。
【元老院】
古代ローマにおいて外せないキーワードがこの「元老院」です。
初代ローマ王、ロムルスは若いながらも常識のある人でした。自分ひとりでは真っ当な政治が出来ない、と気づいていたのです。そこで村の長老たちを集め意見を聞く助言期間を作ったのです。これが元老院。都度、彼らの意見をききながら政治を行っていきました。
当初は正式な期間ではなく単に井戸端会議に毛が生えたものでしたが、王政から共和制に代わるにつれ、その権力は増大していきました。
以後、元老院は名家の知識人の集まりとなり政治を行っていきます。簡単に言うと今の衆議院、参議院のようなものになります。
どうも「元老院」と聞くと権力にかられた頑固な老人たちの集まり、というイメージがありますが最初は王の助言機関、後にはたんなる議会、という感じです。
いろいろありましたが、ローマ発展の理由にはこの元老院が行った善政もあります。
ローマの元老院と市民、つまりローマの主権者を表す"Senatus Populusque Romanus"は「SPQR」という略語として今でもローマの街角で見ることが出来るそうです。

ローマのマンホールの蓋。
更には現代ローマ市の紋章にも書かれています。
 【パトローネスとクリエンテス】
【パトローネスとクリエンテス】
古代ローマを理解するための重要な人間関係(つまりは家関係)がこれです。パトローネス、とは現代も使われている、パトロン、の意味、一方クリエンテスはクライアント、の意。
パトローネスとクリエンテスは簡単に言うと「親分、子分」の関係です。
パトローネスは資産と軍勢を持っている家系。一方クリエンテスはパトローネスに保護される家系。保護、と言っても決して奴隷や子分ではありません。
パトローネスは何かあればクリエンテスを守ります。たとえばクリエンテスの家がどこかの家と争いになったときにクリエンテスが出張って「まぁまぁ」と仲裁します。喧嘩になれば当然、私軍も出します。そのためにクリエンテスはパトローネスに協力します。
そもそもそういう関係が普通だったのでローマは属州支配に関しても「ローマがパトローネス」と思えたのです。
当然のことながらパトローネスの家系の者が選挙に出ればクリエンテスは大きな「票」になります。
ガリア戦争以後、広大なガリア全土の民はカエサル個人にとっての「クリエンテス」となります。それが政治的にカエサルにとても役立った、ということは言うまでもありません。
【ローマ人の王嫌い】
ロムルス王から始まったローマ。ロムルス死後、そのときそのときで実力があるものが王となって行きました。この「王政ローマ」が約200年続きます。しかしタルクィニウスが王の時、ある事件が起こります。王の権力を傘に非道を行ったタルクィニウスをローマ市民が追放したのです。

王追放の首謀者ルキウス・ユニウス・ブルートゥス。(関係ないけど「ブルータス、お前もか」のブルータスはこの人の子孫。王を追放した英雄の子孫が王のような英雄を殺したのは歴史の皮肉でもあります。)
このときに一人に権力が集中することによる弊害を知ったローマ市民、ある宣言をします。
「以後、ローマは王を持たない。ローマの主権は元老院と市民にある」
ここから元老院と市民による政治、つまり「共和制」が始まり、同時にローマ人の「王アレルギー」が始まります。
アウグストゥスが皇帝となるまで、ローマにおいては王を目指した者、あるいは王座を欲していると疑われた者は続々と殺されていきます。
たとえば有名なところでは護民官(後で書きます)として平民の農地を守るため農地改革に取り組んだグラッスス。彼は市民集会(今で言う総選挙)の際に反対者にもみくちゃにされ、壇上から「自分はここにいる、助けてくれ」と仲間に示すために自分の頭に手をかざしました。それを見ていた元老院議員は「グラッススは王冠を求めた、彼は王になろうとしている」と避難し彼を殺害したのでした。
もちろん終身独裁官となったユリウス・カエサルが暗殺されたのも、「カエサルは王を目指している」と思われたからでもあります。
【執政官、護民官、独裁官】
ローマの政治は基本的に元老院によって行われていました。元老院によって法律が決められ、ローマ市民による市民集会で可決される、という流れです。
しかしたとえば戦争で最高指令官が必要、など一人のリーダーが必要な場合があります。
そのためにまず執政官という役職が設置されました。原語では「コンスル」。これは今の日本で言うと総理大臣。議長みたいなものです。任期は1年、そして常に2名体制。ローマ人は王嫌いですから一人に権力が集中しないための仕組みです。そして執政官になれるのは貴族階級のみ。
※ちなみにこの執政官=コンスル、もともとは相談する、熟考する、という意味です。「元老院と相談する人」という意味でした。それは現代でも相談する人、つまり「コンサルタント」として残っています。
執政官、というのは当時のローマにおいてはキャリアのトップですからかなりの栄えある役職です。更に前執政官(プロコンスル)という役職がありました。これはつまり選挙に当選し、来年からコンスルになる人、という意味。プロコンスルは慣例として属州の統治官に任命されました。属州の統治というと大変な感じもしますがそんなことはなくてとりあえずその土地に行って税金などの管理。場合によっては属州からの裏金ももらえましたから金銭的にもかなり割のいい仕事でした。
更にローマも肥大化してくると貴族階級と平民階級の軋轢が生まれてきます。
なぜなら平民は元老院には入れないわけですから政治になかなか参加できません。元老院は貴族ですから自分たちに有利な法律を作ることが出来ます。
というわけで平民の権利を守るために「護民官」という役職が設置されました。これは執政官と同じく任期は1年。しかしこちらは一人。
特権階級である元老院、執政官に対抗するための護民官特権というものを持っていました。
特権の一つ目は「身体不可侵権」つまり護民官を傷つけたり殺したりすることは誰も出来ない、というもの。更に「拒否権」という権利も持っていました。こちらは元老院や執政官が決めた法律でも拒否できる、という権利です。つまり護民官は「誰にも殺されず」「何でも拒否できる」というかなり強い権利を持った役職です。もともと平民の権利は薄いですからその代表である護民官の権利は大きかったのです。
後にアウグストゥスが「私は貴族だけどやっぱり市民の権利は大事だと思う。平民を守る護民官には(貴族だから)なれないけど特権だけくれ」と言って利用するのがこの「護民官特権」です。
更に「独裁官」という役職もありました。
こちらはたとえば戦乱時などの非常時に任命されるもの。特別なものですがすべての公職(元老院議員、執政官、護民官)はこの独裁官の命令に従わなければいけません。護民官最後の武器、拒否権も独裁官には無効。独裁官はローマ最強の役職です。最強だけに任期は非常に短く六ヶ月間。つまり非常事態にだけ任命され平時には解職される役職です。ローマ政治の最強カードとも言えます。
カエサルは執政官、独裁官の経験があります。もちろん貴族出身なので護民官にはなっていません。更にカエサルは掟破りの「終身独裁官」(任期六ヶ月、というルールを破りました)にも就任しています。これが「カエサルは王になろうとしている」と思われカエサル暗殺の要因となります。
【プリンチェプスたるインペラトール・カエサル・アウグストゥス】
カエサル、アウグストゥスは本来、個人名ですが後の世には称号として使われます。こういう称号とか尊称が多くなるから人の名前が長くなるんですが。
まずローマ人の男の名前は基本的に三つから成り立っています。
たとえば、
ガイウス・ユリウス・カエサル
ガイウスが個人名、ユリウスが氏族名、カエサルが家族名。つまりは「ユリウス氏族のカエサル家のガイウスくん」という意味です。
当時の名門氏族と言えばコルネリウス、クラウディウスあたり。
更にローマ人は人をあだ名で呼ぶのが好きでした。有名どころではザマの会戦でハンニバルを破ったスキピオ。この人の本名は、スキピオプブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス、えーっとつまり「コルネリウス氏族のスキピオ家のスキピオプブリウス、あだ名はアフリカヌス」ということです。アフリカヌスはアフリカ王の意味。
そのほかにはポンペイウス・マーニュス(偉大なポンペイウス)、スッラ・フェリクス(幸運なスッラ)など。
カエサル、アウグストゥスも称号として受け継がれていきます。
カエサル、は「皇太子」の意味、そしてアウグストゥスは「皇帝」の意味。つまり皇帝が後継者に決めた人物にはカエサルの称号を授け、皇帝になればアウグストゥスの称号を得る、ということです。
(元は逆に書いてました。。junoさんにご指摘をいただいて誤りを修正しました。)
そもそも皇帝、という役職はなかったのですが逆にカエサルが皇帝を表すこととなり、現在でもドイツ語「カイザー」、ロシア語「ツァーリ」など「皇帝」を表す言葉として残っています。
そしてもうひとつの称号が「インペラトール」。こちらはもともと「軍最高司令官」という意味。凱旋式の時などに兵士が最高司令官を呼ぶ呼び名として使われていましたが特に意味はないものでした。すごーくわかりやすく言うと「わっしょい、わっしょい」くらいな感じ。
ローマ市民の王嫌いをよく理解していたアウグストゥスは軍に対しての自分の呼び名にこのインペラトールを使いました。こちらも皇帝を表す名として受け継がれていきます。もちろん、現代英語の「エンペラー」の語源です。
更に「プリンチェプス」。これは「第一人者」という意味。こちらは単なる「代表」「議長」くらいの意味です。これもアウグストゥスがうまく利用し、「自分は王ではなく市民、元老院議員の代表」という意味で市民に対して使いました。現代英語でも「principal」といえば主要な人、という意味。バレェでも「主役」という意味で使われます。
こういうひとつひとつは決して大きな意味を持たない肩書きを巧妙に寄せ集めた結果、軍でも元老院でもローマ市民の中でも誰よりも権威を持った人間、それがアウグストゥスであり、結果として「皇帝」という強大な権力者になるのです。