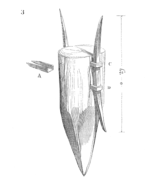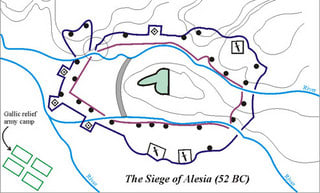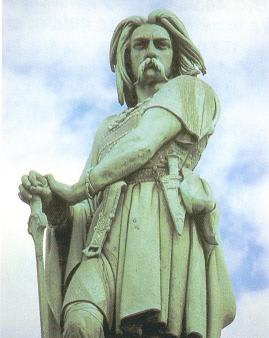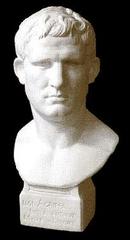ローマ人列伝、まだまだ続きます。
繰り返しますがこの列伝は個人的な趣味で書いているものですから歴史的間違いはご容赦ください。(ご指摘はありがたくいただきます。)
アグリッパ、ヴェルチンジェトリックス、ジューシーと続いてきましたがそれぞれ武将として優れまたドラマティックな人生でした。
しかし今回のティベリウス、あらかじめ言っときますが戦争での華々しいエピソードはありません。いや、正確に言えばアグリッパに負けず劣らず優秀な軍人だったのです。彼はローマという大帝国の中で運命を翻弄されます。しかし彼の人生は冷たく穏やかな鏡のよう。大きな台風の中でもその中心には風が吹いていないように彼の人生もまた静かに流れていきます。

生まれは紀元前42年ですから、カエサル死後2年くらい、ちょうどアウグストゥスがカエサルを継いですぐくらいです。
父は名門ティベリウス家の人。当時ティベリウスったらたくさんの政治家を輩出している名家でした。芸能界の海老名家みたいなもんです。
母はリウィア・ドルシッラ。クラウディウス氏族からリウィウス氏族の養子となったマルクス・リウィウス・ドルスス・クラウディアヌスの娘。うーん言葉の意味は良くわからんがとにかくすごい自信だ。
簡単に言うといいところの坊ちゃん、ということです。三国志で言うと名門袁家みたいなもんです。三代四公でしたっけ?四代三公でしたっけ?忘れたしどうでもいいけど。
もし50年前に生まれていれば彼は当然のごとく元老院入り(当時の国会みたいなもの)どころか文連委員長や学実委員長、そしてキャリアのトップであるローマ執政官(言わば総理大臣)にも当然なっていたでしょう。そういう家です。
しかし生まれた時代が悪かった。15、16、17と私の人生暗かった~、っと。
父は名門が故に体制派、時代はちょうどカエサルにより反体制が体制に移り行く時代です。長年にわたり5世紀にも渡る共和制という「体制」が崩壊を迎えつつある時代。カエサルの死を継いだアウグストゥスとは対立する勢力にいた父に連れられティベリウスは生まれたときから各地を転々とすることになります。
母に抱かれ敵から逃げる名門の子。本来であればローマのど真ん中でぬくぬくと育っていてもいい人です。それが辺境の町から町へ。当時、ティー坊はまだ乳児と言っていい年齢ですからどんな思いだったのかはわかりません。ばぶーとだけ言っていたでしょう。
戦乱が終わり、一家はローマへと戻ります。敗北者とはいえ名門は名門。キャリアはこれから、という話ですがそこに運命の偶然が起こります。
母リウィアを皇帝アウグストゥスが見初めたのです。


(リウィアとアウグストゥス)
この辺は結構適当な当時のローマ人。バツ一、バツ二とかあんまり気にしない人たちです。人の妻を取るのもまぁお互いが納得しているんならいいんじゃなーい、という感じです。皇帝とは言え無理をすればいちいちうるさい元老院とスキャンダル好きのローマ市民が黙っていません。このことからもこの結婚は一応、妻も旦那も納得の上だったと考えられます。
ティー坊の父母はアウグストゥスにより離縁され、母は皇帝の妻となります。そしてティー坊は父に引き取られ、母の愛を知らずに育つことになります。このときティー坊3歳。またもやばぶーと言っていたでしょう。
成長した彼はまず軍人としてキャリアをスタートさせます。奇しくも父の敵だったアウグストゥス軍の一員として。彼はずいぶん優秀な軍人だったようでいくつかの凱旋式にも参加しています。ばぶーと言いながら。いや言ってないけど。
彼は現皇帝の奥さんの実子です。もし普通の世であればどんどん出世したのかも知れません。現皇帝のアウグストゥスはすべてにおいて公平な人でした。しかしひとつだけ、執着したことがありました。それは自分の「血」です。ティー坊は今の奥さんの子ですが自分の血は引いていません。邪魔な存在ではありませんが愛する相手でもありません。ティー坊は一将軍として生きていくことになります。
結婚もしました。相手は皇帝の右腕アグリッパの娘ウィプサニアです。しかしその頃にはアグリッパはその娘の母とは離婚し、アウグストゥスの娘と結婚していました。ぱっと見、いい結婚のように思えますが、よくよく考えるとなんと言うか余りモノを押し付けられたような感じもします。ただティー坊自身は幸せでした。息子もばぶーと言ってましたし。
しかし、運命は彼を幸せなままにしておいてくれないのです。
…to be continued.
繰り返しますがこの列伝は個人的な趣味で書いているものですから歴史的間違いはご容赦ください。(ご指摘はありがたくいただきます。)
アグリッパ、ヴェルチンジェトリックス、ジューシーと続いてきましたがそれぞれ武将として優れまたドラマティックな人生でした。
しかし今回のティベリウス、あらかじめ言っときますが戦争での華々しいエピソードはありません。いや、正確に言えばアグリッパに負けず劣らず優秀な軍人だったのです。彼はローマという大帝国の中で運命を翻弄されます。しかし彼の人生は冷たく穏やかな鏡のよう。大きな台風の中でもその中心には風が吹いていないように彼の人生もまた静かに流れていきます。

生まれは紀元前42年ですから、カエサル死後2年くらい、ちょうどアウグストゥスがカエサルを継いですぐくらいです。
父は名門ティベリウス家の人。当時ティベリウスったらたくさんの政治家を輩出している名家でした。芸能界の海老名家みたいなもんです。
母はリウィア・ドルシッラ。クラウディウス氏族からリウィウス氏族の養子となったマルクス・リウィウス・ドルスス・クラウディアヌスの娘。うーん言葉の意味は良くわからんがとにかくすごい自信だ。
簡単に言うといいところの坊ちゃん、ということです。三国志で言うと名門袁家みたいなもんです。三代四公でしたっけ?四代三公でしたっけ?忘れたしどうでもいいけど。
もし50年前に生まれていれば彼は当然のごとく元老院入り(当時の国会みたいなもの)どころか文連委員長や学実委員長、そしてキャリアのトップであるローマ執政官(言わば総理大臣)にも当然なっていたでしょう。そういう家です。
しかし生まれた時代が悪かった。15、16、17と私の人生暗かった~、っと。
父は名門が故に体制派、時代はちょうどカエサルにより反体制が体制に移り行く時代です。長年にわたり5世紀にも渡る共和制という「体制」が崩壊を迎えつつある時代。カエサルの死を継いだアウグストゥスとは対立する勢力にいた父に連れられティベリウスは生まれたときから各地を転々とすることになります。
母に抱かれ敵から逃げる名門の子。本来であればローマのど真ん中でぬくぬくと育っていてもいい人です。それが辺境の町から町へ。当時、ティー坊はまだ乳児と言っていい年齢ですからどんな思いだったのかはわかりません。ばぶーとだけ言っていたでしょう。
戦乱が終わり、一家はローマへと戻ります。敗北者とはいえ名門は名門。キャリアはこれから、という話ですがそこに運命の偶然が起こります。
母リウィアを皇帝アウグストゥスが見初めたのです。


(リウィアとアウグストゥス)
この辺は結構適当な当時のローマ人。バツ一、バツ二とかあんまり気にしない人たちです。人の妻を取るのもまぁお互いが納得しているんならいいんじゃなーい、という感じです。皇帝とは言え無理をすればいちいちうるさい元老院とスキャンダル好きのローマ市民が黙っていません。このことからもこの結婚は一応、妻も旦那も納得の上だったと考えられます。
ティー坊の父母はアウグストゥスにより離縁され、母は皇帝の妻となります。そしてティー坊は父に引き取られ、母の愛を知らずに育つことになります。このときティー坊3歳。またもやばぶーと言っていたでしょう。
成長した彼はまず軍人としてキャリアをスタートさせます。奇しくも父の敵だったアウグストゥス軍の一員として。彼はずいぶん優秀な軍人だったようでいくつかの凱旋式にも参加しています。ばぶーと言いながら。いや言ってないけど。
彼は現皇帝の奥さんの実子です。もし普通の世であればどんどん出世したのかも知れません。現皇帝のアウグストゥスはすべてにおいて公平な人でした。しかしひとつだけ、執着したことがありました。それは自分の「血」です。ティー坊は今の奥さんの子ですが自分の血は引いていません。邪魔な存在ではありませんが愛する相手でもありません。ティー坊は一将軍として生きていくことになります。
結婚もしました。相手は皇帝の右腕アグリッパの娘ウィプサニアです。しかしその頃にはアグリッパはその娘の母とは離婚し、アウグストゥスの娘と結婚していました。ぱっと見、いい結婚のように思えますが、よくよく考えるとなんと言うか余りモノを押し付けられたような感じもします。ただティー坊自身は幸せでした。息子もばぶーと言ってましたし。
しかし、運命は彼を幸せなままにしておいてくれないのです。
…to be continued.