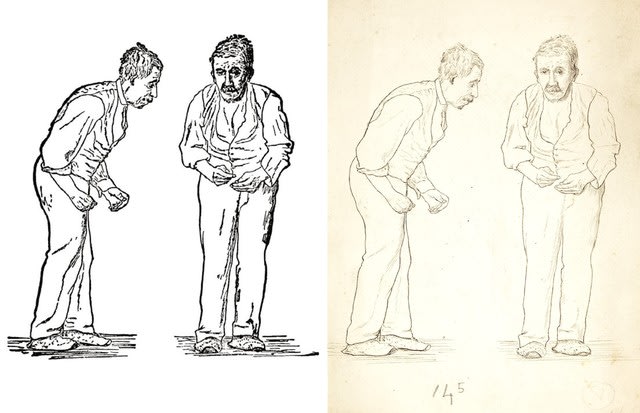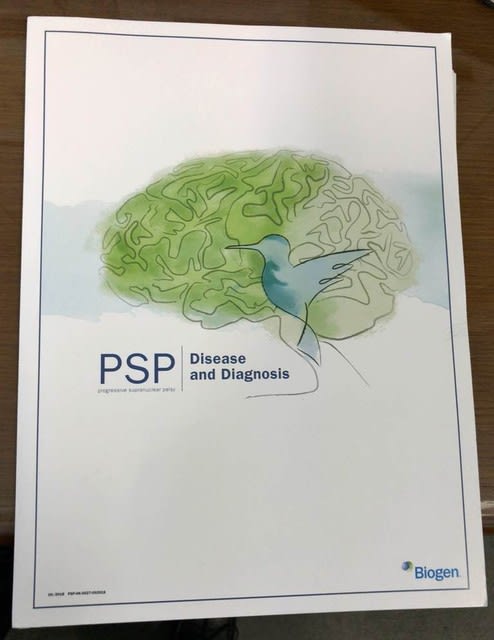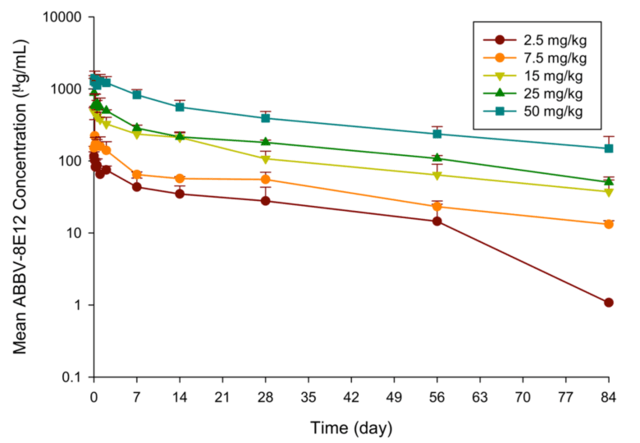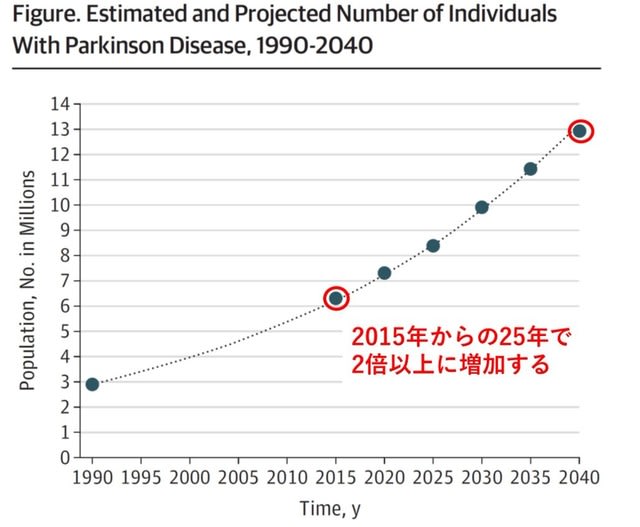パーキンソン病・運動障害疾患コングレス(MDS2019)の目玉企画は,世界各国の学会員が経験した症例のビデオを持ち寄るビデオ・チャレンジです.各症例の不随意運動をいかに評価し,診断・治療に結びつけるか,壇上のエキスパートが議論しますので勉強になります.しかし各国,選りすぐりの症例ですので正しく診断することはなかなか難しいです.それと今年は初めてのことが2つありました.
イランからの素晴らしい症例提示があったことと,症例として馬(!)が提示されたことです.ぜひみなさんもトライしてみて下さい.

Case 1(米国)
主訴と病歴のみ提示.右鼻先周辺の顔面筋の痙攣が,2年かけて徐々に増悪し,目に加えて耳(!)まで収縮まで見られるようになった.
➔ 患者は馬だった.
馬のhemifacial spasm.馬の顔面神経の走行や顔面筋の分布の図が提示された.
Case 2(トルコ)
61歳男性.既往歴に糖尿病.1年前からの右手のヘミジストニアないしヘミコレア.1ヶ月で右腕,右足,右顔面に進展した.軽度の構音障害,下肢腱反射消失.家族内類症・血族婚なし.フェリチン異常高値.頭部MRIで基底核に鉄沈着.
➔
遺伝性無セルロプラスミン血症(セルロプラスミン遺伝子フレームシフト変異ホモ接合).本症の三徴は,糖尿病,網膜変性症および中枢神経症状(不随意運動,小脳性運動失調,認知症).
Case 3(インド)
32歳女性.5年前から行動異常と四肢・体幹の不随意運動.坐位・立位で落ち着かず,体を前後に揺らす(電気生理学的に固有脊髄性ミオクローヌス)..易怒性と妄想.追視困難,緩徐なサッケード.頭部MRI異常なし.
➔
遺伝性低セルロプラスミン血症(セルロプラスミン遺伝子ミスセンス変異ヘテロ接合:既報告の変異).通常は小脳性運動失調症を呈するが,まれにこのような表現型を呈する.
ここでHonorable mentionとして,応募者によるプレゼンはないものの興味深い症例が紹介された.まず3症例が紹介され,1つめは
SCA17(進行性ミオクローヌスてんかんを呈しうる疾患の鑑別),2つめは
ARSACS(Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay)で網膜有髄神経線維の増生やT2 強調画像の橋の線状の低信号,3つめが
AOA4(Ataxia-oculomotor apraxia type 4:PNKP遺伝子重複,10歳台に発症し,失調とジストニア,眼球運動失行,ニューロパチーを呈する.頭部MRIでオリーブ核肥大)が紹介された.
Case 4(イラン)
金メダル受賞!
3歳男児.両親血族婚.発達遅滞.生後4ヶ月から首の不随意運動.3歳でウイルス性呼吸器感染後に急性増悪し,救急外来を受診.頸部と上肢の激しい舞踏運動.歩行・発語不能.テトラベナジン,L-dopa無効だったが,プラミペキソールで劇的に改善した.
➔ 全エキソーム解析で(ドパミントランスポーターをコードする)SLC6A3遺伝子変異の同定.つまり
ドパミントランスポーター欠損症の診断.常染色体劣性遺伝.パーキンソニズム,コレア,バリズム,口舌ジスキネジアなどを呈する.
Case 5(ドイツ)
42歳男性.両親は血族婚.Floppy infantで,脳性麻痺と診断された.青年期から夜間を中心に,頸部と腕の,激しくjerkyな不随意運動(ミオクローヌス+ジストニア)が出現,昼は改善する.低トーヌス.女性化乳房.顕著な喫煙(ニコチン)依存.頭部MRI異常なし.瀬川病はGTPシクロヒドロラーゼⅠ遺伝子検索で否定.
➔ 全エキソーム解析でセピアプテリン還元酵素遺伝子ナンセンス変異ホモ接合.
セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症.本症は3種の芳香族アミノ酸水酸化酵素の補酵素テトラヒドロビオプテリン(BH4)の生合成に関わるSRをコードする遺伝子の異常により,BH4の欠乏を来す常染色体劣性遺伝性疾患.日本でも報告例はあるが極めてまれ.本例はL-dopa 300 mgが有効であった.
ここで2 short casesとして,光過敏性てんかんの2疾患の提示.1つめは
Jeavons症候群の2歳男児.小児期発症の特発性全般てんかんで,欠神発作と眼瞼ミオクローヌスを呈する(眠そうに閉眼する不随意運動だった).2つめは
サンフラワー症候群の9歳男児.光過敏性てんかんによる手を振るような,一見不随意運動に見える発作の紹介があった.さらに光過敏性てんかんということで
「ポケモン症候群」の紹介があった.
Case 7(米国)
70歳男性.30歳台から精神症状,パーキンソニズム,50歳台から歩行障害,転倒,姿勢時振戦などのパーキンソニズムが出現.家族内にパーキンソン病多数.L-dopa有効・・・・頭部MRIにてeye of the tiger sign.
➔
PKAN(Pantothenate kinase-associated neurodegeneration)非典型例(PANK2遺伝子変異).20-30歳台で遅れて発症する非典型例は,精神症状,顔面ジストニア,パーキンソニズム,コレア,認知機能障害を呈し,経過も緩徐進行性である.
Case 8(メキシコ)
33歳女性.5ヶ月前から体重減少,咳,発熱,呼吸困難.2週間の経過で,左下肢主体のヘミバリズム.左足首はコレア様.視神経乳頭浮腫.頭部MRIでは多発異常信号病変(脳梁,橋,右基底核).
➔
結核性髄膜脳炎によるヘミバリズム・ヘミコレア.
Case 9(メキシコ)
66歳男性.2年前から性格変化,近時記憶障害.診察では核上性垂直方向性注視麻痺と運動緩慢を認め,PSP疑い.起立性低血圧,感情失禁あり.頭部MRIで広範で非対称な白質病変+両側基底核病変・・・毛嚢炎,口腔内アフタ.
➔
神経ベーチェット病.運動異常症を呈することは通常まれだがあり得る.ちなみにPSPで起立性低血圧を合併することはまれ(Neurology. 2019 Sep 4. pii: 10.1212/WNL.0000000000008197.).
ここでHonorable mentionとして,自己免疫性脳炎の4症例の紹介.1つめは
抗DPPX抗体脳炎,2つめは
抗CASPR2抗体脳炎でコレア合併例,3つめは
抗IgLon5抗体脳炎でコレア合併例.最後が一側下肢のpiloerection(立毛筋の逆立ち)を呈した
抗LGI1抗体脳炎であった.
Case 11(ドイツ)
69歳男性.2年前からのしゃっくり,腹部の不随意運動.電気生理学的に固有脊髄性ミオクローヌス.ポリニューロパチーも合併.腫瘍合併なし.
➔
抗CASPR2抗体によるisolated segmental spinal myoclonus.免疫療法(ステロイド,アザチオプリン)にて改善.イギリスからの同様の症例(腫瘍合併あり;Neurology. 2018;90:660-661)の紹介.
Case 12(オランダ,チェコ)
同一疾患の2症例の提示.ともに偶然45歳女性.オランダ例は出生時からの不随意運動で緩徐に進行.チェコ例は歩行時と発語時の運動異常が主徴で,脳性麻痺の診断.
➔
グルタル酸血症1型.グルタリルCoA脱水素酵素(GCDH)の障害によって生じる常染色体劣性遺伝性疾患.生後3−36か月の間に,胃腸炎や発熱を伴う感染などを契機に,急性脳症様発作にて発症する.
ここでHonorable mentionとしてジストニア関連の4例の紹介.1つめが全身性ジストニアを呈した母・息子例で,
IRF2BPL(interferon Regulatory Factor 2 Binding Protein Like)遺伝子変異例.全身性ジストニアに発語障害,緩徐眼球サッケードを呈する.のこり2例がジストニアに対してGPi-DBSが有効であった症例(うち1例は順天堂大学からの報告).いずれも
GNAO1遺伝子変異であった.難治性てんかん,知的障害,運動発達障害,不随意運動を呈する.ちなみにGNAO1は3量体Gタンパク質のαサブユニットをコードし,細胞内シグナル伝達に関与する.最後が
ATP1A3遺伝子変異例で,3つの表現型があることが紹介された.(1)小児交代性片麻痺(alternating hemiplegia of childhood;AHC),(2)小脳失調症深部反射消失凹足視神経萎縮感覚神経障害性聴覚障害(CAPOS)症候群,(3)rapid-onset dystonia parkinsonism(RDP)である.
Case 13(フランス)
銀メダル受賞!
68歳男性.急性発症の姿勢時振戦,歩行の不安定,めまいにて救急外来を受診.下向き眼振を認めた!15年前に膀胱がんの既往.II型糖尿病.高コレステロール血症.2012年からの6年間で同様のエピソードを4回繰り返し,2-6週間症状が持続して回復.うち2回では全身性痙攣と認知機能低下を合併した.頭部MRIで皮質下萎縮.脳波で徐波の混入・・・血清マグネシウム著明低下.マグネシウム補充にて回復.
➔ 糖尿病に伴う
腎性低マグネシウム血症.低マグネシウム血症はさまざまな症状(食欲低下,嘔気,不整脈,突然死)を呈する.下向き眼振が特徴的とのこと.
Case 14(イタリー)
56歳女性.ヘビースモーカー.甲状腺機能低下症術後で,数日前から興奮,昏迷状態.上肢の常同運動(stereotypies),一部振戦様.
➔
ビタミンB12欠乏症に伴う脳症.意識障害と常同運動,不随意運動を呈しうる.頸部手術のためビタミンB12欠乏に伴う典型的な神経所見がわかりにくかった.また喫煙はビタミンB12欠乏の増悪因子として知られている.
ここでHonorable mentionとして2例が紹介された.1つめは
チトクロムc酸化酵素欠損症(Cytochrome C oxidase (COX) deficiency).COXはミトコンドリア電子伝達系末端の酵素複合体(複合体IV)で,その遺伝子は核とミトコンドリア両方にコードされるため,常染色体劣性または母系遺伝を呈する.リー脳症,致死性乳児心臓脳筋症,レーバー遺伝性視神経萎縮症などさまざまな表現型を示す.2つめは頭痛,感音難聴,糖尿病,筋萎縮,脳卒中を呈した59歳男性で
MELASであった.
Case 15(米国)
69歳男性.57歳時に左下肢の刺激誘発性の進行性不随意運動(振戦).2014年には歩行に振戦が出現し,転倒が見られた.2017年には振戦が常時見られるようになった.姿勢保持障害も出現した.高頻度の口蓋ミオクローヌスと声帯の振戦を認めた.69歳で死亡.剖検でオリーブ核肥大.
➔
治療抵抗性セリアック病2型.下肢の刺激誘発性のミオクローヌスは特徴的徴候.高頻度の口蓋ミオクローヌスと声帯の振戦も報告がある.セリアック病に関連した自己免疫疾患らしい.
ここでHonorable mentionとして2例が紹介された.1つめは首と音声の振戦を認めた副腎白質ジストロフィー.2つめは進行性の歩行障害を呈し,画像上認めた水頭症様変化に対しシャント術が行われた神経軸索スフェロイドを伴う遺伝性び慢性白質脳症(HDLS;CSF1R遺伝子変異)であった.
Case 16(米国)
銅メダル受賞!
24歳男性.生後5ヶ月から発作性に首を回すような不随意運動が出現.成人してからも下肢の不規則で振幅の大きい不随意運動が,週2回の頻度で,教会に行く月曜と水曜日に誘発される(労作による誘発).寝不足,絶食,カフェインでも誘発される.
➔ SLC2A1遺伝子変異ヘテロ接合に伴う
グルコーストランスポーター1 (GLUT1)欠損症.発作性労作誘発性ジスキネジアの原因としてSLC2A1遺伝子のヘテロ接合性変異が同定された.典型例とは異なり,てんかん発症年齢は遅く,髄液糖低値も有意でないので注意を要する.
【前日に行われたグランドラウンド4症例】
Case 1
53歳男性.右手ジストニア.後頸部の再発性lipoma.母親は糖尿病.
➔
MERRF(Myoclonus epilepsy associated with ragged-red fibers)
Case 2
44歳男性.32歳歩行障害.36歳不随意運動,38歳認知機能障害,小脳性運動失調,すくみ足.常染色体優性遺伝の家系.
➔
SCA48(STUB1ミスセンス変異ヘテロ接合).この遺伝子は常染色体劣性のSCAR16の原因遺伝子として知られていたが,ヘテロ接合で常染色体優性の脊髄小脳変性症になることが昨年報告されている(Neurology 2018;91(21):e1988-e1998).
Case 3
27歳女性.安静時の舌の振戦,手指にも振戦.歩行正常.家族歴,血族婚なし.頭部MRIにてeye of the tigerサイン.
➔
PKAN(Pantothenate kinase-associated neurodegeneration)
Case 4
急性発症のジストニアとパーキンソニズムを呈した男性例..
➔
rapid-onset dystonia parkinsonism(RDP; ATP1A3遺伝子変異)