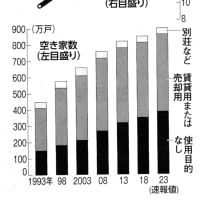この反応に対して、7月6日に戻ってきた査読結果は次のようなものでした。
Thank you for your patience in the time it has taken to move through these revisions. Including one more round - which should adequately address the subject editor's remaining issue with the qualitative values that was also a major concern of the other reviewer.
(これまでの修正に要した間の忍耐、ありがとうございました。課題編集者が気にしている残りの質的価値のある点 - それはもう一人の査読者の主な関心事でもあります- に適切に対応するもう1ラウンドをお願いします)
微細な修正を求められはしましたが、大筋で了解してもらえました。こうなれば、マラソンで言えば最後の競技場が見えたということです。そして7月13日についに以下の
連絡がありました。
It is a pleasure to accept your manuscript entitled "Diets of sika deer invading Mt. Yatsugatake and the Japanese South Alps in the alpine zone of central Japan" in its current form for publication in Wildlife Biology.
(貴殿の「日本中部の八ヶ岳と南アルプスの高山帯に侵入しつつあるニホンジカの食性」と題する原稿を現在の形でワイルドライフ・バイオロジーに喜んで受理します)
(貴殿の「日本中部の八ヶ岳と南アルプスの高山帯に侵入しつつあるニホンジカの食性」と題する原稿を現在の形でワイルドライフ・バイオロジーに喜んで受理します)
フクロウ論文の時のように、良いものにするために色々アドバイスをくれるというのではありませんでしたが、査読者としては自分のアドバイスに対して素直に従わずに、自分たちの主張を曲げなかったのですから、日本の査読者であれば、意地悪く却下する可能性は大いにあったわけです。そういうことに慣れてしまうと、査読者に無意味に従順になる、あるいは媚びたような態度をとることになりかねません。私は残念ながら、日本の査読者にそういう意地悪な姿勢があると断言できます。だからできれば海外の雑誌に投稿する傾向があります。若い研究者が投稿して、意地悪な査読をされれば、査読とはそういうものだと思うようになることは無理のないことで、それは本当によくないことで、心配です。
翻ってスポーツのレフェリーのことを考えると、レフェリーは絶対的な存在です。それだけに、レフェリーは誤審がないように厳しい訓練をするし、ラグビーやサッカーのレフェリーは現役の選手に引けを取らないくらい走ります。しかし私は日本の論文査読者が査読する精神や技術の訓練を受けたという話を聞いたことがありません。大学院生くらいの時に論文を書き始め、意地悪い査読を受けた人は、研究者になって査読をするようになった時、自分がされたと同じような「査読」をするようになるというのはありそうなことです。そういう悪い循環は断ち切らないといけません。
高山のシカの論文では、ちょっと危険と思いながらも筋を通し、それが理解されました。それは科学をする者として爽やかな体験でした。