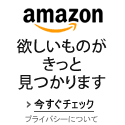今日もお教室あり。いつものように駅に送迎の時、行く時は良い天気だったのに、段々暗くなって来たのね。お客さんを拾ってアトリエに着く頃には、向こうは完全に雨だな・・・って雲行き。ひとまず間に合ったのね。
ただ数時間後には土砂降り・・・天気予報は大当たり。風も強いし・・・そんな中、お教室は?と言うと、手慣れて来た事もあって、随分と切る事が上手くなって来ていて、少しまとまって来た場所もあって、何を作っているか?が判る感じ。
そうなって来ると、慣れたのは切るだけじゃ無くて、眼も慣れるモノで・・・以前張った部分に気に入らない所が発生したりするのね。これは良くある話で、1日では終わらない作品の場合、手のひらにも満たない位が1日分のペースなのね。
では次はいつ?となると、月に1回なら1か月後。中には月に3回って人もいたりすると、当然進み具合は変わって来るんだけれど・・・例えば、生き物だとして、顔の毛並みなんて箇所をやったとする。するとホッペの一部位しか終わらない。
そして来月・・・その時に、前回はこの色を選択したんだけれど、もっと濃く感じるとか、逆に薄く感じるって事が起こったりするのね。それは単独の1色の時のスタートと、何色も使って来た頃合いとでは、雰囲気が変わって来るのね。
最初、思い切りの良い人なら、濃い目スタートなんて事になる。逆に極端に濃いのが好きじゃ無いって人は、薄めになる。ここが絵画と違う所で、選ぶだけだから、混ぜるテクニックはいらない分、平等なのね。何を選ぶか?は。
その時に絵画なら、その色に近寄せる為に色々混ぜて、そっくりに色を作るって事になるのね。所がモザイクは混ぜられないから、どれを選択する?になる。その時に好きか嫌いか?なんて自分の好みでスタートすれば、これ嫌、これ嫌と、
消去して残ったもので、これか・・・って言う選択の仕方だったり、ピンポイントでこれ・・・と迷わず好みに行くってパターンがある。このどちらの場合でも、自分の好みで選んだので、モチーフファーストでは無くて、自分ファーストで
スタートしたのね。それならそれも良いのね。だったら、それを考え方として、モチーフはこの色なんだけれど、自分はこの色にした・・・って事になるから、次はだったら、あの色をこの色に変えたんだから、この色はこれかな?
みたいな変換が必要なのね。所が間違いやすいのは、好きな色を随時選びたくなるのね。そうすると、本来そこにその色を選んだのなら、ここもその色になるはずって場所を、1か月後の自分が同じ色を選べるか?になるのね。
それを気分で好きに決めると、一貫性を失うから、どんどんモチーフから離れ、似ていなくなって行くのね。つまり1日目の1色目はそれが基準になるものなのね。更にその上、あっちもこっちもとなって来ると、濃いのが嫌いだと、パンチが
無くボヤッとするし、逆に濃い味好きでも、全体に濃くなるから、場合に寄っては最後は黒なんて事になるけれど、流石に濃い味好きでも黒に手を出せる?となると、躊躇したりして・・・。後押ししたり、引き留めたりしないとならないのね。
そんな中、比較する色が多くなると、段々それが判りやすくなると、自分でもここが薄いとかここが濃いとか、判りやすくなって来て、剥がしたくなるのね。勿論、それが重要な場所なら剥がしても良いが、その効果が薄ければスルー。
逆に今度はそっくりに真似よう・・・とする場合、似た色がある時は良いが、無い時に困るのね。安易にやると、あった・・・無いからこれで良いや・・・の繰返しになるのね。そうなるとそっくりにならなくなる。
考え方として、そっくりにはならないけれど、風味とかもどきとか、雰囲気を似せるのね。その時のコツが色の温存なのね。いかにこの色を多く使いたいから、この色をここに使うとしたら、ここは・・・何?って感じに。
こう説明すると、そっきの後半の話に似ているんだけれど、大きく違うのは性格なのね。さっきの話は自分の判断で好きか嫌いかで決める人の場合。今の話は好みじゃ無くて、似せたいって趣旨。だから好みを捨てて似せに行っているのに、
その色が無い・・・って悩むのね。この例が楽譜があるか無いか?の考え方に繋がるのね。前者は自由を好むから、好きな色を選んで行くやり方。これは常に考えないとならず、人と違うので、大きく外す事もあるし、上手く行けば満足感満載。
でも似せるに徹するのは、楽譜通りって事になるから、自分の好きにで無い分、良く見て、ちょっとのズレも許さないって言うスタイルの規定演技になる。考えるのでは無くて、遂行するって感じになる。なのに、混ぜられないから作れないし、選びたくてもその色が無い・・・になる。
言い方を変えれば、自由は無いわ、選べないわ、どうしろと・・・になる。実はその不便さがモザイクの難しさであり、そこが腕の見せ所なんだと思うのね。その考え方が、温存する・・・なんだけど。
いかにその特徴である色に近いモノを温存して多く使えるか?そしてその温存した色の影をどれで代用するか?を考える事になるのね。だから常にこれを選んで、これにあった影探し・・・みたいな感覚なんで、常に選択では無くて、最初の
1手のみが選択であって、後はそれに合わせる・・・これがトータルコーディネイト的な考え方で、こんな事が基本になる。ここが出来るようになると、差し色的な個性も出しやすくなるのね。それは基本が安定している分、着崩しがしやすく、その基本がブレると、だらしなくなってしまったりするもので・・・。
ただまだ始まったばかりだから、こんな難しい話は必要無いけれど、とは言え、1.2回で終わるような作品では無いので、ちょっとは必要なのね・・・。まぁそれは頃合いを見て。