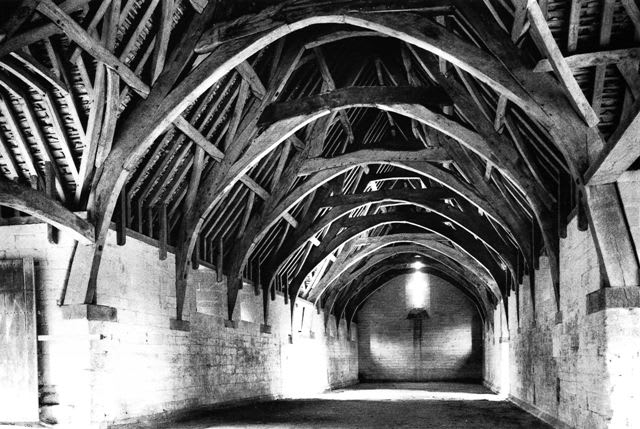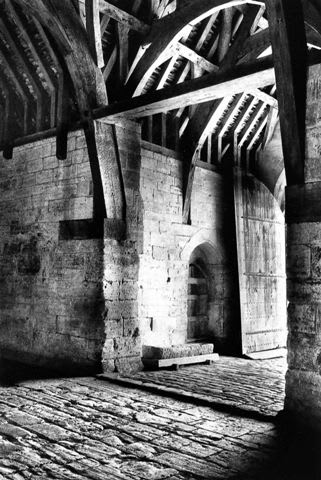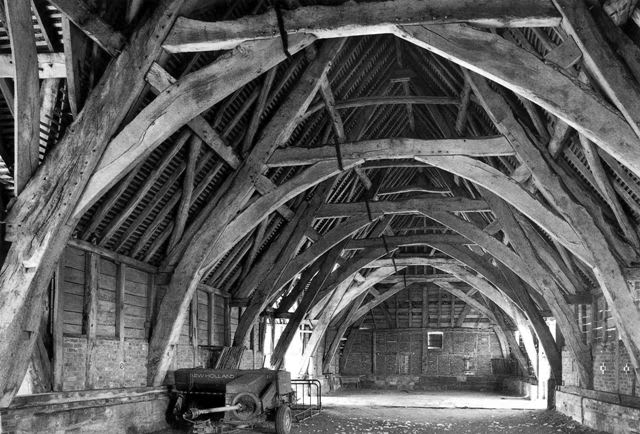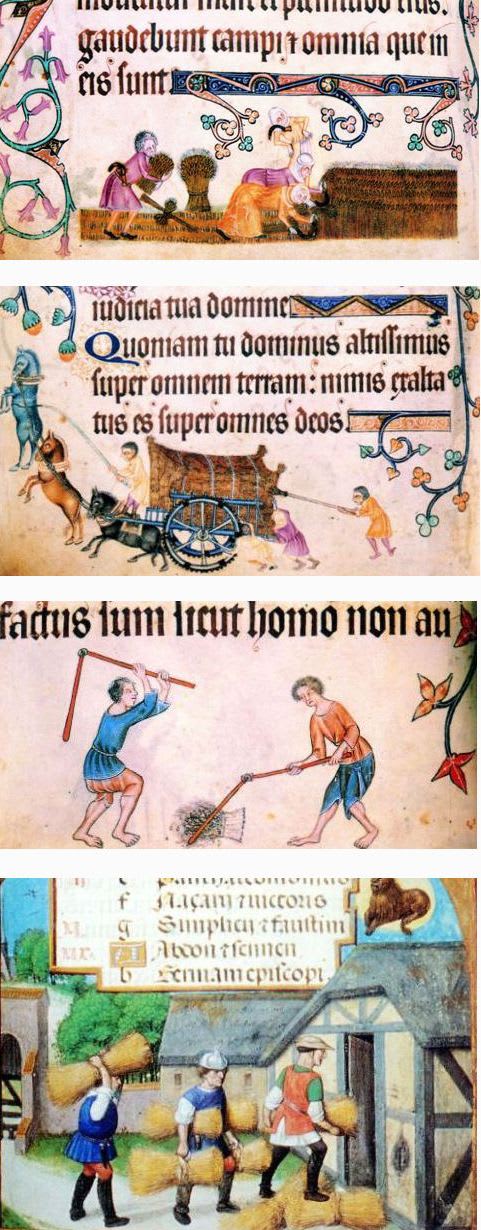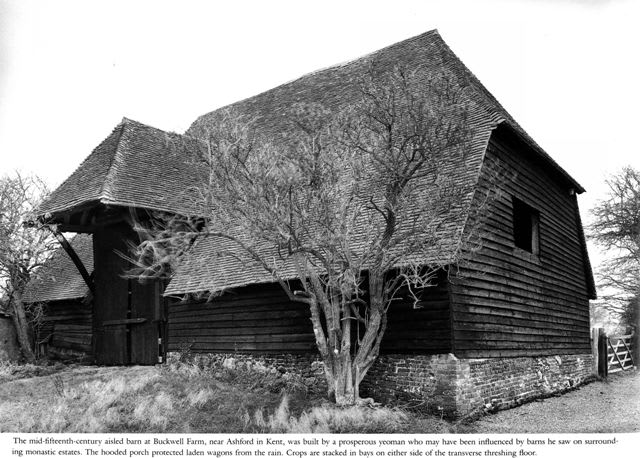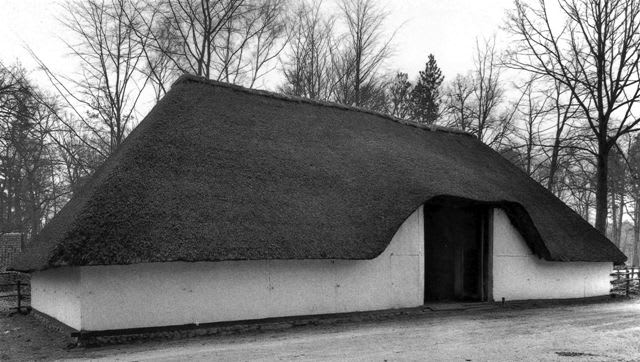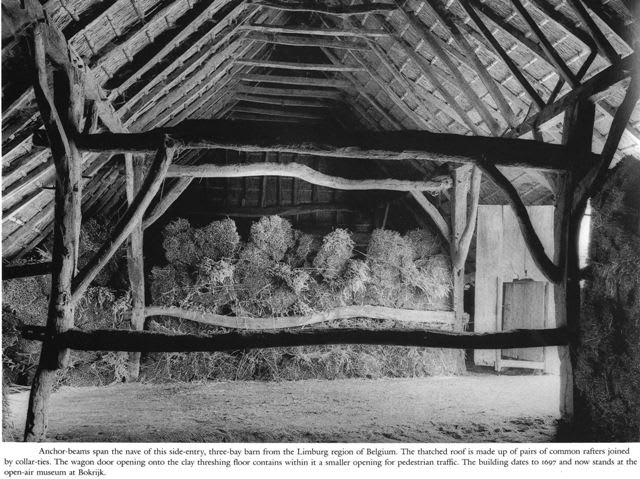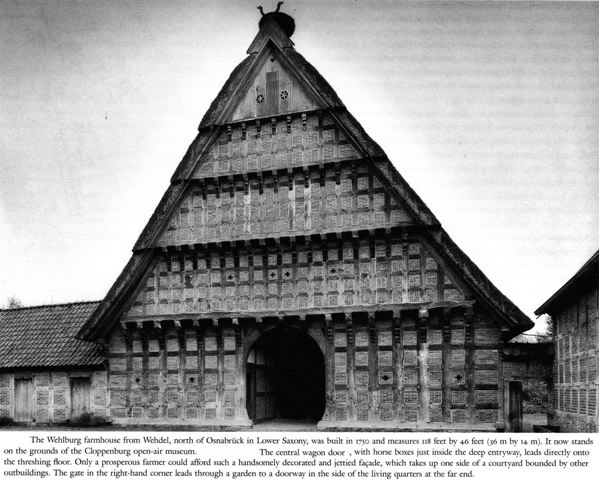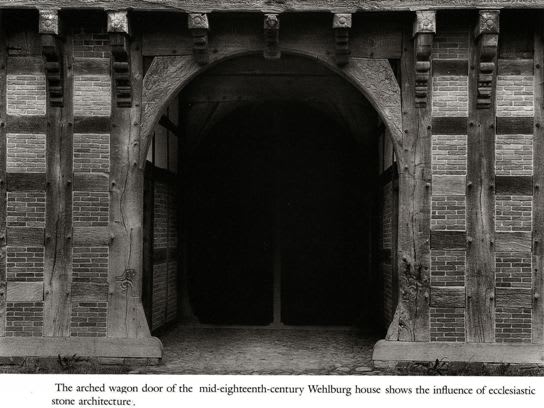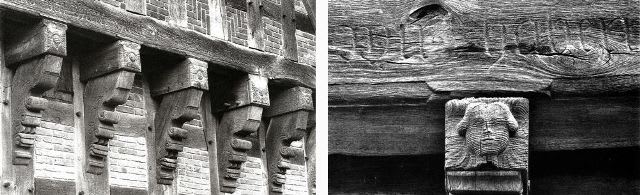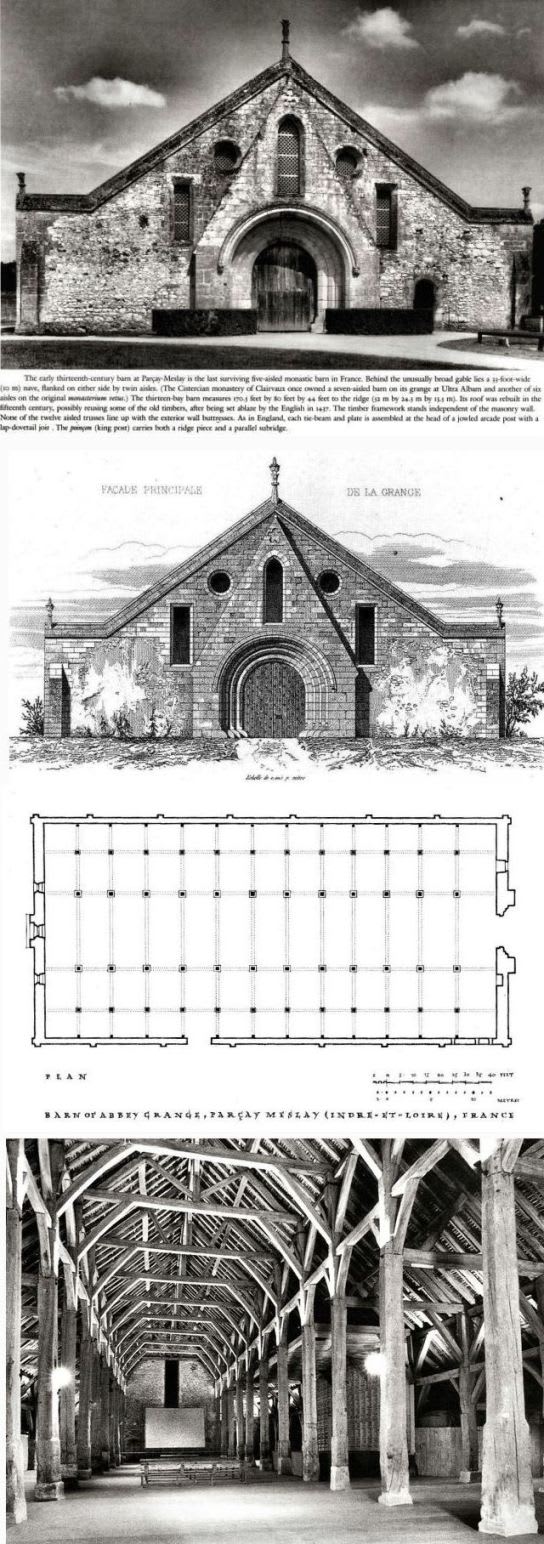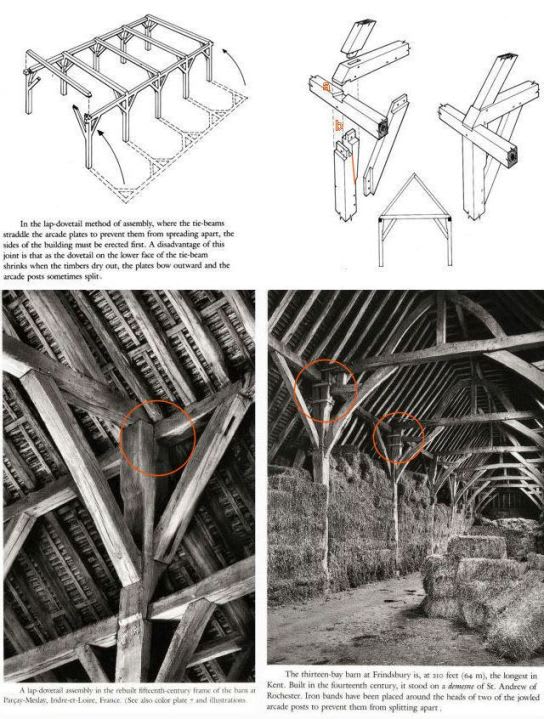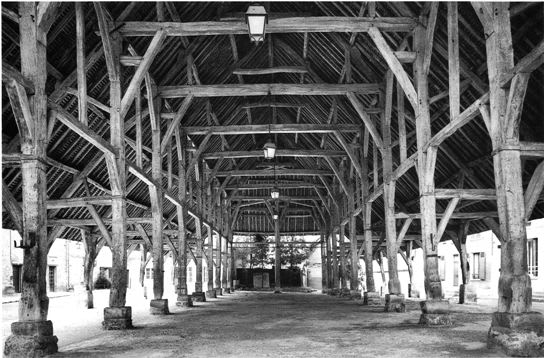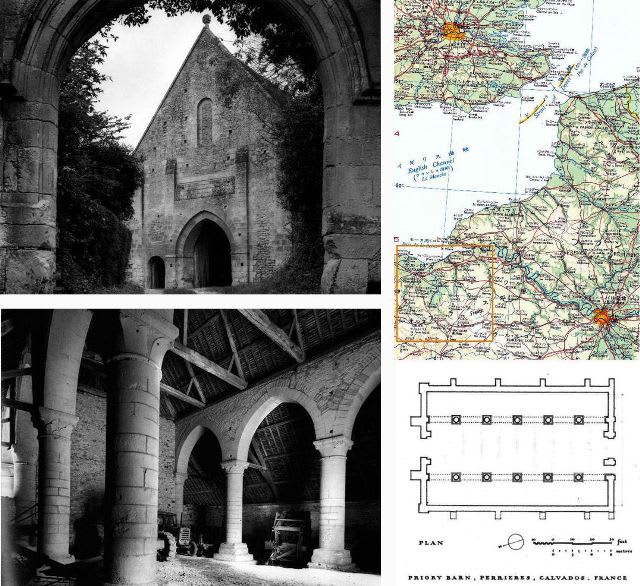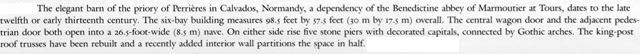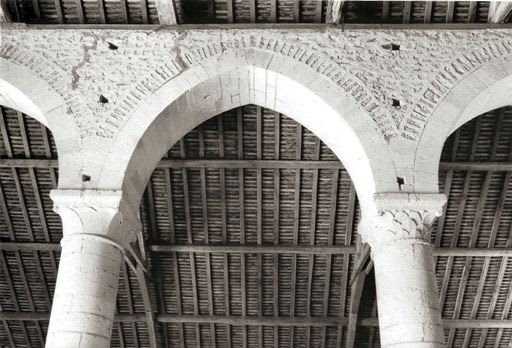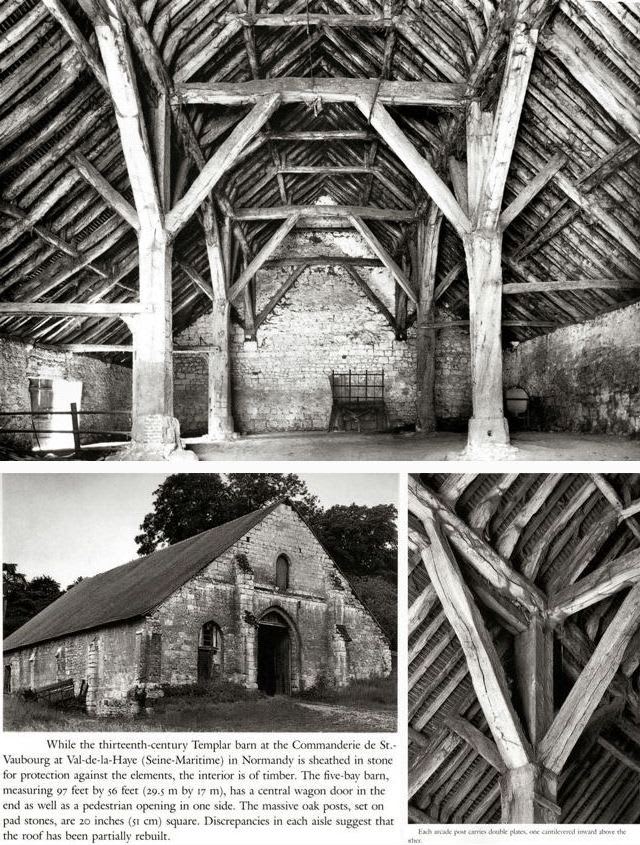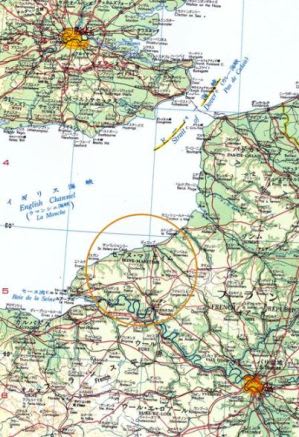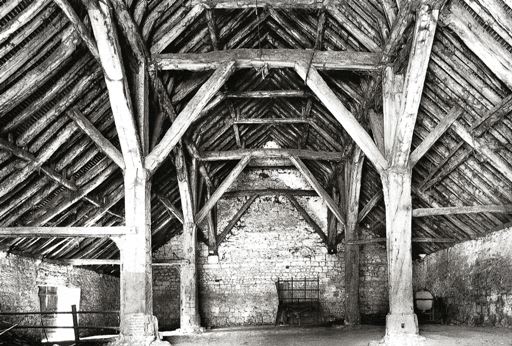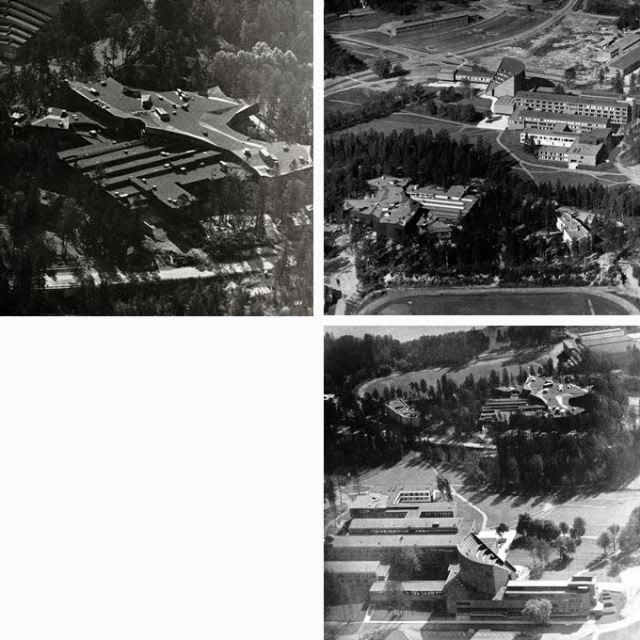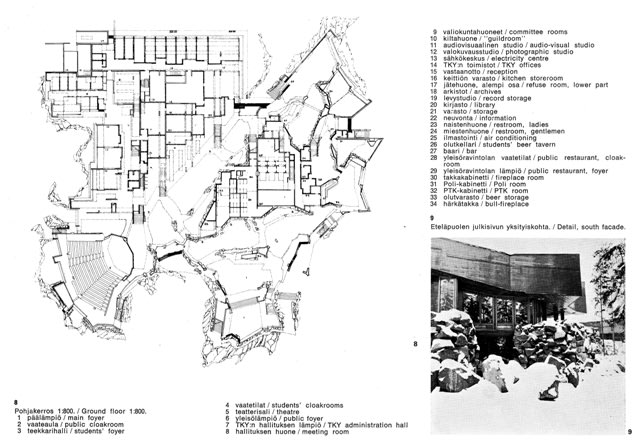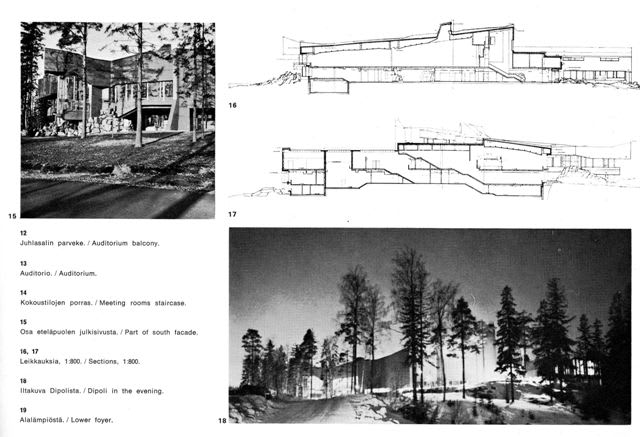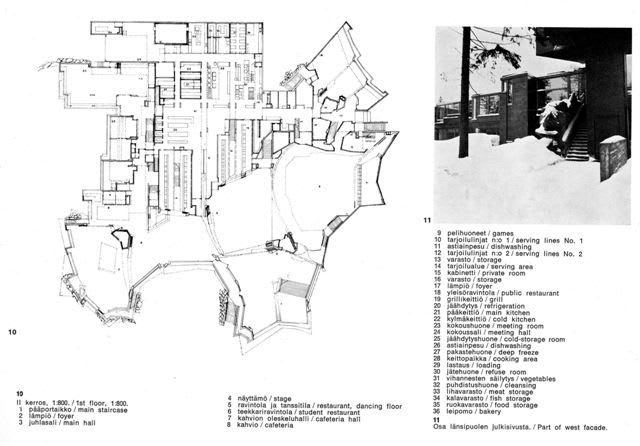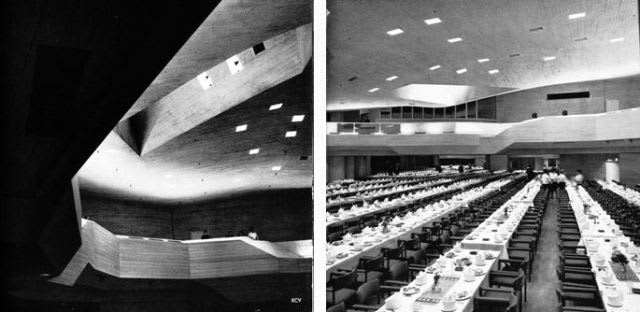ほぼ一段落しましたので、Aisled Barns の紹介から再開します。
******************************************************************************************
[文言追加 26日10.36、10.54][註記追加 27日16.56]
“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介は、今回が最後です。
今回は、ヨーロッパから北アメリカに移住した人びとがつくった bahn 。
移住した人びとは、それぞれ、生まれ故郷のつくりかたで建物をこしらえたようです。
そのため、北アメリカには、ヨーロッパ各地域のつくりかたによる建物が、それぞれの入植地にあります。
今回は、同書に載っているオランダの入植者が18世紀に建てた建物。
Deertz bahn とありますが、Deertz の意味が不明です。固有名詞?
当初、Middleburgh(Schoharie Country), New York に建っていたと説明にありますが、この場所も手持ちの地図では見つかりません。末尾の h のないMiddleburg という地名はワシントンの北にありますが、そこは New York 州ではない。 New York 州は、オンタリオ湖の南部一帯。多分そのあたりの平野部にあるようです。
下の写真は、移築のために下見板( weather boards )を剥がした状態。
「差物」を多用した、と言うより、「横材」はすべて「柱」に「差口」で納めている、骨組が見えます。
「差物」「差口」は、前回までに紹介したヨーロッパの例にも多く見られます。
「差物」「差口」は、決して日本の木造建築の特技ではないのです。誰だって、同じことを考えるのです。

その実測図が下図。柱間は6間。平面は、60ft×50ft(18.25m×15.25m)。
ヨーロッパの bahn との大きな違いは、石の上に直かに柱を立てるのではなく、石の上に流した「土台」上に、「枘差し」で柱を立てていること( tenoned into longitudinal timber sills )。
緩い北斜面に建っていたようです。

「土台」が使われた、ということは、入植者たちが建物づくりに習熟した人たちばかりではなかった、ということを示しているのではないでしょうか。
「礎石」の上に直かに「柱」を立てるには、熟練の技を必要としますが(「礎石」の天端をすべて同じ高さに据えられるとはかぎりませんから、「礎石」ごとに「柱」の長さを調節しなければならない)、「土台」を使用すれば、誰にでもできるからです(「土台」を水平に据えることは比較的容易、そうすれば横材が角材なら、「柱」の長さは全部同じですむ)。
日本の城郭づくりと、同じような状況だったのでは。
「柱」の中途に、床位置とは関係なく「横材」が入っていますが、これは「飛貫」同様の役割を担っているものと考えられます。
以下は、移築時の建て方の様子です。
1990年代の移築ですから、クレーンが使われています。
先ず、「身廊」:上屋に当たる部分を建てます。両妻、そして中央の列を先行したことが分ります。
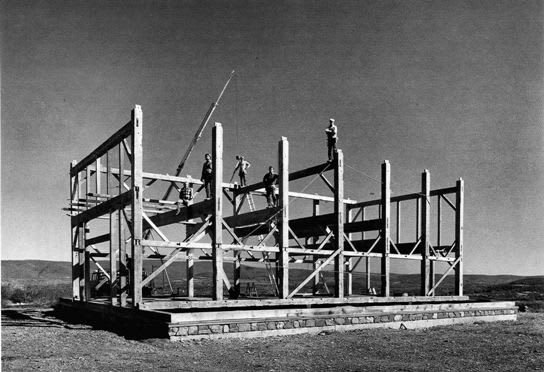
柱の外面に打たれている斜材は、「仮筋かい」。
「仮筋かい」は部分的に入れられていますが、本体に入る斜材は、同じ位置に、すべて入れられていることに留意してください。
入れるなら、全部に入れる、これが「斜材」を入れるときの鉄則。
次は、模型の写真のようですが、左が上の写真の段階の、長手方向から見た写真。
右は、軸部が側廊:下屋 aisle まで組み上がった段階。
まわりの景色は、ヨーロッパの風情ではありません。

次は、「仕口」(「枘差し・込み栓」)のクローズアップと合掌まで仕上がった写真です。これも、まるで模型のよう。
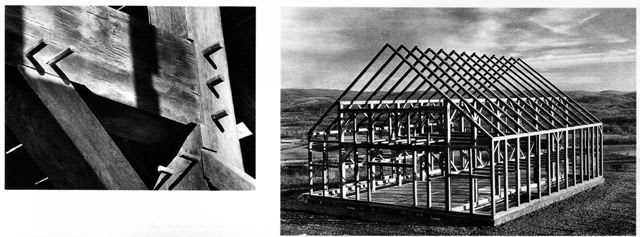
側廊側面の「柱」頂部の「斜材」:「方杖」は、両妻位置と中央の「柱」にのみ設けられていますが、「桁」を中央の柱上で継いでいるからのようです。日本では「肘木」を据えるところです。
******************************************************************************************
ここまで、各地域の木造を主とする Aisled Bahn を紹介してきましたが(イタリア・ドロミテの木造を主とする建物群も過日紹介しました)、人びとが考えることは、洋の東西を問わず、地域によらず、同じである、ということを、あらためて強く感じています。
その土地土地の状況において、人びとはそれぞれなりに建物づくりを考える。
しかし、そのとき人びとが考える「構築の原理」は、結局のところ、同じである、ということです。考えてみれば、きわめて当たり前のこと。
そして、今、日本で、「伝統」「伝統工法」・・と騒いでいることが、ますます馬鹿げたことだ、と私には思えてきました。
なぜなら、日本の建物づくりの「構築の原理」もまた、人びとなら必ず至りつく考えにほかならないからです。
「伝統」「伝統工法」と騒ぐ方がたは、それを「原理」という眼で捉えているようには、思えないのです。単なる「形」としてしか捉えていないように思えるのです。
「伝統」とは、形ではない。もちろんファッションではない。その意が、ますます強くなってきました。
このような日本の「特異な状況」は、ここ1世紀足らずの間の一部の人たちの考え方(耐力壁に依存する考え方)によって人為的に為されてきたこと、その結果生じた現象である、これは、今さら言うまでもないでしょう。
この人たちは、耐力壁に依存する考え方の《普及》のために、「普通の人びと」に「事実を知られないよう」に必死になった。その結果、人びとは「事実を知ること」から遠ざけられてきたのです。[文言追加 26日10.36]
なぜそうしたのか?
自らの《「学」の権威を維持するため》である、としてしか私には考えられません。なぜなら、この人たちの論理には「理」がないからです。
このような状況を「普通の」「当たり前の」状態に戻すには、人びとが「事実を知る」こと以外にありません。
広く、一般に「事実」を開示することです。
「事実」を「一部特権者」の下に秘匿しておいてはいけないのです。
普通の、一般の人びとの存在を無視して、《専門家》が専制的に勝手なことをする、そんなことを放置しておいてよいわけがないのです。
《専門家》が勝手なことができないようにする「最良の策」、それは、「皆が事実を知っていること」、これに尽きるのです。
私はそのように思っています。[文言追加 26日10.54]
註 「伝統」「伝統工法」・・と騒ぐことを馬鹿げたことと思うわけを補足します。
法令を「伝統的工法」の仕様が可能になるように改訂せよ、という「要望・要求」がなされています。
たしかに、そうなれば、当面、「伝統的工法」が「可能になるように見えます」。
けれども、建物づくりの「仕様」は、本来、「場面場面で工夫・考案される」ものです。
法令で規定を定めると、どうなるか。
使える「仕様」が規定され、それ以外は不可。「場面場面での工夫・考案」
言い換えれば、工人の「創意・工夫」は禁じられてしまうに等しいのです。
現に、現行の法令規定によって、私たちは苦労しているではありませんか。
「伝統的工法」仕様が可能になったところで、「創意・工夫」が禁じられることに変りはないのです。
それでいいのですか?「自由」が広がった?狭いより広いからいい?・・・
いわゆる「伝統的工法」は、なぜ、一定の体系にまで仕上がったのか。
それは、つまるところ、年月をかけての「醸成」にあります。
しかし、この「醸成」は、工人たちの「場面場面での創意・工夫」がなければ「なされなかった」。
第一、かつて、工人の「創意・工夫」を「規制」するようなことがあったでしょうか。
法令や「指導」で「創意・工夫」を規制することは、
「技術の固定化」「技術の衰退」を結果する、
これは自明の論理ではないでしょうか。
当面の状況の打開にのみ邁進するのは、私には不可解なのです。「姑息」に写るのです。
[註記追加 27日16.56]
******************************************************************************************
今回の最後に、講習会の「案内」をさせていただきます。
下記をご覧ください。
こういう event 案内に徹したHPがあるのを、初めて知りました!
http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416
******************************************************************************************
[文言追加 26日10.36、10.54][註記追加 27日16.56]
“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介は、今回が最後です。
今回は、ヨーロッパから北アメリカに移住した人びとがつくった bahn 。
移住した人びとは、それぞれ、生まれ故郷のつくりかたで建物をこしらえたようです。
そのため、北アメリカには、ヨーロッパ各地域のつくりかたによる建物が、それぞれの入植地にあります。
今回は、同書に載っているオランダの入植者が18世紀に建てた建物。
Deertz bahn とありますが、Deertz の意味が不明です。固有名詞?
当初、Middleburgh(Schoharie Country), New York に建っていたと説明にありますが、この場所も手持ちの地図では見つかりません。末尾の h のないMiddleburg という地名はワシントンの北にありますが、そこは New York 州ではない。 New York 州は、オンタリオ湖の南部一帯。多分そのあたりの平野部にあるようです。
下の写真は、移築のために下見板( weather boards )を剥がした状態。
「差物」を多用した、と言うより、「横材」はすべて「柱」に「差口」で納めている、骨組が見えます。
「差物」「差口」は、前回までに紹介したヨーロッパの例にも多く見られます。
「差物」「差口」は、決して日本の木造建築の特技ではないのです。誰だって、同じことを考えるのです。

その実測図が下図。柱間は6間。平面は、60ft×50ft(18.25m×15.25m)。
ヨーロッパの bahn との大きな違いは、石の上に直かに柱を立てるのではなく、石の上に流した「土台」上に、「枘差し」で柱を立てていること( tenoned into longitudinal timber sills )。
緩い北斜面に建っていたようです。

「土台」が使われた、ということは、入植者たちが建物づくりに習熟した人たちばかりではなかった、ということを示しているのではないでしょうか。
「礎石」の上に直かに「柱」を立てるには、熟練の技を必要としますが(「礎石」の天端をすべて同じ高さに据えられるとはかぎりませんから、「礎石」ごとに「柱」の長さを調節しなければならない)、「土台」を使用すれば、誰にでもできるからです(「土台」を水平に据えることは比較的容易、そうすれば横材が角材なら、「柱」の長さは全部同じですむ)。
日本の城郭づくりと、同じような状況だったのでは。
「柱」の中途に、床位置とは関係なく「横材」が入っていますが、これは「飛貫」同様の役割を担っているものと考えられます。
以下は、移築時の建て方の様子です。
1990年代の移築ですから、クレーンが使われています。
先ず、「身廊」:上屋に当たる部分を建てます。両妻、そして中央の列を先行したことが分ります。
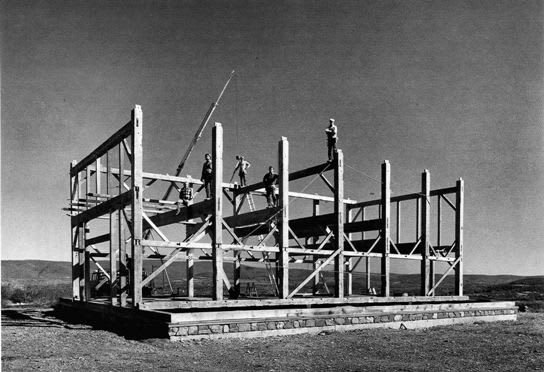
柱の外面に打たれている斜材は、「仮筋かい」。
「仮筋かい」は部分的に入れられていますが、本体に入る斜材は、同じ位置に、すべて入れられていることに留意してください。
入れるなら、全部に入れる、これが「斜材」を入れるときの鉄則。
次は、模型の写真のようですが、左が上の写真の段階の、長手方向から見た写真。
右は、軸部が側廊:下屋 aisle まで組み上がった段階。
まわりの景色は、ヨーロッパの風情ではありません。

次は、「仕口」(「枘差し・込み栓」)のクローズアップと合掌まで仕上がった写真です。これも、まるで模型のよう。
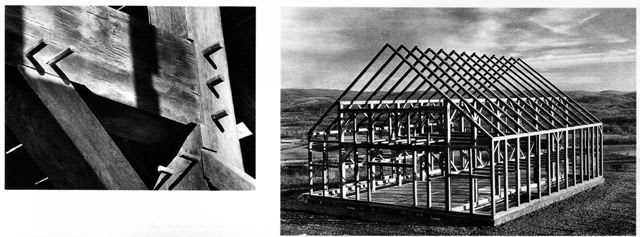
側廊側面の「柱」頂部の「斜材」:「方杖」は、両妻位置と中央の「柱」にのみ設けられていますが、「桁」を中央の柱上で継いでいるからのようです。日本では「肘木」を据えるところです。
******************************************************************************************
ここまで、各地域の木造を主とする Aisled Bahn を紹介してきましたが(イタリア・ドロミテの木造を主とする建物群も過日紹介しました)、人びとが考えることは、洋の東西を問わず、地域によらず、同じである、ということを、あらためて強く感じています。
その土地土地の状況において、人びとはそれぞれなりに建物づくりを考える。
しかし、そのとき人びとが考える「構築の原理」は、結局のところ、同じである、ということです。考えてみれば、きわめて当たり前のこと。
そして、今、日本で、「伝統」「伝統工法」・・と騒いでいることが、ますます馬鹿げたことだ、と私には思えてきました。
なぜなら、日本の建物づくりの「構築の原理」もまた、人びとなら必ず至りつく考えにほかならないからです。
「伝統」「伝統工法」と騒ぐ方がたは、それを「原理」という眼で捉えているようには、思えないのです。単なる「形」としてしか捉えていないように思えるのです。
「伝統」とは、形ではない。もちろんファッションではない。その意が、ますます強くなってきました。
このような日本の「特異な状況」は、ここ1世紀足らずの間の一部の人たちの考え方(耐力壁に依存する考え方)によって人為的に為されてきたこと、その結果生じた現象である、これは、今さら言うまでもないでしょう。
この人たちは、耐力壁に依存する考え方の《普及》のために、「普通の人びと」に「事実を知られないよう」に必死になった。その結果、人びとは「事実を知ること」から遠ざけられてきたのです。[文言追加 26日10.36]
なぜそうしたのか?
自らの《「学」の権威を維持するため》である、としてしか私には考えられません。なぜなら、この人たちの論理には「理」がないからです。
このような状況を「普通の」「当たり前の」状態に戻すには、人びとが「事実を知る」こと以外にありません。
広く、一般に「事実」を開示することです。
「事実」を「一部特権者」の下に秘匿しておいてはいけないのです。
普通の、一般の人びとの存在を無視して、《専門家》が専制的に勝手なことをする、そんなことを放置しておいてよいわけがないのです。
《専門家》が勝手なことができないようにする「最良の策」、それは、「皆が事実を知っていること」、これに尽きるのです。
私はそのように思っています。[文言追加 26日10.54]
註 「伝統」「伝統工法」・・と騒ぐことを馬鹿げたことと思うわけを補足します。
法令を「伝統的工法」の仕様が可能になるように改訂せよ、という「要望・要求」がなされています。
たしかに、そうなれば、当面、「伝統的工法」が「可能になるように見えます」。
けれども、建物づくりの「仕様」は、本来、「場面場面で工夫・考案される」ものです。
法令で規定を定めると、どうなるか。
使える「仕様」が規定され、それ以外は不可。「場面場面での工夫・考案」
言い換えれば、工人の「創意・工夫」は禁じられてしまうに等しいのです。
現に、現行の法令規定によって、私たちは苦労しているではありませんか。
「伝統的工法」仕様が可能になったところで、「創意・工夫」が禁じられることに変りはないのです。
それでいいのですか?「自由」が広がった?狭いより広いからいい?・・・
いわゆる「伝統的工法」は、なぜ、一定の体系にまで仕上がったのか。
それは、つまるところ、年月をかけての「醸成」にあります。
しかし、この「醸成」は、工人たちの「場面場面での創意・工夫」がなければ「なされなかった」。
第一、かつて、工人の「創意・工夫」を「規制」するようなことがあったでしょうか。
法令や「指導」で「創意・工夫」を規制することは、
「技術の固定化」「技術の衰退」を結果する、
これは自明の論理ではないでしょうか。
当面の状況の打開にのみ邁進するのは、私には不可解なのです。「姑息」に写るのです。
[註記追加 27日16.56]
******************************************************************************************
今回の最後に、講習会の「案内」をさせていただきます。
下記をご覧ください。
こういう event 案内に徹したHPがあるのを、初めて知りました!
http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416