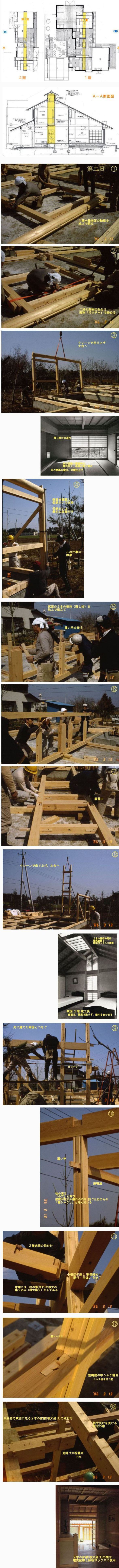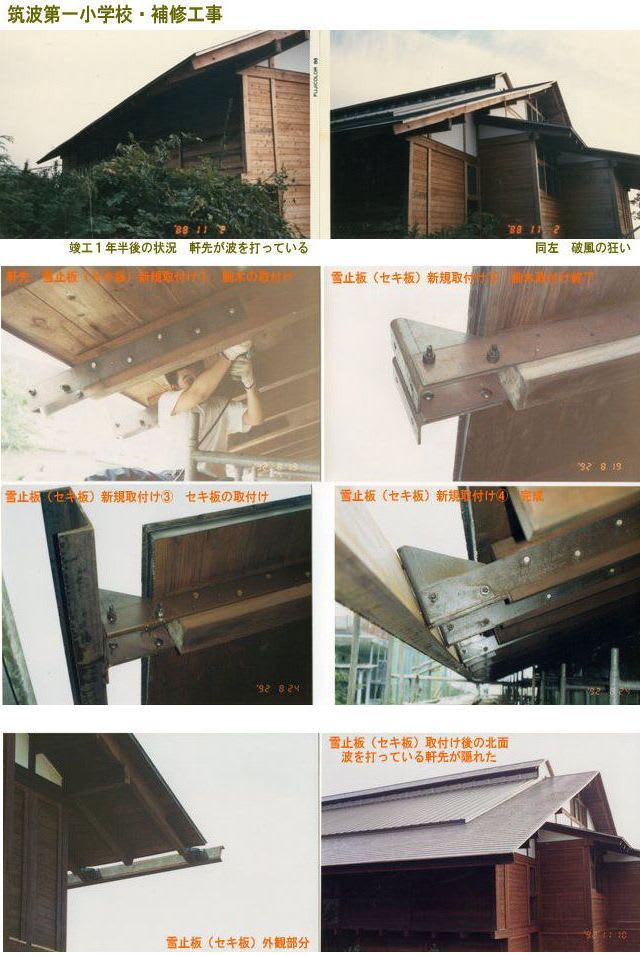この7月に「アリヂゴク・・・・アリヂゴクが棲める床下」(下註)の中で、木造家屋の床下に「防湿コンクリート」を打つことが奨められているが、それは間違い、かえって湿気を呼ぶ、と書きました。
なぜなら、夏の朝などに、湿気た空気が土間コンクリートや舗装道路などにあたると結露するのと同じように、「防湿コンクリート」の表面に、結露するからです。
註 「アリヂゴク・・・・アリヂゴクが棲める床下」
ちょうど今朝、天気の変り目で、当地は、少し暖かくて湿度も高く、朝霧が発生しました。遠くが霧で霞んでいました。
近くの舗装道路が一面、雨の後のように濡れていました。
最初は雨が降ったのかと思いましたが、そうではなく、霧が道路面に結露したのです。
道路わきの雑草にも露が降り、地面は心なしか湿気た色をしていますが、雨が降ったような濡れ方ではありません。
上の写真は、朝食後撮ったもので、朝陽のあたった場所や風通しのよい場所は、すでに乾いていましたが、ところどころ樹木などの陰や、風通しの悪いところでは、まだ道路が濡れていました。
道脇の雑草にも露は降りていますが、地面はほとんど変っていません。
そこで、予定を変更して、急遽ご報告まで。
なぜなら、夏の朝などに、湿気た空気が土間コンクリートや舗装道路などにあたると結露するのと同じように、「防湿コンクリート」の表面に、結露するからです。
註 「アリヂゴク・・・・アリヂゴクが棲める床下」
ちょうど今朝、天気の変り目で、当地は、少し暖かくて湿度も高く、朝霧が発生しました。遠くが霧で霞んでいました。
近くの舗装道路が一面、雨の後のように濡れていました。
最初は雨が降ったのかと思いましたが、そうではなく、霧が道路面に結露したのです。
道路わきの雑草にも露が降り、地面は心なしか湿気た色をしていますが、雨が降ったような濡れ方ではありません。
上の写真は、朝食後撮ったもので、朝陽のあたった場所や風通しのよい場所は、すでに乾いていましたが、ところどころ樹木などの陰や、風通しの悪いところでは、まだ道路が濡れていました。
道脇の雑草にも露は降りていますが、地面はほとんど変っていません。
そこで、予定を変更して、急遽ご報告まで。