 (今日の一葉は、今朝5時40分頃、部屋から見えた虹を最下段に)
(今日の一葉は、今朝5時40分頃、部屋から見えた虹を最下段に)
9月25日(火)は第40回のお話会で、妻が「柳沢吉保と六義園」を語った。私は“映像”担当の助手役で、「Power Point」に取り込んだ画像20枚ほどを映し出した。場所はいつもの本駒込地域活動センターで、降雨にも拘わらず参加者は24名と多かった。
話し終えての感想は概ね好評だった。話が上手だったとか、聞きやすい声だっただけでなく、面白い内容だったとか、知らない事を多々紹介された等々。
実は六義園に関しては、お話会で私が2度ほど語っていた。1度目は「お殿様の散歩道」と題して、吉保の孫の信鴻の、六義園での隠居生活や活発な散歩行動を紹介した。2度目では六義園への水の出入りを語った。妻はその六義園にかなり興味をもっていて、六義園について色々と調べて来ていた。その六義園と製作者柳沢吉保について調べて来た事を語ったことになる。
話には二本の柱があった。六義園は何故和歌山県の和歌浦に模して造らえたのという点と、他の柱は柳沢吉保の人柄と功績。
 奈良時代の神亀元(724)年には聖武天皇は紀伊国に行幸し玉津嶋に10日間滞在したと記録にあるように、ここは風光明媚な土地で、その時同行した「宮廷歌人」山部赤人は“若の浦に潮満ち来れば潟を無み葦辺をさして鶴鳴き渡る”と詠んでいる。これ以降何度も行幸があり、この地で名歌が詠まれて来た。平安以降も貴族達の憧れの地だった。やがて貧しくなった貴族たちはその地に行けなくなり行幸も衰退していったが・・・。
奈良時代の神亀元(724)年には聖武天皇は紀伊国に行幸し玉津嶋に10日間滞在したと記録にあるように、ここは風光明媚な土地で、その時同行した「宮廷歌人」山部赤人は“若の浦に潮満ち来れば潟を無み葦辺をさして鶴鳴き渡る”と詠んでいる。これ以降何度も行幸があり、この地で名歌が詠まれて来た。平安以降も貴族達の憧れの地だった。やがて貧しくなった貴族たちはその地に行けなくなり行幸も衰退していったが・・・。
江戸時代、「古今伝授」を受けていた、幕府歌学方北村季吟は、和歌浦の新玉津嶋神社の神官を勤めたが、その季吟から吉保は元禄13年に古今伝授を受けた。元禄8年に六義園の土地を拝領した吉保は六義園の造園に取り掛かるが、歌の師匠たる季吟の影響大きく、季吟が設計のブレーンだったと思われる。元禄9年に千川上水完成。この水を引き入れての六義園造園。この水が無ければ、和歌浦は造れない!元禄15年に完成。多くの貴人が訪れたことが『松陰日記』に記載されている。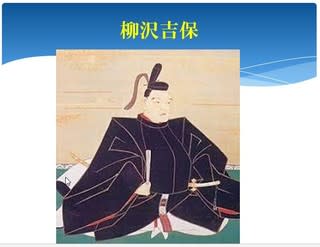 一方、万治元年に武田氏一門一条氏の末裔として誕生した吉保は、7歳にして綱吉に初お目見え。その年譜をみると加増のスピードが一目瞭然。
一方、万治元年に武田氏一門一条氏の末裔として誕生した吉保は、7歳にして綱吉に初お目見え。その年譜をみると加増のスピードが一目瞭然。
仕えた綱吉の改革は武断政治から文治政治への転換だった。理念に儒学を置き、皇室への敬愛の念深く、老中(家柄)の合議制から側用人(能力)を通しての親政。財政改革もあるが、悪名高い「生類憐令」もある。
吉保はかなりの有能な人物だった。川越城主時代の三富開発は世界的にも有名。甲府城主時代は城下整備努め、物流活性化で繁盛し、領民に惜しまれながら大和郡山へ移封された。郡山では息子の吉里以降、養蚕・金魚の養殖に熱を入れた。柳沢家の地元での評判はどの地でも良い。問題点は何よりも綱吉の意志実現に尽力し、批判は一切なかったこと。
現代への遺産としては①犬を食べなくなったこと。②各地の社寺等文化遺産の改修が為されたが、それが現在の観光資源へと繋がっている。
妻は、上に記したことなどを2時間弱で一気に語った。私が翌日聞いた感想「か細いからだの方ですからか細い声しかだせないと思っていましたが、良く通る声で語られていましたね」と。私、答えて曰く「話すことで飯を食べて来ましたから」と。

今日の一葉




















