verse, prose, and translation
Delfini Workshop
銀河系ノート No.1
2016-01-31 / 詩
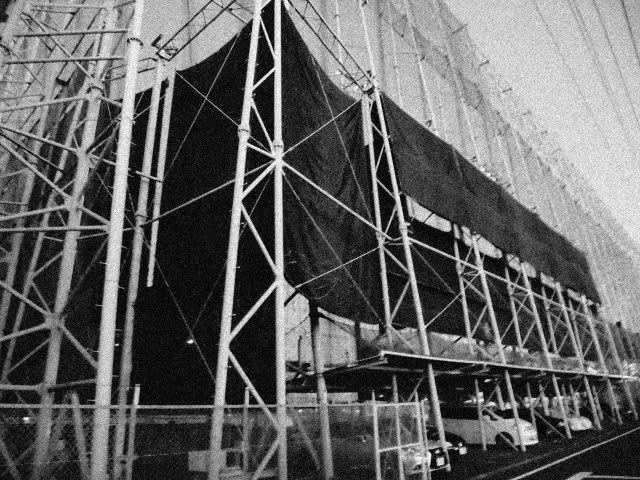
銀河系ノート
―朗読のための―
No. 1 2016年1月30日(土)
辺境
銀河系の辺境に島流しに遭っている。詩を書き始めてから、そんな気がして、もうかれこれ30年になる。40歳で俳句に出会って、詩に関する考え方や書き方がずいぶん変わったように思う。ちょうど40歳を境にその前の15年間は、詩は、テキストだと思ってきた。目という器官で読まれるべき、個人的で個性的な作品なんだと。そして、その作品は、いくぶん悲劇的な色彩を帯びている。
身体
その詩には、全体としての身体が欠けている。俳句は違った。音読され、暗唱され、身体にとり憑く。作品が商品として消費されるのに抗って、とり憑かれた身体はもうひとりの身体を呼ぶのである、笑いながら。それは「和解」の瞬間であり、世界から「肯定性」が救出された瞬間でもある。いま、思うと、俳句をはじめて、詩を朗読することになるのは、時間の問題だった。ことばは存在から出て存在へ帰ってゆくものだから。
歌と語り
この15年は、ずっと朗読を意識して詩を書き、詩を翻訳してきた。朗読を前提にして、と言ってもいいかもしれない。朗読の最初のイメージは、「身体楽器」だった。ことばで、自分の身体を鳴らそうと考えた。テキストは、譜面だった。これは、うまくいく場合と、そうでない場合があった。うまくいくのは、テキストから意味が脱色されているときである。そうでないテキスト―詩は、ことばで書かれているため大部分がそうだが―は、あまりうまくゆかない。うまく歌うことができないのだ。残念ながら、われわれは、もう歌いながら生きてはいない。
語りと演技
ふつう、日常では、感情の起伏をあまり表に出さないのが良いとされている。「人格者」ほど、平板な感情生活をしているように見える。いまや歌は失われ、いたるところで感情は疎外されている。詩を朗読するのは、その詩を批評することであるが、それは、その詩本来のいのちを蘇らせることなのだと思う。そのために、言葉に抑制された表情をつけようと思った。微妙な演技である。表情も演技も、日常の中にヒントがあると思っている。
(「第5回銀河朗読会」資料から 文責 尾内達也)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 第5回銀河朗読会 | 一日一句(1391) » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |
| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |










