今日も減資と増資についてです。ただ、100%減資には限りません。減資と増資が同時に起こる場合の手続に関するオハナシです。
100%減資ではなくても、株主の一部が損失の一部を補填することがあります。例えば、ABCの株主さんがいたとしましょう。株主ABさんが、会社の赤字を補填することになりました。この場合、ABの株式を会社が無償で取得し、株式消却と同時に減資の効力が発生するようにします。さらに減資の効力発生と同時に増資し、ABが追加出資を行います。
減資前(当初出資額1株5万円)
ABC 各100株(総数300株)
純資産額 300万円(1株当たり1万円)
資本金の額 1500万円
増資
AB 各100株
払込金額 1株 6万円(総額1200万円)
減資額 1200万円
自己株式消却 200株
減資・増資後
ABC 各100株(総数300株)
純資産額 1500万円(1株当たり5万円)
↑こうすると、Cさんの1株あたりの額は始めに出資した額になり、ABさんは不足していた1200万円を補填する結果になります。
減資と増資は、こういうことでも合わせて使ったりするようです。
でもですね、こういう場合だったら何も減資と増資の順番を守りなさい、とか、一緒に効力発生しなきゃまずい、などということは問題にならないと思いませんか? だって、少なくとも会社が自己株式を取得すれば、いつでも消却できるし、株主Cは残るのですから増資とのタイムラグは関係ないはずです。
ところがそうではなかったんです。
商法の時代には、ある一定の条件の下で、減資の際の債権者保護手続が不要とされていました。それは、①減資と同じタイミングで増資する場合であって、かつ、②増資後の資本金が減資前の資本金以上であること、です。
つまり、減資の効力が発生した時点で、減資前よりも資本金の額が多い(あるいは同額)のであれば、債権者は不利益を受けない、だから債権者保護手続は不要、ということです。
商法はそんなことは一言も言っていないのですけど、実務上は一般的に運用されていたんです。
会社にとっては、債権者保護手続が要るかどうかは大きな問題ですし、減資のスケジュールも大幅に短縮できるので、もちろん、増資をする場合に限られるのですけど、手続を簡略化するために、一生懸命工夫して同時に効力が発生するようにしていました。
ところが!
とてもひっそりと、実質改正されちゃったんですよ。
このことを大声で言っている方はいらっしゃらないようですが、会社法ではこういう場合、決議機関が株主総会から取締役会になると規定しています(第447条第3項)。
しかし、債権者保護手続が要らないとは規定されていません。
つまり、以前は解釈で認められていた手続の省略について、明確に「やらなきゃダメですよ~っ!」と規定されちゃったワケです。
そりゃあ、決議機関が変わることも手続の簡略化ですけどね。ワタシとしては結構インパクトのある実質改正でありました。
ただ、実を言いますと、法務局によっては債権者保護手続は省略できないという見解もあったんです。結局、実体法の解釈が統一的でなかったから変わってしまったのかも知れません。逆になればよかったのに、残念です。
100%減資ではなくても、株主の一部が損失の一部を補填することがあります。例えば、ABCの株主さんがいたとしましょう。株主ABさんが、会社の赤字を補填することになりました。この場合、ABの株式を会社が無償で取得し、株式消却と同時に減資の効力が発生するようにします。さらに減資の効力発生と同時に増資し、ABが追加出資を行います。
減資前(当初出資額1株5万円)
ABC 各100株(総数300株)
純資産額 300万円(1株当たり1万円)
資本金の額 1500万円
増資
AB 各100株
払込金額 1株 6万円(総額1200万円)
減資額 1200万円
自己株式消却 200株
減資・増資後
ABC 各100株(総数300株)
純資産額 1500万円(1株当たり5万円)
↑こうすると、Cさんの1株あたりの額は始めに出資した額になり、ABさんは不足していた1200万円を補填する結果になります。
減資と増資は、こういうことでも合わせて使ったりするようです。
でもですね、こういう場合だったら何も減資と増資の順番を守りなさい、とか、一緒に効力発生しなきゃまずい、などということは問題にならないと思いませんか? だって、少なくとも会社が自己株式を取得すれば、いつでも消却できるし、株主Cは残るのですから増資とのタイムラグは関係ないはずです。
ところがそうではなかったんです。
商法の時代には、ある一定の条件の下で、減資の際の債権者保護手続が不要とされていました。それは、①減資と同じタイミングで増資する場合であって、かつ、②増資後の資本金が減資前の資本金以上であること、です。
つまり、減資の効力が発生した時点で、減資前よりも資本金の額が多い(あるいは同額)のであれば、債権者は不利益を受けない、だから債権者保護手続は不要、ということです。
商法はそんなことは一言も言っていないのですけど、実務上は一般的に運用されていたんです。
会社にとっては、債権者保護手続が要るかどうかは大きな問題ですし、減資のスケジュールも大幅に短縮できるので、もちろん、増資をする場合に限られるのですけど、手続を簡略化するために、一生懸命工夫して同時に効力が発生するようにしていました。
ところが!
とてもひっそりと、実質改正されちゃったんですよ。
このことを大声で言っている方はいらっしゃらないようですが、会社法ではこういう場合、決議機関が株主総会から取締役会になると規定しています(第447条第3項)。
しかし、債権者保護手続が要らないとは規定されていません。
つまり、以前は解釈で認められていた手続の省略について、明確に「やらなきゃダメですよ~っ!」と規定されちゃったワケです。
そりゃあ、決議機関が変わることも手続の簡略化ですけどね。ワタシとしては結構インパクトのある実質改正でありました。
ただ、実を言いますと、法務局によっては債権者保護手続は省略できないという見解もあったんです。結局、実体法の解釈が統一的でなかったから変わってしまったのかも知れません。逆になればよかったのに、残念です。










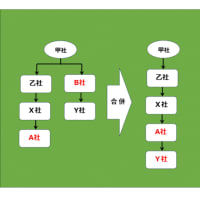
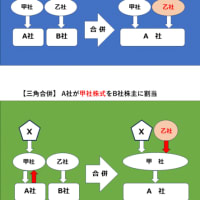
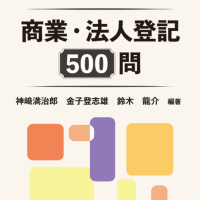
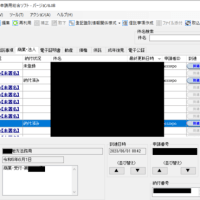
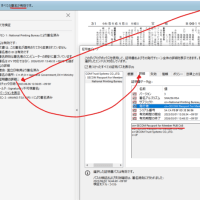
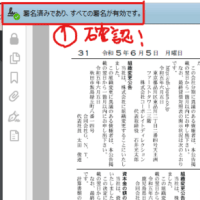










今も、この増減資同時でも債権者保護手続きは必要というのは変わっていませんよね?
全然会社法についていけていないので、不安になってしまいました。。。
最近、このハナシが話題になっているようですが、会社法下では、債権者保護手続きを省略することはできません。
ご安心ください♪