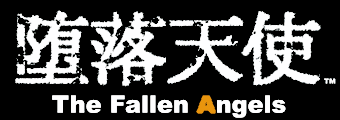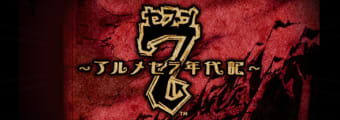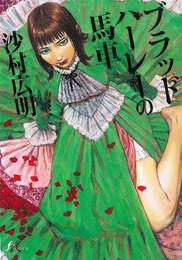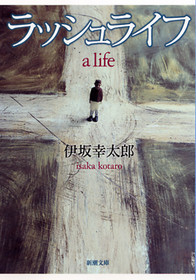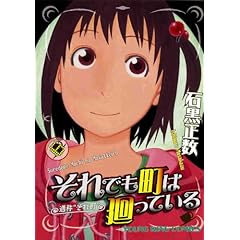秋口に買った三津田信三氏の「~如く~」シリーズ。
何分蒐集癖に近いモノが自分にはあるので、
刊行されてるシリーズ4作をまとめて買ったんですが、
しばらくは積んでたんですね。
その後部屋を片付けるコトを思い出して漫画・小説の類を段ボールに詰め込んでいく内に、
ふとした時に読める本が無くなっていることに気付きまして…
文庫のミステリでも読む?と思ったけど、
「十角館の殺人」も「葉桜の季節に君を想うということ」も、読了してからまだ日が浅い。
そこで目に付いたのが、積まれてた当シリーズだったと。
多汗症ゆえに、ブックカバーを買ってから読もう…と思っていたのですが、
騒ぐ本の虫VSニートの購買意欲の勝負となると、結果は明白なワケで…。
でも「出来るだけ早いうちに買わないと…」と再確認させられたけどな。
ベッタベタだもんね…
三津田氏の作品自体、ミステリーとオカルトの要素が多いらしく、
「~如き~」シリーズはオカルト・怪奇分が多めのバランス。
ここんとこ読んでたんは海外の王道探偵ミステリだったり、
或いは国内の新本格派ミステリと呼ばれているモノだったんで、
一種のゲテモノ喰いにトライしてみたかったのも有るんでしょうね。
その上で入念に、とはいえないけど、やはり文庫本と比べると
ハードカバーの価格設定には抵抗があったので、割と下調べをした上で購入を決意。
2chのおすすめミステリスレで挙げられてたのと、
その時に見かけたタイトルに惹かれました。
ほんとあのテのスレに居る識者には感謝し通し。
三津田氏の「~如き~」シリーズは今のところ全四作、
うち原書房はミステリー・リーグより、
「厭物」「首無」「山魔」の三作が刊行されているのですが、
「首無」の前に「凶鳥」が講談社文庫より出てるんですね。
この「凶鳥」がしばらく前にミステリー・リーグよりハードカバーで出ましたんで、
これを機会に、と前述の通り買い求め、
幸いに作品の発表された順に読むことが出来てます。
ラッキー。
ということで発表された順に「厭物」「凶鳥」の二冊を。
■厭物の如き憑くもの

いきなり憑物筋の集落が舞台。
平成の世の中にこれって…と心配もするんだけど、
舞台は戦後しばらく経ったぐらいの日本っぽい所だし、
地名や人名・団体名は面白いぐらいハッタリの効いた架空の名称ですから安心。
やっぱりオカルト要素が濃いためなのか、
素直に読んでいくと逆に後味が悪くなるような気が。
語り部の刀城さんがキッチリと説明をつけてくれるんだけど、
最初っから最後までオカルト要素が付き纏うので、
逆に彼の説明の方があっけらかんとしている感が…
冒頭の「はじめに」でも触れられているとおり、登場人物の日記・ノートに加え、
第三者視点で(筒井康隆の「天の一角」チックに)物語を書いていくという試み。
最初は違和感がありこそすれ、最後まで読み終われば納得のカタチ。
このオチを付けるなら、このカタチじゃないと反則だわな。
難点を挙げるなら、中盤以降の展開が速すぎると感じる点ですか。
憑物筋なんていうモノを読者に理解させるためなのか、
前半はほぼ憑物筋の歴史や登場人物達の関係を把握するので精一杯。
そして中盤からバタバタ死に出す被害者達。
場面が変われば死んでいる、といっても良いぐらい。
ここだけはちょっと…と思いましたね。
■凶鳥の如き忌むもの

そして二作目の「凶鳥」。
書き下ろしとして「天魔の如き跳ぶもの」も収録。
元が文庫だったのでちょいと余ったんでしょうか。
主役である刀城氏が学生の時のお話になりますが、
「凶鳥」本編でも名前だけ出てくる阿武隈川先輩も大活躍!!
ページを埋めるための書き下ろしだからか、尺が足りない感もありますがね…
本編では密室での消失トリックに刀城氏が挑むワケですが、
「厭物」前半での解説パートは構成上やむ無いってことを再確認。
しかしながら、十八年前の消失事件をリンクさせようとしたコトは、
文庫での文字数制限からか、少々無謀だった気もする。
フィクションにしても、都合良すぎて納得しづらい感じ。
思うに、こういったミステリの解決編の理想というのは、
「実は○○は××で△△だったんだよ!!」
「な、なんだってェーッ!!」
などという読者のリアクション。
前作の「厭物」では二段構えのオチに加え、前半から引っ張られていた伏線もあり、
まぁ上記の例のようなリアクションはあっても良い。
ところが今作の場合、
「ああ…まあ……いや…でも……ねぇ…?」
といった感じか。
中盤から薄々とは感じていた消失トリックの解答に加えて、
「あの人は器用だっというし、そのぐらい出来ないワケではない」という旨の推理。
「ジョバンニが一晩でやってくれました」をちょっと思い出したわ…
18年前の消失事件のオチも、読者を納得させるには厳しいかなぁ。
後を追うように殺された二人の被害者には謝らないといけないレベルかも。
憤慨はしないけどちょっとゲンナリ。
ってことで手始めの二作の感想は以上。
二作読んで思ったのは、登場人物のリンクこそあれど、
作品内で別の作品に触れたりすることが無いので、
別にシリーズ全部集めて順番に読む必要は無いってことっすかね。
あと、シリーズを通して統一された雰囲気のイラストも目を引くんですが、
「厭物」では作中で重要な役割を担った「蛇」の目で、
「凶鳥」では大鳥様と崇められる「鷲」の目。
こういうちょっとした遊びが効いてて良い感じです。
期待していたほど「~如き~」ってタイトルの意味も無いな…とも思ったがね…