大学の今後の強化のための考え方について私の考えを整理してみたい。
コメントにも入っているように、大学の教授というか研究室の評価はほとんどなされていないのが実態である。それは教授会が大学の意思決定機関になっていて、教授の身分は保証されているから、という点から来ていると私は考えている。従って、企業のように「人事考課」のような仕組みを取り入れることは大学の構造を根本から変えることになり、私立大学ではできても公立大学では現実的ではないと思う。
現在、大学教授に対する「人事考課」が存在しない(教授になるときには評価される)、からと言って大学教授に業績に関するフィードバックが機能していないわけでは無い。殆どの大学では教授は給料はもらえるが研究費は自動的にはもらえない。「研究費は自分で稼いでこい」というのが大学のスタンスであり、教授たちは様々なプロポーザルを書いて国または企業から研究費を稼いでくる。その意味で大学教授は中小企業の社長と言える状況であり、大学の教員は(教授だけでなく)自分の研究成果をうまくプレゼンする能力は開発される。これは黙々と仕事をやっていれば上司が評価してくれる企業とは異なった環境で、企業より良い面もあると思う。研究費の大部分は科研費と呼ばれる文部科学省の研究費であり、これは各大学からのプロポーザルを他の大学の同じ分野の教授たちが評価していると言える。
現在、文部科学省はこれまでの一般的予算を徐々に減らして、学長裁量を増やしたり、競争的資金というのを増やしたりしている。競争的資金というのは個別の教授の研究資金ではなく、ある程度まとまった複数の研究を一つの大きな流れにまとめ上げるもので、5年間くらいの期間で、企業や地域を巻き込んで行うことが求められる。大学間の提案でコンペを行い、審査に通った案が資金を得られるので、大学では教授たちが集まってストーリーを作っている。このやり方は一定の効果を生みそうに思う。大学内でも社会の役に立つ有力な研究をやっていて中心的に動けるのは誰か、という点が明確になる。実態としてどのような案が高く評価されるのか、研究はうまくまとまっていくのか、等に問題はあっても方向性は良いと思う。
私が最近の動きで「良いな」と思った例はStanford大学のCARSという組織である。これは自動運転に関して、技術開発から、法整備、保険の考え方など自動運転に関わる幅広い分野を総合的に研究する組織で、Stanford大学の教授たちが核となって組織を作り、多くの自動運転に参入しようとする企業が賛同して研究員を送り込むような組織に発展している。私の居た東工大では「環境エネルギー協創教育院」という組織ができていて省エネ技術などを研究する組織となっているので似たような性格だと思う。だが、地球温暖化を巡る先進国と新興国の対立をどう解くか、とかCO2の取引価格のビジネスモデルはどうするべきか、とかいった技術以外の分野に関する取り組みは弱く、技術的内容が殆どであったように思う。この組織から気候変動を議論する国際会議の日本案が出てくるような位置づけになれば面白かったのに、と思う。このような、技術と経済、法律を合わせたイノベーションが求められている分野は少なからずあると思っている。
政府はそれなりに工夫している状況がみられるので、大学がどういう動き方をするべきかについて考えてみたい。大学の意思決定が教授会をベースとしているという仕組みを変えるのは抵抗も大きいしうまくいくかを見通すのが難しいので継続するべきだと思う。教授会が各教授の評価をするのは現実的ではないので、准教授以下を評価するべきだろうと思う。准教授や助教の評価は今より時間をかけて行い、何年間かの評価の結果としてその人の成長を見定めて昇進を決めるべきだと思う。
教授の評価を大学内でどうするかは難しく、私も良いアイデアを持っていない。教授の業績を評価するよりも大学としてのブランド価値構築にその教授や学科がどれだけ貢献しているかを評価して、新組織を立ち上げるときの参考にするなどが良いのではないだろうか。これは教授会の上の理事会で行うのが良いと思う。一般的には「あの大学のあの分野は強い」といった認識がある。これを戦略的に「強いところを一層強くする」のが大学が取るべき戦略だと思う。
これまでは主に「研究」について書いてきた。大学のもう一つの大きな役割は「教育」であり、どういう人材を育成するべきか、は大きな問題であるか、この点に関しては別途気の付いたときに書くことにしたい。










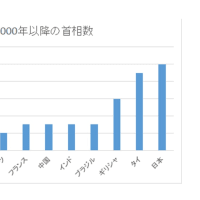
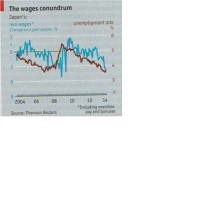
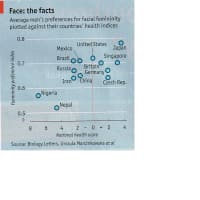
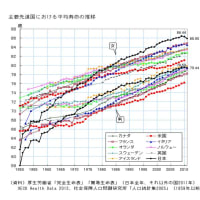



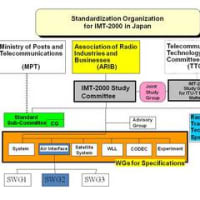


地球環境は事象が複雑すぎて、結局何が(人類にとって?)最良なのか結論は出ていない(国地域によっても異なる)と考えています。イデオロギーと利権だけで動いていると言っても過言ではない気がいたします。極端なことを言えば、暖かい地域に住む人は気温が上がらない方が良いし(?)、寒い地域に住む人は暖かくなってほしいと思っている(?)ということです。世間はあまりにも「地球温暖化問題」ありきで突っ走っているように見えます。
よって、研究者がこの問題に首をつっこむのはあまり良い結末を連想できません。