武雄記念の決勝。並びは郡司‐中村の南関東,野原‐村上の近畿,山田‐大坪の九州で山崎と深谷と松浦は単騎。
山田,郡司,中村の3人がスタートを取りにいきました。最内の山田が誘導の後ろを確保して前受け。3番手に郡司,5番手に野原,7番手に深谷,8番手に松浦,最後尾に山崎で周回。残り3周のホームの手前から野原が上昇。これに合わせたのが郡司。山田も引かなかったので,ホームでは3人が併走する形。誘導の退避を待って山田が突っ張り,郡司は大坪の後ろに。野原は立て直してバックから発進。ここに続いた松浦が3番手となって打鐘。外を上昇してきた山崎がホームの手前で野原を叩いて前に。そこから深谷が発進。うまくスイッチしたのが松浦で,松浦の後ろを郡司が追走。中村を捌いた野原が4番手になってバックを通過。深谷との車間を開けていた松浦が直線の手前から発進。マークする形になった郡司の追撃を凌いで優勝。松浦マークになった郡司が4分の3車身差の2着で,郡司マークになった野原が2車身差の3着。逃げた深谷が4分の1車輪差で4着。
優勝した広島の松浦悠士選手は前回出走のウィナーズカップからの連続優勝。記念競輪は2月の高松記念以来となる6勝目。武雄記念は初優勝。このレースは松浦,深谷,郡司の3人が脚力で上位。先行はおそらく野原か深谷で,野原が先行の場合は3人のうち,深谷が先行の場合は残るふたりのうち,よい位置を確保できた選手が有利になるだろうと思っていました。機敏に動いて深谷の番手を確保できたのが勝因でしょう。力量上位の選手が最終バックで前から3人で並んでは,ほかの選手に出番はありません。もっと工夫したレースが必要だったと思います。
エピステーメーの中に党派的なものが存在したという点に関する考察はここまでとして,次の課題に移ります。
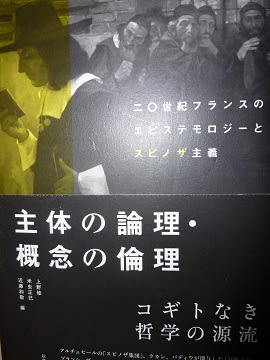
『主体の論理・概念の倫理』に関する考察の中で,バディウAlain Badiouについて触れた部分がありました。ただし僕は,バディウがどういう観点からスピノザを批判したのかはよく分かっていませんでした。というか,なぜバディウがスピノザを批判しなければならなかったのかということが分からずにいたのです。これについて『〈内在の哲学〉へ』の中で,理由が示されていましたので,そこのところを補足しておきます。ただしこの補足には事前に注意しておいてほしいことが含まれます。
『〈内在の哲学〉へ』の第7章は「メイヤスーとバディウ」という表題になっています。これは,メイヤスーQuentin Meillassouxがバディウを解釈し,それに対する批判をしているのを,近藤が検討するという内容になっています。ものすごく大まかな説明で,正確性を欠いているといわれればその通りではありますが,とりあえずそのような内容であると思ってください。このとき僕は,メイヤスーの考え方については何も考察しません。あるいはメイヤスーの主張について,それを検証するということはしません。同様に,近藤がメイヤスーのバディウ批判をどのように解しているかということも考察しませんし,近藤の解釈の正当性についても検証はしません。ですからここではバディウの考え方について補足をしていくのですが,それを紹介しているメイヤスーや近藤の見解の正当性については何も問わないのですから,メイヤスーによるバディウの理解や,近藤によるメイヤスーのバディウ批判に対する理解に何らかの誤解が含まれているとしたら,その誤解が含まれたまま僕の考察も進んでいくということになります。これは考察としては大きな危険を孕むものではありますが,さすがにそれらの正当性について評価するには,僕には能力も足りませんし,かといってその評価のために時間を費やすのも,僕自身の関心からいえば徒労ですから,止むを得ないこととしておきます。これは僕がなぜ『〈内在の哲学〉へ』を読んだのかを説明したときにいったことからもお分かりいただけるでしょう。
山田,郡司,中村の3人がスタートを取りにいきました。最内の山田が誘導の後ろを確保して前受け。3番手に郡司,5番手に野原,7番手に深谷,8番手に松浦,最後尾に山崎で周回。残り3周のホームの手前から野原が上昇。これに合わせたのが郡司。山田も引かなかったので,ホームでは3人が併走する形。誘導の退避を待って山田が突っ張り,郡司は大坪の後ろに。野原は立て直してバックから発進。ここに続いた松浦が3番手となって打鐘。外を上昇してきた山崎がホームの手前で野原を叩いて前に。そこから深谷が発進。うまくスイッチしたのが松浦で,松浦の後ろを郡司が追走。中村を捌いた野原が4番手になってバックを通過。深谷との車間を開けていた松浦が直線の手前から発進。マークする形になった郡司の追撃を凌いで優勝。松浦マークになった郡司が4分の3車身差の2着で,郡司マークになった野原が2車身差の3着。逃げた深谷が4分の1車輪差で4着。
優勝した広島の松浦悠士選手は前回出走のウィナーズカップからの連続優勝。記念競輪は2月の高松記念以来となる6勝目。武雄記念は初優勝。このレースは松浦,深谷,郡司の3人が脚力で上位。先行はおそらく野原か深谷で,野原が先行の場合は3人のうち,深谷が先行の場合は残るふたりのうち,よい位置を確保できた選手が有利になるだろうと思っていました。機敏に動いて深谷の番手を確保できたのが勝因でしょう。力量上位の選手が最終バックで前から3人で並んでは,ほかの選手に出番はありません。もっと工夫したレースが必要だったと思います。
エピステーメーの中に党派的なものが存在したという点に関する考察はここまでとして,次の課題に移ります。
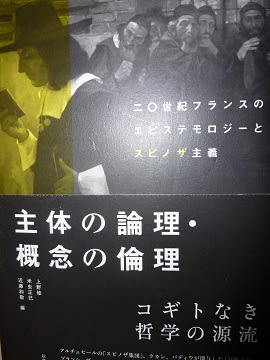
『主体の論理・概念の倫理』に関する考察の中で,バディウAlain Badiouについて触れた部分がありました。ただし僕は,バディウがどういう観点からスピノザを批判したのかはよく分かっていませんでした。というか,なぜバディウがスピノザを批判しなければならなかったのかということが分からずにいたのです。これについて『〈内在の哲学〉へ』の中で,理由が示されていましたので,そこのところを補足しておきます。ただしこの補足には事前に注意しておいてほしいことが含まれます。
『〈内在の哲学〉へ』の第7章は「メイヤスーとバディウ」という表題になっています。これは,メイヤスーQuentin Meillassouxがバディウを解釈し,それに対する批判をしているのを,近藤が検討するという内容になっています。ものすごく大まかな説明で,正確性を欠いているといわれればその通りではありますが,とりあえずそのような内容であると思ってください。このとき僕は,メイヤスーの考え方については何も考察しません。あるいはメイヤスーの主張について,それを検証するということはしません。同様に,近藤がメイヤスーのバディウ批判をどのように解しているかということも考察しませんし,近藤の解釈の正当性についても検証はしません。ですからここではバディウの考え方について補足をしていくのですが,それを紹介しているメイヤスーや近藤の見解の正当性については何も問わないのですから,メイヤスーによるバディウの理解や,近藤によるメイヤスーのバディウ批判に対する理解に何らかの誤解が含まれているとしたら,その誤解が含まれたまま僕の考察も進んでいくということになります。これは考察としては大きな危険を孕むものではありますが,さすがにそれらの正当性について評価するには,僕には能力も足りませんし,かといってその評価のために時間を費やすのも,僕自身の関心からいえば徒労ですから,止むを得ないこととしておきます。これは僕がなぜ『〈内在の哲学〉へ』を読んだのかを説明したときにいったことからもお分かりいただけるでしょう。













