
医学生が臨床実習に参加する際,一般診療に関する基本的臨床能力を備えていることが望ましい.このため医学生は,病棟での臨床実習を始める前に,その基本的臨床能力をテストされる.これが客観的臨床能力試験 Objective Structured Clinical Examination OSCE(オスキー)と呼ばれるものである.自分が学生の頃にはこのような試験はなかったが,教える側には負担がかかるものの,教わる側にとってはとても良い制度である.試験項目は医療面接,頭頸部の診察,胸部の診察, 腹部の診察,脳神経の診察,小外科基本手技(縫合・抜糸)などで,学生は試験会場において,上記実技を行う各ステーションを順々にめぐり課題を行い,評価者は点数をつける.評価によっては落第することもある.恥ずかしいことに自分自身,神経内科領域以外の基本的診察法は自信がなくて,OSCE用の参考書を1冊購入した.診察と手技がみえる vol.1 (1) この本はかなり勉強になる代物で,いまの医学教育は恵まれているなと感じた(学生以外にもお勧めである).
この本はかなり勉強になる代物で,いまの医学教育は恵まれているなと感じた(学生以外にもお勧めである).
さて神経内科領域のOSCEについても,教科書によって診察法や記載法が異なり,戸惑ったりすることもある.おそらくこれは日本といえど,いろいろな流派の診察法があるためと思われる.さらに昨今の清潔操作や感染防止の概念が診察法に影響しているようだ.たとえば表在覚検査は,清潔操作や感染防止の見地から筆やローラーは使わず,その代りティッシュをこよりにしたものや爪楊枝を使うよう指導される.顔面の表在感覚を診る場合には,「ティッシュこより」を両手に持ち,左右の顔面を顔の中央から左右外側に向けて同時にこするよう指導されるのだが,何も知らず診察風景を見れば現役神経内科医は何をしているのだろうと驚くだろう.
また神経内科診察で,学生が一番苦手なものは腱反射のようだ.どこをどう叩けば反射が出るのか,もし出せたとしてどのように記載すれば良いのか分からないという.腱反射の出し方としては,「被検者をリラックスさせ,検査する筋の力を抜かせて,それぞれの筋に応じた正しい肢位で,適度な強さで腱をポーンと叩くのが基本で,健常者であればだれでも誘発することができる腱反射(いわゆるBabinskiの5大反射;上腕二頭筋反射,回内筋反射,上腕三頭筋反射,膝蓋腱反射,アキレス腱反射)を確認し,評価は作動筋の「速さ」「程度」「持続時間」で判断する」よう指導する(Clinical Neurosceince 22; 889-891, 204).しかし学生の「すべての腱を同じように叩かないと評価できないのでは?」という鋭い質問には返答に困ってしまった.いつも変らぬ強さで,適切な強さで,かつ左右同じ強さで,叩けているのだろうか?これは学生に指摘されるまでもなく,ずっと気になっていたことである.
これはどんなハンマーを使っているかということも大事なのではないだろうか?たとえば適切な強さで叩けているかについては,何回か叩いてみて一定の筋収縮が得られるのであれば,おそらく「適切に」叩けていると判断して良いと思うが,それでもハンマーの叩く部分が軽すぎると力が加わらずうまく反射を出せないような気がする(ヘッドの部分の軽いハンマーは,日本で発明されたハンマーに多い;大貫型,吉村型などがこれに当たる).また日本で一番使われていると思われるアメリカ式のTaylor型打腱器は個人的にもよく使うが(ヘッドのゴムが,黒,オレンジ,白とあって,白がやわらかく通常の診察では患者さんの痛みのことを考えてこれを使っている),これでもまだヘッドが軽い.自分は腱反射の有無をきちんと確かめたい微妙なときは,「マイ勝負ハンマー」としてTroemner型を使っている(写真左).これは米国神経学会(AAN)の学会場やAAN storeで購入できるが(学会員52ドル,非学会員62ドル),「出せない反射も出せる」というキャッチコピー通り,振り心地が重厚で手にしっくりきて,確かに反射も出るような気がする(でも患者さんは痛い).Babinski反射用の足底をこする柄の反対部分は適度に角が丸くなっていて,こちらは患者さんにやさしい(新品のTaylor型打腱器は鋭くとがっていてあまりに痛い).またQueen square型ハンマーというヘッドが円形で,柄の部分がプラスチックのものも売っているが,個人的には柄のしなりのお蔭で強く叩けて好きな半面,長さゆえにときどき正確に腱を叩けなかったり,携帯しにくい欠点があったが,今回,柄の伸縮するタイプ(Rabiner型)が発売されたので,早速,購入し持ち歩いている(写真中,伸ばすと右になる).これはヘッドの向きも柄に対して水平・垂直に変えることができて,打腱しやすくなっている(ひゅっと伸ばしてみんなが驚くのが楽しい).
神経内科は腰椎穿刺以外,ほとんど技術はいらないと自嘲したりすることもあるが,必ずしもそんなことはない.いかに適切に同じ強さで腱を叩けるか神経内科医の重要な技術である.でもハンマーへのこだわりは他科ドクターには決して理解できないでだろうが・・・
世界で使われている打腱器の種類 Clinical Neurosceince 22; 892-896, 2004(田代先生のコレクションのすごさに恐れ入ります)
さて神経内科領域のOSCEについても,教科書によって診察法や記載法が異なり,戸惑ったりすることもある.おそらくこれは日本といえど,いろいろな流派の診察法があるためと思われる.さらに昨今の清潔操作や感染防止の概念が診察法に影響しているようだ.たとえば表在覚検査は,清潔操作や感染防止の見地から筆やローラーは使わず,その代りティッシュをこよりにしたものや爪楊枝を使うよう指導される.顔面の表在感覚を診る場合には,「ティッシュこより」を両手に持ち,左右の顔面を顔の中央から左右外側に向けて同時にこするよう指導されるのだが,何も知らず診察風景を見れば現役神経内科医は何をしているのだろうと驚くだろう.
また神経内科診察で,学生が一番苦手なものは腱反射のようだ.どこをどう叩けば反射が出るのか,もし出せたとしてどのように記載すれば良いのか分からないという.腱反射の出し方としては,「被検者をリラックスさせ,検査する筋の力を抜かせて,それぞれの筋に応じた正しい肢位で,適度な強さで腱をポーンと叩くのが基本で,健常者であればだれでも誘発することができる腱反射(いわゆるBabinskiの5大反射;上腕二頭筋反射,回内筋反射,上腕三頭筋反射,膝蓋腱反射,アキレス腱反射)を確認し,評価は作動筋の「速さ」「程度」「持続時間」で判断する」よう指導する(Clinical Neurosceince 22; 889-891, 204).しかし学生の「すべての腱を同じように叩かないと評価できないのでは?」という鋭い質問には返答に困ってしまった.いつも変らぬ強さで,適切な強さで,かつ左右同じ強さで,叩けているのだろうか?これは学生に指摘されるまでもなく,ずっと気になっていたことである.
これはどんなハンマーを使っているかということも大事なのではないだろうか?たとえば適切な強さで叩けているかについては,何回か叩いてみて一定の筋収縮が得られるのであれば,おそらく「適切に」叩けていると判断して良いと思うが,それでもハンマーの叩く部分が軽すぎると力が加わらずうまく反射を出せないような気がする(ヘッドの部分の軽いハンマーは,日本で発明されたハンマーに多い;大貫型,吉村型などがこれに当たる).また日本で一番使われていると思われるアメリカ式のTaylor型打腱器は個人的にもよく使うが(ヘッドのゴムが,黒,オレンジ,白とあって,白がやわらかく通常の診察では患者さんの痛みのことを考えてこれを使っている),これでもまだヘッドが軽い.自分は腱反射の有無をきちんと確かめたい微妙なときは,「マイ勝負ハンマー」としてTroemner型を使っている(写真左).これは米国神経学会(AAN)の学会場やAAN storeで購入できるが(学会員52ドル,非学会員62ドル),「出せない反射も出せる」というキャッチコピー通り,振り心地が重厚で手にしっくりきて,確かに反射も出るような気がする(でも患者さんは痛い).Babinski反射用の足底をこする柄の反対部分は適度に角が丸くなっていて,こちらは患者さんにやさしい(新品のTaylor型打腱器は鋭くとがっていてあまりに痛い).またQueen square型ハンマーというヘッドが円形で,柄の部分がプラスチックのものも売っているが,個人的には柄のしなりのお蔭で強く叩けて好きな半面,長さゆえにときどき正確に腱を叩けなかったり,携帯しにくい欠点があったが,今回,柄の伸縮するタイプ(Rabiner型)が発売されたので,早速,購入し持ち歩いている(写真中,伸ばすと右になる).これはヘッドの向きも柄に対して水平・垂直に変えることができて,打腱しやすくなっている(ひゅっと伸ばしてみんなが驚くのが楽しい).
神経内科は腰椎穿刺以外,ほとんど技術はいらないと自嘲したりすることもあるが,必ずしもそんなことはない.いかに適切に同じ強さで腱を叩けるか神経内科医の重要な技術である.でもハンマーへのこだわりは他科ドクターには決して理解できないでだろうが・・・
世界で使われている打腱器の種類 Clinical Neurosceince 22; 892-896, 2004(田代先生のコレクションのすごさに恐れ入ります)















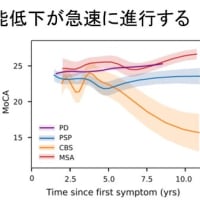
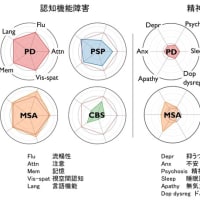


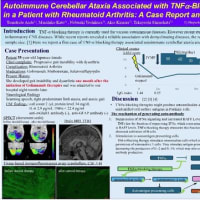

ギャルの勝負パンツのような
ひそやかな決意みたいな感じでしょうか!???
学生の頃、重さからいくと金や銀などを使った
高級ハンマーがあればすごいのではないか!??、
どなたかご高名な先生の何かの記念などで部下たちが
寄付出し合って24金特注ハンマーなどプレゼントしたりして・・・と
夢想したことがありました。
銀細工用の焼いて簡単に作れる粘土があることを聞き
コレで近いものが出来ないかなーなどと密かに
作ってみようと思ったりしています。
富山からこっそり読ませていただいております
これからも拝読させていただきたいと思っております。
今日はじめてきましたが、興味をそそる記事ばかりですね^^
拝読させていただきます^^
下顎反射は軽く口を開けてもらうこと.上肢は肘を屈曲し,おへそのあたりを手のひらで押さえるように置くこと.下肢のアキレス腱反射は,ハンマーを持たない手の方で足首の関節をきちんと90度になる感じで屈曲させ関節を固定することです.ハンマーで直接叩かないのは,下顎反射と上腕二頭筋反射で(下顎ないし上腕二頭筋の腱の指を添えて,その上から叩きます),それ以外は適切な部位を直接叩きます.あとはなるべく遠慮せず,左右同じように叩くこと,解釈の仕方も左右に明らかなさがあった場合には,とくに重視するようにすること・・・と教えています.頑張ってください.