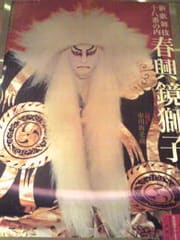1/3の国立劇場初春歌舞伎初日公演に行ったという簡単な報告の記事はこちら
1/3の国立劇場初春歌舞伎初日公演に行ったという簡単な報告の記事はこちら
【通し狂言 旭輝黄金鯱(あさひにかがやくきんのしゃちほこ)】
尾上菊五郎大凧宙乗りにて黄金の鯱盗り相勤め申し候
並木五瓶=作「けいせい黄金鱐(こがねのしゃちほこ)」より
尾上菊五郎=監修 国立劇場文芸課=補綴
国立劇場美術係=美術
序 幕(京)宇治茶園茶摘みの場、宇治街道の場
二幕目(尾張)那古野城内大書院の場、同 天守閣屋根上の場
三幕目(美濃)笠縫里柿木金助隠家の場
大 詰(伊勢)御師大黒戎太夫内の場
(尾張)木曽川の場、鳴海潟の場
東京新聞の記事が詳しいので、以下、概要とあらすじを引用、加筆。
「江戸時代の名古屋の盗賊で、処刑後に名古屋城天守閣の金の鯱のうろこ三枚を盗んだという伝説が生まれた金助が主人公。1783年に初演されたが、明治末期以降は上演が途絶えていた。当時はお上をはばかって鯱盗りの場はなく、本水も使っていなかったが、今回はこうしたスペクタクルをふんだんに取り入れ、四幕八場、約三時間に縮めてスピードアップを図った。・・・・・・菊五郎による同劇場の復活狂言は2002年から本格化し、今年で八作目。」
「時は室町末期。尾張那古野城主の小田家と足利将軍家に父を滅ぼされた金助は、小田のお家騒動を利用して天下を狙う。立ちはだかる別の盗賊・向坂甚内は、実は当主・小田春長で金助とは乳兄弟だった。天守閣で盗んだ金鯱の口から忍びの伝書を手に入れた金助、妖術でこの金鯱を木曽川で大暴れさせるが、小田の忠臣・鳴海春吉に格闘の末取り押さえられる…。」

<今回の配役>
菊五郎=盗賊柿木金助
時蔵=足利家乳人園生/金助母村路
菊之助=小田春長実は小田家家臣鳴海春吉
松緑=盗賊向坂甚内実は小田春長
松也=小田春勝 梅枝=足利国姫
亀三郎、亀寿、萬太郎、男寅、尾上右近
亀蔵、権十郎、萬次郎、團蔵
彦三郎、田之助、ほか

序幕の宇治茶園茶摘みの場は小田春長の弟春勝と足利家の国姫との色模様になる場面なのだが、松也・梅枝コンビが実に若々しくて美しい。特に梅枝の華奢で初々しく美しい赤姫ぶりの押し出しがよくなってきていたことに驚いた。昨年7月の国立劇場の歌舞伎鑑賞教室で藤娘を一ヶ月間踊りぬいたことで大きく成長したのではないだろうか。時蔵が今回は若い女の役をしなかったこともあり、これからは赤姫は梅枝に世代交代を図ってきたかと思えた。梅枝の女方の印象は七之助と同様に玉三郎系の細面の美しさ。これから期待の若女方として注目していこう。

松緑の盗賊向坂甚内も主役の菊五郎の盗賊柿木金助に位負けしないで並び立って堂々としていてよい。小田春長になってからも天下人になる大きさが出ていた。「時今桔梗旗揚」の小田春長も松緑で観てみたいと思った。

二幕目に菊五郎が一昨年の染五郎と同じように大凧の宙乗りを見せるという前評判に期待していたが、3階下手の鳥屋から舞台上手の名古屋城天守閣の屋根に降りてきた。凧自体が1階客席の上で上下したり方向を変えたりという仕掛けだったが、凧に身体をしっかり縛りつけて両手も左右の綱を握り締めて安全第一、菊五郎の年齢もあるし、まぁこんなものかと思っていた。しかしながらそれでは終らなかった。
天守閣の屋根にある金の鯱に隠された忍びの伝書を盗むのだが、そこからさらに天井へとフライングがあり、そこは予想外のサプライズとなって満足!国立劇場の菊五郎の芝居の時はいつも感心する仕掛けがあるが、今回も天守閣の屋根の大仕掛けとともに大道具の工夫に感心。

三幕目の柿木金助隠家の場。金助に頼まれた母村路が国姫を誘拐して隠していたのだが、向坂甚内が乗り込んできたために愁嘆場になる。村路の夫が死んだ後、暮らしのために敵の小田家の若様と知らずに向坂甚内の乳母に出ていたことがわかり、息子の金助とは乳兄弟だったのだ。二人の対峙の間にたった村路は自害して果てる。やはりこういう因縁話が歌舞伎狂言の味付けには欠かせないようだ。

大詰めの冒頭はぐっと気分を変えるチャリ場。菊五郎劇団の喜劇の面白さの炸裂。小田家の悪臣でいつもは團蔵の役どころと思われる役を今回は亀蔵がやっていて、團蔵は?と思っていたらこの場の伊勢の御師大黒戎太夫で登場。金助が策謀の金策のためにここに姿を変えて潜入して金儲けをしているという場面だ。
ここで前評判に高かった
2007年の「俳優祭」の北千住観音のパフォーマンスが再現。「金鯱観世音」をでっち上げて信者からお布施を巻き上げている。北千住観音はどぎつくケバケバしいほどのメイクや衣裳だったが、今回は金助がゲジゲジ眉毛を八の字型につけた情けない顔に変装していて、その顔は変えずに観音になるために金キラの衣裳だけを簡単に身につけての登場。千手観音の後ろの手を出す黒衣たちはさすがに今回も息が合っていて客席を盛り上げていた下座音楽はEXILEのチューチュートレインらしい。
チャリ場の盛り上げに團蔵の軽妙な芝居も必須。筋書によるとこの演目監修の菊五郎のサポートをしっかりしていたようで納得である。それとここで男寅が下女の役で出ていたが、裏返るような声がチャリ場にぴったりだったけれど声変わり最中なのだろう。けっこうナイスキャスティングだ。ここでの時局ネタは「招き猫ダック」(笑)

もうひとつの話題、菊之助の本水の「黄金の鯱つかみ」の立ち回り。金助が妖術を使って川で暴れさせ洪水を起こしているのを鳴海春吉が格闘して鯱を取り押さえるという場面。歌舞伎の定番「鯉つかみ」はまだ観たことがないのだが、
海老蔵が「石川五右衛門」で金の鯱と格闘したのは観たことがある。その時に浪布を使った川の大道具の中で水衣と息を合わせて作り物の竜がいかにも暴れていてそれと格闘しているかのように見せる芸の面白さがわかった。今回はそれに本水装置が加わるわけで、菊之助の奮闘を期待していた。
赤い下帯をしめて身体中を白塗りにした菊之助の身体は胸板も薄く、その痩身は少年のようだった。可愛いお尻も前から9列目で見せてもらって「カワイイ~」とおばさんは満足したのであった。今回、菊之助の美しい女方の役はなかったが、まぁそういう役は梅枝に譲って、この本水の立ち回りで十分としておこう。

田之助が小田家後室操の前で元気に姿を見せてくれていたが、筋書によると昨年両膝に人工関節を入れたとのこと。座る芝居はできないが、舞台にいてくれるだけで有難い存在だ。

初めてのお正月歌舞伎の初日公演初体験で、文句なく明るく楽しいエンタメ作品を堪能。できれば毎年恒例にしたいものだが、親兄弟の集まりの予定がぎりぎりまで決まらない関係で、チケットを早くから押さえられない。今年は実にラッキーだった。

写真は公式サイトより今回公演のチラシ画像。