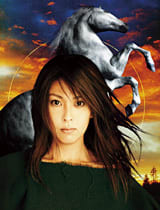歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」通し上演を初めて観るので、雨の中を口上人形に間に合うようにいつもより早めに家を出た。第一回東京マラソンの交通規制があるということだったが、地下鉄東銀座駅から出てすぐだから影響はなかった。それでもギリギリかと思ったら余裕があった。今回から11:00開演後に始まるようになったらしい。慣習も知らない人が多くなれば最早変えざるを得ないということだろうか。

関容子さんの『芸づくし忠臣蔵』にも登場されていた中村仲太郎が定式幕の前に黒衣姿で出て人形を遣って口上を述べる。
主だった配役を昼の部だけでなく夜の部まで読み上げるのだが、重要な役の前にはエヘンエヘンエエッヘンとわざと咳払いをして注意を引きつけて役者の名前を二度読み上げる。咳払いあり一度読み上げ→咳払いなし一度読み上げ、と扱いの大きさが耳からもわかって面白い。
おかるの名前は「腰元おかる」「女房おかる」「遊女おかる」とよびわけているのもなぁるほどだった。

幕開きもいつもと違って大げさだ。「天王立下り端」というおごそかな鳴り物の中で柝が間隔をあけて47回打つことになっている。定式幕はいつ開き始めたのかわからないくらいの感じで開き始める。最初はゆっくりゆっくり、真ん中以降でスピードが上がっていく。心地よい鳴り物に身を委ねて柝の音を数えてみたが、途中でわからなくなった。ゆっくり数えるって苦手だ。
幕があくと下手から役者が「人形身」になって目を閉じて頭を垂れて静止しているのが見えてくる。幕が開ききったあとでも、人物はすぐには動き出さない。竹本は出語りではなく御簾うちで語る。誰の語りであるかをイヤホンガイドで聞いて知る。竹本が主だった役の名前が呼ぶと初めて首をクックックッと上げていき目を開き、正装の大きな袖をふわっと浮かせて居住まいをただして人間としての命が入って動き出す。歌舞伎の方で人形浄瑠璃を意識した演出をしているようだ。
大序というのは時代物浄瑠璃の第一段のことで、それがきちんと残っているのはこの「仮名手本忠臣蔵」だけとのこと。このかなり大げさな厳かさを味わえるのがこれだけというのは貴重である。特に人形から人間になるところはゾクゾク感が走った。この幕開きは何年かに一回は観たくなりそうな予感がした。

【大序 鶴ヶ岡社頭兜改めの場】
文楽の「鶴ヶ岡社頭兜改めの場」の感想はこちら
今回の主な配役は以下の通り。
高師直=富十郎 塩冶判官=菊五郎
桃井若狭之助=吉右衛門 足利直義=信二郎
鷺坂伴内=錦吾 顔世御前=魁春
信二郎の直義は気品があって美しい。4月の錦之助襲名が楽しみだ。陪臣の礼服である素袍大紋を身につけ烏帽子を被った姿も色とりどりで美しい。
文楽で遅れて観ていなかった冒頭部分。師直と若狭之助の言い争いとその仲介に入る判官のやりとりを観て、実録では短気な浅野内匠頭のイメージがこの狂言では若狭之助にわりふられ、判官はおっとりとした好人物にしたのだなぁとあらためて思った。『太平記』にあったという高師直の塩冶判官の妻に横恋慕したエピソードとつなげていったというあたりも作者たちの工夫に感心する。

さらに顔が佳いから顔世というネーミングにしたらしく、顔世御前には大事件を起こす横恋慕の対象となる色っぽい美しさが必要らしい。魁春は品格はあると思うのだが残念ながらそこまでの色っぽさを感じることはできない。お元気ならば雀右衛門、そうでなければ芝雀あたりの配役で観たかったというのが本音。

富十郎の師直がとにかく立派!若狭之助をいびるところは憎憎しさたっぷりだし、懸想する顔世を登場からずっと見つめ、言い寄るところなど恋するおじさんの可愛げがあふれていた!!富十郎のお年でこれだけ元気にいじめ元気に女に言い寄る役ができるというのはすごいことなのではないだろうか。
吉右衛門の若狭之助もとにかく若い。正義感が強く気が短い小大名を演じていて可愛さを感じてしまった。富十郎とのやりとりも気合十分で見ごたえあり。菊五郎の塩冶判官がとにかくいい人なので、この3人のバランスが見ていて心地よかった。

写真は今月の「耳で観る歌舞伎」表紙の富十郎師直。
以下、この公演の別の段の感想
2/18歌舞伎座昼の部「仮名手本忠臣蔵」三・四段目
2/18歌舞伎座昼の部「仮名手本忠臣蔵」道行旅路の花聟
2/25歌舞伎座千穐楽夜の部「仮名手本忠臣蔵」11段目