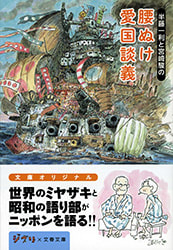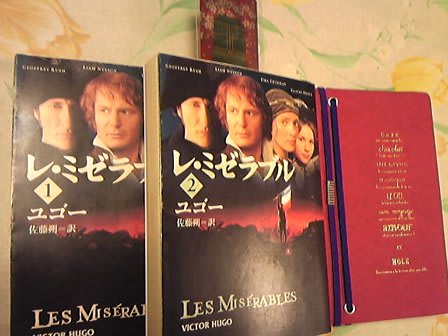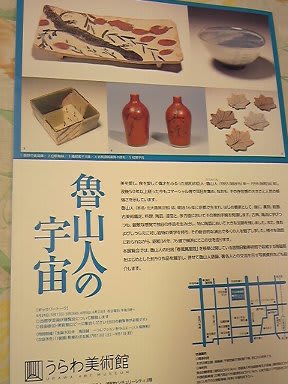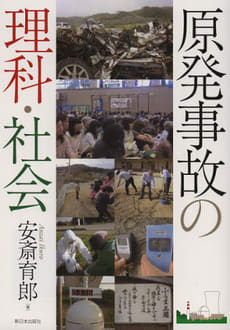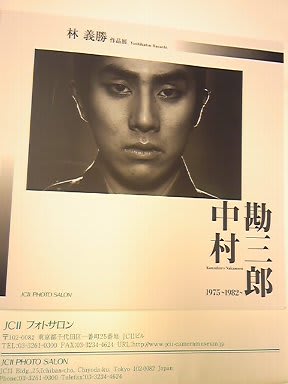2008年7月に「姜尚中の本を読む」という記事
2008年7月に「姜尚中の本を読む」という記事を書いた。
2007年12/13の夜、新宿サザンシアターで姜尚中×小森陽一トークショー&サイン会「2008年、日本はどうすべきか」のトークで、あぁ本当に金大中氏を尊敬しているんだなぁという話しぶりだったことをよく覚えている。大学時代に韓国の民主化を求めて運動に明け暮れていた姜さんにとって、金氏は「たった一つの青春のシンボル」とでもいうべき存在だったという。

6/24(日)、久しぶりにゆっくりした私はBOOKOFFの105円コーナーで掘り出し物はないか探していると、
姜尚中著『リーダーは半歩前を歩け──金大中というヒント』(集英社新書)を見つけた。字も大きいので一気読み終了。
2005年5/23、東京大学は金大中元韓国大統領を安田講堂に招いて講演会を開催。金氏の招聘に一役買った姜さんは、2009年2月に思い切って面談を申し込んだところ念願がかない、4/7にソウル市内の金氏の自宅で1時間半ほどの対話が実現したという。その記録が第4章だが、出版準備をすすめている中、金氏は体調を崩されて8/18に逝去された。この本はその翌月22日に出版されている。
以下、ウェブでの紹介の文章を引用。
政治も経済も未曾有の混迷期にある現在、私たちは「リーダーシップ」という古くて新しい問題を、問い直す必要がある。安全保障の激変期における政治家とは? 金融崩壊後の市場で持続可能な成長を実現し得る経営者とは? 明確なビジョンを示す上司とは? 本書は、古今東西の政治家や歴代の日本の首相に言及しつつ、悩める時代を突き抜ける「7つのリーダー・パワー」を提言する。韓国元大統領にしてノーベル平和賞を受賞した金大中氏との対談も収録。指導者不在が叫ばれる日本社会で、現代を代表する政治学者が思い描く、理想のリーダー像とは?

金大中氏との対話の中で、ここはと思ったところを以下、抜粋してご紹介する。
姜 先生のお話の中で私がいつも感銘を受けるのは、「フランス革命」と「イギリス名誉革命」の比較についてです。先生はこの2つの革命のうち、「イギリス名誉革命」の方を評価していらっしゃいます。というのもフランス革命では、ロベスピエールによって、王をはじめとする旧体制の人びとが粛清されました。これに対して、名誉革命は妥協的だったけれども、新旧の勢力が歩み寄ろうとしました。先生は「革命とは血が流れるものである。しかし、どんな場合でも、流血はできるだけ避けて、新旧双方が宥和する道を探るべきである」と一貫しておっしゃってきたように思います。そのようなお考えは、いつごろからお持ちなのでしょうか。
金 先ほどあなたが名前をお出しになったトインビーの『歴史の研究』を読んで多くを学んだと思います。
(中略)
姜 先生から日本の政治家に、──韓国の政治家に対してでもよろしいのですが、歴史に学ぶときに何がいちばん重要かということを提言していただけませんか。
金 いちばん重要なのは、長い歴史とよく対照して、自分たちがやった誤りを見つめることです。そして、反省して、それによって新しい歴史を再生していくことです。ドイツはそれをやりましたよ。敗戦ののち、世界に謝り、ユダヤ人に対していろいろな償いをしました。ドイツの学生は、子供のときから過去に対する教育を受けます。ドイツはあちらこちらにあるユダヤ人虐殺現場や収容施設を遺跡として保存しました。そのような反省をしたから、周辺の国々もドイツを信頼するようになったのです。
ドイツはいまEUの一員として活動しているでしょう?北大西洋条約機構(NATO)の加盟国です。東ドイツが西ドイツと合併すると言って立ち上がったとき、かつては「ドイツの統一など、ぜったいに許さない」と言っていたイギリスやフランス、それからソ連も賛成しました。それは、ドイツの戦後の反省態度を認めたからです。
同じように、日本も歴史に学んでください。そうすれば、われわれも日本をもっと愛するようになるのではないでしょうか。いまでも中国や韓国ではときどき反日デモが起こりますが、そういうこともなくなると思います。過去に日本に侵略されたアジアの国々には、いまだに日本に対する恐怖が、多かれ少なかれ残っています。不信感を拭いされていないから、日本がこれ以上強くなるのを恐れて、国連安保の常任理事国入りにも反対しているのです。
(中略)
姜 日本では過去と向き合うことがなかなかできづらい面があるようです。その根っこはどこにあると先生はお考えでしょうか。
金 そうですね。日本の民主主義はマッカーサーが来て、プレゼントしてくれたようなものではないですか。だから民主主義の基盤が、いまひとつはっきりしないのかもしれないですね。風が少し吹いただけで揺らいでしまう。日本の人たちは、私たちのように「民主主義を勝ち取るために、血を流して闘った」という思いがないのではありませんか。何となく手に入れてしまったから、あまりありがたいと思わない。だから「昔もよかった」などと言う。昔を懐かしんだり、戻ろうとしたりする。そのせいもあって、あんなに経済的に貢献しているのに、国際的にはあまり評価されないのです。歴史をきちんと見ないからです。損ですよ。
民主主義はタダではないのです。民主主義を勝ち取っても、それを守るために積極的に努力していかないと、逆戻りすることがあります。ですから、私は日本の友人として、どうぞドイツに学んでくださいと、重ねて言いたいですね。そうすれば、私たちも日本を信用して、本当の友人になりたいと思うでしょう。私は一度、小渕首相と話し合って、ずいぶんとよい雰囲気になったのです。ところが、それからいくらもたたないうちに、また過去を美化するような動きが出はじめてしまいました。
いま、戦後64年です。日本人の中でも、終戦時に10歳以下だった方は、当時のことをよく知らないはずです。ですから、教育で教えていかないと、彼らの子供、孫の世代は過去にどういうことがあったのか理解できないでしょう。とくに、いまの若い人などは、悪意があるわけではないのだと思います。意味がわかっていないのです。なぜ戦後何十年もたっているのに、いまだに罪人みたいに言われるのか、わからないのです。もう謝ったじゃないか、なぜいつまでもしつこく言うのか──と、たぶんそういう気持ちなのでしょう。彼らを悪いとは言えません。なぜなら、ちゃんと教えられていないからです。
日本は、国民に対してきちんとした教育をしてください。過去の歴史に対して、真実を学んでください。そうすれば、日本は世界から愛される、偉大な国になる。私はそう思います。
(中略)
姜 それでは、そのようにグローバル化が進んだ世界になるとすると、その中でのリーダーはどうあるべきでしょうか。
金 政治家は、目の前の状況をよく見ながら、国民とコミュニケーションをとらなければいけないでしょう。
(中略)
だから、リーダーは国民と一方では手を握りながら、その手を離さないで半歩前に行く。もし国民がついてこないようなら、ちょっと立ち止まって、手を離さないで説得をする。そして国民の声を聞く。そうして意見を合わせる。そのようなやり方が、いま、成功する秘訣ではないかと思います。



金大中氏は、軍事政権によって死刑宣告を受け、長く刑務所に入れられたり軟禁生活を送らされたが、その中で多くの読書をしたのだそうだ。それが理念や思想を形づくったと語っていることに感銘を受けた。

日韓両国で歴史教育の内容を検討する機関をつくろうということになって、ようやくドイツが周辺国と取り組んできたことに日韓は手をつけることができたという思いを抱いたものだが、それは確か小渕首相と金大中大統領が会談した時の合意ではなかっただろうか?

私が子どもの頃の韓国は軍事独裁政権の時代だったが、それがいつの間にか日本よりも民主主義が進んだ国になっている。やはり国民的な運動で闘って勝ち取ったという歴史的経験のためかと納得する。韓国の経済危機が深刻になり、現在も若者の失業問題は日本よりも深刻だと聞いているが、そこへの対応の試みは、日本よりも進んでいる面がかなり見受けられる。アジアで初の「社会的企業育成法」をつくったことなどに注目しているところだ。
それに関わる記事はこちら
また、私は『ベルサイユのばら』以来、フランス革命が好きだったが、
ミュージカル『M.A.』(マリー・アントワネット)では、革命の理想と流血の問題が心にのしかかってきたものだ。民主主義の模索の道について、イギリスの状況について、少し真面目に追及してみようかという気持ちが強くなってきた。ちょうど同じく105円コーナーで
山口二郎著『イギリスの政治日本の政治』(ちくま新書)も買ってきたので、しっかり読もうと思う。

(追記)
今日、衆議院で消費税増税案が可決されてしまった。この間の消費税増税が企業減税や金持ち減税とほぼ同じ規模であり、後者を元に戻すのが先だと思っているが、そういう勢力は小さいままだ。マスコミ報道はすぐに政局問題に流れてしまうのが問題だ。
この年になって、仕事も観劇も読書も忙しい日々となってきた。しっかりと自分の頭で考えて声を上げていきたい。