
松嶋屋の若手役者二人が主演する映画「Beauty」は全国一斉ロードショーではなく、製作・上映を成功させる会による全国上映企画が連続的に各地で取り組まれている。東京でも3/14から
シネマート六本木と
銀座シネパトスで上映が始まったが、レディスデイの夜に観ることができるラストチャンスにかけつけた。

【Beauty うつくしいもの】
<主なスタッフ>
監督:後藤俊夫 / 製作総指揮:角川歴彦 /
音楽:小六禮次郎 / 振付:藤間勘十郎
<主な出演者>
片岡孝太郎、片岡愛之助、麻生久美子、嘉島典俊、大西麻恵、二階堂智、赤塚真人、串田和美、井川比佐志、北村和夫
<あらまし>
大鹿村サイトのエキストラ募集の記事が一番わかりやすい。

後藤俊夫監督は信州・伊那谷で生まれ育ち、13年前に東京から戻ってきて伊那を舞台に映画を撮影。「こむぎ色の天使・すがれ追い」から9年、長年温めてきた村歌舞伎を伝承する人々を描いた本作を撮ったのだという。映画づくりで地域を元気にしたいという思いで伊那市のふるさと大使にもなって、この作品も地元の企業や行政、村歌舞伎を伝承する人々の力が集められた。
その取材中に
13代目仁左衛門が大鹿歌舞伎を二度も観に来たことを知って松嶋屋に強い思いを持っていた。プロデューサーを通じて脚本が当代に渡り、息子の孝太郎が脅威を示してくれて出演してくれることになったのだという。
このプログラムの監督の話には感動した。

昭和10年時の子ども時代の半次・雪夫・歌子を演じる子役3人がそれぞれよくて一気に物語に引き込まれる。赤塚真人が演じる村歌舞伎の義太夫の師匠の娘歌子がはしかで出演できなくなって「新口村」の梅川の代役を雪夫に乞われたことから半次は村歌舞伎の世界に入る。雪夫の立役と半次の女形のコンビで村の看板役者となってしまうのだが、歌子は二人を支える存在になっていく。二人の舞台の映像で大人の役者にタッチ交替。

昭和19年。そんな歌子と雪夫が相愛の中になっているのだが、彼ら若者たちのもとにも召集令状が届きお別れの舞台が出征を祝う会を兼ねる。その舞台は「太十」(太平記十段目)。孝太郎と愛之助と並んで武智光秀をつとめた政男役の嘉島典俊も立派だった。雪夫は歌子に気持ちを伝えないまま出征。
終戦後にシベリアの強制収容所に送られた半次たちは厳寒の地で過酷な労働の日々を送るが、政男が肺炎で死んでいく。雪夫も伝染病になって隔離され別れ別れのまま帰国の日を迎えた半次は雪夫から託された遺書を家族に届け、一緒に連れて帰れなかったことを詫びる。歌子にも詫びて雪夫の気持ちを伝えると、歌子はこれまでの気持ちをぶつけるが、二人は戦争で途絶えかけた村歌舞伎を再興することで寄り添っていく(ここで二人が結ばれるってことにはしない展開?!)。製材所で働きながら立役もつとめながら村歌舞伎の仲間をまとめていった。
しかし雪夫は生還していた。しかし目と心に深い傷を負っていたために家族のもとに戻らず、二人の前にも姿を見せない。失明して按摩で生計をたてていた雪夫は半次たちの舞台に駆けつけていたのだが、心の傷のうずきに耐えられずにまた身を潜めてしまっていた。
ある時、遠く離れた村で本来は伊那谷だけに伝わる芝居「六千両」を演じる役者がいることという新聞報道を見せられた半次はその男を訪ねていくと座長(串田和美)から幸夫の病状も聞かされる。雪夫の家に訪ねた半次は3日後の「新口村」で一緒の舞台に立って欲しいと説得。その日時間ぎりぎりに駆けつけた雪夫とともに舞台にたつ。しかしその幕切れに雪夫の命は尽きてしまった。

その後の長い年月を村歌舞伎のリーダー役をつとめた半次の引退の舞台は思い出の舞踊「天竜恋飛沫(てんりゅうこいしぶき)」。新調した衣裳は直前に止めて幸夫の衣裳で踊る半次。戦争の古傷がうずく足元はふらつき、古い衣裳の袴はひもが千切れて小袖姿になってしまう。それでもレンギョウの精と水底で添い遂げる最後まで踊りきる半次。幸夫の想いと添い遂げたということだろうか。
麻生久美子も本当に華奢な身体で歌子を健闘。半次とともに村歌舞伎を支えることが彼女の幸夫への想いを全うすることだったのかもしれない。
3人の関係はちょっともどかしいほどせつなかった。

北村和夫が村長役で村の英霊を迎える場面だけ出演しているが、撮影半ばで亡くなって遺作になってしまって場面を減らしたらしい。本当に残念だが、一場面でも素晴らしい存在感を添えてくれたことに感謝したい。

幸夫の心の傷とは中国戦線で満蒙開拓団の引揚げで遅れた女子どもたちをソ連軍の捕虜にさせないために手榴弾で殺したことだった。爆発物のかけらが眼に入ったことがもとで失明したということだろうが、上官命令を実行したとはいえ人の命を奪ってしまったことの記憶が消えないという時代の悲劇もしっかり描いていた。
シベリアの抑留問題の歴史も実際に抑留されていた方のお話も聞いたことがあるし、
劇団四季の「異国の丘」を観たり、その原作
『夢顔さんによろしく』などを読んでいた。今回も病人が出るとうつされたくないと冷たい行動をとる人間もいるリアルな様子、その中で支えあう仲間の素晴らしさも描かれていた。肺炎の政男が弱っていき死んでしまう展開にまず泣けた。

井川比佐志演じる実直な木地師のじっちゃんの存在感も貴重。半次が帰ってきて迎えてくれたのは遺影で村の道普請で倒れて村のみんなに看取られて死んだというあたりでも泣ける。

戦死した者も銃後で死んでいったものも、戦時の暮らしに耐えた者も時代の過酷さに翻弄されている。そこから立ち直って生きていく、こだわった文化を再生させていくことのもつ重みも感じさせる。
とにかくこの作品は過剰な音楽も演出も感じさせず、淡々と描いているのが逆にしみてくる。何度も何度も涙がにじんだ。

松嶋屋の若手二人が頑張っていたのが嬉しい。孝太郎は地味ではあるがひとつのことを地道に積み上げていく人物の素晴らしさを実に誠実に体現していたと思う。愛之助は背負ってしまった苦悩に悩む姿も美しい。失明して按摩になっている長髪を束ねた姿は「大王四神紀」のペ・ヨンジュンみたいだと思ってしまった。このコンビが相乗効果をあげているのがいい。本物の歌舞伎役者が村芝居に見えるように苦心して演技したということだが、美しさは本物なのがこの作品のひとつの魅力でもある。

二人の父も特別出演しているのが嬉しい。秀太郎は蕎麦屋の客で本当に普通のおじさんみたいだった。仁左衛門は半次の引退公演を観に来た観客で半次がよろけると心配そうな表情が大写しになったし、エキストラたちと一緒に芝居を楽しんでいる表情もご馳走だ。映画の題字も仁左衛門とのこと。
松嶋屋贔屓にはそういうことも嬉しい映画であった。

やはり村歌舞伎をとりあげたドラマの
「おシャシャのシャン!」も観ている。ひとつの地域の人々の中に根付いた伝統としての村歌舞伎の雰囲気が素晴らしい。
(追記)
シネマート六本木で同時期に上映されている「さらば、わが愛~覇王別姫~」と思わず比較してしまった。古典芸能の世界に関わる男二人と女一人が時代の波に翻弄されていく物語という共通点あり。「Beauty」では歌子に役をとられたというあたりに確執はあるものの、愛情の三角関係ではない。そのあたりで結末が大きく違ってくるという相違あり。蛇足で失礼m(_ _)m






































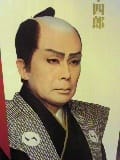








 →
→













