

チケットをとった時の記事はこちら
【初瀬/豊寿丸 蓮絲恋慕曼荼羅(はちすのいとこいのまんだら)】
主な配役は以下の通り。
初瀬=坂東玉三郎 豊寿丸=市川段治郎
藤原豊成=市川門之助 照夜の前=市川右近
月絹=市川笑三郎 嘉藤太=市川猿弥
老女=市川寿猿
紫の前=市川春猿
あらすじは以下の通り。
右大臣藤原豊成と妻の紫の前は、子どもができるように泊瀬(はつせ)寺に参籠。観音のお告げ通りに娘を授かる。その由来で初瀬と名づけられた娘が7歳になる前に、両親のうちのどちらかが命を失うというお告げの通りに母が身罷る。父は妻の生前より橘家の照夜の前の元に通い、豊寿丸を得ていた。母の死後に同居した異母弟は姉の初瀬を慕う。
美しく聡明に育った初瀬は琴の名手でもあり、父とともに参内してその音を愛でた帝に三位中将の内侍の称号を賜った。継母の照夜の前はそれが面白くない。さらに息子の豊寿丸が自分のすすめる姫に会おうともせずに初瀬に執着していることが気になっていた。初瀬もこのところ豊寿丸を避けるようにしているので、豊寿丸の思いは募るばかり。屋敷の裏口で姉の帰りを待ち伏せする豊寿丸。物乞いが寄ってきても身分が違うと追い散らす。帰宅前に近づいてきた物乞いに施しをしてしまう初瀬に侍女の月絹は苦言を呈する。姫の評判をききつけて物乞いが増えるばかりになるという。世は政が乱れ、天変地異が相次いでおり、物乞いが街中にはあふれていた。
豊寿丸は待ち伏せに成功。月絹を夫の将監が呼んでいると偽って引き離し、初瀬に言い寄ってついには押し倒す。そこを照夜の前とお付の老女田束が見咎めると、とっさに豊寿丸は自分が襲われたのだと嘘をつく。継母に打ち据えられ髪を引きずりまわされる折檻を受ける初瀬。さらに父豊成が帰宅し、手討ちにされるところを月絹や将監のとりなしで、宇陀の里雲雀山山中にある庵に蟄居することになる。
照夜の前は真相を見抜いており、息子の執着を断ち切るために初瀬を殺すことを警護の嘉藤太に申し付ける。
庵につく前に嘉藤太は他の供の者を帰して姫を斬ろうとする。気絶させられている月絹の命を助けることだけを条件に従容と念仏を唱える姫をどうしても斬れない。
主の照夜の前を偽ることを約束しているところへ豊寿丸が身替り首を持ってくる。行き倒れの娘の首と言っていたが、娘を探す身内の話から豊寿丸が殺したことがわかり、姉のためには常軌を逸してしまう異常性が浮き彫りになる。豊寿丸は嘉藤太と目撃者の修験者をも殺してしまう。
その修験者の情報で初瀬が生きていることを知った照夜の前は自ら殺しにやってくる。母の動きを察知した豊寿丸は姉を逃がしにやってくるが、すでに遅い。照夜の前は緋袴を身につけ小袖を被った者を刺し、憎しみをこめてえぐるが、それは初瀬ではなかった。豊寿丸が身替りになったのだ。苦しい息で「生まれ変わっても姉上の弟に」という豊寿丸は姉の腕に抱かれて死んでいく。
事態を聞いてかけつけてきた豊成。照夜の前は地獄谷に投身自殺してしまう。家に連れ帰ろうとした初瀬は出家を願い、当麻寺に入ることを父に許しを請う。豊成は自分の罪業の報いを家族が受けたことを悔い、初瀬の出家を許して自らは弟の謀反の鎮圧に出陣していく。
その夜、初瀬の夢枕に母の紫の前が立つ。蓮の茎を集めて一丈五尺四方の曼荼羅を織り上げるように告げて消えていく。月絹の声に目を覚ました初瀬の前に母が手にしていた蓮の花があった。
下山を助けるために山守の息子がやってきた。蓮介というその若者は豊寿丸に似ていて「こんなに美しい姫様が世を捨てるのか」ときく。初瀬は「いいえ、世を拾いにいくのです」と晴れやかに微笑んだ。

こうして思い出して書きながら場面場面を思い出すだけで、思いが満ち満ちてくる。この作者の方の人生経験の豊かさがにじんだ作品という玉三郎丈の指摘に全くその通りだと思う。
三位中将の内侍の称号から「中将姫」と言われてたくさんの伝説があるということだが、今回の観劇まで詳しいことはほとんど知らなかった(バスクリンのツムラの昔のマークが中将姫だったような気がするが)。
子どもの頃に「おしゃかさま」という絵本を読んで以来、仏教には関心がある方で特に仏像が好きだった。就職して関西に8年住んだ時にもう少しお寺めぐりをすればよかったと思うが、その頃は仕事に労働組合活動に忙殺され、さらに妊娠出産育児でままならなかった。

私は長じて無神論者になったが、宗教にはずっと関心をもって三大宗教の原理的なことは一応認識したつもりでいる。もちろんそれもごく浅いものだし、さらに詳しい宗派についての理解までは及んでいない。

しかしながら、この物語に流れる思想についてはいろいろと考えさせられる。初瀬は、そもそもこの世に苦しむ人々を救うために働くよう、観音によって遣わされたのではないかという気がした。しかしながら人間として生まれた以上、生まれてすぐにその使命を自覚できない(聖徳太子は例外的)。それを自覚させるために罪業を背負わせたのではないか。そのために弟に懸想されて苦しみ、さらに自分のために死んでしまうという、地獄に落ちてもいいとまで思える苦しみを与えられたのだと思えた。その究極の苦しみの中で「人が生きてこの世で救われる方法」を真剣に求めたことにより、出家と仏の世界をこの世に伝える曼荼羅を作り上げるということを発心できたのではないかと。

以上の書き方だと、まるで全ては仏の掌の上の出来事のようにも思える。しかしながら初瀬が苦しみながらも発心できるかどうかということは、その主体性にかかっていることだとも思える。だからこそ、全ての運命の中で主体的に生きる女主人公の姿は清清しい。

玉三郎丈はこの作品を澤潟屋一門で上演することが決定した上で演出を依頼された。作品を読み込んでいくうちに「これは若い人でやれる役なのか」と思うようになり、自らが初瀬として主演することを決意されたのだという。確かにこのお役は精神性の高い難しい役だし、この役の出来いかんでせっかくの作品自体が薄っぺらなものになってしまうだろう。時分の花のレベルで演じられるものではない。大輪の芸の花を咲かせている立女形にしか演じきれる役ではないだろう。そもそも作者が玉三郎丈を想定して書いた作品なのではないだろうか。

何色もの壁が動き、照明が変化するだけのシンプルな舞台装置。衣装だけは本格的に身につけた登場人物。音楽も琵琶の音や宗教的な意味合いが強い場面で使われた声明。柝は最初と最後だけ。中世の貴族の愛憎と貧しさに苦しむ庶民とを対照させ、自らの苦しみからの解脱だけでなく、世の人々全てに仏による救いをもたらそうとする女主人公。それを必要最低限の演出で描き出していた。
こんな舞台を創り出した玉三郎丈そのものが「世拾い人」のように思えて仕方がなかった。21世紀のこの日本にも必要な文化面での「世拾い人」のおひとりだ。そして、このような美意識あふれるお仕事が中将姫の曼荼羅にあたるのではないかと!

千穐楽のカーテンコールで国立劇場開場40周年記念公演の最後の舞台でのご挨拶があった。国立劇場開場の頃からのご自身とのかかわりをふりかえられ、40周年とはいえ400年続く歌舞伎の歴史の中のほんの一部分であり、これからも精進される決意を語られた。このご挨拶を詳しくレポされている六条亭さんの記事をご紹介させていただきたい(→こちら)。
その中で30周年記念公演で「阿古屋」を演じられたというお話もあった。ということは本当に国立劇場の節目節目では玉三郎丈に寿いでいただくような関わりがお互いにあったということなんだと納得。50周年にも何かの形できっと関わってくださるに違いないと思えた。

さらに国立劇場の研修生出身者が今回の公演で何人も舞台に上がっていることにもふれられたことあらためてハッとさせられた。この育成事業の成果が目にみえてきたということだ。こうしたことで若い力はより励まされていくに違いない。
このご挨拶をきいているうちに滂沱の涙が伝い、ぬぐう余裕もなく一番端の席なのを最大限活用して立って手を伸ばして拍手させていただいたのだった。






写真は公式サイトより今回の公演のチラシの画像。













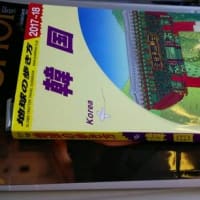
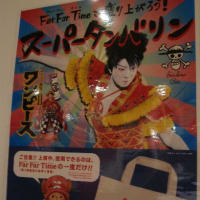

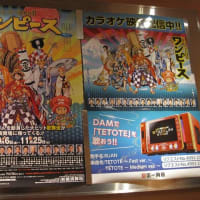
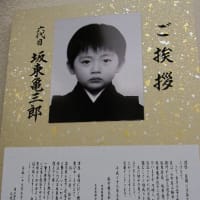
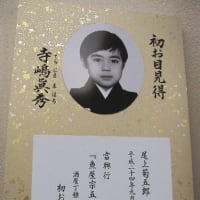

例の「キャンディード」をまったく理解できなかったワタクシが、この作品がドツボに嵌った。やはり、アジアの仏教文化のなかで育ったのだなあ、と自覚いたしました。
(ワタシも、ぴかちゅうさん以上の無信仰人間ですが)
あと、はっきりしたことがひとつ。ワタクシは、玉さまの美意識、世界が好きだ!ってことです。この方の目指しているもの、それは、伝統的古典歌舞伎の維持とは違う方向かもしれないけれど。世界に発信すること、他の芸術分野とのコラボレーションも、玉さまはめざしておられると拝察しております。
高校生のとき、マクベス夫人で玉さまに嵌ったワタクシ。やはり、そのころから、彼の感性に惹かれるものがあったのでしょうね。
ことしは、鼓童との舞台もみるぞ!
それにしても、おもだかの皆様、私服もオシャレですね^。
私も無神論者ですが、仏教的思考は生まれながら持っているようですから、今回の新作の主題はぴたりとはまりました。「世拾い人」の言葉はとくに印象に残りました。
作者は玉三郎さんに主演してもらい、あのような完成度の高い舞台が作り上げられたのですから、作者冥利に尽きるでしょうね。
これからも玉三郎さんが新しい舞台に挑戦してくれることを期待したいです。
>高校生のとき、マクベス夫人で玉さまに嵌ったワタクシ......私は同じ頃に玉さまのデズデモーナを観たのだけど、正直あまり大したことないなぁと思ってしまってました。マクベス夫人の方がキリッとしてよかったでしょうね。
ここ数年での歌舞伎観劇再開で玉さまに再会したら、あまりの芸の花の咲き誇る様子にすっかり虜になってしまってます。私、若い頃の玉さまがそんなに好きじゃないのね。若い頃の写真を見てもそんなにいいと思えない。今がもう最高です。この円熟期を見逃さずにすんでよかった~。「アマテラス」・・・考えます。
★六条亭さま
>「世拾い人」の言葉はとくに印象に残りました......渡辺保氏は劇評の中でその言葉がわかりにくいのではないかと危惧されていましたが、そんなにわかりにくいかなぁという感じがしました。大丈夫ですよね。
これからの丈の挑戦をずっと追いかけていくことが私の大きな力になると思ってます。
HineMosNotariさんの記事をせっかくですのでこちらでご紹介しておきたいと思います。力作です!
http://blog.goo.ne.jp/hm_notari/d/20070316
こちらから、TB返しさせて頂きました。
3月25日の千穐楽を観劇されたとの事、羨ましい限りです。
うしろ姿から「後光がさす」事ができるのは・・・・・
「玉三郎様!あなただけです!」なんて思ってしまいました。
千穐楽のカーテンコールでは、国立劇場開場40周年記念公演の
最後の舞台でのご挨拶があったとのこと、やはり玉三郎さまの
語りを私も聞きたかったです。
カーテンコールのご挨拶にも感動して滂沱の涙!!ご自身のさらなるご活躍と若手のご指導を一層お願いしたい気持ちでいっぱいになりました。
遠征はできませんが、なるべくしっかりと玉三郎丈の舞台は観ていこうと思っています。