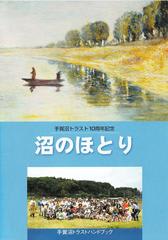99年2月28日、手賀沼トラストという市民団体が発足しました。
そして、今年は10年目の節目を迎えています。
これまで何をしてきて、どこまで到達したのかを確認するため、
ハンドブックという名の10周年記念冊子を作成しました。
前半は手賀沼トラストの活動の紹介、
後半は中心的事業である「農教室」の講習内容のポイント。
手賀沼周辺のライフスタイルの一つの提案として
また、考えるきっかけとして活用していただけたら
幸いです。
原稿作りには多数の会員の皆さんが関わっています。
活動紹介の各項目ごとにはプロジェクト担当の会員が、
農教室の作物ごとにもそれぞれの講師陣が
文責者となっています。
さらに、
活動フィールドの鳥瞰図や作物のイラストはIさん。
写真はブログも担当しているTさん他のみなさん。
編集作業にはKさんに力を発揮していただきました。
表紙等を飾る絵画は昨年夏に急逝された
元代表のHさんの作品。
快く使わせていただいた奥さまに感謝します。
そして、限られた予算の中で予算以上の成果を出していただける
デザイナーのAさん、
いつもお人柄に甘えてしまい、申し訳ありません。
今回もいいものが完成しました。
関係機関やこれまでお世話になっている皆さんには
現在、お届けしている最中です。
近在の自治体の図書館にも寄贈させていただきます。
見かけましたならぜひ手にとってみてください。
もし遠方の方で手に入れたいという方がいらっしゃれば
ご連絡ください。
たいへん恐縮ですが、
一部500円(送料込み)にてお分けします。
そして、今年は10年目の節目を迎えています。
これまで何をしてきて、どこまで到達したのかを確認するため、
ハンドブックという名の10周年記念冊子を作成しました。
前半は手賀沼トラストの活動の紹介、
後半は中心的事業である「農教室」の講習内容のポイント。
手賀沼周辺のライフスタイルの一つの提案として
また、考えるきっかけとして活用していただけたら
幸いです。
原稿作りには多数の会員の皆さんが関わっています。
活動紹介の各項目ごとにはプロジェクト担当の会員が、
農教室の作物ごとにもそれぞれの講師陣が
文責者となっています。
さらに、
活動フィールドの鳥瞰図や作物のイラストはIさん。
写真はブログも担当しているTさん他のみなさん。
編集作業にはKさんに力を発揮していただきました。
表紙等を飾る絵画は昨年夏に急逝された
元代表のHさんの作品。
快く使わせていただいた奥さまに感謝します。
そして、限られた予算の中で予算以上の成果を出していただける
デザイナーのAさん、
いつもお人柄に甘えてしまい、申し訳ありません。
今回もいいものが完成しました。
関係機関やこれまでお世話になっている皆さんには
現在、お届けしている最中です。
近在の自治体の図書館にも寄贈させていただきます。
見かけましたならぜひ手にとってみてください。
もし遠方の方で手に入れたいという方がいらっしゃれば
ご連絡ください。
たいへん恐縮ですが、
一部500円(送料込み)にてお分けします。