★乱氏に誘われて大学生――先日の教育実習生の模擬授業研修で紹介した彼等のうちの一人――の授業を観にいく。
懸命に「黒板に向かってしゃべらない」という努力をしていることが、よく伝わってきた。
下手な俳優は、親が息子の首根っこを押さえ「この親不孝者が!」とぶつ場面で、「セリフ」と「ぶつしぐさ」を同時にやってしまうが、上手な俳優はセリフのあと、そのセリフにこめられている幾種類かの思いをこめて、きっちりとぶつ演技をするといわれる。(この情報は、近時、TVから得たのか、インターネットから得たのか、もう出所を忘れてしまったm(_ _)m。)
指導者が、板書事項を指して語る(説明する)場面もこれに似ている。
きっちりと「指し」つつ、きっちりと生徒と目を合わせ、きっちりと「語」らなければならない。
きょうのT実習生は、これが出来ていた。
感心、いや、感動に近い気持ちで眺めた。
模擬授業研修の成果にちがいない。
T実習生には、やや失礼な言い方になってしまうけれど、「黒板に向かってしゃべらない」という、たったこれだけの努力で、瞬間、瞬間に限定しての話だが、黒帯のプロ教師に見えた。
指示・発問・語りのリズムもいい。
ただし、そのリズムを重視したために、班や個人作業の達成状況の確認が、形式的に流れてしまった。

★生徒への説明の過程で、重要部分や重要単語を押さえて、一斉音読させる場面について。
(1)「音読はパワー、いつでも音読、なんでも音読」。
T実習生の指導者である研修主任・公麿Tが得意とする手法である。
それを短期間でよくマスターしている。
(2)プロの教師がその手法を取り入れている授業場面ではなく、実習生がその手法を取り入れている場面を見て、ポイント音読の学習効果の高さを再認識した。
(3)「住居」を、生徒が「ジュウイ」と読む場面があった。
欲をいえば、(ま、国語教師からすると)、ここは、正しい読み方を教えた上で、一斉音読させ、さらに「念のために」と、もう一度、一斉音読させてほしい場面だった。
いってみれば、社国連携だ。
国語科でやっている。
社会科でもやっている。
おそらく理科や技術家庭科など、他教科でもやっている可能性があるし、これはまた「話す力」や「聞く力」などについてもいえる。
複数の教科が連携&融合することによってこそ、これからの社会で求められる「言語力」は育成できる。
本校の「教科企画書」――教科で現在、取り組んでいる学習内容を、職員会議で他教科の教員に提示し、具体的な連携&融合を働きかける――のねらいはここにある。



(4)生徒が一斉音読のときの発声と、個人音読のときの発声の区別ができていない。
個人で音読の指名を受けたときは、1人で学級全体に聞こえるように読むのだという気合い、ギアチェンジが必要だ。
ギアチェンジができる生徒。
本校の課題だ。
これができるようになると、本校は変わる。
★次に課題(=代案)を列挙する。
(1)逆接ではない、中止法の「が」は、指示場面では使わない。
×「教科書には※※※が書いてあるんですが、~ページを開きましょう」→「教科書には※※※が書いてあります。~ページを開きましょう」
(2)①発問し→②個人指名し→③解答を発表させて→④「はい、正解」とやるケースで、①発問が全体のものになっていない。
③④「解答」が全体のものになっていない。
全体のものにできるか? できないか?
プロとアマの差だ。
(3)さらに、④正解の生徒に対して「がんばりの認め方」がワンパターン。
「いいですね」とほめるにしても、最低、3通り、いや、5通りはもちたい。
「すごい」だって、同じ。
ひとりひとりをほめる短い言葉を、たくさんもっていて、それを瞬間、瞬間、ポンポンと発する教師になってほしい。
ほんの一言の、ことばがけが、子どもを成長させる。
変容させる。
(4)上記の解答場面について。
達成状況がチェックできていない。
問題が3つのテーマに別れ、そのテーマごとに小問がいくつかあるという構成。
僕だったら、テーマごとに「全問正解した人?」「4問正解した人」とやって、達成状況をチェックする。(時間の関係もあるから、全テーマについて、やる必要はない。)
(5)授業はいくつかの段落で構成されている。
この「段落」の輪郭がぼんやりしている。
新しい段落に移るときに、前段階をまとめ、次段階の目標を提示し、さあ、ここから新しいステージへいくんだという意識づけ、切り替えが必要。
合わせ技として、同時に、机を整とんさせたり、姿勢を正させたり……ということもある。
授業の「段落」がぼやけると、授業はたるむ。
ここもプロとアマの差が大きく出た。
(6)作業させるとき、当然、時間を指定する。
指導者のほうから一方的に時間を指定している。
指導者が一方的に「2分」とやるのではなく、生徒自身に「自分だったら何分でできるだろう?」「先生は何分っていうんだろう?」と考えさせる――考えさせるだけでいい。この――一瞬の間が必要だ。
(7)実習生が筆順がまちがえて板書した漢字がある。
国語教師である僕は、構造的責任を感じてしまったm(_ _)m。
もちろん、プロ野球のピッチャーが9回完投するように、50分完投というわけにはいかなかったが、テレビドラマを撮るときのように、カット、カットでやると、いいドラマになるという感じの授業だった。
僕が塾経営者で、その「ドラマ」を見せられたら、即、T実習生と契約するだろう。
ただ、こういう超・優れた人材は公立学校の「教師」という職業を選んでくれないかもしれない(ノ△・。)。
ま、いずれしても、彼の今後に明るい光が射すことを祈る(^_^)v

画像=上からT実習生、教室風景、乱氏。
|
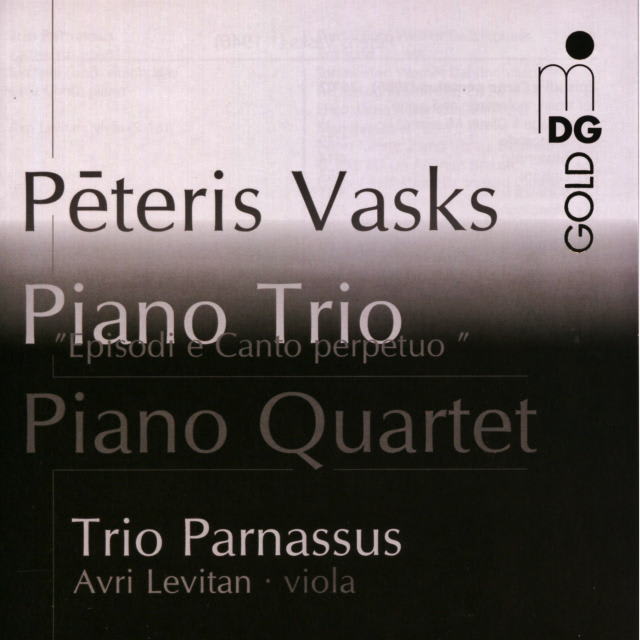


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます