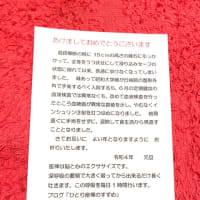禅宗の臨済宗*黄檗宗では、長く吐く呼吸に意識を集中しながら、座禅を行うようにHPで出ております。 またはじめに息を吐くことから、始めます。 私は幸いなことに、禅宗の坐禅の時の作法を、一切知りませんでした。
ここでの長く吐く呼吸は、はじめに大きく息を吸います。 生まれて初めて胡座を組んでの座禅(静功)を行なった時に、子供の頃に行ったラジオ体操での、深呼吸を思い出していました。
従って大きく息を吸ってから、出来るだけ長く息を吐いていました。 試しに全部息を吐き出してしまうと、苦しくなって後が続きません。 そこで、全部息を出し切る寸前に、軽く息を止めてまた息を大きく吸うようにしました。
息を吸う、息を吐く呼吸を繰り返し行うときには、出来るだけ自然に流れるような感覚で行う方が、長く出来ることを感得しました。
後年、息を吸うときには胸は拡がり、下腹は凹みます。 この事実から息を吸うときには下腹の臍下丹田は、気を吐くことを感得しました。 また息を吐くときには胸は元の大きさに戻り、下腹の臍下丹田も元の大きさに戻ります。 このことは息を吐く時には、下腹の臍下丹田は気を吸うのです。 この動きが、私たちの体の生理の自然な動きなのです。
臨済宗・黄檗宗の呼吸法は、はじめに息を吐き出すときに、同時に下腹からも吐き出すようにHPに記載があります。 息を吸うときには下腹も膨らませるような記載もあります。 私は自分の体験から、この呼吸法は、からふぁの生理的な動きには反していると思っております。
私たちが内在する悪いものをはじめに全て吐き出すと云う「無」の理念によって、禅宗の呼吸法が成立しておりますが、理念が先行して、体の自然の動きを無視しているようにも感じます。
禅宗の呼吸法は一般的には腹式呼吸と云っておりますが、吐く時にイメージで体の中へ吐く呼吸を、逆腹式呼吸と云います。 因みに禅宗の逆複式呼吸は、下のものを硬くするような効果があるようです。
ここでの深呼吸の要領で行う長く吐く呼吸は、イメージで吐く息を体の中へ吐き入れる呼吸(ここでの逆複式呼吸ろ云います)ですが、下のものが硬くなることはありません。