自分に折り合いをつける最期の時間。
毎度のことながら不勉強のため、名作と誉れ高い黒澤明監督の「生きる」は未見である。
それでも主演の志村喬が雪の中でブランコに乗っているシーンは知っている。静かなのに、静かだからこそ人の心に強く残る日本映画史上屈指の名場面と言えるだろう。
そんな名作を、日本人の血を持つノーベル賞作家であるカズオイシグロの脚本でリメイクしたのが本作である。
舞台は1950年代の英国。主人公は役場の市民課で課長を務めるウィリアムズ。
役場の仕事というのが全世界共通なのかは分からないが、常に忙しそうにしているものの、市民の陳情に対しては「所管が違う」とたらい回しにするか、「支障がないから預かっておく」と机上の資料の山に乗せるだけという日常が続く。
ある日、ウィリアムズは医者から末期がんにより余命がせいぜい半年であることを宣告される。そこで彼は気づく。自分は一体どういう人間になりたかったのか。そしてその思いは叶えられているのか。
自分らしく生きることなく死にたくはない。しかし、長年の役場仕事がしみついてしまっていて、どうすればいいのか分からない。彼は無断欠勤をし、知らない町で会った男性や市民課の若い女性職員・マーガレットと話して、残された人生でやるべきことを見つけ出す。
人は生まれたときから、死へのカウントダウンが始まっている。時間が限られていることが分かっているのにそれを大切にしないのは、カウントダウンの時計に明確な時間が示されていないからである。
四六時中死の影に怯えて暮らすわけにはいかない。ただ、年齢がかさんでくると人生のまとめ方を考えるようになるのは必然で、だからこそ最近は終活やエンディングノートなんていうものが流行るのである。
ウィリアムズが人生の最後に取り組んだ仕事は、いい話であるが理想論、絵空事に近いといった感想を持つかもしれない。ただ本作の肝はそこではない。
それが分かるのが、遺された市民課の同僚が「課長の遺志を継いでこれからは責任感を持って仕事をしよう」といった数か月後にはすっかり元のお役所に戻っている場面である。意外なことにそれは決して否定的に描かれていない。
そしてウィリアムズ自身も若い職員に遺した遺書の中で、「自分は特にえらいことをしたわけではない。ただ今後生き方で迷うようなことがあったときに、あの公園を見て思い出してほしい」と語っている。生きることについて人はどうあるべきなのかが重要であり、公園整備はたまたまあった一つの道具に過ぎないのである。
現代は1950年代以上に息苦しい世の中で、誰もが他人の目を気にして生きている。ただ、他人にとって自分は、会わなくなれば忘れられるような小さな存在である。最期に向き合うのは自分であり、いかに納得して人生を終えられるのかが重要なのだということを改めて噛みしめる。
(80点)
毎度のことながら不勉強のため、名作と誉れ高い黒澤明監督の「生きる」は未見である。
それでも主演の志村喬が雪の中でブランコに乗っているシーンは知っている。静かなのに、静かだからこそ人の心に強く残る日本映画史上屈指の名場面と言えるだろう。
そんな名作を、日本人の血を持つノーベル賞作家であるカズオイシグロの脚本でリメイクしたのが本作である。
舞台は1950年代の英国。主人公は役場の市民課で課長を務めるウィリアムズ。
役場の仕事というのが全世界共通なのかは分からないが、常に忙しそうにしているものの、市民の陳情に対しては「所管が違う」とたらい回しにするか、「支障がないから預かっておく」と机上の資料の山に乗せるだけという日常が続く。
ある日、ウィリアムズは医者から末期がんにより余命がせいぜい半年であることを宣告される。そこで彼は気づく。自分は一体どういう人間になりたかったのか。そしてその思いは叶えられているのか。
自分らしく生きることなく死にたくはない。しかし、長年の役場仕事がしみついてしまっていて、どうすればいいのか分からない。彼は無断欠勤をし、知らない町で会った男性や市民課の若い女性職員・マーガレットと話して、残された人生でやるべきことを見つけ出す。
人は生まれたときから、死へのカウントダウンが始まっている。時間が限られていることが分かっているのにそれを大切にしないのは、カウントダウンの時計に明確な時間が示されていないからである。
四六時中死の影に怯えて暮らすわけにはいかない。ただ、年齢がかさんでくると人生のまとめ方を考えるようになるのは必然で、だからこそ最近は終活やエンディングノートなんていうものが流行るのである。
ウィリアムズが人生の最後に取り組んだ仕事は、いい話であるが理想論、絵空事に近いといった感想を持つかもしれない。ただ本作の肝はそこではない。
それが分かるのが、遺された市民課の同僚が「課長の遺志を継いでこれからは責任感を持って仕事をしよう」といった数か月後にはすっかり元のお役所に戻っている場面である。意外なことにそれは決して否定的に描かれていない。
そしてウィリアムズ自身も若い職員に遺した遺書の中で、「自分は特にえらいことをしたわけではない。ただ今後生き方で迷うようなことがあったときに、あの公園を見て思い出してほしい」と語っている。生きることについて人はどうあるべきなのかが重要であり、公園整備はたまたまあった一つの道具に過ぎないのである。
現代は1950年代以上に息苦しい世の中で、誰もが他人の目を気にして生きている。ただ、他人にとって自分は、会わなくなれば忘れられるような小さな存在である。最期に向き合うのは自分であり、いかに納得して人生を終えられるのかが重要なのだということを改めて噛みしめる。
(80点)











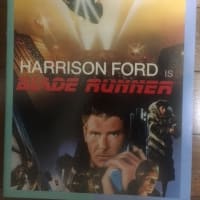







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます