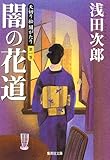僕が子どもの頃に一番最初に読んだアンパンマンってまだアンパンマンとバイキンマンしか出てなかったと思う。記憶をたどってみるとたぶん、お腹が減ってる猿がいて、それにアンパンマンがアンパン(もちろん自分の顔ね)を上げる話だったと思う。なんか池の中からネッシーみたいなのが出てくる話しだったと思うんだよなぁー。
と思って「アンパンマン 池から怪獣」で検索したら出てきた。すごいね、Google。
そうこれこれ。
僕にとってアンパンマンという存在は結構大きくて、家には富良野のアンパンマンショップで買ったポストカードが飾ってある。

こういう機会だからてらいもなく言ってしまうけど、これが僕の理想の行動なんだよね。自分の身を削ってでも、お腹を空かしている人にアンパンを上げる、ということが。
富良野のアンパンマンショップのことは前にも書いたけど、いいんだよなぁ。1階はアンパンマンショップなんだけど、2階にはやなせたかしの絵が飾ってあるの。

冬のシンとした富良野でこういうの見たらそりゃ泣いちゃうよ。
やなせたかしの作品でもちろん一番大きなものはアンパンマンだろうけど、それと同じくらい僕にとっては「手のひらを太陽に」も大きい。

上の姪っ子がまだ幼稚園の頃、幼稚園で覚えたばかりのこの曲を歌ってくれたことがある。大好きなカワイイ姪っ子がふりつきで歌う歌がカワイイのと歌詞がすごくよくって膝から崩れ落ちそうになりましたよ。
改めて全部聴いてみると、すごい歌詞だな、と思う。
-----------------------------------------
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 歌うんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから かなしいんだ
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
ミミズだって オケラだって
アメンボだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 笑うんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから うれしいんだ
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
トンボだって カエルだって
ミツバチだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから おどるんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 愛するんだ
手のひらを太陽に すかてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
スズメだって イナゴだって
カゲロウだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだ
-----------------------------------------
僕がすごいと思うのは、「生きているから」の後の歌詞の順番。
普通、子ども向けの歌であれば最初に「生きているって素晴らしい」とかそういうのがあって、その後に「たまに悲しいけどね」くらいになるんじゃないかと思う。
でもこの歌詞は、
「生きているから 歌うんだ」から始まり、かなしいんだ、笑うんだ、うれしいんだ、おどるんだ、愛するんだ、と続く。
生きていることはかなしい、と最初に言ってしまうことが子どもに対してだろうと真実を伝えようとしているところがすごいと思うんだよね。
悲しい「生きること」をアンパンマンがどれだけうれしくしてくれたことか。それはもう子どもではない(ないよな、たぶん)僕だってそうだし、現役バリバリの子どもだって同じだろう。
94歳で亡くなったけど、本当に「ありがとうございました」と言いたい。
そして出来れば、今すぐ、現役バリバリアンパンマン好きの下の姪っ子と会って「君が好きで俺も子どもの頃好きだったアンパンマンを作った人が亡くなったから、俺はいますごく淋しいんだよ」って言いたい。
と思って「アンパンマン 池から怪獣」で検索したら出てきた。すごいね、Google。
そうこれこれ。
僕にとってアンパンマンという存在は結構大きくて、家には富良野のアンパンマンショップで買ったポストカードが飾ってある。

こういう機会だからてらいもなく言ってしまうけど、これが僕の理想の行動なんだよね。自分の身を削ってでも、お腹を空かしている人にアンパンを上げる、ということが。
富良野のアンパンマンショップのことは前にも書いたけど、いいんだよなぁ。1階はアンパンマンショップなんだけど、2階にはやなせたかしの絵が飾ってあるの。

冬のシンとした富良野でこういうの見たらそりゃ泣いちゃうよ。
やなせたかしの作品でもちろん一番大きなものはアンパンマンだろうけど、それと同じくらい僕にとっては「手のひらを太陽に」も大きい。

上の姪っ子がまだ幼稚園の頃、幼稚園で覚えたばかりのこの曲を歌ってくれたことがある。大好きなカワイイ姪っ子がふりつきで歌う歌がカワイイのと歌詞がすごくよくって膝から崩れ落ちそうになりましたよ。
改めて全部聴いてみると、すごい歌詞だな、と思う。
-----------------------------------------
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 歌うんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから かなしいんだ
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
ミミズだって オケラだって
アメンボだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 笑うんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから うれしいんだ
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
トンボだって カエルだって
ミツバチだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから おどるんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 愛するんだ
手のひらを太陽に すかてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
スズメだって イナゴだって
カゲロウだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだ
-----------------------------------------
僕がすごいと思うのは、「生きているから」の後の歌詞の順番。
普通、子ども向けの歌であれば最初に「生きているって素晴らしい」とかそういうのがあって、その後に「たまに悲しいけどね」くらいになるんじゃないかと思う。
でもこの歌詞は、
「生きているから 歌うんだ」から始まり、かなしいんだ、笑うんだ、うれしいんだ、おどるんだ、愛するんだ、と続く。
生きていることはかなしい、と最初に言ってしまうことが子どもに対してだろうと真実を伝えようとしているところがすごいと思うんだよね。
悲しい「生きること」をアンパンマンがどれだけうれしくしてくれたことか。それはもう子どもではない(ないよな、たぶん)僕だってそうだし、現役バリバリの子どもだって同じだろう。
94歳で亡くなったけど、本当に「ありがとうございました」と言いたい。
そして出来れば、今すぐ、現役バリバリアンパンマン好きの下の姪っ子と会って「君が好きで俺も子どもの頃好きだったアンパンマンを作った人が亡くなったから、俺はいますごく淋しいんだよ」って言いたい。