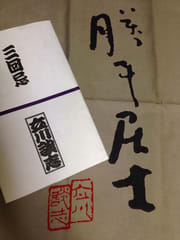手塚治虫の「火の鳥」 は全巻持っている。小学生の頃、図書室に置いてあって読んだ覚えがあるし、僕らの世代だと「鳳凰編」がアニメ映画にもなったよね。
は全巻持っている。小学生の頃、図書室に置いてあって読んだ覚えがあるし、僕らの世代だと「鳳凰編」がアニメ映画にもなったよね。
大人になってから角川文庫版で出たので古本屋で見つけるとついつい買ってしまって結局、全巻揃ってしまった。
何年かに一度、ふと思い出して読み返すとやっぱり全巻読んでしまう。
すごい漫画だなぁと思いますね。
どんだけすごいかと言うと、2巻目の「未来編」は西暦3404年に始まります。そこで一度、地球上の生物全部が滅びて50億年くらい経ってまた生命が誕生する、という話なんです。それをなんとただ1巻でやってるのよ。すごいねぇ。今の時代だったらこれだけで50巻くらいになってしまうと思う。
更にこのラストシーンで1巻目の黎明編の冒頭につながるようになってるの。
つまり、1巻目である「黎明編」は2巻の「未来編」の後に読んでも先に読んでもいいし、なんなら最終巻である「太陽編」の後に「未来編」を読んでもいい。この時間軸の感じは本当に素晴らしい。
それで最近、アプリで「週刊手塚治虫」というのがあって、毎週少しずつ手塚治虫の漫画が無料配信される。ブラックジャックの1話とかね。そこで「火の鳥望郷篇」の1編は配信されてたんだけど、読んでて「あれ?」と思った。もちろん望郷篇は好きだし何度も読んでる、単行本も持ってるんだけど「こんなキャラクターいたっけ?」と思った。
そのキャラクターというのはノルヴァという宇宙人。雌雄同体の宇宙人。話の筋も少しだけ違っていて不思議に思ったのでつい望郷編を電子書籍で購入してしまった。
調べてみると望郷篇は雑誌掲載版、朝日ソノラマ版・講談社版、角川書店版で加筆修正が多々ある話らしい。へーそうなんだ。何度も読んだ「望郷篇」だけど違うキャラクターが一人出てくるだけで結構味わいが違くて楽しめた。ノルヴァがいたほうが更に輪廻転生な感じが強く出てきていていいですね。ズダーバンが死ぬ理由もなるほど、と思うし。
しかしさぁ、こんな漫画思いつく手塚治虫ってほんとすごいよね。全体的な流れもすごいし細部もそれぞれすごい。望郷篇の無生物の惑星とか改めて読んでも「怖いな」と思います。
もうこれ日本人の課題図書でしょ。
メインどころは大体好き(太陽編、宇宙編、望郷篇、鳳凰編、、)だし、短編~中編と言える回も好きです。中でもすごいなぁと思うのは「羽衣編」ね。これは全コマすべて舞台劇のような形で書かれている。つまり固定カメラのような印象。すごいよねぇ、なんでこんなの思いつくんだろう?
大人になってから角川文庫版で出たので古本屋で見つけるとついつい買ってしまって結局、全巻揃ってしまった。
何年かに一度、ふと思い出して読み返すとやっぱり全巻読んでしまう。
すごい漫画だなぁと思いますね。
どんだけすごいかと言うと、2巻目の「未来編」は西暦3404年に始まります。そこで一度、地球上の生物全部が滅びて50億年くらい経ってまた生命が誕生する、という話なんです。それをなんとただ1巻でやってるのよ。すごいねぇ。今の時代だったらこれだけで50巻くらいになってしまうと思う。
更にこのラストシーンで1巻目の黎明編の冒頭につながるようになってるの。
つまり、1巻目である「黎明編」は2巻の「未来編」の後に読んでも先に読んでもいいし、なんなら最終巻である「太陽編」の後に「未来編」を読んでもいい。この時間軸の感じは本当に素晴らしい。
それで最近、アプリで「週刊手塚治虫」というのがあって、毎週少しずつ手塚治虫の漫画が無料配信される。ブラックジャックの1話とかね。そこで「火の鳥望郷篇」の1編は配信されてたんだけど、読んでて「あれ?」と思った。もちろん望郷篇は好きだし何度も読んでる、単行本も持ってるんだけど「こんなキャラクターいたっけ?」と思った。
そのキャラクターというのはノルヴァという宇宙人。雌雄同体の宇宙人。話の筋も少しだけ違っていて不思議に思ったのでつい望郷編を電子書籍で購入してしまった。
調べてみると望郷篇は雑誌掲載版、朝日ソノラマ版・講談社版、角川書店版で加筆修正が多々ある話らしい。へーそうなんだ。何度も読んだ「望郷篇」だけど違うキャラクターが一人出てくるだけで結構味わいが違くて楽しめた。ノルヴァがいたほうが更に輪廻転生な感じが強く出てきていていいですね。ズダーバンが死ぬ理由もなるほど、と思うし。
しかしさぁ、こんな漫画思いつく手塚治虫ってほんとすごいよね。全体的な流れもすごいし細部もそれぞれすごい。望郷篇の無生物の惑星とか改めて読んでも「怖いな」と思います。
もうこれ日本人の課題図書でしょ。
メインどころは大体好き(太陽編、宇宙編、望郷篇、鳳凰編、、)だし、短編~中編と言える回も好きです。中でもすごいなぁと思うのは「羽衣編」ね。これは全コマすべて舞台劇のような形で書かれている。つまり固定カメラのような印象。すごいよねぇ、なんでこんなの思いつくんだろう?