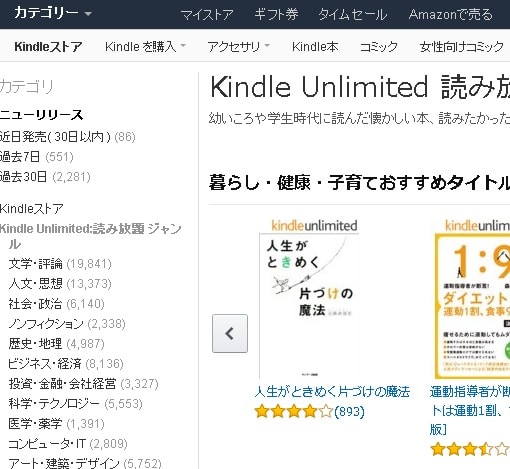塩野七生の「ローマ人の物語」はたいそう面白く全部読んだ。
僕は文庫版で読んでいたんだけど、毎年、9月位に最新刊が発売されて「おお、もうその季節かー」と思って文庫本を買ってローマの話を読むのはとても楽しいことだった。
「ローマ人の物語」も全部読み終わり、その後「ローマ亡き後の地中海世界」が発売され、そのあとに「十字軍物語」が発売された。


十字軍物語〈1〉
僕は「まぁ、文庫本で読もうかなー」と思っていたんだけど、これがまたなかなか出ないんですよ。調べたら「十字軍物語」が出たのって2010年。もう丸6年経とうとしているのにね。まぁ、そういうところは色々事情があるだろうから文句を言っても仕方がない。
ということで読み始めてしまいました。
あのねぇ、、、おもしろいね!!
僕は学校で世界史とかまったくやってこなかった人間なので十字軍についてもほとんど知識がない。そういう人間からしてみるとまったく新しい話でドキドキしますよ。
「カノッサの屈辱」(言葉だけは知ってる)というのが契機になったんだねぇ。。
すごーく大雑把にまとめてしまうと要はキリスト教とイスラム教の戦いなわけでそれって現代社会でも終わってないといえば終わってない。
カノッサの屈辱は西暦1077年の話で約900年前の話。うーむ、歴史というのは興味深いね。
まだ1巻だけだから、始まりの始まりだけなんだけど、こういうの読んでると例えば三国志における反董卓連合の成り立ちとちょっと似てるな、と思ったりする。
歴史、というか結局のところ人間のやることってここ2,000年くらい変わってないのかも知れないね。
ローマ時代の話もずいぶん「人名」で苦労したけど、今回も人名では苦労している。特にイスラム側はなかなか耳慣れない。スルタン・アルスラン、ヤギ・シヤン、ケルボガ、アフメド・イヴン・メルワン、、などなど。
ということでノートにメモしながら読んでる。
更に中東の地理ってのもなかなか難しい。(そうだそうだ、学生時代、地理も苦手だったんだ) レバノン、シリア、イスラエルあたりの地名がね~、なかなかわからないですよ。
ということでテーブルの上をこんな風にして読んでます。

受験生みたいだ(笑)
僕は文庫版で読んでいたんだけど、毎年、9月位に最新刊が発売されて「おお、もうその季節かー」と思って文庫本を買ってローマの話を読むのはとても楽しいことだった。
「ローマ人の物語」も全部読み終わり、その後「ローマ亡き後の地中海世界」が発売され、そのあとに「十字軍物語」が発売された。

十字軍物語〈1〉
僕は「まぁ、文庫本で読もうかなー」と思っていたんだけど、これがまたなかなか出ないんですよ。調べたら「十字軍物語」が出たのって2010年。もう丸6年経とうとしているのにね。まぁ、そういうところは色々事情があるだろうから文句を言っても仕方がない。
ということで読み始めてしまいました。
あのねぇ、、、おもしろいね!!
僕は学校で世界史とかまったくやってこなかった人間なので十字軍についてもほとんど知識がない。そういう人間からしてみるとまったく新しい話でドキドキしますよ。
「カノッサの屈辱」(言葉だけは知ってる)というのが契機になったんだねぇ。。
すごーく大雑把にまとめてしまうと要はキリスト教とイスラム教の戦いなわけでそれって現代社会でも終わってないといえば終わってない。
カノッサの屈辱は西暦1077年の話で約900年前の話。うーむ、歴史というのは興味深いね。
まだ1巻だけだから、始まりの始まりだけなんだけど、こういうの読んでると例えば三国志における反董卓連合の成り立ちとちょっと似てるな、と思ったりする。
歴史、というか結局のところ人間のやることってここ2,000年くらい変わってないのかも知れないね。
ローマ時代の話もずいぶん「人名」で苦労したけど、今回も人名では苦労している。特にイスラム側はなかなか耳慣れない。スルタン・アルスラン、ヤギ・シヤン、ケルボガ、アフメド・イヴン・メルワン、、などなど。
ということでノートにメモしながら読んでる。
更に中東の地理ってのもなかなか難しい。(そうだそうだ、学生時代、地理も苦手だったんだ) レバノン、シリア、イスラエルあたりの地名がね~、なかなかわからないですよ。
ということでテーブルの上をこんな風にして読んでます。

受験生みたいだ(笑)