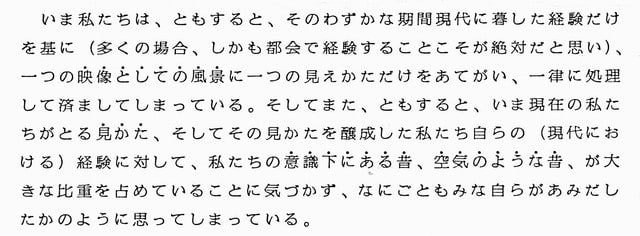
水田の風景・・・・ものの見えかた・・・・ 1982年度「筑波通信 №3」
〇水田風景、それは驚異的である
筑波の近在では、ちょうど四月末から五月初めへかけての連休の前後が田植えの季節である。(茨城に隣りあう利根川の向う側の埼玉県では五月九日でもやっと田をおこしているだけだった。) いま、水の張られた田んぼが、少し大げさに言えば、はてしなく延々と続いている。その昔、私の小さかったころ、田植えどきには、これも大げさに言えば、田んぼという田んぼは人で埋まっていた。しかしいまは、田植え機という機械がそのおかしげな手を振りまわして、あっという間に植えてしまう。それはそれなりに見ていて面白い。(人の手によっていたとき、苗は実にみごとな直線をなして植えられていたものだが、機械によるようになってからというものは、ぎくしゃくした平行線が描かれるようになってきた。ぎくしゃくというのは、すなわち機械の走った軌跡なのである。こんなに不ぞろいの線でも構わないのなら、人手にたよっていたときの、糸を張ってまで一直線に植えようとした、あの努力はいったい何であったのかと思わずにいられない。)こういう田植えのやりかたのせいで、見まわしても、人はあちらに二人、こちらに三人といった具合にほんとにまばらにしか見あたらない。昔の活気あふれる田植えどきを見知っているものの目には、まるでうそのような、なにか気のぬけた、妙な言いかたかもしれないけれども「これで大丈夫なのかね」という不安感さえわいてくる、そんな光景である。中国の畑作地帯で見かけた、これも大げさに言えば、地面が見えなくなるほど人が群がりながら土地を耕していた姿、これで農業の機械化をしたときこの人たちはどこにゆきつくのかと考えた、そんな光景が対比的に私の頭をよぎっては消えた。とにかくそういうわけで、この人のいない水平面の連続は、なお一層広々と見える。
いつもこの水の張られたときの水田を見て思うことなのだが(というのも、他の季節、たとえば刈入れどきにはそのように見えないからなのだが)およそ人間のやってきたことのなかでなにが一番驚異的といってこの水田開発ぐらいすごいことはないのではないかと思う。
この水平面これは天然自然の海原や湖水ではない、全くの人工の水平面なのだ。それもただの水平面ではない。ただの水平面なら、大きな穴でも掘って水をためればすぐできる。しかし、水田のそれはそんななま易しいものではない。水平面の連続と先に書いたけれども、それは決して一つの水平面なのではなく、言わば無数に近い異なった水平面で構成されているのである。それぞれの水平面が一定の水深を保ちつつ、水上から水下へと微妙な段差で隣りあう。水は、幅広い水面を成しながら、わずかな落差のひな段形の滝を落ちつつ時間をかけて流れてゆく。その落差なのだが千分のー、つまり千メートル行って1メートル落ちるという程度の場合などざらにある。建物などの排水の場合のそれは、どんなにゆるくても百五十分の一程度なのだから、水田のそれがいかにゆるいものなのか分るだろう。しかも、水田をゆっくりと流れ下ってきた水の末端は、いまでこそ排水ポンプがあるからどうにでもなるけれども、そういう便利なもののない時代では、自然の流下で河川に戻らなければならないのだ。
つまり、末端は河川より少しでも(しかも河川の増水で逆流しない程度に)高くなければならない。大規模住宅団地の土地造成で排水計画をたてたところどうやっても末端で排水ポンプで吸み上げることになってしまうのに、ふと隣りあう水田はと見てみれば、そこでは平然と自然流下にまかせてあり、あらためてその水田造成技術の卓越さに舌をまいたという話をきいたことがあるが、ことほどさようにこれはそんなに簡単なことではないのである。自然の流下にまかせたまま延々と続く水田風景は、だから、ただ単にのどかな水田風景として見て済ましてしまうにはまことにおそれ多い、人間が成した一大偉業なのである。驚異的なのである。
もっとも、いま私が目にしているのは、もともと自然流下にたよって開かれたものを、農業の近代化により改善した、機械による給排水に切りかえた水田である。田んぼの水の源になる河川は深く掘り下げられ排水を容易にし(それによりずぶずぶの深田も適度になる)その代り給水はポンプで吸み上げることになる。そして、河川は掘り下げられたのだから全長の高低差はつじつまが合わなくなり、ところどころで排水ポンプの厄介にならざるを得なくなる。こういった近代化にたよれば、いままでは到底考え及びもしなかったようなところにも水田をつくることが可能になり、だから丘のてっぺんに田んぼがあっても別にそう珍らしくもないし、山林の一部が伐採されて田んぼが突如できていたりする。昔からの田んぼを知っているものの目には、こういう風景は異和感を伴って映ってくる。しかしその異和感は、単に私自身のなかにできあがってしまっていた田んぼというものについてのイメージと比べてのそれだけではなく、よくまあそこまで割りきって機械にたよれるものだ、機械が動かなくなったら(たとえば台風などで停電でもしたら)どうするのだろう、そういうような思いを抱かせるような、機械に対する絶大な信頼に対しての異和感でもある。
〇水田風景、その成りたちの背景
このような機械力にたよる近代農法が水田の拡大・整備をそれなりにすすめたことは確かではあるけれども、しかし、その基になっていた、普通私たちが「田んぼ」ということばでイメージする広々とした水田地帯の風景自体もまた、その成立の時期はそんなに旧いものなのではないのである。たとえば、関東平野の中央部、利根川の南(埼玉県の北部にあたるが)その一帯に見ごとに拡がる一面の水田風景:夏の午後ともなればむんむんとした草いきれに充ちじとっと汗ばんでくる、そして収穫期ともなればその夏の姿がまるでうそのように軽快な一面の黄金色の大地になる、その背後の遠景に、それぞれの季節それぞれの風情をかもしだしながら村々の森がここそこにぽっかりと浮いている、こういった典型的とも言える農村風景:これは高々三百年、徳川の世になってから徐々に開かれその基ができあがってきたのである。水を引き、その自然流下にまかせた幡広くそして延々と続く水田の開発という一大農業土木工事が営々として行なわれてきたのである。しかも、かくも見ごとになったのは:全面的に埋めつくされるようになったのは、むしろ最近ということばの範囲に入る時期の話だと見てよく、明治期にはまだあちこちに手のつけられない湿地帯:池沼が残っていたようである。初期の機械化はそういった湿地の解消すなわち排水に向けられたのである。各地の排水機場のそばに行くと、いかにその地の農事が水とのたたかいであったかなどということを綿々と書き記した石碑がよく建てられているけれども、それはある施設が完成したことを単に記し残しておくという以上の思いがこめられているはずなのだ。(これは、明治以来数度にわたり編集しなおされてきた国土地理院の地図を、その年代順に見比べてみると極めてよく知ることができる。
(こういった見かたでは、日本図誌体系など種々の地理学の成果があるが、残念ながら、地理学の範囲外では問題にされないようだ。地理は地理学のためにのみあるのだろうか。)
つまり、いま私たちが目にする水田風景が成りたつ少し前に、あちこちに池沼を残したままの状態、何度もしつこくその水田化をはかりつつも一進一退を余儀なくさせられていた時期が、しばらくの間続いたのである。それを、単に技術がなかったからだと見るのは簡単な話である。技術というのはそうやたらに天から降ってくるものではない。本来的に技術というものは、間題の解決のためにあみだされる。問題意識の高まりが新らしい技術を生みだす下地となる。だから、むしろこの時期は、それなりの問題はかかえていても、解決のための技術が思いつかない時期だったと見るのが素直なのだ。彼らには、排水をすればよいのだということは分っていても、水は高きから低きへ流れるといういかんともしがたい原理を大々的にくつがえすやりかたが見つけられなかっただけなのだ。だからこそ、排水ポンプという機械の導入とともに、問題意識の高まりをおさえていたせきが切れ、あっという間に低地水田化が進んだのである。
いま私たちは、とかく、技術というものがあって、それをいかに利用するかという発想をとりがちなのだが、そのやりかたで全てを律してしまうのは、当然のことながらまちがいである。技術の意味をほんとに知ろうとするならば、そのときどきの問題とその意識がどう高まり、それがどう解決されてきたか、その過程を見なければならないだろう。技術の利用というのも、本来、それを利用する側にある解決すべき問題が確として存在していて初めて可能なのだ。(そうであるにも拘らず、現在では、多くの場合それが逆転している。)
もしも、いまの私たちが更地(手のつけられていない土地)の関東平野を目の前にして、そこに水田を開こうとしたらどうするだろうか。おそらく、私たちはもう実に色々な水田つくりについての知識を持っているから、私たちはそれらの知識を総動員して、低湿地の解消:乾地化から手をつける、あるいは手はつけなくてもそのことを念頭において事をすすめるだろう。(というのは、更地としての関東平野には、もともと自然現象としての湿地・低地が各所に散在しているのである。) つまり、平野全体を総体的に見まわした上で、低・高のつじつまを考慮に入れ、低地から高地へと攻め上ってゆく発想法を採るだろう。なぜなら、最低部は東京湾の海面に他ならず、そこを基準面にして上へ上へと考えてゆくのが合理的というものだ。

しかし、現実にこの平野で行なわれてきたことは、全くこれとは逆であった。高地から低地へと攻めてきたのである。しかも、高地から低地、そして更に次の低地へと、順次そのつどその局面での高低のつじつまだけを考えて攻めてきたから、低地がより低地になればなるほどつじつま合わせが苦しくなるのは明らかで、最終的には既存の自然現象として在った湿地帯に行きつき、そこで足踏みしてしまうか、あるいは、その自然の湿地帯を、更に輪をかけた形で拡げ、一層始末におえない湿地帯にしてしまったのである。江戸期末、明冶の初め、多分平野はこういう状態であったと思って、まずまちがいない。当時までの考えつくされた技術(それは、高地から低地へと攻め下るに際し順次獲得されてきたのだが)では、そこまでだったのである。しかし、そこで手をこまねいていたわけではないことは先にも書いたとおりであり、一進一退の状況つまり、それまでの比較的順調な水田面積の増加がしばらく足踏み状態となる状況が、初期的な機械の導入がはかられるまでのしばらくの間続くのである。
〇なにが合理的か
先に述べたいまの私たちならするであろうやりかたと比べたら、この現実にやられてきたことは、極めて非合理的である。しかし、それをして合理的でないと見なすのは容易なことだ。だが、そう思うことは、むしろ根本的に誤まりだろう。それは結果論にすぎない。結果を見てどうこう言うことぐらい楽なことはない。
現実にこの平野の開拓に係わってきた人々は合理的ではなかったのだろうか。「合理的」なることを、いまの私たちならするであろうことで全てであると見るならば、確かに彼らはそうではない。しかし、私たちにとって「合理」であると見なされているやりくちというものは、あくまでもいまの私たちにとってしか意味がないということは忘れるべきではないだろう。彼らもまた、彼らにとって合理的なやりくちをしてきたという意味でも合理的であったのだし、ことによると、ことの本質的な意味では、いまの私たちよりもずっと合理的であったのかかもしれないのだ。彼らは、いま私たちが機械にたよって水の流れのあの単純な原理:高きから低きに流れる:にさからってまでして(しかも自然の良田を一方で休耕田と称して荒地に変えながら)開田をしている様を見たら、なんという無茶な、非合理な、と言うにちがいない。
・・・・研究者は近代合理主義と経済合理主義を強く押し出して、解釈しがちになる。しかし河川開発は、時に思わぬ猛威をふるう自然現象に対する人間の挑戦である。とくに江戸時代初期の自然河川に相対したとき、いわゆる近代科学を足場とする近代合理主義で理解できない部分が非常に多い。・・・・(小出博「利根川と淀川」より)
では、関東平野の開田で、何故低地から高地へと上るのではなく、実際には高地から低地へと下りてくるやりかたがとられたのか。おそらくその理由は簡単な話なのだ。人は、そのとき抱いている所期の目的を達成するために、そのときの状況において最もよき結果を生むだろうと予測され、しかもそのときの状況で最も彼らにとって容易なやりかたをとろうとするものだからである。
この原理は、いまの私たちだって変りあるまい。稲を栽培することに拠って生きることを見つけた人たちがいたとする(実際、縄文時代の後期にそういう人たちがいたわけだ)。彼らは初めに稲作に適する土地とはかくかくしかじかなりという研究をしつくし、それによりしかるべく土地を造成し、しかる後いよいよ稲の栽培にうつる、などということをやるだろうか。いまの私たちなら、おそらくそうするかもしれないが、彼らはそんな気長なことはしなかった。もっと手っとり早く、既存の自然現象としての地形のなかで適当な所を探しだした。深すぎもせず浅すぎもせず、洪水ですぐ洗われることもない、ほんのたまり水程度の湿地帯、つまり先号のあとがきで記した「ぬた」「のた」「やち」「うだ」などと呼ばれるようなちょっとしたわき水や小川のそば、そういうほんのちょっとした山あいのねこの額ほどの谷状の所をそのまま(手も加えずに)利用することから始まったのである。そういう所を探しまわっては、住める所に人は定住しだしたのだ。何故なら、彼らにとっての所期の目的は、そういう土地で十分に達せられるからである。そしてそこから、実にそういう場所から、人々の開田という壮大なドラマは始まったのである。人々が定着し、人口も増え、従って拠るべき水田も増やさなければならなくなる。所期の目的のなかみが変ってくる。人々はそこで初めて、彼らがかつて自然地形のなかに探し求めたと同じような状況の土地を「造りだす」ことを覚え(そのための技術を覚え)かつての自然田に続く下流へと、徐々に平野へ向けて下りだすのである。自然利水の段階から、次々に利水の技術が、人々の目的の変化に応じて生みだされる段階へと変っていったわけである。(これは何も関東平野についてだけ言えるのではなく、およそどこの平野・盆地においても同様の経過を見ることができる。)
つまり、人々が最初に定着したのは、平野をとりかこむ山々のへりの部分からだったということだ。それが、人々にとって極めて合理的な営為だったのである。だから、古代から中世にかけての関東平野では、いまでこそ全体万遍なく手がつけられ人々は最低地部に集中しているけれども、いまの県名で言うと埼玉西部、群馬、栃木にかけてが中心になり栄えたのである。これらいま書いてきたようなことは、(遺跡)地図上に、初期の稲作依存に拠った人々の住居・村跡、水田の条里制遺構、古墳、国府の所在地、東山道の道すじ(道とは先ずもって人が住む所をつなぐ。まして支配を企てたものがつくる道:官道は、そのとき最も栄えている所を通ることに意味がある)、有力荘園の所在、古代豪族の拠点とした地、あるいは中・近世の村の位置、等々の分布性向を、時代をおって確かめることによって、自ずと明らかになることだろう。
(関東北辺の古代文化などは、普通、学校の歴史ではあまり教わらないだろう。飛鳥・大和がクローズアップされる。ところでこの飛鳥の地もまた、この関東の辺地の古代の中心と同じような、言わば山あいのねこの額のような所なのである。大和平野のまんなかではない。)

遺構・遺跡、それは人間がなにかを考え、なにかをやった、その名残りだからである。けれども私は、そういったことについては門外漢である。そこで、こうした平野開発の常道について述べた専門家の解説を掲げておく。この人の著書は大変勉強になった。
・・・・(鎌倉時代、埼玉平野の)古利根川筋、中川筋の湖沼・沼沢地帯に大規模な開発工事を行なうことは、たとえ鎌倉幕府の強い権力を背景とし、関東武士団が・・・・多くの農民層の労役を駆使したとしても、技術的に不可能であったと思われる。技術的にという意味は、当時この低地を乱流する利根川、渡良瀬川、荒川を治めることがむずかしいため、開発ができなかったということではない。この考えはいかにももっともらしく、良識的である。しかしわが国水田の開発経過をみると、治水が利水に先行して行なわれた場合はほとんどなく、治水を前提としなければ水田開発ができない場所はごく限られ、河畔の局部にわずかに分布するにすぎない。農民による水田開発がある程度すすんだ段階で、はじめて治水が取り上げられ、生産の場の安定と整備の役割を巣すというのが普通であって、これが沖積地低地開発の常道であった。この意味で、利水は常に治水に先行する。従ってこの場合、問題は利水(水田化)のむずかしさにあったといわなくてはならない。湖沼・沼沢の開発は、技術的に非常にむずかしい多くの間題をもっている。まず湖沼・沼沢の排水をどうするか、排水に必然的に伴う用水の確保は可能か、ということは開発に当って直面する重要な課題である。その解決は、当時まだ経験的に知られていなかっただろうし、ことに水田農業ですすんだ技術をもつ西南日本で(も、そういう場面はほとんどないから)、ほとんど経験のないことである。従って広大な湖沼・沼沢に(対し、その水田化へ向けて)深い関心をもったとしてもただちに大開発をすすめることはできなかったにちがいない。湖沼・沼沢を取り囲む自然堤防に居を構え、地先を部分的に排水して低湿田とし、可能な場合にかき上げの囲堤を設け、不安定な水田を開くことがせいいっぱいで、まず農民の発想でこれが行なわれたのではないだろうか。・・ 太字著者 (小出博「利根川と淀川」より)
〇風景の見えかた
都会の雑踏をのがれ、あるいは日々の生活をはなれ、言わゆる田舎に出向いたとき(いま都会型の生活をしている私たちを想定しているわけだが)私たちの目の前に拡がる山々や川や湖沼や森や林、そして田園風景。考えてみると、最近私たちは、そういった風景を単に映像としての風景:景観としてしか見ないようになっているのではないか。いまここで書いてきたような見かた、つまりそののどかな風景、すばらしい風景の背景とその奥行の深さについて思いをめぐらすような見かたを、私たちの大部分はしなくなってしまったのだ。
人と大地の係わりだとか風土と人間の関係などについては確かにあちこちで語られてはいるけれどもその多くは観念的でリアリティを欠いている。水田と言った瞬間から既に稲を植えるために仕立てた土地のことというが如き辞書的説明が頭に描かれ、それは実は人間がつくったのだという事実についての思いはついぞ頭にひらめかない。そこで見えていることは、まさに映像としての風景にすぎず、それと人間一般とをただつきあわせたところで、人と大地、風土と人間の係わりが分る道理もないのにも拘らず、相変らずそういう見かたが横行している。
稲を植えるために「仕立てた」のは、その稲で、稲に拠ってその土地で生きなければならなかった(一般的な意味のではなく特定の)人々であったという理解が見失なわれてしまったのである。私にとってもこのことが身にしみて分ってきたのは、というより分るいとぐちが見えてきたのは筑波に移り住んで実際にそういう風景の一画に身をおくようになってからのことだった。おそすぎたなあと何度思ったかしれない。いままで何度も私は、いまの小・中・高の学校教育で教えられている地理や歴史の教えかたに対して文句を連ねてきたけれども、その文句のなかには、そこにおいて単に「知識」を並べたてるのではなくそれらの「見かた」について触れられていさえすれば、もつと早く気づいたのに、という私の愚痴が半分以上含まれている。
もしも私たち全般に、一つの風景を単に映像としての風景としてのみ見て終らすのではなく(まして、それを一つの思いいれの見かただけで見て済ますのではなく)その背景にまで思いを至らしめて見ようとする習慣があたりまえになっていたならば、たとえば畑や山林一つをとってみても、単にそれを〇〇が栽培されている畑、〇〇の植わっている林、として扱い済ますのではなく、これはあの村の、そしてこれはこの村の人たちが営んでいる畑でありまた山林である、あるいは、それがいまのような形になるまでにはかくかくしかじかの過程があったにちがいない、といったまさに人と風土との係わりが目に見えてくるはずなのだ。そして、そうであれば、仮にそこを貫いて新しい道を一本通さなければならない場面にぶつかったときでも、いい加減なことはできないという正当な「ためらい」が心にわき上ってくるはずなのである。
町村合併の促進がまた言われだしている。しかし、村の拡がり、村塊、あるいは村という単位:まとまりは、決していま言う行政区画:行政単位としてあったのではなく、むしろ、もともとは村が先にあった。村をなして入々はこの太地の上に住んでいた。その単位を行政の巣位として利用したのである。いったいだれが行政のために(支配されて)生きることを、はじめから望むだろう。村と村の間の合議というのはしばしばあったろうが、自らすすんで合併しようとすることは、おそらくなかったろう。合併の発想は、支配し易さ、つまり行政の発想なのである。行政にとって掌握し易くなる合併は、逆に人々にとっては村を掌握し難くする。
この連休、憲法記念日、それほどよい天気ではなかったが、久しぶりに自転車で散歩に出た。かねてから土浦市の自然保護団体がその保存を叫んでいる宍塚(ししづか)大池を見に行ってみようと思いたったのである。いま私が住んでいるあたり一帯は、全般的に霞ヶ浦に続く低地なのであるけれども、そのなかにもあちこちに小高い丘陵が谷地(やち)を刻みこみながら点在している。そういう丘陵地のなかに、谷地に水のたまった池が数多くある。宍塚大池というのはその一つなのだ。
その池は私の住んでいる所から東に四・五km行ったあたり、わが桜村と土浦市との境にある。舗装された道で近道をするのも面白くないからわざわざ集落の点在する丘陵地をぬって自転車を走らせた。微妙にひだが入りくんでいるから、道は激しく上ったり下ったりする。それとともに林があり、田んぼがあり、池がある、また林があり畑が拡がる、といった風景が次々に展開する。そんな山林のなか、草でおおわれて辛うじて道らしいとしか思えない言わばあぜ道風な道が交又していて、はてどちらに行こうか、まあいい、いずれにしろ大したまちがいはないだろう、などと思って自転車を草を分けてこぎだそうとする。と、その草のかげに、なんと道しるべ、石の道しるべが立っている。宍塚へ〇丁、古来〇丁、古瀬へ〇丁、上の室へ〇丁。因みに古来は「ふるく」、吉瀬は「きせ」、上の室は「うえのむろ」と読む(古来、吉瀬は土浦から学園都市へ通ずるバスの停留所名にあるのだが、初めてそのバスに乗って「ふるく」「きせ」と告げられても、どういう字か分らなかった覚えがある)。これはどれも集落の名前である。明治の町村合併以前は村の名前であった。
いま私が目の前にしている道が草ぼうぼうで右も左も分らないからこんな道しるべが建てられたわけではない。そうではなく、いま私の目の前にある道は、ほんのついさっきまで、これらの集落をつないでいた主要な道だったのだ。ここを村の人たちは歩いたのだ。その人たちのための道案内。私にはあらためて、この丘陵地のこの地方でもつ意味、集落の立地、道の意味‥‥こういったことが実感をもって見えてきた。自動車の都合で低地のまん中を走るようになってしまった現代の道の上を走るバスの中からこの丘陵をながめていて、いったいどれだけの人が、あの丘の上をつないでかつて主要道が走っていたなどと思うだろうか。大抵の場合、いまも昔も変りなく、道はここを走っていたと思うだろうし、またそう思ってあたりまえなのだ。
道しるべに従ってかなり無理して(というのも道はもう道の態をなしてないから)走らせると、右手下にほんとに静まりかえった水面が見えてきた。かなり大きい。まちがいなく目ざす池はこれだ。まわりをかなり濃く繁った森にとり囲まれ、木々の枝が水面にかぶさっている。季節には渡り鳥が安心して群れているというのももっともだ。つり人が数人糸をたれている。岸辺のあちらこちらによしが群生して枯れた幹をつきだしている。私は東京の井の頭(いのかしら)公園、しかも子どものころのそれを思いだした。井の頭の池もこんな感じだった。その池から小さな川:神田(かんだ)川が台地の間の低地を蛇行しながらゆっくりと流れ、低地一面が(いまは川もコンクリートのかたまりとなってまっすぐになり見るかげもないが)水田であった。この池も同じ、谷地がより低地へと続き、その頭の部分にあるのがこの池だ。わき水でもあるのだろう。これはそのまま「公園」になる。
しかし、そう思った次の瞬間、そう思った私自身のなかに、ある種の異和感とでも言うべき思いがわいてきた。「公園」?「公園」って何だ。私に「そのまま公園になる」と思わせたわせたのは、いったい何か。いったいこの近在にながく住んでいた人たちも「これは公園になる」と思うだろうか。彼らはそうは思うまい。「しょうもない」沼地、むしろそんな風に見るのではないか、見てきたのではないか。私が「これは公園になる」と思ったのは、こういう景観:映像としての風景は「公園」のものだという見かたが、既にてんからあたりまえのものとして私のなかに在ったからなのではないか。一つの映像は、一つの見えかたでしか見えない、そう勝手に私は思いこんでいたのだ。これはまちがいだ。
一つの映像としての風景が、見る人の見かたにより別の見えかたになる、こんなあたりまえなことはないではないか。この池を「しょうもない」沼地と見る(だろう)近在のいまの農民の見かたも、それはいまの見かたなのであって、古代の農民なら逆に、この沼地をもってこいの田だと(まわりが田になる所だと)見たかもしれないのである。それを、一つの見かたで一律に処理することがどんなに危険なことか。私たち、都会に育った私たちは、これまでどんなにまちがった見えかたを押しつけてきたことか。
この池を見ていて私の頭のなかに去来したこと、思い至ったこと、それは久しぶりに私にとって衝撃的なできごとであった。
帰りはバス道路を行こうと思い、往路と逆に谷地沿いに走りだした。谷地沿いに、これはもういまの通常の水田では目にすることも少なくった昔ながらの不整形の田が、見るからにほそぼそと(そう見るのも通常の田を見慣れているからだが)耕されていた。傍に苗代があり、田植えはこれからである。ふと見ると、苗代の端に向いあわせに二本の太めの竹がつきさしてあり、その先から何か黒い物がぶら下っている。遠くから見ると鳥のような形にも見える。何だろうか。近くに寄ってみた。鳥であった。カラスの死骸である。合点がいった。これは鳥よけなのである。これも衝撃的であった。といって、なんと残酷なことを、などという意味ではない。大げさに言えば、ここには近代以前がある。まわりの水田の形といいこのカラスといい、これは近代以前の姿ではないか。ゴンベが種まきゃカラスがほじくる、いまでこそそれは歌のなかでおかしげにうたわれるだけだけれども、考えてみれば、近代以前、田畑はずっと森に近く在り、従ってカラスも沢山いて、こんな状景も単なる戯歌のなかの話ではなく、日常的なことだったのだろう。自分の身うちの死体があればカラスも寄ってこないのではないか、そう考えたのかどうかは知らないが、言わばまじないに近い鳥よけが、近代農法とともに在る。この鳥よけは、おそらく先代から営々として引きついできたやりかたなのにちがいない。あるいはそうではなく、期せずして先代と同じような状況におかれて、その状況に対する解法としていまあらためて思いだしたやりかたなのかもしれない。いずれにしろ、近代が近代以前と同居しているのである。近代は突如として近代という形をなして私たちの目の前に現われたのではない。近代はそれ以前を、そしてまたそれはそれ以前の、常にその前代の人間の営為をひきずっている、そしてそれはことによると同じいまに共存することだってあり得るのだ、そのことをこのカラスは、まさに身をもって見せてくれているではないか。それが私にとって衝撃的だったのである。
実は、この大池めぐりの自転車散歩においての私にとって衝撃的な体験、それが今回の一文を書く動機になったのである。
〇知ること、分ること、「ためらう」こと
ほんの数ページ前で私は、現代の道の上をバスで走っていて、どれだけの人が昔はあの丘の上を道が走っていたと思うだろうか、大抵は、いま走っているこの場所を昔もいまも変らずに道は通っていたと思うだろうし、それであたりまえだ、と書いた。そうなのだ。それであたりまえなのだ。いまの日常の生活は、いまの現実との対応であけくれるのだから、それであたりまえなのであり、それは都会から新にここへ移り住んできた人にとっても、代々ここに住んできた人にとっても、現象としては同じだろう。第一昔はどうだったかなどとも思いはしまい。しかし、同じだというのは、あくまでも現象としてなのだ。都会からきた人たちは単純に知らないからそう思うのであり、代々住んできた人たちは知ってはいたけれども現実の生活のなかで忘れてしまったからなのだ。地つきの人たちは、言わば意識下にそういったことをしまいこんでしまっているのである。だから、やろうと思えばカラスの死体をぶら下げるやりかたを、この近代農法の世のなかで、持ちだすことがいつでもできるのだ。思いだす、つまり、しまいこんでいたものをほこりをはらって持ちだすことができるのだ。それを非合理だとか残酷だとか言って笑うのは、意識下になにもしまっていない人、近代・現代が突如として近代・現代という形をなして目の前に現われたと思いこんでいる人だ。
考えてみれば、それぞれの土地で人々は、そのときのいまを、そのときの昔を意識下にしまいながら、生き、そしてそのいまを、そのいまでの生活を基におき、変えてきたのである。いや、それが人々の「生活」というものなのだ。そのときのいまに生きているそのさなかにある人々にとって、そのときの昔はさしづめ空気のようなものでしかない。だからそれらは日常的には眼中にないし、またよほどのことでもない限り頭に浮かんでこないだろう。それが先に言ったあたりまえだということだ。
そしてまたおそらく、近代以前にあっては、その土地に新らしく移り住んできた人たちが先ずやったことといえば、その土地の空気のようなものを知ろうとすることだったろう。なぜなら、そうすることがいまその土地で生きることだということを、そこへ移り住む前の生活で身をもって知っていたはずだからである。そして多分、そこでなにごとかを行なうにあたっては、必らず、これでいいのだろうかという「ためらい」を抱いただろう。それはしかし単なる新入りの遠慮のそれではなく、正当な「ためらい」だったはずである。
(「昔」のことを知るのは歴史家だけに必要なのだろうか。歴史は歴史家のために、郷土史は郷土史家のためにのみ存在するのだろうか。彼らはそれでしあわせかもしれないが、私たちにとっては、環境破壊以上に恐ろしいことなのだ。)
いま私たちは、ともすると、そのわずかな期間現代に暮した経験だけを基に(多くの場合、しかも都会で経験することこそが絶対だと思い)、一つの映像としての風景に一つの見えかただけをあてがい、一律に処理して済ましてしまっている。そしてまた、ともすると、いま現在の私たちがとる見かた、そしてその見かたを醸成した私たち自らの(現代における)経験に対して、私たちの意識下ある昔、空気のような昔、が大きな比重を占めていることに気づかず、なにごともみな自らがあみだしたかのように思ってしまっている。とりわけ、近代合理主義的な思考方法に徹すれば、むしろ卒先してこんな「空気のようなもの」は切り捨てようとするだろう。というより、そんなものの存在を認めてないのである。吸ってきた「空気」の存在を知らず認めず、現代が現代という形をして突然現れたと思っている、いかんともしがたくしあわせな人。考えてみると、いまや、多くの建築や地域の計画の専門家という人たちはこういうタイプの人たちだ。こういう人たちは、いまに生きているそのさなかにある人(彼らは「空気」を吸っている、しかしいまに夢中でそれに気づかないだけ)にはなり得ないし、まして、その人たちを知ることさえ、分ることさえ、できないのである。できるわけがないのである。彼らはそれでしあわせかもしれないが、私たちにとっては、環境破壊以上に恐ろしいことなのだ。
いまに生きるそのさなかにいる人がその吸っている「空気」に気づかない、それは先にも書いたように、あたりまえだ。しかし、専門家は、専門家こそ、専門家である以上、このいまに夢中の人たちが気づかない「空気のようなもの」を積極的に、意識的に見ようとすべきなのではなかろうか。そして、そうであれば、専門家はなにごとかを成すにあたって、しばし、正当に「ためらう」はずなのだ。一つの風景を映像としてのみ扱い済ますはずもなく、一つの見えかただけで律しようと思うはずもないのである。
あとがき
〇「風土:大地と人間の歴史」(平凡社選書30)の著者玉城哲氏の随筆「水紀行」のなかの一文を、ある人からわざわざコピーして送っていただいた。著者が奥入瀬(おいらせ)川のそばをバスで通ったとき、その川の管理上の名(建設省の呼ぶ名前)が相坂川であることを見つけ、いったい地元ではどちらの名で呼ぶのかと思って、乗りあわせていたおばあさんに尋ねたところ、そのおばあさん、知らない、よその人はオイラ・・とか言うらしいけど、と言う。いささか驚いて、川の名前知らないの?と重ねてきくと、知らない、そこに松の木があれば「松の木川」さ、というこたえがかえってきて二度びっくりした、そういう話である。要するに、一つの川には一つだけ名がある、そうでなければならない、いくつもあれば不都合だからーつに統一する、などと思っているのは、思いあがりもはなはだしいのではないか、そうやって当然と済ましているものの見かたは、実は根本的に誤まりなのではないか、というのである。私たちの足元をゆすぶる、非常にいい話である。おばあさん万歳!
〇しかし、あいかわらず、一つの風景を、―つの統一された、しかも期待される見えかたで見ることを教えたがる人がいる。内申書裁判判決。
〇ときどき私は、私が大学を出るまでに教えられてきたことを、ことごとくひっくり返してみようとしているのではないか、そんな気がしてならない。私は別に、そんなにへそまがりだとは思えない。ただ、教えられたことによると、つじつまのあわないことが多すぎる。それだけのことだ。教えられたこと、いったいそれは何だったのだろうか。
〇ひっくり返しついでにもう一つ。いま国鉄の経営改革が話題になっている。民営化への答申もでたようだ。しかしふと考える。いずれの議論も、国鉄は企業であるという前提を、当然のこととして設定している。くだいて言えば、商売だというのである。その前提をとっぱらったらどうなるか。つまり、企業でないとしたらどうなるか。自衛隊は企業である。そう悪う人がいるか?(もっとも自衛隊が企業だと空恐ろしいことになる。採算のために、戦争が商品になる。)国鉄職員の怠慢は、企業性の欠如のせいだ、というのと同様に、自衛隊員の士気はその企業性の有無による、などと言えるか?この前提を疑ったとき、初めて国鉄のほんとの意味が見えてくるのではないか。独立探算、どうしてそうでなければならないのか(と疑わないのか)。自衛隊への探算を無視した投資の何分のーかの投資で、国鉄は国鉄になる。その方がよほど国を守るからである。それに文句をつける国民が、どこかにいるか。
〇あと十日もすると、田んぼは一面の縁となって水面は見えなくなり、その代り、田んぼをわたるそよ風が目に見えるようになる。今夜、ほととぎすが鳴いた。
〇それぞれなりのご活躍を!そして、その共有されんことを!
1982・5・19 下山 眞司

























