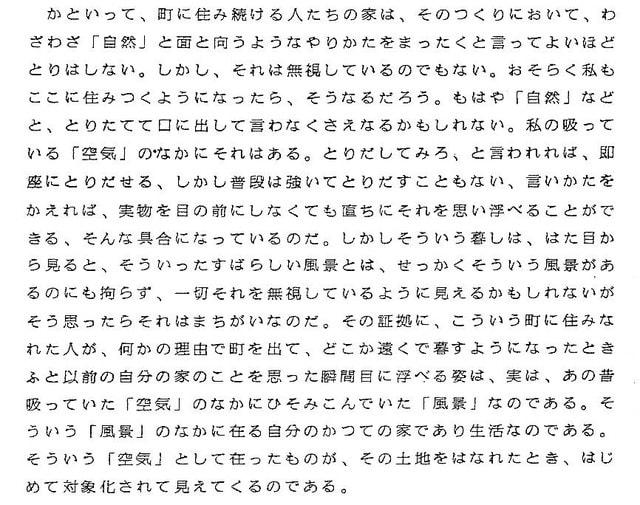
風景について 1982年度「筑波通信 №11」
風景、景色、光景、景観・・・・といろいろ似たことばがあるが、ここでは、それほど厳密な定義づけをして風景なる語を使っているわけではない。普通に使っている風景の意として気楽に読んでほしい。
暖冬だから雪はないだろう、そう思ったのはまったくの思いちがいであった。暖冬であるが故に例年になく雨が降る。そして、このような高地では、雨は雪になる。
この正月三が日、南信州のとある山小屋で寝正月をきめこんだ。この時期、この地方は北信の裏日本型気候とちがって冷えこむことはあっても雪が降りつもるほど降るということは少なく、そうなるのはもう少しおそく少しばかり春めいて低気圧がしきりと南岸を通るようになってからだ。しかし今年は、もう二・三十センチも積っていた。どうやら筑波の暮の雨がここでは雪であったらしい。それも、風もなくしんしんと降り積ったらしく、吹きだまりもなく一様に積っている。春が来るまでとけないだろう。
それでいて、いつもこの時期には真白のはずの八ヶ岳や蓼科山などはちょっとがっかりするぐらい冬らしくない。例年ならとっくの昔に積ってしまったはずの雪が、ようやっと最近になって積りだしたのだろう、まだところどころに山はだか見える。そうであってもやはり、その山なみの日に映える姿はすばらしい。三が日、天気は弱い冬型、南信は快晴。実に心地よく澄みきった空が拡がっている。ところどころに一見春を思わせるような柔らかい雲が泳いでいる。山のあなたの空遠く・・、そういう想いはこうでなければ生まれはしまい、そんな風に思わせるほど山の向うが輝いて見える。あの山の向うには、こちら側とはちがう何かがある、そういう想いをほんとに馳せらせる何かがある。そういう向う側まで予測させるほどにまで、山はくっきりとその姿を見せている。日が動くにつれ山容は刻々と変る。そして夕映え。私の一番好きなときが来る。あれほどにまで快活であった空が徐々に寂しげな色に変り、やがて暮れ残る空のなかに山は夕日を浴びて一段と輝きを増し、そして一瞬ののち山はあたかも切絵のようになり宙に浮く。日の入った方をふと見やれば、シルエットになった山の端が燃えている。見る見るうちに空はその深さを増し、星があそこにもここにも光りだす。そして、また山が輝きだした。月が上ったのである。そういえば、年の暮が満月であった。深いやや青味を帯びた闇のなかに、昼間のあの明るさとはちがい冷たく輝く山が浮びあがる。街の燈火が眼下の谷間の平地のあちこちに点滅しはじめた。手前の、葉がすっかり落ちてしまった林間では、積った雪が昼にもまして明るく、しかしやや青白く、新鮮に輝きだしている。木々の影は枝先の一本一本まで数えられるかのようにくっきりと雪の上に刻まれて動かない。風がないのである。静寂。外はもう氷点を大分割っただろう。
私はいま、山小屋のなかから外をながめている。室内は、無粋な石油ストーブのおかげで、大分暖かい。けれども風景の見える窓ぎわによると、そこは北側だから、大きなガラスが直かに外の冷気のかたまりを伝えてきて、ひんやりとする。私のいる山小屋は、北斜面に、北を大きく開けて建っているのである。
本州の中央部、甲府盆地の西で、一本の谷間を隔てて、北に八ヶ岳、南に南アルプス(赤石山脈)が相対している。谷間をぬって中央線が走っている。私のいる山小屋は、そのあたり、南アルプス山系の北端の山の一角、八ヶ岳の西面の全容を一望にできる北斜面に在る。八ヶ岳だけではない、そこから続く蓼科山・霧ヶ峰・・・・と一連の山々を一度に見ることができる。けれどもそんなところだから、冬至の前後の一時期、まともに陽の当らないときがある。後に背負った山の端すれすれに太陽が通ってしまうのだ。まわりに在るのも、ほとんどがこういう北に開いた山小屋ばかりで、土地の人の家はまず一軒もない。住んでいないのだ。と言うより、住むはずもない、住もうという気もおきない、そういうところである。
標高約1150メートル。土地の人たちは標高1000メートルぐらいから下の方の、谷沿いの比較的平らな部分:山々のすそ野に、いくつかのまとまりをなして住んでいる。その家々の燈火が、夜、私のいる小屋から、またたいて見えるのである。ここは高冷地農業の本場。高原野菜の産地。高冷地にもかかわらず米もつくっている。米の収量日本一の農民が出たこともある、という信じられないような話を聞いたことがある。厳しい環境ゆえに、逆に仕事に熱が入るのかもしれない。すそ野にある田畑は、比較的最近の開拓であるらしい。八ヶ岳の広大なすそ野を開いた整然とした田畑を、私のいる小屋から、あのすばらしい山々の風景の前景として望むことができる。
こういう風景がとびこんでくるように、私のいる小屋の中心をなす室の北面いっぱいが大きく開け放たれているのである。普通言うところの「借景」である。この小屋は、実は私自身の設計なのだが、この風景を全部のみこんでやろうという試みは設計当初からのものであった。と言うより、この敷地の選定に係わりをもったときからその気があったと言った方がよい。そういう風景が目の前に拡がるような、そういう場所をわざわざ選んだのである。そして、実のことを言えば、そのすばらしい風景を見るとなると北向きになるなどということは観念的には分っていたのだけれども、それが実際にどんなことになるのかほとんど気にもせず、まったくその風景をたよりにしてつくってしまったのである。山へ向いている意識の方が強く、北を向いているなどという気はほとんどなかったから、あるとき磁石で方位を確かめてみて、あらためてびっくりしたことがある。それは、ある年の暮、陽が少しも当らないので不審に思って調べてみたときのことである。冬至のころ、太陽がずっと低く寝てしまうということに、これもあらためてびっくりした。もしも、このような陽のあたらない家を普通につくってしまったら、それこそ目もあてられない。なぜそんな場所を選んだのだと、一生たたるはずである。この小屋が、ときおりこの風景を味わうために来るためのような家だからこそ救われるのである。
「(浅間温泉の)宿の上等の座敷というのは、むしろ山とは逆な方角に窓を開いていた。アルプスの見える窓などは、冬になると寒い風が吹きこんでくるものとしか考えられていなかった。・・・・」これは一昨年の通信№5(1981 ・ 8)で紹介した文章の一節である。そうである以上、この宿は、おそらく陽あたりのよい場所に南面でもして建っていたのにちがいあるまい。そして、私のいる山小屋の眼下に点在する家々もまた、まずそのほとんど全部、家のなかからすばらしい風景が見える、などということには一切関係ないつくりかたで建てられているとみてよいはずである。冬期、この地方は、谷に沿って風が吹きぬける。ただでさえ寒いのに風が吹くと一段と冷えてしまう。家々は、その広大な大地から頭を出さないように、大地のひそみに建てこんでいるのが実際である。まずどの家も、すばらしい景色の拡がる北側を閉じている。第一、大地のひそみに入りこんでしまえば、そんな景色など見えなくなってしまう。敷地の選びかたからして、風景などとは無縁なところできめられているのである。
だとすると、こういう土地の人たちの家のつくりかたと、私がこの山小屋で試みたような「借景」というつくりかた、この二つについて考えてみたくなる。
京都に行くと、あちこちに、「借景」の庭あるいは建物があるけれども、考えてみると、それらもまずほとんど全て、普通の人たちの家ではなく、寺院や宮家の別荘の庭や建物である。普通の人の家にあるとすれば、それは母屋ではなく離れにおいてである。寺院の場合も、方丈など寺院の本体部分にはなく、それより奥の、ややくだけだ書院の部分においてよく見られる。(と言って、それは日常の生活が行われているところではなく、日常生活は更にその裏手の部分、いわゆる庫裏を中心に営まれている。そして庫裏は普通の家と大差ない。)京都の北に、円通寺という「借景」で名の知れた寺があるが、そこでは比叡山をとりこむため書院の部分が東を向いて開いている。実際、そのあたりから見る山はなかなかのものだ。けれども、その寺のまわりの家々は、山容をとりこむことなどとは関係なく、大体南向きである。
私が現在住んでいる所でも、筑波山がよく見える。筑波山という山は平原のへりに突出して立っている山だから、その山容もそれなりの景観となる。その昔、江戸の町からも、西の富士山、北の男体山(日光)とならんで際だって見える山の一つでもあったらしい。いまでも、よく晴れた日には、高層ビルからなら見えるそうである。この筑波山のふもとあたり、平原のとっつきには、昔から人が住みつき、いまでも大きな町はそのあたりにある。江戸中期以降に開かれたと思われる集落が、山から少しはなれた平原のなかに数多く点在しているが、そこから見る筑波山も、それは足もとからてっぺんまでの全容が見えるから、なかなかのものだ。だから、このあたりの小学校の校歌で、筑波山に触れないものは皆無であると言ってよいくらいである。しかし、そういった町や村を歩いても、筑波山の景色をそのままとりこんでしまおうなどと考えてつくられた家はこれも皆無であるといってよく、それは、いま私がいる山小屋のある町や村の、土地の人たちの家々とまったく同じである。
私は先年、この八ヶ岳のふもとの町で、ある人と知りあいになった。とある食堂で、このあたりの風景を描いた素朴な木版画が壁にかかっているのを見かけ、これをつくったのが町の人だと聞いて尋ねて見る気になり、そして知るようになったのである。彼は元校長先生。この町の生まれ。在職中信州中を転勤で歩きまわり、そのとき印象に残ってしまった風景を、なんとか記録しておきたいという気になり、退職後はじめたらしい。写真より版画の力が感じをよく伝える、そう思ってはじめたことであるらしいが、もともと素人。それがかえって素朴な味をだしているようだ。この人の家は町なかにあり、普通の家とかわりなく南面していたのだけれども、ただ彼の仕事場の一角は、それは倉を改造したものらしかったが、そこだけ北東側に大きな窓が開けられ、あっと驚くほどすばらしい八ヶ岳を望むことができた。そうなるように直したのだそうである。私のいる小屋とちがって、南アルプス、富士山、そして八ヶ岳を一望できるところに建っているから、なおさらすごい。気のむくままに、母屋からここへ出てきて、独りこの景色に見入るのだそうである。版画を彫り、あるいは刷り、そして手を休めてお茶をのみつつ景色を見やり季節を想い、かつて訪ねた土地を想う。そしてときにはそこをはなれてスケッチ旅行に赴く。言うならば、自適の生活。そういう毎日。
土地の人たちの家のつくりかたが、景色などとは無縁である、そう書きながら実はこの人の家のことを思いだしたのである。母屋の方も、その立地上、つくりようによっては景色をのみこむことができるのに、一切そういう手だては講じてない。だから、この人の仕事場も、普通の人たちの家からすれば異例なのである。
その気になって、この町のあちこちを歩きまわってみると、そういったすばらしい風景をとりこもうとしたつくりかたは、最近建ったらしい旅館、民宿、ドライブインといった類のいわゆる観光施設と山荘・別荘などに見られ、もしも普通の家でそれらしきものがあるとすれば、それはまったくたまたまその場所に普通のやりかたで建ててしまったら景色が見えてしまった、そういうような場合のようで、だからとりたてて景色がよく見えるように、などという策を弄したりはしていない。
それでは、土地の人たち(普通の人たち)がそういった景色などに対してまったく無関心なのか、というとそうではない。立ち寄ったガソリンスタンドや店の人が、今日は山がよく見えるでしょう、だとか、今年は山の雪がおそい、とか、紅葉がだめだ、とか私に話しかけてくるのは、必ずしも私がよそもので一見観光客風に見えるためだけではないだろう。もしも彼らがそういったことを日ごろ気にしてなかったとしたら、それを話題にすることもないからである。寒い、とか、暑い、とか、天気がいい、とかいう時候のあいさつの一つとしてそれが語られると見た方が自然なのである。私がそれに適当に応じていると、ときには、どこそこに行ってみなさいよ、南アルプス、富士山、八ヶ岳どころか諏訪湖の向うに北アルプスはもとより中央アルプスまで見えるから、いい気分だよ、などと教えてくれる人もいる。行ってみると、なるほどすごい。まるで日本のまんなか、それも屋根の上にでも登って、大げさに言えば、四海を独り占めにでもしたようないい気分になる。土地の人たちも、いい景色をちゃんと知っているのである。ただ。その場所には家は建っていない。小高い、田畑のまんなかである。冬のいまが一番見通しがきくのだけれども、しかし立ちつづけていると、吹きさらしだから凍えてしまう。
こうして見てくると、土地の人たちは、すばらしい景色、風景というものをちゃんと気にはとめてはいても、少なくとも見えがかりの上ではそれを直かに建物のつくりかたに反映させるというような、そういうつくりかたは、普通にはしないのだということが分る。
それでは、いま私のいる山小屋と、先の元校長先生の仕事場とは、それがともに外の風景を内にとりこもうとしている点で似ており、それゆえ同じつくりかたなのだ、と見てしまってもよいのだろうか。つまり、京都の円通寺も、この町の元校長さんの仕事場も、そして私のいる山小屋も、あちこちにあるドライブインも、それはどれも(金のかけかたの多少、つくりかたの巧拙、は別にして)「借景」という手法を使った同じつくりかたなのだ、と見なしてよいのだろうか。
いったい、私をして、いま私が居るこのようなつくりの山小屋をつくろうと思わしめたもの(それ以前に、このようないわば人も住めないような場所を敷地として選ばしめたもの)は何であったのか。
それは、そこからながめる景色が、構図として、あるいは図柄・絵柄として、きれいな、すばらしい、あるいは美しい・・・・景色であった、ただそれだけのことだったのだろうか。あるいはそのような言いかたでもよいのかもしれない。それがきれいであり、すばらしい、あるいは美しい・・・・ということは、どうやらまちがいのない(私だけではなく他の人たちもそう思う)ことのようであるから。だが、ふと、このきれいだとかすばらしいとか美しい・・・・とかいうことが何であるのかと考える。すると、これらの形容詞が、実は、ある景色に面と向ったとき、それを見ている人の口から思わずとびだした、言うならば感嘆詞のごときものである、ということに気づく。だから、きれいな景色だとかすばらしい景色だとかあるいは美しい景色・・・・だとかいうのは、より正確な言いかたをするならば、そのような言わば感嘆詞を人をして発せしめるような景色のことだ、ということができる。その景色が、それに対した人に、そのような言わば感嘆のことばを発せしめるようなある思いを抱かせた、そういう言いかたが許してもらえるだろう。それゆえ、つまるところ、そういう感嘆のことばの根底にある思い、それがいったいいかなるものであるかが、なににもまして問題にされなければならないのではないだろうか。
けれども、いま通常では、この思い、すなわち見ている人の側のことは(それが個々の人の間題であるからだろうか)むしろ問われず、景色そのものの側、すなわちその景色の図柄・絵柄としての構成・構図などが問題とされる。きれいだとかすばらしい・・・・という形容詞にて示されるものが、景色そのものにてんから備わっている属性であるかのように扱われている。きれい、すばらしい、あるいは美しい・・・・こういった人の側にわき起った状況を形容するための詞が、固いとか重いとかいう物そのものの性状を形容する詞と同列に扱い済まされているということである。
およそことばというものは全て、かならず人の感性を通過して生まれるのであるけれども、しかし生まれたことばには、言わば感性に密着したレベルにとどまるもの、感性を通過しきって言わば対象の側に付与されたと言ってよいレベルのものまで、その間に多様なレベルで存在しているにも拘らず、いまや、それを一様に、しかも対象の側に付与された、対象と一対一の関係を保つものとしてのみ 扱う傾向にある。そうならないものは、むしろ、厳密さを欠くものと見なされる。そこでは、ことばというものを、あの多様なレベルに言わば分散配置せしめた、人間の巧まざる知恵・思慮深さ、真の意味での厳密さ、についての認識がまったく失われてしまっている。
省みてみると、私がこの山小屋をつくったときのその言わば動機となった私の思いは、いま私が小屋のなかから外の景色を見つつ思っている思いと、ほとんど差がないように思われる。もし違っているとすれば。初めてこの地の風景を見たときよりかれこれ十年近く経過し、見える風景に係わる多少の知見が増えたことだけだろう。初めのころは、夜景の街の燈りを見ても、それはあくまでも闇に点滅する光の群れ、一言で言えば「きれいな夜景」としてしか見えなかったけれども、いまでは、あたりを歩きまわった結果の多少の知見ゆえに、あのまたたいているのはあの集落のあの曲りかどのあたりだとか、あそこに一つだけきわだって見える燈は八ヶ岳農場のはずだ・・・・とか比定できるようになっているし、昼間ならばもっといろいろな所を比定できる。しかし、私が景色を見て感じいっているのはその初めのころとほとんど変りなく、あの町この町がどんなであろうともそんなこととは関係なく、言わば「自然」そのものに私は感じいっているのである。私の向う側に在る、私を越えた。そして私を圧倒して在る言わば抽象的な概念としての「自然」に対している、そういう気分である。それはちょうど、海岸で打ち寄せる波に見入っているとき、あるいはまた流れる川面をあきずながめているとき、そういうときおちいるあの気分、ひきずりこまれてしまうのではないかとおそれつつたたずんでいなくてはいられないあの気分に似ている。見入るうちに、自分自身がなんとなく所在ないもののように見えてくる。
そして、考えてみると、私はこの気分を求めてときおりこの小屋に来るのだし、そもそもがそのためにこういう小屋をつくったのだと言ってよいように思われる。いかなる町が在り人がいようとも、少なくとも当面それはどうでもよい。はなはだきざな言いかたをすれば、そういう景色を見ているうちに、見ている自分がそれとの対比のなかで見えてくる、それにより自身を見つめることができる、そのために、求めてここへ来るのである。そういう小屋にしたかったのである。
こう書いてくると、このような思いに私をおちいらせるためには、ある自然の風景、しかもきわだって目に入るすばらしい風景がありさえすればよいかのように思われるかもしれない。もしもそうならば、観光地で見かける展望台やながめのよいドライブインなどでも、言わゆる景観のすばらしい所ならどこでも、そういう気分にならなくてはならないのだが、どうもそうではない。たしかに、その場をはなれがたく思う、そのまま見入り続けたいと思う場合もないわけではない。行きつけの店のきまった席というのがあり、ひまさえあればそこに座って外の景色をじっとながめている、などという映画のシーンや歌謡曲の一節のような場面も実際にないわけではないだろう。しかし、展望台などからのながめは、言うならば一過性のきれい・すばらしい・・・・で終ってしまう。あるいはきれいな図柄・絵柄・・・・で終ってしまう場合の方が、どう考えても多いようである。つまり「絵葉書」的すばらしさへの感動である。私がこの山小屋で思っている思いは、そういった「絵葉書」的感動とは別のむしろそれを越えたもののようであり、対面している景色が、他よりもきわだった、すばらしいものであればどんなものでもよい、というわけでないのはたしかである。では、どういう場合に私はそう思うのか、そういう思いを抱くのか。どうも、見ている景色が一つの画面として私の前に、私をはなれて、ついたてのごとくに在る場合(そう感じられる場合)はだめで、私自身がその景色の一部に言わば組みこまれてしまっている、そんなように感じられる場合にそういう思いにかられるらしいのであるが、しかしそこのところは私にも未だによく分りきっていない。いずれにしろたしかなのは、すばらしい・・・・とかいう形容の意味することには、「絵葉書」的感動レベルのそれとは違う、それを越えたレベルのものもある、ということである。
けれども、すばらしい、きれい・・・・ということばを対象が備えている属性のごとく扱うだけでなく、更に、この「絵葉書」的レベルの話としてのみ扱い済ますのが世の大勢でもあるらしい。風景・景色・景観・・・・いろいろなことばが飛びかっているけれども、その意味することは、多くは、言わば「銭湯の富士の絵」なのだ。
先に私は、私がこの山小屋を訪れるのは(従ってこういう思いに浸るのは)ときおりであると書いた。
しかし、もしも(そこが住める所か否かは別として)私が仮に住みついたとしたら、私の思いはどうなるだろうか。あいかわらず私はそこに私を越えた言わば抽象的概念としての「自然」を見続けるのだろうか。
おそらくそうではないだろう。
ときおりとは言え、十年近くもここを訪れることを重ねると、そこで目にする風景に係わる多少の知見が増えるということを先に書いたけれども、これがそこに住みつくとなると、この知見はいやおうなしに増えてくる、というより増えざるを得ないだろう。初めのうちの知見は、これも先に記した通り、地物についてのそれが多い。歩きまわること(これには、ある目的をもって歩く場合もあるし、気の向くままにそぞろ歩くこともあれば、そして不本意ながら道に迷って歩くこともある)によって得た地図的な知識と、現に目の前にしている景色とを重ねてみて、目に見えているそれぞれの地物が比定されてゆくのである。比定されてゆくのには自ずと順序があり、具体的に自分が何らかの理由でその地物と深い係わりを持たざるを得なかった所(それには当然、道に迷ってえらい目にあった、などというのも合まれる)から順に定まってくる。
面白いことに、見えている地物を、たとえば五万分の一の地図と、照しあわせながら比定していった場合には、そこで得た知識は、その時その場かぎりとなってしまうことが多い。次に見るときにはすっかり忘れている。私のいる小屋からは、はじめに書いたように八ヶ岳の西面が一望にでき、ご承知かと思うが八ヶ岳はその名の通りいくつかの峰より成っている。私はその峰々の名を覚えようとした。ところが、そのうちのいくつかは覚えたのだがたしか赤岳と権現岳だったと思うが、なかなか覚えられない。そのときは覚えたつもりが、次に訪れたときには、どっちがどっちだか忘れているのである。というのも、私のいる所からは、その二つがなんとなく似て見えるのである。おまけに視角の関係で、地図の上の配列通りにあるいはその物理的高さの順に、見えはしないから、地図の上のならび方を覚えてもだめである。いつも、地図の上に私のいる地点を見つけだし、そこから直線をそれぞれの峰の頂へ向けて引き、つまり地図上の作図で、なるほどなるほどと思うわけである。この作業自体は、それはそれなりに面白いけれども、しかし、そういうことで覚えたことと、実際に言わば足でかせいで覚えたこととは、そのなかみが違うようである。
そしてもちろん、住みつくようになれば、ときおり訪れる場合とはまた少しばかり違って、暮してゆくために必然的に係わりをもつものの比重が大きくなる。そして時間が経てば経つほど、その量も増え、目の前の風景は知った色で塗りつぶされてゆく。しかもその知見の内容は、はじめのうちは単なる地物そのもの(あの曲りかど、あの道、〇〇小学校、〇〇の工場・・・・いう類)であったのが、だんだんそうではなくなってくる。たとえば、あのあたりの田畑はどこそこのだれそれのものだ、とかいう具合に、それまではあくまでも私自身に係わりをもつことがらだったのに比べ、言うならば風景とともに他人の顔が浮んできたりするようになってくる。小学校といったって、ただ小学校ではなく、自分の子どもが通っている、あるいはあの家の子が通っている学校、〇〇さんの奥さんが先生をしている学校・・・・というように、私のそこでの暮しが必然的に係わりを持たなければならない言わば人の世が、目に見える風景ともども私に見えてくる。
「自然」にしてもそうである。きれいな山だとか林だ・・・・などというものではなくなる。あのあたりはたらの芽がよく採れるんだ、昨年はあいつが先きまわりしていいとこ全部持っていっちまったから、ことしは・・・・だとか思いながら見るようになる。いや、これは単に目に見える風景についてだけではない。朝起きて今日は一段と冷えこんだな、などと思った瞬間、あのガソリンスタンドのおばさん(多分〇さんといった具合に名前で思うだろうが)「きょうは寒いねえ」などと方言まるだしで、もこもこ着こんでストーブにかじりついてぼやいているぞ、なんて光景が浮んでくる。土地っ子に似あわず、おかしいくらいに寒がりだからである。こんな具合に、そこに住めば住むほど、見るにつけ(そして聞くにつけ)私の頭のなかは、私がここで暮してゆくにあたって係わりを持たなければならない人の世のイメージでいっぱいになる。おそらくそうなってくると、たとえば町で人とすれちがい、寒いねえ、とか、冷えるねえ、とか一言二言交しても、それは単なる儀礼的時侯のあいさつなのではなく、ほんとのあいさつ、つまりきょう二人がともに味わったことのお互いの確認の意昧をもったことばになってくるのではなかろうか。
おそらくこの町の一角に住みつき、なじんてしまうと、私の目の前に拡がる一帯は、それを見ることによって直ちに人の世が浮びあがってくる所とそうでない所という具合に、人の世の浮びあがる強さ、濃さに応じて塗り分けられるようになるだろう。それはまた裏返して言えば、すなわち私自身が思うがままに歩きまわれる言わば私の世界の地図が具体的に描かれる、そう言ってもよいのである。それは当然、私の生活のしかた、つまり町のなかにこもりきってすごすか、それとも隣り村はおろか遠くまでその行動範面にするか、によって変ってくる。
こうなってきたとき、あの「自然」はどこへいってしまったのだろうか。私の念頭から、まったく去ってしまったのか。そうではない。ちゃんと存在している。ただ、その存在のしかたが変っているのである。うまい表現のしかたがないのだが、あえて言えば、私の暮しが係わる風景のなかで(つまり私の世界のなかで)「自然」はもはや対象化し得ない形で、その私の世界のなかにくみこまれてしまっているのである。なくてもよいものではない、それがあってはじめて私の生活がある、切っても切れないもの、「空気」みたいなものとして、それは存在しているのである。そうであるからこそ、それについてのちょっとした話題も、時候のあいさつ同様、そこに住む人たちの共通の話題、すなわち共通の認識となることができるのだ。だからこそ、ときおり訪れるとはいえ、顔なじみになったガソリンスタンドや店の人が、あそこからだったら山がきれいでしょう、などと話しかけてくるのである。
かといって、町に住み続ける人たちの家は、そのつくりにおいて、わざわざ「自然」と面と向うようなやりかたをまったくと言ってよいほどとりはしない。しかし、それは無視しているのでもない。おそらく私もここに住みつくようになったら、そうなるだろう。もはや「自然」などと、とりたてて口に出して言わなくさえなるかもしれない。私の吸っている「空気」のなかにそれはある。とりだしてみろ、と言われれば、即座にとりだせる、しかし普段は強いてとりだすこともない、言いかたをかえれば、実物を目の前にしなくても直ちにそれを思い浮べることができる、そんな具合になっているのだ。しかしそういう暮しは、はた目から見ると、そういったすばらしい風景とは、せっかくそういう風景があるのにも拘らず、一切それを無視しているように見えるかもしれないがそう思ったらそれはまちがいなのだ。その証拠に、こういう町に住みなれた人が、何かの理由で町を出て、どこか遠くで暮すようになったときふと以前の自分の家のことを思った瞬間目に浮べる姿は、実は、あの昔吸っていた「空気」のなかにひそみこんでいた「風景」なのである。そういう「風景」のなかに在る自分のかつての家であり生活なのである。そういう「空気」として在ったものが、その土地をはなれたとき、はじめて対象化されて見えてくるのである。
だから、もし私が一念発起してこの町に住みつきはじめたなら、はじめ対象化して見えていた風景は、どんどん日常的な「空気」と化していってしまうのである。おそらくそれが、住み慣れる、ということなのだろう。日常的な生活では、はた目から見ればきわだって見える風景も、とりたててとりあげるまでもないあたりまえなものとして扱い済まされるのである。私が正月をすごした小屋がある町は、その名を富士見という。諏訪から甲州へ向ってここまで来ると、ここではじめて富士山をまのあたりにすることができる。そこから町の名が生まれたのである。ところが調べてみると、この名は、明治7年の町村合併に際してはじめて生みだされた名前で(そのときは富士見村であった)、合併した旧村名にはそのどれにもそれらしき名はない。もちろん八ヶ岳のふもとにあることを言い表すような名もない。原の茶屋、木の間、大平新田、若宮新田・・・・といった名である。当然富士も見えたし、八ヶ岳は目の前にあった。しかし彼らは、それをもって村の名にはしなかったのである。明治になってはじめて景色をはた目で見る見かたが入ってきた、そう考えてよいだろう。それまでは、そこで富士が見え、八ヶ岳を仰ぐことは、そこに住みついている人たちにとっては、とりたてて騒ぐこともないあたりまえのことだったと言ってもよいのではなかろうか。よそから来た人には目新しいことも、その土地の人にはあたりまえなのだ(そして、よそから来た人たちにとってもそれは、その人が住みついてしまえば、あたりまえなものに変ってゆく)。
「観光」というのは、よそものの目に目新しく映るものによってなりたつのである。だからときおり、どこそこの山はいい山ですね、などと土地の人に話しかけたりすると、そうかねえ、なんて、いささか拍子ぬけの返事が返ってきたりすることがある。なにがそんなにいいのかね、というわけである。実際、その土地の人にとってはなんでもないようなことが「観光」の対象になってしまうのである。それをして「観光資源」というらしい。
それでは、もうこの町にすっかり住みついてしまった私が(もっともほんとに地に足が生えたように住みつくには相当時間がかかると思うけれども)、その吸う「空気」のなかから、意識的に「風景」をとりだして見る気になったならば、どうなるのか。
実は、この状態が、先に紹介した(いまは風景版画に熱中し自適の生活を送っている)元校長先生の毎日なのであり、そしてその仕事場のつくりも、それに心したものであったのである。
いま、その町に住みついているのではない私と、もうなが年住みついている元校長先生は、同じ部屋の同じ窓から、同じ景色をながめている。目に入ってくる光景はたしかに同じである。すばらしいですねえ、いいなあ、と私がいう。彼も、ね、いいでしょう、と応ずる。なんとなく話が合ったように私は思いこむ。だが、その思いこみは、既に書いてきたことで明らかなように、必ずしも彼の「いい」と合っているわけではない。いや、少しは合っていないこともないけれど、むしろ、大きく見れば、合っていない、と言った方がよりよいかもしれないのである。なぜなら、彼は、まず「空気」の存在を自覚し、そのなかからその風景を抽出して見ているのに対し、私は(この町に住みついていない段階での私は)、その「空気」を知らない。私が吸っているのは、ここの「空気」ではなく、別の所:現に私が住みついている所の「空気」なのである。(あるいはことによると、私自身が既にその吸っている「空気」が何であるのか分らなくなってしまった私になってしまっているかもしれないのである。)そうであるとき、同じ景色を見ているのだから、彼も私と同じようにそれを見ている、などと思いこむなどは、はなはだおこがましいことなのだということに気づく。唯一の救いは、彼と私が、その見ていることはどうやら違うにも拘らず、同じ風景を目の前において話ができている、ということだ。
おそらく彼とのつきあいを深めていけば、私は彼の見ているものにほど近いものを見ることができるようになるだろう。同じものを目の前に置いているからである。そしてまたおそらく、そうなり得るということこそが、すばらしい風景、きわだった風景、気になる風景・・というものの効用というものだろう。(ただし、このような場合、私と彼の見ているものが同じに近くなるためには、そこに住みついていない私の方から、極力彼の立場に近づくべく努めなければだめだろう。)
このように考えてくると、明らかに、住みつくようになってからの私と、ときおり訪れる私とでは、同一の風景に対していても、その見えかたが違ってくる、ということができそうだ。
先に私は、ときおりそこを訪れる私が、その目に入る風景に、私を越えた、言わば抽象的な概念としての「自然」を見ているのだ、というような趣旨のことを書いた。そして、いま書いてきたように、そこに住みついた私も、その「空気」のなかから意識してとりだして「風景」を見ることができ、そしてそこに同じように抽象的な「自然」を見るだろう。そして、ことによると、その「自然」を言おうとして、少なくともことばの上では同じ表現をとるかもしれない。だが、ことばの同一、表現上の同一は、必ずしもそのことば・表現に託されたなかみの同一であることは保証せず、この場合は、むしろそのなかみは違うと言った方がよいだろう。同じように抽象的な「自然」であっても、その「抽象」のなかみが違うのである。
だが私には、まだ、この違いについて、うまい説明ができない。それを承知であえて言えば、そこに住みついた私が見る風景に見出している「自然」は、その場所:町での私を含めた人の世のなかから(つまり私のその場所での生々しい具体的な生活のなかから)真の意味で抽象した「自然」であり、従ってそれによって得たなかみ(概念)は、それを更により高度に抽象化した概念へと昇化させることができる一方、それとは逆に、それをもとにして、生々しい具体的なそこでの生活を想起することもできる、という性格を備えている。(それゆえ、その風景はその町の「生活」を象徴するものになり得、だからこそ、その町を遠くはなれて町を思うとき、その風景が目の前に浮びあがるのである。)当然そこでも「私」というものが見えてくるはずだが、その「私」もまた、そこに生活している生々しい具体的な私から抽象された、ふくよかなふくらみをもった「私」の姿であって、決して観念的な(理屈の上での)それではないだろう。
それに反し、先に私がはなはだきざっぽく、自分を見つめたいがためにその風景を見にくるのだと、鼻もちならない書きかたをしたとき(それは決してうそではないけれども)、その風景はなにもその風景でなくてもよかったのである。私の生々しい日常の具体的な生活はそことは別の所にある。その日常の本拠地をはなれ、なおかつ「私」をきわだたせてくれるような、そういう風景ならば、強いてこの町でなくたってよかったのである。そしてまた、そうやって「私」を見つめるやりかたは、日常の生活のなかで「私」をみつめるやりかたよりも、数等容易なことであり、ややもすると単に対比という観察レベルとどまり、あるいは観念的な、理屈の上の認識にとどまってしまうのではなかろうか。
ときおり訪れる私がある町のある風景に見るもの、そしてその町に住みついた私がその同じ風景にみるもの、その見るものの違い(あるいは見えかたの違い)というのは、おそらくこういうものではないかといま私は考えている。しかし私自身がまだすっきりしていないから、あいかわらずこれは私にとって宿題である。
ところで、ある町に住みついた私が、その吸う「空気」と化してしまった事物に対し、意識的に目をやったなら、などといとも簡単に言ったのであるが、これはそんなに容易なことではない。日常の生活(それはあくまでもその「空気」の存在ゆえになりたっているのだが)に没頭している人にとって、一々その「空気」を気にしなければならない必然性は何もないし、第一その人たちが係わる事物がその人たちにとってしっくりとおさまって、とりたてて目だたない状態であるからこそ「日常」と言うのであり、もしその「空気」をかき乱したりしたならば、それはすなわち「日常」ではなくなってしまうと言ってもよく、だから、日常の生活を営みながら且つその「空気」をもとりだして見つめてみるなどということは至難の技なのである。だからこそ通常に日常の生活を送っている人たちは「空気」をあげつらいはしないのである。そして実際に私自身の日常を省みても、自分の日常が何であるか分ろうとすることがいかに難しいことか、それだけはよく分る。見つめなければならない対象がすなわち見つめている本人なのだから。
(「筑波通信№11後半」に続きます。)

























