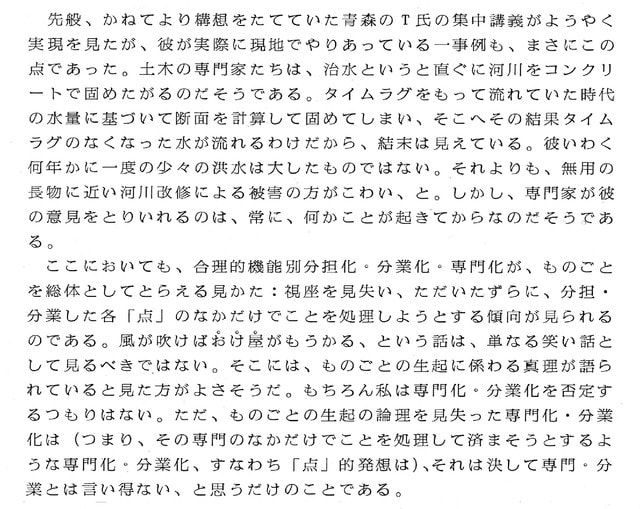
PDF「 点 と 線 」(1983年「筑波通信№8」A4版8頁)
「 点 と 線 」
朝八時半、やや薄くもやがかかり、地物は全て露を帯びている。甲州の十月半ばの朝は、霜の朝ももうそう遠いことではないことを思わせる。
折しも、黄ばみ始めたぶどう園に囲まれた急坂を、一人のおばあさんが気ぜわしそうに登ってきた。かなりの歳のようだ。家のだれかに送ってもらったのなら、坂の上まで車で来れたはずだから、きっと先ほど国道を上っていったバスを降り、ここまで歩いてきたのにちがいない。坂の途中で一息つきかけ、その時問も惜しむかのように、ほんの一瞬天を仰ぐかの素振りを示しただけで歩みを続け、建物の中に消えていった。
私は今でもそのときの情景を鮮明に思いだすことができる。丁度そのとき私はカメうを手にしていたのであったが、その印象深い情景に対してカメラを構えることはしなかった。というより、カメラを持っていることを忘れ、おばあさんの心の内に思いをはせ、半ばぼうぜんと、その情景を見つめていたのである。
昨日から私は再び「 S 園 」に来ている。冬に向って、暖房の試験のために訪れたのである。そして今日は園の運動会。昨夜は園生たちもはしゃぎ、そして指導員たちは(それを見るのはほんとに久しぶりのことだったのだが)てるてる坊主をつくって、所々にぶらさげ、好天を祈っていた。
あのおばあさんは、孫の運動会を観に、開始は十時だというのに、心せいてもう訪れたのである。聞けば、孫に会いに、今までも足繁く通ってきているのだそうである。
私も半日つきあうことにした。園には広い庭がないから、運動会は園から2kmほど下った町の中心にある昔の高校分校跡を借りて開かれる。いつもは駐車場になっている元校庭は、今日ばかりは晴々しく飾られていた。昨日のうちに、指導員たちの手で整えられたのである。父母たちも集まり、町の人たちもちらほら様子を見にきている。おばあさんは最前列に陣どり、始まるのを待っていた。
たどたどしいことばの園生の開会の辞があり、運動会は始まった。全部あわせても百人足らずの、ほんとに小さな小さな運動会だから騒がしくなるほどのにぎわいにはならないけれども、それなりの熱気・活気のある競技がくり拡げられている。会場整備も含め、さきごろ開かれた保育園の運動会よりも立派だ、というのが観にきていた町の人のことばだった。私もその熱気にのまれ、一日カメラマンになる気になった。私は園生たちの素顔を撮りたかった。格好の場所があった。校庭に面した元校舎の二階である。そこからは、全景も、そしてカメラを意識しない一人一人の表情も、手にとるように見ることができる。
そんな活気のなかで、一度だけ、白けたな、と思えるような瞬聞があった。園生たちにとって、大きな楽しみの一つである昼食のときのことである。昼食は幕の内弁当と園の調理員たちが前日から仕込んだおでんに豚汁。父母たちもそれぞれなにがしかを用意してきているようだった。家族が観に来ている園生たちに家族と一緒の食事が許され、それまで一かたまりになっていた園生の群れから彼らが抜け出たあと、その一瞬は起きた。約半数の、家族がだれも来ていない園生がそこに残された。私は彼らの表情に、寂しそうなかげりを見たような気がしたのだが、それは私の思いこみのせいだけだっただろうか。なにかその一角から空気が抜けてしまったような、そんな気がした。まずいな、と私が思ったとき、その気配を察したかのように、指導員のいく人かが、おでんを載せた盆を持って、努めて快活に、さあ食べよう、と分け入りその場の空気をかえたので、瞬時にしてまた前のように和んだように見えた。だが、彼らは確実に、家族がそこにいるかいないか、その差を感じとったのではあるまいか。ことによるとそれは、彼らにとっては日常茶飯事だったのかもしれないが。
私は、昨夜園の役員の一人から聞いた話を思いだした。いま入居している園生の半数以上のいわゆる家庭環境には、何らかの問題があるのだという。身寄りがない、身寄りはあっても、たとえば兄弟姉妹は、それぞれの生活で手いっぱいである、あるいは経済的に厳しい状況にある、・・・・という環境。昼食のとき園生席にとり残された人たちは、もちろんなかには単なる都合でだれも観に来なかったという人もあるだろうが、大半はそういう事情を背負った人たちだと見てよいだろう。
そうであるとき、そういう彼らには単なる運動会の昼食時の白けなどとは比較にならない大きな問題がのしかかってくることは自明だろう。
彼らが更生施設での生活を送るなかで、社会復帰できるまでになった:更生した、としよう。だが、それが、彼らが自立した生活を送ることができるようになった、ということを意味しているかというと、決してそうではない。これはあたりまえだ。彼らの生涯は、依然として、一定程度の「支え」を必要とするのである。だれが支えるか。身寄りはそういう状況にある。彼らが歳をとれば、身寄りも歳をとる。(それは、家庭環境に問題がない場合でも同じである。)つまるところ、園を出たら彼らは一人になる。たとえ就労先が見つかったとしても、拠るべがない。それゆえ、園を出るに出れない。園は更生施設ではなく定住施設化してしまう。その結果、更生施設への(とりわけ信頼がおけると思われる施設への)入園希望者は、列をなして待つことになる。
これは、つまるところ、制度としてはたしかに養護学校・更生施設・通勤寮・授産施設・・・・といった具合に外見上は整えられてはいても、障害者の生涯という視点から見ると、それはあくまでも単に「点」としての対応しか示していない、ということだ。しかも、それらの「点」の相互のスムーズな連携は決して十全であるとは言いがたい。「点」はあっても「線」がない。健常者ならばそれでもよいだろう。自力で「線」を構築できないわけではないからである。心障者の場合はそうはゆかない。
いま各地で心障者を抱える親たちの自分たちの施設づくりが盛んになっているが(この「 S 園 」もその一例だし、この園の見学者のなかにもそういう意向を持った親たちが多い)、それらはどれも「点」としての施設ではなく「線」としての施設:自分たちがいなくなったあとでもその代行をしてくれる施設を望んでいる、と見た方がよいだろう。明らかに、制度と要望がくいちがっているのである。
いわゆる公共施設・社会施設というものは、言うまでもなく、人々の生活を補完するためのものだ。そして、その整備にあたっては、半ば常識的に、人々の生活をいわば縦割りの機能別断面でとらえる対応(たとえば、教育・医療・福祉・・・・)が考えられ、制度化されてきている。先に記した心障者の施設群も、心障者の状態を年令別・成長別、あるいは障害度別に、すなわち機能別に考えられたものだ。それは、少なくとも外見上、心障者の状態に対して、合理的な因数分解で対応しているから、あとは個々の因数:個々の施設を充実すればよいかのように思われる。実際、心障者の施設はもちろん、いわゆる公共施設は全て、この機能分担、縦割り分業でその整備がすすめられているのは事実である。
だが、こと心障者に対するかぎり、重要な視点が欠落していた。つまり、年令・成長も、障害度の軽減:更生も、それは一個人の上に継続して起きる、という認識:視座の欠落である。だから、現状では、心障者は、その成長とともに、機能別に段階別に用意された施設を次々と渡り歩くことになる。まして、身寄りがない場合には、その人の生涯は、それは本来連続したものであるにも拘らず、いくつかの「点」に分断され、たらいまわしとなる。心障者を抱えた親たちの心配は、まさにこの点にある。親たちは、外見上の合理的機能分担・分業によって、あたかも荷分け作業でもするように、一人の人間を分類して片づける発想ではなくあくまでも一個人の連続した生活に視座をおいた発想を求めているのである。
しかし、考えてみると、この発想の転換、つまり、人々の個々の生活の視点にたっての公共施設の役割のとらえなおしは、全ての公共施設についてもなされる必要があるだろう。なぜなら、人々の生活を補完することを考える、ということは、人々の生活をその外観上で因数分解・機能分解することではなく、あくまでも、人びとの個々の生活を補完すべく考えるということのはずだからである。言いかたを変えれば、ある公共施設の価値は、単にその施設自体が整備充実しているか否かによってきまるのではなく、それが、人々の個々の生活遂行にあたりどのように取りこまれ有効に働いているか、によってきまるということだ。現状の多くの公共施設には、この個々の人が個々の生活に応じて使う、という発想はなく、あるのは全て、合理的機能分担・分業自体の強化だけだといってよい。それは必ずしも、人々の個々の生活遂行にとって都合がよいわけではない。むしろ、多くの場合は不都合のことの方が多いはずだ。にも拘わらず、不満が顕在化しないのは、人々が(止むを得ず)、先に記したように、それら「点」と「点」の間を自力でつなぎ、とりあえず済ましてしまっているからだ。そして、たまたま心障者の場合はそれがなし得ないがゆえに、顕在化して表われている。多分、いやきっと、こうであるにちがいない。機能別断面で見る分業化・専門化が、そもそもの本義:生活の総体を見えなくしているのである。
先号のあとがきで、最近多発している甲信地方の洪水についての感想を記したが、その後、あいついで、それに係わる話を知る機会があった。一つは、10月10付の朝日新聞「論壇」に載った論文によってである。全文をそのままコピーして載せることにする。

水田が、洪水の際の遊水池としてもさることながら、洪水になる以前の水量調節弁として重要な役割をもっていた、という指摘は、既に紹介した「土は訴える」という本にも述べられている。長野県下の全水田に10cmの水をためると、その総量は6000万t、諏訪湖に匹敵する水量となるそうである。ということは、降雨時には、なににもまして水量調節のクッション役をしてくれるということに他ならず、見かたを変えると、水田がダムの代りをしていてくれるのである。(ついでに言えば、水田は重要な地下水供給源でもあるという。水田には、代かきから収穫までなんと1500mmの水が注ぎこまれるのだそうである。その水は、元をただせば天水なのであるが、水田はその天水を直接河川へ流下させず、一時滞留させているわけである。)そしてそのある部分は地下へ浸透するのである。)
昭和の初め、日本の「たな田」(極端な例では「田毎の月」と呼ばれるような例、「千枚田」などとも言われる)を見たアメリカの地理学者が、「日本のピラミッド」つまり、これをつくりあげた農民のエネルギーは、ピラミッド建設のエネルギーにもまさる、と言ったそうである(いずれも同書による)。そして、長野県下では、昭和55年に、全水田面積の20%にあたる水田が、米の生産調整のために消えていったという。それは、先はどの計算でゆくと、中規模ダム一個分、1500万tの機能に相当するのである。そしてまたその減反は、機械化農業に不適な「たな田」状の田(つまり、山ぎわの田)がねらわれるから、その点から考えると、水田のダム機能は、上流に近い所ほど減ったことになる。
それに加えて、この論文にあるように、全ての小河川はコンクリートで固められ、水があふれないように改修された。結果は、これも論文にあるように、本流が一挙に増水する。タイムラグなく小河川(支流)から水が流れこむからである。そして、本流の断面はそれに耐えきれずに決壊してしまう。多分このような事態は、論者の指摘をまつまでもなくこれから各地で起きるのではなかろうか。
そして、この事態への対応は、今度は本流そのものの断面拡幅だろう。しかしこれがとてつもないことになるのは自明である。もしそれを完全にやるとしたら、本流流域の耕地は大幅に削限せざるを得ないだろう。
先般、かねてより構想をたてていた青森のT氏の集中講義がようやく実現を見たが、彼が実際に現地でやりあっている一事例も、まさにこの点であった。土木の専門家たちは、治水というと直ぐに河川をコンクリートで固めたがるのだそうである。タイムラグをもって流れていた時代の水量に基づいて断面を計算して固めてしまい、そこへその結果タイムラグのなくなった水が流れるわけだから、結末は見えている。彼いわく何年かに一度の少々の洪水は大したものではない。それよりも、無用の長物に近い河川改修による被害の方がこわい、と。しかし、専門家が彼の意見をとりいれるのは、常に、何かことが起きてからなのだそうである。
ここにおいても、合理的機能別分担化・分業化・専門化が、ものごとを総体としてとらえる見かた:視座を見失い、ただいたずらに、分担・分業した各「点」のなかだけでことを処理しようとする傾向が見られるのである。風が吹けばおけ屋がもうかる、という話は、単なる笑い話として見るべきではない。そこには、ものごとの生起に係わる真理が語られていると見た方がよさそうだ。もちろん私は専門化・分業化を否定するつもりはない。ただ、ものごとの生起の論理を見失った専門化・分業化は(つまり、その専門のなかだけでことを処理して済まそうとするような専門化・分業化、すなわち「点」的発想は)、それは決して専門・分業とは言い得ない、と思うだけのことである。
その意味で、T氏がここ四半世紀にわたり青森上北地方ですすめてきた施設創りの紹介は、その発想が単なる縦割りの「点」の集合でない点で(つまり柔軟な点で)まさに傾聴に値するものであった。かといってそれをリアリティをもって語ることは、到底私にはできがたい。その一部のことについては、先年、ほんのその上っ面だけを「七戸物語」のなかで紹介したが、あれではまったく不十分である。なんとかして本にまとめてもらおうと、いま考えているところである。
彼は、集中講義の最後にこう学生たちに語った:「どこの地域にも通用するようなやりかた、というものはない。それぞれの地域に、それぞれのやりかたがあるはずで、人々はそれを目ざし、専門家はそれを考えなければならないのではないか」と。
このなかの「地域」ということばは、そのまま「場合」ということばに置き換えてもよいだろう。要は一律の分断法でものを見ては困る、ものの見かたの根本になければならないのは、あくまでも総体を見ることでなければならないということなのだ。
あの「 S 園 」の役員が語ったことを続けると、いま、この園の設立に係わった親たちのなかで、もう一つ別の夢物語がかわされているのだという。それは、老人ホームの夢である。ゆくゆくは老人ホームをつくりたい、というのである。私がちょっと不審そうな顔をしたのを見て、彼は説明した。老人ホームと言っでも、いま園にいる人たちだけが入るのではない。自分たち、つまり親も一緒に入るのだ、と。老後、自分たちもまた、だれかに支えてもらわなければならないときが来るだろう。そのとき、これも一定の支えを必要とする成年した我が子とともに、そこで暮す。少しのことなら老人の自分たちにもできるだろう。そういう老人ホームをつくれないだろうか。
聞きようによると、これはこの人たちのエゴイズムだ、と言われかねない。けれども私は、そうは思わなかった。本来、公共施設・社会施設が補完しなければならない人々の生活というものの実相は、(別の言いかたをすれば、人々が公共施設・社会施設に望んでいるものは、)まさにこういうものだと私は思うからだ。いまの制度は、このことをまったく忘れてしまっている。その合理的因数分解の発想のなかで、個々人の姿が見えなくなってしまったからだ。
あとがき
〇10月の初め、文中にも書いたけれども、青森のT氏が来られ、集中講義が開かれた。「共存互恵」。これが、彼のこの四半世紀にわたってやってきた地域計画の根本であると言ってよい。普通なら直ぐに町村合併をしてしまうのに、そしてそれこそが合理的だと思われるのに、この青森上北地方の四町村は、あくまでの四町村のまま、しかし合同で、地域の諸々の計画を行ってきた。その計画の卓抜さ、柔軟な発想は、まさに驚くべきものであった。録音して多くの人々に聴いてもらいたいと思うほどだ。その話を聞いてしまうと、一時中央で盛んに言われた「地方の時代」などというせりふがいかに安っぽいものであるか、よく分る。中央はそんなせりふを言う前に、地方が地方であるための最高の策、地方分権の強化こそやるべきなのだ。そのとき多分、地方は中央を上まわった形の動きを示すにちがいない。だが、T氏たちは、中央にほとんどの権限をにぎられたなかでなお、これだけのことをしてきたのである。(T氏が「自治あおもり」誌に書いた論文「共存互恵」が私の手元にある。もしご希望の方があれば、コピーしてお送りします。それにより、四半世紀のほほ概略が分ると思う。)
〇「 S 園 」に泊ったとき、園生のO君のお母さんも来ておられた。私はてっきりO君に面会に来られているのだと思っていたら、実はそうではなかった。指導員の方々と一緒になっていろいろと園生の世話をしていたのである。家にいるよりもここにいる方が安まる、とのことであった。
〇ことしは寒くなるのが早いようだ。紅葉はあまりきれいではないが、毎朝、落葉が道を埋めるようになってきた。そして夜は、とめておいた車の窓に露が一面に下りている。もう少したつと、これが氷になる。そうなるとやっかいだ。うっかりしてウォッシヤーでもかけようものなら、それもたちまち氷と化す。もうじきそういう冬が来る。
〇それぞれなりのご活躍を!風邪をひかれぬように!
1983・10・31 下山 眞司

























