和妻の藤山新太郎氏の著書「手妻のはなし」(新潮選書)を読んだ。
実に良く調べたもので、また糸あやつりに関わる記述も見え、とても面白く読んだ。
そのあとがきに、
「先人の立場に立って、先人の考え方を共有した上で改良を加えなければ、ちぐはぐな
ものになってしまう。」
とあった。
これは大切な事である。
色川武大著「寄席放浪記」中の矢野誠一との対談にあった会話。
「孫三郎は二代目が吉祥寺にいる。だけど、みんな芸術になっちゃうんですよ。・・略
・・文楽のミニチュア版なんですね。」
以前この言葉を目にして、いろんなことを考えさせられた。
糸あやつりの古典作品は、文楽の作品以外になにがあるのだろう。
歴史に関しては糸あやつりに関しての研究者がほとんどいないらしく
おざなりなものしかない。
ただ共通しているのは、"資料がない"と書かれてあること。
一介の人形遣いが調べるのだから、集まる資料にも限度がある。
畢竟"人形遣いの勘"が中心になるだろう。
でも敢えて仮説として考えを述べたいと思う。
新しい資料が手に入ったら書き加えればよいし、
仮説が間違いだと分かったら、訂正すれば良い。
島根県益田市の糸あやつり人形に関わった事も大きい刺激になった。
時間のかかることだけれども、ゆっくりと進めたい。
実に良く調べたもので、また糸あやつりに関わる記述も見え、とても面白く読んだ。
そのあとがきに、
「先人の立場に立って、先人の考え方を共有した上で改良を加えなければ、ちぐはぐな
ものになってしまう。」
とあった。
これは大切な事である。
色川武大著「寄席放浪記」中の矢野誠一との対談にあった会話。
「孫三郎は二代目が吉祥寺にいる。だけど、みんな芸術になっちゃうんですよ。・・略
・・文楽のミニチュア版なんですね。」
以前この言葉を目にして、いろんなことを考えさせられた。
糸あやつりの古典作品は、文楽の作品以外になにがあるのだろう。
歴史に関しては糸あやつりに関しての研究者がほとんどいないらしく
おざなりなものしかない。
ただ共通しているのは、"資料がない"と書かれてあること。
一介の人形遣いが調べるのだから、集まる資料にも限度がある。
畢竟"人形遣いの勘"が中心になるだろう。
でも敢えて仮説として考えを述べたいと思う。
新しい資料が手に入ったら書き加えればよいし、
仮説が間違いだと分かったら、訂正すれば良い。
島根県益田市の糸あやつり人形に関わった事も大きい刺激になった。
時間のかかることだけれども、ゆっくりと進めたい。












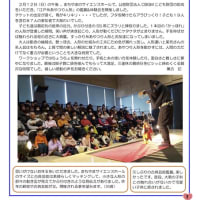













上條さんのお人形に会わなくては。どのお人形も不思議と好きになるような気がします。
左様、御免下さいませ。