
『もうひとりのシェイクスピア』をTOHOシネマズシャンテで見ました。
(1)シェイクスピアについては、戯曲とソネットが残っているだけで、その実像が全く分かっていないことから、例えば日本の東洲斎写楽のように(注1)、その人物について色々な説が立てられているようです。
勿論、本流は「シェイクスピア=ウィリアム・シェイクスピアだと考える正統派(ストラトフォード派)」でしょうが、劇場用パンフレットに掲載されている早稲田大学教授・小田島恒志氏のエッセイによれば、それを疑う「懐疑派(反ストラトフォード派)」には、「当時を代表する学識者フランシス・ベーコン説」や「シェイクスピアと同年生まれの劇作家クリストファー・マーロウ説」など様々なものがあるようです。
本作は、もう一つ別の「オックスフォード伯説」に基づいて、すなわち当時の貴族のオックスフォード伯爵エドワードが、シェイクスピアが作ったとされる戯曲や詩の影の作者だったということで、一つの物語を作り上げています。
物語の舞台は、エリザベス女王(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)の16世紀末(注2)。

彼女は結婚していないので子供がおりません。
その後継者を巡って、宰相セシル(デヴィッド・シューリス)らのスチュアート朝派とオックスフォード伯らのチューダー朝派とが対立することになります。
本作の主人公オックスフォード伯(リス・エヴァンス)は、ひそかに戯曲を書き、劇作家ベン・ジョンソン(セバスチャン・アルメストロ)を通じて(注3)、劇場にて上演させ(注4)、庶民を味方につけようとします。

ところが、上演後、割れるような喝采によって作者の登場が観客から求められると、読み書きの満足にできない役者のシェイクスピア(レイフ・スポール)が、書いたのは自分だと名乗りをあげます。
さあ、オクスフォード伯の狙いはうまくいくのでしょうか、エリザベス女王の後継者はどうなるのでしょうか、……?
本作では、本当のシェイクスピアは誰だったかという詮索よりも、むしろ宰相セシル対オクスフォード伯といった宮廷内抗争を描くことの方に重きが置かれているように見えるところ(注5)、その話の内容がなかなか興味深いものであり、かつまた16世紀末のロンドンの有様が様々な技法を使って巧みに再現されていたりして、随分と面白い作品に仕上がっていると思いました(注6)。
俳優陣については、イギリス人が多いせいなのでしょう、余りなじみがない人が大部分ながら、『ジュリエットからの手紙』や『ミラル』でおなじみのヴァネッサ・レッドグレイヴは、さすがの貫禄でエリザベス女王を演じています(注7)。
(2)想像力が奔放に働かない歴史物は余り好みではないところ、様々な議論のあるところに切り込んでいく映画ならば面白いのではと思って見に行ったのですが、実はもう一つの動機もあります。
たまたま年末からお正月にかけて読んだスティーブン・グリーンブラット著『1417年、その一冊がすべてを変えた』(河野純治訳:柏書房、2012.12)です。
同書は、ローマ教皇庁の秘書官だった人文主義者ポッジョ・ブラッチョリーニが、1000年以上もの長い間見失われていたルクレティウスの『物の本質について』の写本をとある修道院で発見することを巡る実に面白い歴史物語ですが、そのなかに、「シェイクスピアはオックスフォードやケンブリッジで学んだことはなかったが、ラテン語に堪能で、ルクレティウスの詩を自力で読むことができた」、「劇作家仲間のベン・ジョンソンとルクレティウスについて語り合った可能性もある」、「シェイクスピアは彼のお気に入りの本の一冊の中で、ルクレティウスに出会っていたはずだ。その一冊とは、モンテーニュの『エセー』である」などと述べられているのです(P.302)。
あのシェイクスピアとこんなところで出会えるのかと思って大層驚き、丁度上映中の本作にも関心が向いたというわけです(注8)。
(3)本作には、当時ロンドンに設けられていた劇場が登場しますが、フランシス・イエイツの『世界劇場』(藤田実訳、晶文全書)で衝撃を受けた者にとっては、グローブ座の様子が目を惹きました。
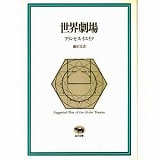
フランシス・イエイツは、同書において、「18世紀の中頃に、かつて地球座の敷地であったところの近くに住んでいて、地球座の建物の土台を見ている」スレイル夫人による、「地球座の外側は六角形で内側は円形であった」との「記述は完全に信頼してもよい」として、グローブ座について一つの平面図の試案(上に掲載した同書の表紙を参照)を提示しています。
さらに、F・イエイツは、この試案に正方形(楽屋棟と舞台の両方を含めたもの)を加え、こうすると、「ヴィトルーヴィウス的人間図に接近したものになる」として(注9)、「この平面図は少なくとも現代の思考の枠組みではなく、ルネッサンスの時代の思考の枠組みで作った試案である」と述べています(同書P.163~P.166)。
他方、劇場用パンフレット掲載の「Production Notes」に、美術担当の「クラウィンケルは、外装をクラース・ヴィン・フィッシェルの絵で見たことのある高い塔に近いものにしたかった。内装は、現在のロンドンにあるグローブ座を再現しようとはせず、当時の貴族のドレスのような感じを出そうとした。明かりで光輝くような色鮮やかで、豪華なものだ」などとあり、「歴史的な正確さは重要」とされながらも、ヴィジュアル的にアピールするよう、本作においてはいろいろ工夫されているのではと思われます。
(4)渡まち子氏は、「文豪シェイクスピア別人説を重厚なタッチで描く歴史ミステリー「もうひとりのシェイクスピア」。監督があのローランド・エメリッヒというのが一番の驚き」として70点を付けています。
(注1)東洲斎写楽については、このエントリをご覧ください。
(注2)エリザベス女王は1603年に亡くなります。
(注3)本作では、ベン・ジョンソンがオックスフォード伯との連絡係とされており、またオックスフォード伯が書いた戯曲などの草稿はすべてべン・ジョンソンに託されることになります。

映画の冒頭では、ベン・ジョンソンが、その草稿を持っているところを兵士に追われ、グローブ座に逃げ込み、それを衣装箱に隠すものの、劇場に火を付けられてしまい捕えられる様子が描かれます。
(尤も、Wikipediaによれば、グローブ座は「『ヘンリー八世』の上演中、装置の大砲から出た火によって火災が発生し焼失した」とされていますが)
(注4)オックスフォード伯は、ベン・ジョンソンに対し「お前の名前で上演しろ」と言いますが、作者の名前は明かされずに上演されます(映画の原題は「anonymous」)。
(注5)本作では、宰相セシルは、スコットランド王ジェームス1世を擁立したのに対し、オックスフォード伯らは、エセックス伯を支持していたとされます。
さらに、本作では、若き日のエリザベス女王とオックスフォード伯とは愛人関係にあり、エリザベス女王が密かに産んだ子がエセックス伯であり、またエセックス伯につき従っているサウサンプトン伯は、オックスフォード伯が別の女性に産ませた子であるとされています〔追記:下記の「シスターズ」さんのコメントによれば、ここの記述にはクマネズミの誤解があるようです〕。
エセックス伯は、宰相セシル及びその息子のロバート・セシルを宮廷から排除しようと立ち上がりますが、逆にエリザベス女王の怒りをかって斬首刑に処せられてしまいます(サウサンプトン伯は、オックスフォード伯の嘆願により辛くも助命されます)。
(注6)とはいえ、映画の冒頭に現代人が登場し、これから始まる劇について口上めいた話をしますが(そしてまた、ラストにもこの現代案内人は登場しますが)、そんな大仰な構えにする必要性があるのかな、という気がしました。
(注7)主演のリス・エヴァンスについても、『ミスター・ノーバディー』でニモの父親に扮していたところ、同一人物だとはなかなか分かりませんでした。
また、シェイクスピア役のレイフ・スポールは、そういえば『ワン・デイ』でイアン(アン・ハサウェイのエマが一時同棲していた相手)に扮していました。
(注8)著者グリーンブラット氏がどうしてシェイクスピアを持ち出したのかというと、同氏はもともと類いまれなるシェイクスピア学者なのです。
上記の引用からもわかるように無論「ストラトフォード派」であり、例えば『シェイクスピアの驚異の成功物語』(河合祥一郎訳:白水社、2006年)が有名です。
ちなみに、同書では、「『ハムレット』は「シェイクスピアの作家人生に大きな断層を作」り出しているが、そうなったのは「シェイクスピアの人生になんらかのショックがあったためではないだろうか」として、上記「注5」で触れたエセックス伯の「暴挙」が「一つのショック」だったかもしれない、と述べられています(P.436)。
尤も、そのすぐ後で、著者は、「実はシェイクスピアの『ハムレット』は、どうやらエセックス伯が運命の決行に踏み切る前に上演されたらしい」として(P.440)、『ハムレット』に登場する亡霊の役を演じる「シェイクスピアの胸のうちには蘇ってきたに違いない、墓の中から聞こえてくる死んだ息子(ハムネット)の声が、死にゆく父親の声が、そしてひょっとすると、自分自身の声が」と述べています(P.455)。
(注9)「ヴィトルーヴィウス的人間図」については、F・イエイツは、さらに「この人間図は、ルネッサンスの基本的な図像であって、幾何学的象徴を用いて人間と宇宙との関係をあらわし、その調和ある構造が大宇宙の調和と関係を持つ小宇宙=人間をあらわすものである」と述べています(P.166。図はこちらに掲載されています)。
なお、F・イエイツの『世界劇場』については、こちらが参考になります。
★★★★☆
象のロケット:もうひとりのシェイクスピア
(1)シェイクスピアについては、戯曲とソネットが残っているだけで、その実像が全く分かっていないことから、例えば日本の東洲斎写楽のように(注1)、その人物について色々な説が立てられているようです。
勿論、本流は「シェイクスピア=ウィリアム・シェイクスピアだと考える正統派(ストラトフォード派)」でしょうが、劇場用パンフレットに掲載されている早稲田大学教授・小田島恒志氏のエッセイによれば、それを疑う「懐疑派(反ストラトフォード派)」には、「当時を代表する学識者フランシス・ベーコン説」や「シェイクスピアと同年生まれの劇作家クリストファー・マーロウ説」など様々なものがあるようです。
本作は、もう一つ別の「オックスフォード伯説」に基づいて、すなわち当時の貴族のオックスフォード伯爵エドワードが、シェイクスピアが作ったとされる戯曲や詩の影の作者だったということで、一つの物語を作り上げています。
物語の舞台は、エリザベス女王(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)の16世紀末(注2)。

彼女は結婚していないので子供がおりません。
その後継者を巡って、宰相セシル(デヴィッド・シューリス)らのスチュアート朝派とオックスフォード伯らのチューダー朝派とが対立することになります。
本作の主人公オックスフォード伯(リス・エヴァンス)は、ひそかに戯曲を書き、劇作家ベン・ジョンソン(セバスチャン・アルメストロ)を通じて(注3)、劇場にて上演させ(注4)、庶民を味方につけようとします。

ところが、上演後、割れるような喝采によって作者の登場が観客から求められると、読み書きの満足にできない役者のシェイクスピア(レイフ・スポール)が、書いたのは自分だと名乗りをあげます。
さあ、オクスフォード伯の狙いはうまくいくのでしょうか、エリザベス女王の後継者はどうなるのでしょうか、……?
本作では、本当のシェイクスピアは誰だったかという詮索よりも、むしろ宰相セシル対オクスフォード伯といった宮廷内抗争を描くことの方に重きが置かれているように見えるところ(注5)、その話の内容がなかなか興味深いものであり、かつまた16世紀末のロンドンの有様が様々な技法を使って巧みに再現されていたりして、随分と面白い作品に仕上がっていると思いました(注6)。
俳優陣については、イギリス人が多いせいなのでしょう、余りなじみがない人が大部分ながら、『ジュリエットからの手紙』や『ミラル』でおなじみのヴァネッサ・レッドグレイヴは、さすがの貫禄でエリザベス女王を演じています(注7)。
(2)想像力が奔放に働かない歴史物は余り好みではないところ、様々な議論のあるところに切り込んでいく映画ならば面白いのではと思って見に行ったのですが、実はもう一つの動機もあります。
たまたま年末からお正月にかけて読んだスティーブン・グリーンブラット著『1417年、その一冊がすべてを変えた』(河野純治訳:柏書房、2012.12)です。
同書は、ローマ教皇庁の秘書官だった人文主義者ポッジョ・ブラッチョリーニが、1000年以上もの長い間見失われていたルクレティウスの『物の本質について』の写本をとある修道院で発見することを巡る実に面白い歴史物語ですが、そのなかに、「シェイクスピアはオックスフォードやケンブリッジで学んだことはなかったが、ラテン語に堪能で、ルクレティウスの詩を自力で読むことができた」、「劇作家仲間のベン・ジョンソンとルクレティウスについて語り合った可能性もある」、「シェイクスピアは彼のお気に入りの本の一冊の中で、ルクレティウスに出会っていたはずだ。その一冊とは、モンテーニュの『エセー』である」などと述べられているのです(P.302)。
あのシェイクスピアとこんなところで出会えるのかと思って大層驚き、丁度上映中の本作にも関心が向いたというわけです(注8)。
(3)本作には、当時ロンドンに設けられていた劇場が登場しますが、フランシス・イエイツの『世界劇場』(藤田実訳、晶文全書)で衝撃を受けた者にとっては、グローブ座の様子が目を惹きました。
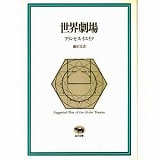
フランシス・イエイツは、同書において、「18世紀の中頃に、かつて地球座の敷地であったところの近くに住んでいて、地球座の建物の土台を見ている」スレイル夫人による、「地球座の外側は六角形で内側は円形であった」との「記述は完全に信頼してもよい」として、グローブ座について一つの平面図の試案(上に掲載した同書の表紙を参照)を提示しています。
さらに、F・イエイツは、この試案に正方形(楽屋棟と舞台の両方を含めたもの)を加え、こうすると、「ヴィトルーヴィウス的人間図に接近したものになる」として(注9)、「この平面図は少なくとも現代の思考の枠組みではなく、ルネッサンスの時代の思考の枠組みで作った試案である」と述べています(同書P.163~P.166)。
他方、劇場用パンフレット掲載の「Production Notes」に、美術担当の「クラウィンケルは、外装をクラース・ヴィン・フィッシェルの絵で見たことのある高い塔に近いものにしたかった。内装は、現在のロンドンにあるグローブ座を再現しようとはせず、当時の貴族のドレスのような感じを出そうとした。明かりで光輝くような色鮮やかで、豪華なものだ」などとあり、「歴史的な正確さは重要」とされながらも、ヴィジュアル的にアピールするよう、本作においてはいろいろ工夫されているのではと思われます。
(4)渡まち子氏は、「文豪シェイクスピア別人説を重厚なタッチで描く歴史ミステリー「もうひとりのシェイクスピア」。監督があのローランド・エメリッヒというのが一番の驚き」として70点を付けています。
(注1)東洲斎写楽については、このエントリをご覧ください。
(注2)エリザベス女王は1603年に亡くなります。
(注3)本作では、ベン・ジョンソンがオックスフォード伯との連絡係とされており、またオックスフォード伯が書いた戯曲などの草稿はすべてべン・ジョンソンに託されることになります。

映画の冒頭では、ベン・ジョンソンが、その草稿を持っているところを兵士に追われ、グローブ座に逃げ込み、それを衣装箱に隠すものの、劇場に火を付けられてしまい捕えられる様子が描かれます。
(尤も、Wikipediaによれば、グローブ座は「『ヘンリー八世』の上演中、装置の大砲から出た火によって火災が発生し焼失した」とされていますが)
(注4)オックスフォード伯は、ベン・ジョンソンに対し「お前の名前で上演しろ」と言いますが、作者の名前は明かされずに上演されます(映画の原題は「anonymous」)。
(注5)本作では、宰相セシルは、スコットランド王ジェームス1世を擁立したのに対し、オックスフォード伯らは、エセックス伯を支持していたとされます。
さらに、本作では、若き日のエリザベス女王とオックスフォード伯とは愛人関係にあり、エリザベス女王が密かに産んだ子がエセックス伯であり、またエセックス伯につき従っているサウサンプトン伯は、オックスフォード伯が別の女性に産ませた子であるとされています〔追記:下記の「シスターズ」さんのコメントによれば、ここの記述にはクマネズミの誤解があるようです〕。
エセックス伯は、宰相セシル及びその息子のロバート・セシルを宮廷から排除しようと立ち上がりますが、逆にエリザベス女王の怒りをかって斬首刑に処せられてしまいます(サウサンプトン伯は、オックスフォード伯の嘆願により辛くも助命されます)。
(注6)とはいえ、映画の冒頭に現代人が登場し、これから始まる劇について口上めいた話をしますが(そしてまた、ラストにもこの現代案内人は登場しますが)、そんな大仰な構えにする必要性があるのかな、という気がしました。
(注7)主演のリス・エヴァンスについても、『ミスター・ノーバディー』でニモの父親に扮していたところ、同一人物だとはなかなか分かりませんでした。
また、シェイクスピア役のレイフ・スポールは、そういえば『ワン・デイ』でイアン(アン・ハサウェイのエマが一時同棲していた相手)に扮していました。
(注8)著者グリーンブラット氏がどうしてシェイクスピアを持ち出したのかというと、同氏はもともと類いまれなるシェイクスピア学者なのです。
上記の引用からもわかるように無論「ストラトフォード派」であり、例えば『シェイクスピアの驚異の成功物語』(河合祥一郎訳:白水社、2006年)が有名です。
ちなみに、同書では、「『ハムレット』は「シェイクスピアの作家人生に大きな断層を作」り出しているが、そうなったのは「シェイクスピアの人生になんらかのショックがあったためではないだろうか」として、上記「注5」で触れたエセックス伯の「暴挙」が「一つのショック」だったかもしれない、と述べられています(P.436)。
尤も、そのすぐ後で、著者は、「実はシェイクスピアの『ハムレット』は、どうやらエセックス伯が運命の決行に踏み切る前に上演されたらしい」として(P.440)、『ハムレット』に登場する亡霊の役を演じる「シェイクスピアの胸のうちには蘇ってきたに違いない、墓の中から聞こえてくる死んだ息子(ハムネット)の声が、死にゆく父親の声が、そしてひょっとすると、自分自身の声が」と述べています(P.455)。
(注9)「ヴィトルーヴィウス的人間図」については、F・イエイツは、さらに「この人間図は、ルネッサンスの基本的な図像であって、幾何学的象徴を用いて人間と宇宙との関係をあらわし、その調和ある構造が大宇宙の調和と関係を持つ小宇宙=人間をあらわすものである」と述べています(P.166。図はこちらに掲載されています)。
なお、F・イエイツの『世界劇場』については、こちらが参考になります。
★★★★☆
象のロケット:もうひとりのシェイクスピア




















当然ながら同じように(?)シェイクスピアを描いた『恋におちたシェイクスピア』と劇場や風景もそっくりだったが今回は熊と犬を戦わせる場面があったのが“事実”どうりで面白かった。つまり当時のサウスバンクの劇場は同時にあのような見世物小屋でもあったから円形構造になっていたわけです。
ちなみにロンドンのグローブ座のウォーキング・ツアーに参加したことがあるが現在のグローブ座だけでなく、かってのローズ座やグローブ座の場所やInn(宿屋)の中庭で芝居をやった場所にも案内してくれ面白かったです。
ちょっと『恋におちたシェイクスピア』に関わりすぎて申し訳ないが、こちらは完全なフィクションでシェイクスピア本人が主人公なので当然別人説は採らないが、ある面では今回の作品より“事実に基づく”場面が多い。ところが映画のタイトルバックにサインの練習(?)をする場面があり不思議なことに、William Shakespear ではなく、(読みにくいが) Willm Shagspere(実際の教会の記録)William Shakspere(次女の洗礼簿)などのほか Shakepen 、Shakesbee、Shagsbeard などと書いては捨てる。もちろんこの場面はスランプに陥っているための遊びと解釈すべきだろうが反ストラトフォード派の1つの根拠でもあるサインの問題に関連するので実は別人説を匂わせているとも解釈できる。今回のシェイクスピアは文学的には無能だったが『恋におちたシェイクスピア』でも「ロミオとジュリエット」の題名やストーリーを他人のアイデアを盗用したり別人説ともとれる表現があったのが面白い(もっともシェイクスピアの大部分の作品には元ネタがあるのだが)。
今回の作品ではShake-Speare とわざわざサインに後からハイフンを入れる場面があった。もちろんこれは(現実に有力な候補の一人である)オックスフォード伯がハイフンによって別人の証拠を潜ませると同時に槍を振る(Shake-Speare)のが自分の紋章だったからなのだが。
もうひとつ、直接映画に関係ないがSouthampton の発音。日本では昔はサザンプトンと表記したが最近はサウザンプトンやサウサンプトンが多く原音はどうかと注意して聞いていたが人によって違ううえサウスハンプトンも3回出てきた。
それから、映画の冒頭とラストの口上ですが確かに映画では何の意味もないし効果があるとも思えない。しかも御丁寧に渋滞だったか遅れて息まで切らして1分前ぐらいに飛び込むが現実なら恐らくすでに代役をたてるはず。
まあ一応シェイクスピアの時代の舞台では(現在のグローブ座でも)上演前に口上を述べるのが習慣だったから、ということでしょうが。
今年もよろしくお願いいたします。
今回も、シェイクスピアのサインとかSouthamptonの発音など実に興味深いお話しをありがとうございます。
なお、クマネズミも、エントリで触れた本に、シェイクスピアがラテン語を読めると書いてあるのを見て、そんなに高い学識があるのなら一介の役者ではないのでは、やはり別人説が成り立つのではとも思いましたが、ただその本で中心的に取り上げられているポッジョは、ラテン語の大家でありながらも、決して裕福な生まれというわけでもなさそうで、そうならばシェイクスピアも勉強してラテン語が読めるようになったのかもしれませんから、一概に別人だと決め付けるわけにもいかないな、なかなか難しい問題だなと思いました。
彼らの子供はサウサンプトン伯です
エセックスはエリザベスの子ですが父親は描かれてません
http://shakespeare-movie.com/cast.html
どうやらクマネズミの方に誤解があったようです。
本作のロバート・セシルによれば、オックスフォード伯自身がエリザベスの隠し子である可能性(王に就く可能性も)があるそうなのですから、いろいろ混乱してしまいました。