(冒頭写真は、2023.03.25付朝日新聞「書評」ページより、バリー・マイヤー著「ペイン・キラー アメリカ全土を中毒の渦に突き落とす、悪魔の処方薬」を撮影したもの。
本日は、当該著書に対する朝日新聞 本社論説委員・生方史郎氏による「過剰摂取で年間10万人超が死亡」と題する書評を引用する。
以下に、その書評の要約をしよう。
米国では2021年、薬物の過剰摂取で過去最多の10万人が亡くなったとみられ、その多くはオピオイドという麻薬性鎮痛剤が原因だ。 そう聞いても、どこかピンと来ないでいた。
痛みから逃れるために薬に頼る気持ちはよくわかる。 でも、どうやったら処方箋がないと入手できない薬で死亡に至り、国民の平均寿命を下げるまでになるのか。 そんな疑問がようやく解消した。
この本に登場する16歳の女子高校生の場合、別にどこかが痛かったわけでも何でもない。 彼女が住むのはかつて炭鉱でさかえた地域で、トランプ前大統領誕生の原動力にもなった「ラストベルト(さびついた工業地帯)」をどこか想像させる。
最初に吸ったときには吐き気がしたが、すぐに筋肉が弛緩してすべての緊張が消え去ったという。 当然だが、薬が切れれば元に戻る。 いとも簡単に激しい苦痛を伴う離脱症状が起きる状態にもなり、一度も大量摂取すれば呼吸困難を起こして亡くなることもある。
高校生が薬を入手出来てしまうのは、むろん不正な流通経路があるからだ。 地域の異変に気付いた医師らが製薬会社を相手に立ち上がり、やげて司法当局が動く。 一方、製薬会社は司法経験者や有能な弁護士を雇い入れ、議員や関連団体には献金攻勢をかける。 さならが映画のような展開だ。 (途中大幅略)
念のために書き添えれば、癌の痛みに麻薬性鎮痛剤を使っても依存や中毒は起らない。 ただし、市販の鎮痛剤や咳止めでも依存が起きうることは知っておくべきだろう。
(以上、朝日新聞「書評」ページより一部を引用したもの。)
話題を大きく変えて、原左都子が左膝複雑骨折手術後に病院の薬剤師氏より処方された「鎮痛剤」の話をしよう。

こちらは、8日間手術入院した後の退院時に処方されたもの。
ただの一粒も飲まずに、引き出しの中に置き去ったままだ。
ただし、我が主治医が理解ある医師であることに助けられた。 正直に鎮痛剤を一切服用していないことを告げると。 「痛みが無いのならそれで十分です。患者さんによれば“追加の鎮痛剤が欲しい”とおっしゃる方もいますが。」😱
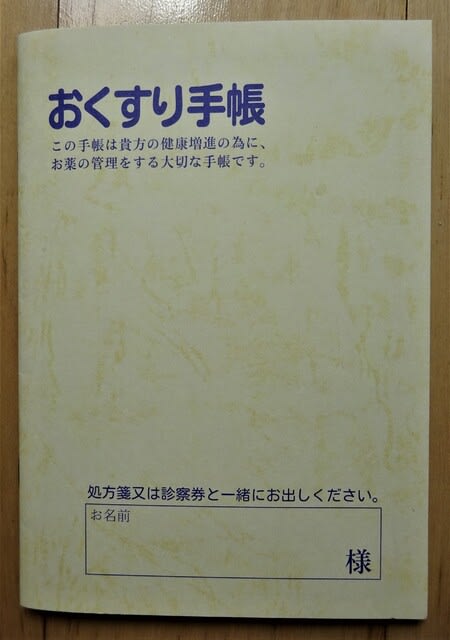
こちらは、同時に薬剤師より頂いた「お薬手帳」。
最初に「現在お使いの『お薬手帳』をお持ちですか? と尋ねて下さるので。 「過去に何度かそれを配布されたことがありますが、基本的に薬を飲まない主義ですので、いつも捨てています。」と応えた。
そう言ったにもかかわらず、薬と手帳を配布されてしまった、とのいきさつだ…
冒頭の書評に記した米国の事例は、多少極端かもしれないが。
我が国でも、病院へ行けば大量の薬剤を配布されることが常識化してしまっているように私は捉えている。
おそらく皆さん、それらの薬剤を“素直”に“真面目”に飲んでおられるのだろう。
その慣習が老後までずっと続いてしまったら、ご自身の身体が一体如何に変化するのかを想像したことがおありだろうか?
我が義母の事例を挙げると。
昔から一貫して病院から配布される「薬」を信用し切っていて、それらをすべて“飲みこなして”いる人物だ。
亭主との晩婚直後に、その義母が私相手に配布された薬を広げつつ「私はこんなに薬を飲まなきゃいけない身体なのよ」との“自慢話”を始めるではないか!😖 😲
ところが、我が診断だと義母とは何らの致命的疾患や基礎疾患が無い。 にもかかわらず、身体のどこかに痛みや違和感が発生すると、せっせと病院通いをして薬のコレクションをする癖があるようだ。
義母は早くから認知症を抱える身であり、現在91歳を過ぎて尚元気ではあるものの。 義母の認知症の原因の一つに「薬剤多用習慣」があると私は考えている。 (まあ義母の場合は、基本的に“他者依存性の強さ”や“物事に対する興味の低さ”等も認知症の原因であろうとみてはいるが。)
我が国の場合は、冒頭の書評内に書かれているがごとくの“高校生が危険薬剤に手出しする”との事例は極少と信じたいが。
一般人の病院処方薬依存は、幅広い世代に渡る現象なのではあるまいか?
いやもちろん、それを処方されねば命にかかわるがごとくの病気や症状もあるため、それに関しては医師や薬剤師の指導に必ず従うべきなのだが。
とにかく薬には副作用がつきものであるし。
国立大学医学部パラメディカル分野出身者でもある原左都子としては。
安易過ぎる薬の乱用は、主治医と十分に相談の上に慎まれては如何だろうか?? と、アドバイス申し上げたい。


















