独特の味わい。
ここのところ読んでるモノがミステリとホラーに寄ってるせいか、
このアイデア勝負的な三作品が独特に感じたのかもね。
読み心地の軽さは伊坂的なんだけど、どの作品もそれなりに陰惨な話だよねー。
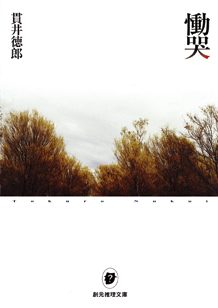
慟哭
連続幼女誘拐事件に苦しむキャリア課長と、職を失い昼間っから街中をフラつく男。
誘拐事件は解決に向かわず、無職の男は新興宗教に興味を抱くようになり…
一見無関係のエピソードが物語の終盤へ向かうにつれ集約されてくってのはよくあるお話。
伊坂だとアヒルと鴨がそうだし、折原一だとロンドや冤罪者、被告Aがそういう形だったなぁ。
今回読んだ三作の中だと手法がありふれたモノだったこともあって、
ミステリ色が一番濃い作品、と言っていいものなのかも。
どちらかというとハードボイルド的な匂いの方が強く、
普通のミステリとは違う仕上がりにはなってますがね。
タイトルの「慟哭」って言葉がそれなりに重い作品でありまして。
一回読んだらすぐにもう一回読み返すことをオススメします。
救われない終わり方を嫌う人にはオススメできない作品、ってことも付記しておくか。
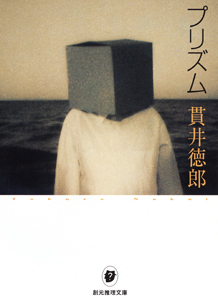
プリズム
小学校に勤務する女性教師が不審死。
事故とも殺人事件とも受け取れる死に方に疑問を持つ関係者たち。
教師が受け持っていたクラスの子供たち、同僚教師、元カレ、不倫関係にあった愛人と、
皆が皆その真相へ近づこうと行動する、というあらすじ。
先ほどの「慟哭」が割合ありふれている手法で物語を展開させていったのに対し、
こちらは4人がリレー形式で事件を追っていく形になってまして。
アイデアの妙と言ってもいいんじゃないでしょうか。
似た形式の作品(もしくはオマージュ元)として「毒入りチョコレート事件」という海外作品があるらしいんで、
こっちも後々読みたいと思ってますが…
Scene1では子供たちが探偵役で、親や他クラスの教師に聞き込みを行ったり、
被害者の住んでいたアパートの大家に話を聞いて、頭の中で事件を構築させていきます。
Scene2では先ほどの子供たちから意外な情報を得たコトをきっかけに同僚教師が動き、
被害者の親族を通し元カレ達と接触して互いに情報を交換する。
Scene3ではその元カレが…といったように、
シーンごとに探偵役は自分の知れるだけの情報をまとめ、自分の中で事件を解決させて終わります。
その過程で接触し情報を提供しあったりした人間が次章の語り手となるけれど、
実際の事件の解決にはなっていないワケで。
「慟哭」ほど重くない話なのですが、読後のモヤモヤ感はこちらの方が上でしょうか。
煮え切らない話を嫌う人は避けた方がいいでしょうね…
突き放されたってワケじゃなく「それぞれ納得いくような捉え方で構いません」といったようなオチですが、
その辺が内容の濃さより手法の切れ味を優先させた結果なのかも、とか思ってます。

愚行録
こちらも手法が凝ってる。
一家惨殺事件に対してのインタヴュー部分と「あたし」の一人語りを交互に噛ませて話が進む。
話が進むと言っても、スジらしいスジは無いと言ってもいいんじゃなかろうか。
インタヴュー部分はホントに生前の被害者のコトを聞いてるだけで、
聞き手は一言も喋りませんからね。
「あたし」の一人語り部分も、「あたし」が誰なんかわからんし特に事件と関係しているトコは無さそうだし…
読み進めるにつれ、こりゃどういうミステリなのか?と、そんな疑問が湧いてきたりします。
まぁ最後まで読むとちゃんとミステリ然としてるってのは分かるんですがね。
かなりの変化球であることは間違いない。
似た手法の「プリズム」と比べると解りやすい終わり方になってますが、
オチを迂回しつつ語るのが大変難しい作品でもあるワケで…
「プリズム」以上にアイデア勝負感が漂う作品ですし、深く触れれば触れるだけボロも出るでしょう。
上記2作のどっちかを読んで興味が湧いたらどうぞ。ぐらいに留めておきましょう。

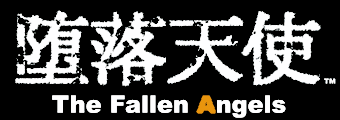
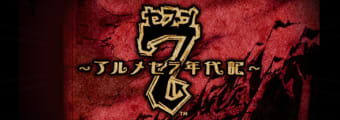










 月華美刃 5巻
月華美刃 5巻 サンレッド 14巻
サンレッド 14巻 センゴク天正記 13巻
センゴク天正記 13巻 ニッケルオデオン 赤
ニッケルオデオン 赤 ムダヅモ無き改革 7巻
ムダヅモ無き改革 7巻 DOGS 7巻
DOGS 7巻 水車館
水車館 迷路館
迷路館 人形館
人形館 鼻
鼻 クリムゾンの迷宮
クリムゾンの迷宮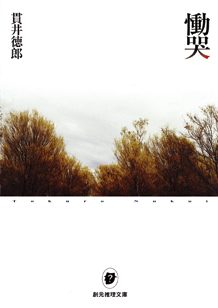 慟哭
慟哭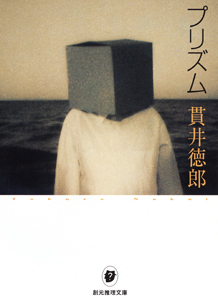 プリズム
プリズム 愚行録
愚行録 占星術殺人事件
占星術殺人事件 密室殺人ゲーム王手飛車取り
密室殺人ゲーム王手飛車取り 嘘喰い 23巻
嘘喰い 23巻 ジョジョリオン 1巻
ジョジョリオン 1巻 進撃の巨人 6巻
進撃の巨人 6巻 嵐ノ花 叢ノ歌 4巻
嵐ノ花 叢ノ歌 4巻 玩具修理者
玩具修理者 家に棲むもの
家に棲むもの 狼の口 3巻
狼の口 3巻 金の靴 銀の魚
金の靴 銀の魚 外天楼
外天楼 冒険エレキテ島 1巻
冒険エレキテ島 1巻 ドロヘドロ 16巻
ドロヘドロ 16巻 月華美刃 4巻
月華美刃 4巻 センゴク天正記 12巻
センゴク天正記 12巻 シドニアの騎士 6巻
シドニアの騎士 6巻 聖☆お兄さん 7巻
聖☆お兄さん 7巻 ベルセルク 36巻
ベルセルク 36巻 サンレッド 13巻
サンレッド 13巻 ドリフターズ 2巻
ドリフターズ 2巻