私が入社したころは世の中は重厚長大から軽薄短小へ向かう、と言われており、「縮み志向の日本人」等という本も出て日本人は箱庭のように大きな世界を小さなところに押し込めるのが好きだからこれからの時代にマッチしている、と言われていた。
実際、半導体と通信技術の驚くべき進歩でこの分野は大きく発展し、日本企業も大きくなった。しかし最近は軽薄短小のいわゆる弱電企業は軒並み業績が悪く、重厚長大の部門を持っていた日立、東芝、三菱などの業績が良い。これらの会社は事業の力点を重電分野においている。世界的に軽薄短小の市場が小さくなったわけではない。新技術は今でも次々と生み出されて発展は続けているが競争が激しく価格低下も進んでいるので拡大のペースが大きく下がってきたということである。
日本の携帯電話産業などを見てもどんどん新技術が生み出され便利になっているし、生活に密着してきており、国民にとっての携帯電話の重要性は高まっているにもかかわらず、産業規模はここ10年くらい横ばいである。横ばいなのだからそれほど悪くないはずだが、拡大を想定して雇用などを続けてきた企業は業績が悪化している。しかし弱電企業の業績が悪い最大の理由は、国際競争力が下がってきているからだというのは衆目の一致するところだろう。
それではなぜ重電分野は好調なのか? 私は重電には詳しくないので良く分からないが、国際競争力が上がっているようには思えない。下がっていないという程度ではないかと思っている。重電分野が好調なのは過当競争に陥っていないからなのではないか、と感じている。
今、スマートシティや発電所、水道、鉄道、といったインフラビジネスが注目を浴びている。日本勢もそれなりに食い込んではいるがそれほど成功しているとも思えない。こういったインフラビジネスが個別の受注生産であった時代には日本勢もそれなりに存在感を示していたのだが、市場規模が拡大してきてあちこちで並行してビジネスが起こるようになってくると、個別対応するよりも標準化してパッケージビジネスにするほうが効率が良い。要素技術をパッケージ化した上で、それぞれの国の個別事情に合わせてコンサルティングをして、組み合わせを変えていく。今世界のインフラビジネスはその方向に向かっているのだが、その面で日本企業が主導的な役割を果たしているという話は聞かない。むしろ今だに日本市場で確立した技術を海外に売りに行く、というスタイルが中心のように思う。
重電が好調なのは参入が少ないというだけの理由ならいずれは弱電と同じ道をたどるだろう。日本の重電機器メーカがどれほど本気でグローバル市場を考えているかで今後、弱電と同じ道をたどるかどうか、今が分かれ道のように思う。










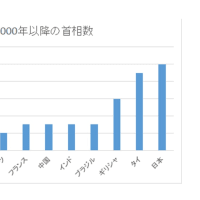
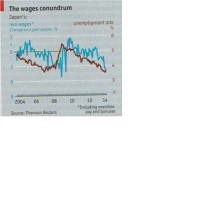
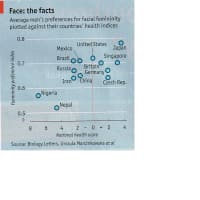
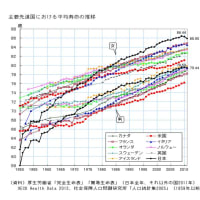



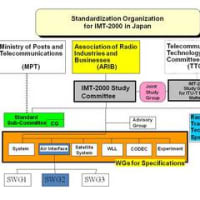


標準化は、デジュールでも、デファクトであっても、この流れを作るなり、読み切って、その主流の中核メンバとしての動きをするのに、なかなか苦労し、結果的に、フォロアー程度の分け前しかもらえなかった。重電の世界では、スマートグリッドが、まさにこの中核の課題。この辺りはウィトラさんが、今までの経験を生かしながら、行政を巻き込むなり、今後、次の世代を育成することで、少しずつ改善が見込めると期待する。
「量産化」、弱電が韓国勢に負けたのは、円高が大きい。但し、韓国勢は集中投資による重点化を推進したことが、日本勢を引き離す大きな差別化でも合ったと思う。日本勢の場合は、横並びの意識が災いして、「より強い」競争力を維持できなかったのではなかろうか? 単なる規模による原価低減にとどまっていた例が多いように感ずる。この辺りは、今後韓国勢が、追いかけてくる中国、インドネシア、インド、ベトナム等をいつまでリードを保てるかだ。今まで、ウォン安がうまく作用してきたが、3-4年の間に、大きく競争力が落ちてくるのではなかろうか? 重電の世界では量産化の波は、おそらく大丈夫であろう。勿論、韓国勢も原子力発電所などで少しずつ成果を挙げてくるだろうが。
「ソフト化」の問題は、PC業界におけるマイクロソフト、ソリューション分野におけるIBMの例を見てもわかるように、大きな意味で流れを読みきり、その主流で動き回ることが、米国勢はうまい。これは教育制度、文化等が影響しているとおもわれる。重電の世界でもソフト化は出てきているものの、まだ大きくはないようだ。
一言で「重電」といっても、発電(火力、水力、原子力)、送変電設備、ケーブル、配電 等で色々な事業分野があるし、確かに日本企業の競争力が見劣りする領域があるかもしれない。この様な観点で見てくると、重電の世界は、日米の大手が既に連合でグループを形成し、欧州勢の有力なグループに対抗している構図が見えてくる。この為、日本の不得手な領域を、グループ形成というアライアンスで補強しているように見える。 だから、「国内市場中心で競争が少ないからだ」とのウィトラさんの指摘は、少し当たっているものの、一部の見方でしかないように感ずる。
現在、発電と送配電の分離が、時々話題になるが、導入され、日本の重電産業が再編されるきっかけになったとしても、産業力自体が衰退し、韓国勢、中国勢に譲ることにはならないでしょうね。(楽観的かな?)
私にとって、この分野での指標になるのは日揮です。日揮は一見日本企業の苦手と思われるようなインフラ・コンサルビジネスで成功しているように見える。これが長く続く強さなのか、今だけ(早く取り組んだからというだけ)の強さでいずれはしぼんでいくのか、というのが大いに興味のあるところです。
私には日揮の事業分野は日本人は得意でない分野に見える。それでも彼らが成功しているのは本物なのか、本物だとしたら自分の認識を改めないといけないと思っています。