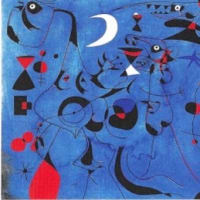日常生活の中で過去を忘れ去っていくのは、
記憶の法則であり、避ける事ができない。
当事者でないなら、なおさらだ。
だが、解決していない問題ならば、まだ忘れるには早い。
東日本大震災がそうだ。
当事者でない者として、せめて年に1日(祥月命日)だけでも思い出したい。
被災者ではないが、わが人生で一番のショックな災害である東日本大震災(自身が震度5強を体験し)から3年目に入る今日、
仕事がないので、自分なりに追悼の一日とした。
まずは有楽町のスバル座で映画『遺体』
(原作:石井光太、監督:君塚良一、主演:西田敏行)を観た。
岩手県釜石市の遺体安置所が舞台。
当時、東京にいた私にとっては、原発事故の方が自分に振りかかる問題となってしまい、
津波の惨事に思いを馳せる余裕がなかった。
震災の本来的な被害者である津波犠牲者とその家族、
そして安置所のスタッフが目の前の”死”と向き合う姿に多少でも触れる事ができた。
映画の中で、安置所では個々の遺体のことを「ご遺体」と呼ぶということを知った
(下に紹介する本でもインタビュー記事でその表現が堅持されていた)。
その足で書店に行き、震災のコーナーに向かい、
『封印された震災死 その真相』(吉田典史著、世界文化社)を購入。
大川小学校の事例は別に一冊の本となっているが、
この書はそれ以外の話題にもなっていない犠牲者の死を検証するルポ。
この書のテーマは後日改めて記したい。
そして、郵便局に行き、日本赤十字社宛の東日本大震災の義援金を振込む。
被災地に旅をするのもいいが、その交通費を含めて送金した。
夕方になったので、昨年に続いて、
半蔵門の国立劇場での追悼式会場に献花に行く。
内閣府主催で、主催者側のスタッフらは皆喪服。
その人たちが礼をする中を抜け、静かな音楽が流れる会場に入り(上写真)、
普段着姿で舞台に上がり、献花用の花を受け取って
献花台の中央、慰霊の柱の下に献花し、合掌する。
ここも2万人(関連死を含めると2万人を超す)の犠牲者に心理的に直面する場だ。
大量の献花が犠牲者一人一人を表しているかのよう
(といっても2万という数はずらりと並んだ献花数よりはるかに多いだろう)。
形式的でなく、心から合掌していると、こみ上げてくるものがある。
合掌を終え、出口の脇で、舞台に向って写真を撮った。
このブログの読者にも見てほしいから。
記憶の法則であり、避ける事ができない。
当事者でないなら、なおさらだ。
だが、解決していない問題ならば、まだ忘れるには早い。
東日本大震災がそうだ。
当事者でない者として、せめて年に1日(祥月命日)だけでも思い出したい。
被災者ではないが、わが人生で一番のショックな災害である東日本大震災(自身が震度5強を体験し)から3年目に入る今日、
仕事がないので、自分なりに追悼の一日とした。
まずは有楽町のスバル座で映画『遺体』
(原作:石井光太、監督:君塚良一、主演:西田敏行)を観た。
岩手県釜石市の遺体安置所が舞台。
当時、東京にいた私にとっては、原発事故の方が自分に振りかかる問題となってしまい、
津波の惨事に思いを馳せる余裕がなかった。
震災の本来的な被害者である津波犠牲者とその家族、
そして安置所のスタッフが目の前の”死”と向き合う姿に多少でも触れる事ができた。
映画の中で、安置所では個々の遺体のことを「ご遺体」と呼ぶということを知った
(下に紹介する本でもインタビュー記事でその表現が堅持されていた)。
その足で書店に行き、震災のコーナーに向かい、
『封印された震災死 その真相』(吉田典史著、世界文化社)を購入。
大川小学校の事例は別に一冊の本となっているが、
この書はそれ以外の話題にもなっていない犠牲者の死を検証するルポ。
この書のテーマは後日改めて記したい。
そして、郵便局に行き、日本赤十字社宛の東日本大震災の義援金を振込む。
被災地に旅をするのもいいが、その交通費を含めて送金した。
夕方になったので、昨年に続いて、
半蔵門の国立劇場での追悼式会場に献花に行く。
内閣府主催で、主催者側のスタッフらは皆喪服。
その人たちが礼をする中を抜け、静かな音楽が流れる会場に入り(上写真)、
普段着姿で舞台に上がり、献花用の花を受け取って
献花台の中央、慰霊の柱の下に献花し、合掌する。
ここも2万人(関連死を含めると2万人を超す)の犠牲者に心理的に直面する場だ。
大量の献花が犠牲者一人一人を表しているかのよう
(といっても2万という数はずらりと並んだ献花数よりはるかに多いだろう)。
形式的でなく、心から合掌していると、こみ上げてくるものがある。
合掌を終え、出口の脇で、舞台に向って写真を撮った。
このブログの読者にも見てほしいから。