奈良競輪場で行われた大阪・関西万博協賛競輪の決勝。並びは佐々木‐菅原の神奈川,中井‐元砂の奈良,松岡‐松川の熊本に三宅で佐藤と大矢は単騎。
元砂がスタートを取って中井の前受け。3番手に松岡,6番手に佐藤,7番手に大矢,8番手に佐々木で周回。残り3周のホームから佐々木が上昇を開始。ゆっくりとした上昇で,バックの出口で中井を叩きました。だれもこのラインには続いていなかったので,3番手に中井,上昇した大矢が5番手で松岡が6番手,最後尾に佐藤という隊列になってホームを通過。バックで佐々木が内を開けたので,内から中井,外から松岡が上昇。中井を打鐘で叩いた松岡の先行に。中井は引かずに松川の内から競りにいきましたが,これは松川が守りました。バックから大矢が単騎で発進。松川に競り負けた中井の後ろの元砂は大矢にスイッチ。直線は粘る松岡の外から大矢,そしてスイッチした元砂が両者の中を割って3人の争い。外の大矢が制して優勝。マークになった元砂が4分の3車輪差で2着。逃げ粘った松岡が4分の3車輪差で3着。
優勝した東京の大矢崇弘選手はこれがS級での初優勝。初めてS級に昇級したのは2017年の6月ですから,S級では頭打ちだったといっていいクラスの選手で,最近はFⅠでも決勝に進出できていませんでしたから,単騎での優勝は正直いって驚きました。展開としてはそこまで楽だったわけではありませんから,これくらいの力はあったということで,たぶんレースで自身の力を十全に発揮するというような形に持ち込むのが苦手というタイプなのではないでしょうか。発進したときの加速にもやや課題があるようには感じます。
自己の能力potentiaの観想contemplatioは,最高の満足でもあり得るのですが,他者との比較という表象imaginatioが介入すると,あまりにもつまらない不快事になってしまうとスピノザは第三部定理五五備考でいっています。そしてこうしたことをいいたいがために,スピノザは第三部定理五三を,この部分では第三部定理五五の前振りとして使ったと國分はいっています。本当にスピノザがそのような意図を有していたか僕には分かりません。ただ,この部分の文脈の流れがそのようになっているのは確かだといえるでしょう。

これに関連して僕の方からいっておきたいことがあります。
第四部定理五二は,理性rationeから生じる最高の満足が自己満足acquiescentia in se ipsoであるといっています。では受動的な満足のうち最高の満足は何であるかといえば,それも受動的な自己満足であろうと僕は考えます。ただこのことは,それを感じるその当人にとってそうであるというだけで,人間が協働して生活を送っていくということを考慮した場合は,その最高の満足がかえって他者に対して迷惑を及ぼすこともあるでしょう。スピノザが第三部定理五五備考のようなことをいうのは,そうしたことも考慮に入れている,というかむしろ人間は共同で生活していくものだということを念頭に置いているからだといえると思います。たとえば人間は他者の力potentiaと自身の力を比較して,自身の力を過大に評価することによって喜びlaetitiaを感じるということがあります。これは自分の力を観想するcontemplari,表象するimaginariという意味ではありますが観想することによって感じる喜びですから自己満足にほかなりません。一方,ここでは自身の力を過大に評価するということを前提としているわけですから,自己満足のうちとくに第三部諸感情の定義二八にある高慢superbiaであるといえるでしょう。この定義でいわれている自己への愛philautiaというのは自己愛philautiaなのであって,スピノザはとくに受動的な自己満足についてそれを自己愛といっているからです。ですから高慢というのは,人間が受動的に感じる喜びの中では,最高の満足のひとつであるといっていいでしょう。ところが第三部定理二六備考では,この高慢が狂気といわれているように,きわめて否定的に評価されているのです。
元砂がスタートを取って中井の前受け。3番手に松岡,6番手に佐藤,7番手に大矢,8番手に佐々木で周回。残り3周のホームから佐々木が上昇を開始。ゆっくりとした上昇で,バックの出口で中井を叩きました。だれもこのラインには続いていなかったので,3番手に中井,上昇した大矢が5番手で松岡が6番手,最後尾に佐藤という隊列になってホームを通過。バックで佐々木が内を開けたので,内から中井,外から松岡が上昇。中井を打鐘で叩いた松岡の先行に。中井は引かずに松川の内から競りにいきましたが,これは松川が守りました。バックから大矢が単騎で発進。松川に競り負けた中井の後ろの元砂は大矢にスイッチ。直線は粘る松岡の外から大矢,そしてスイッチした元砂が両者の中を割って3人の争い。外の大矢が制して優勝。マークになった元砂が4分の3車輪差で2着。逃げ粘った松岡が4分の3車輪差で3着。
優勝した東京の大矢崇弘選手はこれがS級での初優勝。初めてS級に昇級したのは2017年の6月ですから,S級では頭打ちだったといっていいクラスの選手で,最近はFⅠでも決勝に進出できていませんでしたから,単騎での優勝は正直いって驚きました。展開としてはそこまで楽だったわけではありませんから,これくらいの力はあったということで,たぶんレースで自身の力を十全に発揮するというような形に持ち込むのが苦手というタイプなのではないでしょうか。発進したときの加速にもやや課題があるようには感じます。
自己の能力potentiaの観想contemplatioは,最高の満足でもあり得るのですが,他者との比較という表象imaginatioが介入すると,あまりにもつまらない不快事になってしまうとスピノザは第三部定理五五備考でいっています。そしてこうしたことをいいたいがために,スピノザは第三部定理五三を,この部分では第三部定理五五の前振りとして使ったと國分はいっています。本当にスピノザがそのような意図を有していたか僕には分かりません。ただ,この部分の文脈の流れがそのようになっているのは確かだといえるでしょう。

これに関連して僕の方からいっておきたいことがあります。
第四部定理五二は,理性rationeから生じる最高の満足が自己満足acquiescentia in se ipsoであるといっています。では受動的な満足のうち最高の満足は何であるかといえば,それも受動的な自己満足であろうと僕は考えます。ただこのことは,それを感じるその当人にとってそうであるというだけで,人間が協働して生活を送っていくということを考慮した場合は,その最高の満足がかえって他者に対して迷惑を及ぼすこともあるでしょう。スピノザが第三部定理五五備考のようなことをいうのは,そうしたことも考慮に入れている,というかむしろ人間は共同で生活していくものだということを念頭に置いているからだといえると思います。たとえば人間は他者の力potentiaと自身の力を比較して,自身の力を過大に評価することによって喜びlaetitiaを感じるということがあります。これは自分の力を観想するcontemplari,表象するimaginariという意味ではありますが観想することによって感じる喜びですから自己満足にほかなりません。一方,ここでは自身の力を過大に評価するということを前提としているわけですから,自己満足のうちとくに第三部諸感情の定義二八にある高慢superbiaであるといえるでしょう。この定義でいわれている自己への愛philautiaというのは自己愛philautiaなのであって,スピノザはとくに受動的な自己満足についてそれを自己愛といっているからです。ですから高慢というのは,人間が受動的に感じる喜びの中では,最高の満足のひとつであるといっていいでしょう。ところが第三部定理二六備考では,この高慢が狂気といわれているように,きわめて否定的に評価されているのです。















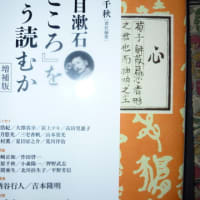

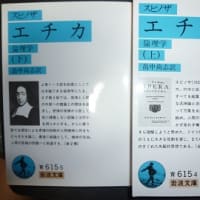

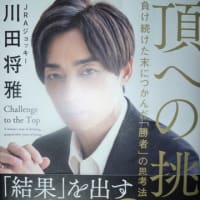




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます