岸和田競輪場で開催された昨日の第76回高松宮記念杯の決勝。並びは深谷‐郡司‐松谷の南関東,寺崎‐脇本‐古性の近畿,太田‐清水の山陽で末木は単騎。
古性,深谷,清水,太田と内の4人がスタートを取りにいきました。誘導の後ろに入ったのは太田でそのまま前受け。3番手に寺崎,6番手に深谷,最後尾に末木で周回。残り2周のホームに入るところから深谷が上昇。末木が続きました。太田は引かずに突っ張り,バックで深谷は浮いてしまったのですが,清水の後ろに続いた郡司が迎え入れて深谷が3番手になって打鐘。すぐさま巻き返した寺崎が太田を叩き,ホームに入るところで近畿勢が前に。バックに入ると後ろからの捲りを待たずに脇本が番手から発進。これで脇本と古性が抜け出して優勝争い。脇本が差を詰めさせずに優勝。古性が1車身差の2着で近畿のワンツー。太田の番手から出た清水と外を捲った深谷の間に進路を取った郡司が6車身差で3着。清水が4分の1車輪差で4着。

優勝した福井の脇本雄太選手は2月の全日本選抜競輪以来の優勝。ビッグは12勝目でGⅠは10勝目。高松宮記念杯は第71回を優勝していて5年ぶりの2勝目。このレースは南関東と近畿のラインが手厚く,前を回る深谷と寺崎がどういう意向で走るかによって結果が左右されそうでした。太田が前受けして深谷が後ろになったため,深谷が押さえにいったところで太田と深谷の先行争いが発生。これによって寺崎は発進しやすくなりました。ラインで出きりましたので近畿ラインが圧倒的に有利に。脇本の番手捲りのタイミングはやや早かったような気がしなくもないですが,展開の利とそれを生かした寺崎の判断が優れていたと思います。
まずこの順序に気を付けなければなりません。僕たちは僕たちの身体corpusを感じることによって,僕たちの精神mensを構成する観念対象ideatumが僕たちの身体であるということを知るのではありません。これが逆でなければならず,僕たちの精神を構成する観念の対象が僕たちの身体であるということを前提するがゆえに,僕たちの身体が僕たちが感じている通りに存在しているということを知ることができるのです。第二部定理一三系は,それだけを抽出してみれば,いかにも僕たちの身体が他の物体corpusから区切られて僕たちの精神によって知覚されるといっているかのようにみえますが,僕たちがそのように知覚するpercipereには前提条件があるのであって,第二部定理一三がそれであるというように把握しなければならないのです。
さらに,第二部定理一三もまたそれ自体で僕たちに知られる事柄ではないのであって,これを知るための前提条件があります。そしてそのうちのひとつが第二部定理一一です。このことはスピノザによる第二部定理一三証明の中で,スピノザが第二部定理一一を援用していることから明らかだといわなければなりません。そしてこの定理Propositioでいわれていることは,人間の精神mens humanaの現実的有actuale esseを構成するのは現実的に存在するある個物res singularisの観念ideaであるということです。ただし,ここでは個物といわれていますが,第二部公理五でいわれているように,僕たちが認識するcognoscere個物というのは諸々の物体か諸々の観念すなわち物体の観念のいずれかになりますから,この定理でいわれていることを,僕たちの精神の現実的有を構成する観念は物体の観念であると解してもそう大きな間違いを犯すことにはなりません。というのも,公理Axiomaは僕たちが物体の観念だけを認識するといっているのではなく,物体も認識するといっているのですから,僕たちの精神の現実的有を構成する観念が物体の観念の観念だけであるというのは不自然であって,物体の観念もそこに含まれなければならないのは明白であるからです。そしてここが重要ですが,この場合の物体というのは,必ずしも僕たちの身体のことだけを意味しているわけではなくて,物体一般を意味していると考えなければならないということです。
古性,深谷,清水,太田と内の4人がスタートを取りにいきました。誘導の後ろに入ったのは太田でそのまま前受け。3番手に寺崎,6番手に深谷,最後尾に末木で周回。残り2周のホームに入るところから深谷が上昇。末木が続きました。太田は引かずに突っ張り,バックで深谷は浮いてしまったのですが,清水の後ろに続いた郡司が迎え入れて深谷が3番手になって打鐘。すぐさま巻き返した寺崎が太田を叩き,ホームに入るところで近畿勢が前に。バックに入ると後ろからの捲りを待たずに脇本が番手から発進。これで脇本と古性が抜け出して優勝争い。脇本が差を詰めさせずに優勝。古性が1車身差の2着で近畿のワンツー。太田の番手から出た清水と外を捲った深谷の間に進路を取った郡司が6車身差で3着。清水が4分の1車輪差で4着。

優勝した福井の脇本雄太選手は2月の全日本選抜競輪以来の優勝。ビッグは12勝目でGⅠは10勝目。高松宮記念杯は第71回を優勝していて5年ぶりの2勝目。このレースは南関東と近畿のラインが手厚く,前を回る深谷と寺崎がどういう意向で走るかによって結果が左右されそうでした。太田が前受けして深谷が後ろになったため,深谷が押さえにいったところで太田と深谷の先行争いが発生。これによって寺崎は発進しやすくなりました。ラインで出きりましたので近畿ラインが圧倒的に有利に。脇本の番手捲りのタイミングはやや早かったような気がしなくもないですが,展開の利とそれを生かした寺崎の判断が優れていたと思います。
まずこの順序に気を付けなければなりません。僕たちは僕たちの身体corpusを感じることによって,僕たちの精神mensを構成する観念対象ideatumが僕たちの身体であるということを知るのではありません。これが逆でなければならず,僕たちの精神を構成する観念の対象が僕たちの身体であるということを前提するがゆえに,僕たちの身体が僕たちが感じている通りに存在しているということを知ることができるのです。第二部定理一三系は,それだけを抽出してみれば,いかにも僕たちの身体が他の物体corpusから区切られて僕たちの精神によって知覚されるといっているかのようにみえますが,僕たちがそのように知覚するpercipereには前提条件があるのであって,第二部定理一三がそれであるというように把握しなければならないのです。
さらに,第二部定理一三もまたそれ自体で僕たちに知られる事柄ではないのであって,これを知るための前提条件があります。そしてそのうちのひとつが第二部定理一一です。このことはスピノザによる第二部定理一三証明の中で,スピノザが第二部定理一一を援用していることから明らかだといわなければなりません。そしてこの定理Propositioでいわれていることは,人間の精神mens humanaの現実的有actuale esseを構成するのは現実的に存在するある個物res singularisの観念ideaであるということです。ただし,ここでは個物といわれていますが,第二部公理五でいわれているように,僕たちが認識するcognoscere個物というのは諸々の物体か諸々の観念すなわち物体の観念のいずれかになりますから,この定理でいわれていることを,僕たちの精神の現実的有を構成する観念は物体の観念であると解してもそう大きな間違いを犯すことにはなりません。というのも,公理Axiomaは僕たちが物体の観念だけを認識するといっているのではなく,物体も認識するといっているのですから,僕たちの精神の現実的有を構成する観念が物体の観念の観念だけであるというのは不自然であって,物体の観念もそこに含まれなければならないのは明白であるからです。そしてここが重要ですが,この場合の物体というのは,必ずしも僕たちの身体のことだけを意味しているわけではなくて,物体一般を意味していると考えなければならないということです。











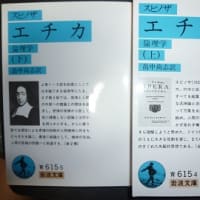
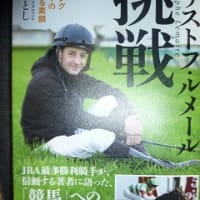





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます