25日に指された第36期女流王位戦五番勝負第五局。
振駒で福間香奈女流王位の先手となって中飛車。後手の伊藤沙恵女流四段が向飛車にしての相振飛車となりましたが,先手は2筋に飛車を戻りました。この将棋はたぶん先手の作戦勝ちで,中盤からはリードしていたのではないかと思います。

すでに先手がよいかと思いますが,ここから☖6七歩☗同金☖4八角成☗6四歩と進み,先手の優勢がはっきりしました。
ここでは☖8五香と銀を取ってしまうのがよかったようです。これには☗6七香と打つ手があり,実戦はそれを避けるための☖6七歩だったのですが,☖3三角と引いておけば先手はすぐに☗6三香成とはできず,一旦は☗5五歩と受けに回ります。それなら☖6四歩と打てますから,これはまだ難しいです。なので先手は☗6四歩☖同金としてから☗6七香と打つ方がよいのですが,これも☖3三角☗6四香に☖6三歩と打っておけば,そこまで簡単ではありませんでした。
福間女流王位が3勝2敗で防衛。第23期,26期,27期,28期,30期,31期,32期,33期,34期,35期に続き七連覇で11期目の女流王位です。
村上は一例として『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』の第一部定理二一を示していますので,ここではそれに沿って考えます。ただしその前に,以下の点に留意してください。
『デカルトの哲学原理』は,スピノザがカセアリウスJohannes Caseariusに講義したノートが基になっています。ただしスピノザが講義したのは『哲学原理Principia philosophiae』の第二部と第三部の一部であって,第一部は講義していません。出版する際に第一部もあった方がよいというマイエルLodewijk Meyerの提言があったので,第一部は講義と無関係に書き下ろされました。なので『デカルトの哲学原理』のうち,最も遅く書かれたのがこの部分であることになります。また,『デカルトの哲学原理』は文字通りにデカルトRené Descartesの『哲学原理』の解説書,とくにデカルトが分析的方法で著述したものを綜合的方法に書き改めたものですが,この第一部に関しては,『哲学原理』よりも『省察Meditationes de prima philosophia』の方が多く利用されています。ですからこの部分は総合的にみて,最もスピノザの考え方,デカルトとは異なったスピノザの考え方が入り込みやすくなっていて,かつその対象が『哲学原理』におけるデカルトの考え方に対してというよりも,もっと広くデカルトの哲学の全体に対してというようになっています。
この定理Propositioというのは,「長さ,広さ,深さを持つ延長的な実体が実際に存在する。そして我々はその一部分と結合している」というもので,これは『省察』にも『哲学原理』にもみられる考え方です。そしてこの定理が『デカルトの哲学原理』の第一部の最後の定理となりますから,この定理を証明しようとすれば第一部を遡っていかなければなりません。それをすればとても長くなりますし,そもそも現状の考察にとっては不要でもありますからそれはしません。留意しておかなければならないのは,スピノザがこの定理の証明Demonstratioを終えた後,すなわち第一部の最後に,短い注意,たぶんこの定理だけに妥当するのではない注意を記述している点です。
その中でスピノザはふたつのことを要請しています。ひとつは,身体corpusを離れた思惟する者としてこれを理解することです。もうひとつは,身体が存在するということを信じていた理由を先入見として退けることです。
振駒で福間香奈女流王位の先手となって中飛車。後手の伊藤沙恵女流四段が向飛車にしての相振飛車となりましたが,先手は2筋に飛車を戻りました。この将棋はたぶん先手の作戦勝ちで,中盤からはリードしていたのではないかと思います。

すでに先手がよいかと思いますが,ここから☖6七歩☗同金☖4八角成☗6四歩と進み,先手の優勢がはっきりしました。
ここでは☖8五香と銀を取ってしまうのがよかったようです。これには☗6七香と打つ手があり,実戦はそれを避けるための☖6七歩だったのですが,☖3三角と引いておけば先手はすぐに☗6三香成とはできず,一旦は☗5五歩と受けに回ります。それなら☖6四歩と打てますから,これはまだ難しいです。なので先手は☗6四歩☖同金としてから☗6七香と打つ方がよいのですが,これも☖3三角☗6四香に☖6三歩と打っておけば,そこまで簡単ではありませんでした。
福間女流王位が3勝2敗で防衛。第23期,26期,27期,28期,30期,31期,32期,33期,34期,35期に続き七連覇で11期目の女流王位です。
村上は一例として『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』の第一部定理二一を示していますので,ここではそれに沿って考えます。ただしその前に,以下の点に留意してください。
『デカルトの哲学原理』は,スピノザがカセアリウスJohannes Caseariusに講義したノートが基になっています。ただしスピノザが講義したのは『哲学原理Principia philosophiae』の第二部と第三部の一部であって,第一部は講義していません。出版する際に第一部もあった方がよいというマイエルLodewijk Meyerの提言があったので,第一部は講義と無関係に書き下ろされました。なので『デカルトの哲学原理』のうち,最も遅く書かれたのがこの部分であることになります。また,『デカルトの哲学原理』は文字通りにデカルトRené Descartesの『哲学原理』の解説書,とくにデカルトが分析的方法で著述したものを綜合的方法に書き改めたものですが,この第一部に関しては,『哲学原理』よりも『省察Meditationes de prima philosophia』の方が多く利用されています。ですからこの部分は総合的にみて,最もスピノザの考え方,デカルトとは異なったスピノザの考え方が入り込みやすくなっていて,かつその対象が『哲学原理』におけるデカルトの考え方に対してというよりも,もっと広くデカルトの哲学の全体に対してというようになっています。
この定理Propositioというのは,「長さ,広さ,深さを持つ延長的な実体が実際に存在する。そして我々はその一部分と結合している」というもので,これは『省察』にも『哲学原理』にもみられる考え方です。そしてこの定理が『デカルトの哲学原理』の第一部の最後の定理となりますから,この定理を証明しようとすれば第一部を遡っていかなければなりません。それをすればとても長くなりますし,そもそも現状の考察にとっては不要でもありますからそれはしません。留意しておかなければならないのは,スピノザがこの定理の証明Demonstratioを終えた後,すなわち第一部の最後に,短い注意,たぶんこの定理だけに妥当するのではない注意を記述している点です。
その中でスピノザはふたつのことを要請しています。ひとつは,身体corpusを離れた思惟する者としてこれを理解することです。もうひとつは,身体が存在するということを信じていた理由を先入見として退けることです。










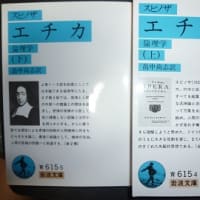
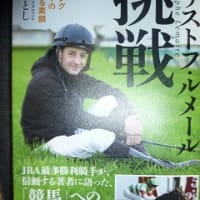







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます